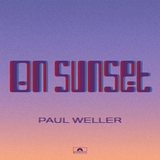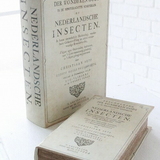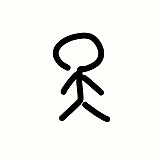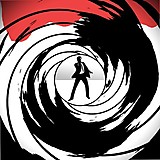火垂るの墓(1988)のレビュー・感想・評価
全111件中、81~100件目を表示
ドロップアウト
よく自業自得だと言う人がいるが
戦時中という過酷な状況の中で、必死に生きる道を探し、苦しみ、踠いていく中学生に対して自業自得だと片付けるのはあまりにも非情ではないか。幼い女の子の未来を戦争によって奪われてしまった、救いのない悲劇映画として観れないのか。
これは反戦映画ではない。どちらかと言えばウシジマ君に近い。
この火垂るの墓。大人になって随分と見方が変わった映画の1つ。
昔は反戦映画だと思っていたけれど、いまは痛烈な現代社会風刺映画にしか見えない。
というのも清太は、現代で言えば、女を不幸にする男の典型・・・というか単なる甲斐性なしの男の人生を描いているとしか見えない。まあそういうダメ男に対して女の方もそれで満足してるなら、それはそれで幸せなのかも知れないが。その結果として待っているのは破滅である。
戦争があろうとなかろうと、こういう男は今の時代にも結構たくさんいる。
現代であれば、そんな甲斐性なし男でも、離婚したり、親の脛をかじって生きて行くことができるが・・・。
分かりやすく言えば、この清太君、ウシジマ君に出てきそうな感じなんだよね。僕的に言えばだけど。
自分はそれが悪いとは思わない。人生ってそういうもんだよな、と思うだけであり、明日はわが身である。
ここまで救いがなく描くことができたからこそ、
火垂るの墓は何故かわからないが忘れることのできない映画なのだと思う。
高畑勲さんご冥福をお祈りします。
戦争孤児
僅か2ヶ月の出来事だったのかと何度も鑑賞しようやく気付いた。
14歳の清太は海軍の父と病弱の母、10歳離れた4歳の妹セツコと何不自由無く贅沢な暮らしをしていた。
空襲に遭い家は焼け、母は死んだ。
残された清太とセツコは西宮の親戚に身を寄せる。
小母さんの棘ある一言一言は清太のプライドをへし折るように刺さる。
戦時中に働かずケラケラ笑い妹と遊び呆ける清太に小母は更なる仕打ちを…
自炊する2人に冷やかな視線の小母。
強情な清太と夜泣きするセツコに向かい小母の一撃。
お国のために働いてる娘達が眠れない何とかしろ!とまくしたてられ清太はセツコと池の淵の洞穴で暮らす。
健気な兄妹の暮らしにもやがて陰りが来る。
セツコは栄養失調で衰弱死した。
清太はセツコを1人で火葬した。
その小さな白い骨をドロップ缶に入れて持ち歩き、清太もまた戦争孤児の衰弱死としてかたずけられた。
意地悪な小母さんと可哀想な兄妹の話だと初めの数回は涙を流し鑑賞していたが、私自身母となり鑑賞した時、清太の可愛げのない性格に腹が立った。セツコは死なずに済んだのに清太の強情さによって死んでしまったのではないのか?と思うようになった。清太の自己満足の犠牲となったセツコの屈託のない笑い声が更に切ない。
戦争と言う暗い題材だが自然の美しさと蛍の光が美しい映画。
基本的には、 よくできた映画です
迫力ある爆撃シーンと、 戦時中のつらい生活が中心のはなしです。 といっても、 主人公は勝手に厳しい環境で生活することを選択しているため、 そもそも親戚の家にすみ続けていれば、 妹の節子が死ぬこともなかったのですが。
基本的には、 よくできた映画です。 しかし、 テンポの悪さが有り、 どうしても退屈だと感じるシーンが有りました。 また、 主人公の亡霊が過去を振り返るような演出がありますが、 非常に分かりづらく、 亡霊と本人の区別もつきづらいです。 そういった演出上の不備もマイナス要素でした。
戦争の悲劇・・
戦争が生んだ悲劇
高畑勲監督の訃報がニュースになったのをきっかけに、ちゃんと見てみようと思いレンタル。
清太の判断が、生きるために正しい決断だとはちょっと言えない。きっと他の選択肢には、生き延びれるものがあっただろう。
でも、14歳で、母が死に、戦争という地獄の中で、自分に正しい判断ができるのかとも思う。少なくとも清太には、妹を守らねばという使命感があって、不安な思いをさせたくない気持ちでいっぱいだったんだろう。それを思うと、批判はできないし、やっぱり憎むべきは戦争であって。
戦争を体験してないからわからないけど、平気で隣の人が死んでいくような世の中に、今の常識なんて通用しないよなあ。虚し悲しい。
納得いかない
なぜ本来の面白さを伝えないんだろう
タイトルなし(ネタバレ)
戦争の悲惨さ、平和の大切さを子供にもわかりやすく伝えている映画。
子供のころにみたときは、親戚のおばさんがいじわるで嫌いと思ったけど、
どう見てもお兄ちゃんがよくない。
お兄ちゃんのわがままで親戚のおばちゃんの家を飛び出し、幼い妹の命を奪ってしまう。。
節子が栄養失調で弱っていくシーンはかわいそうで涙なしには見れません。
最後はお兄ちゃんも節子も死んでしまうバッドエンド。
考えさせられます。
戦争の犠牲者を忘れるな
今日は終戦の日。娘が観ているTV放映を、ラストだけ後ろから覗く。
戦争が終わって、蓄音機から華やかな音楽が流れる。若い女性たちが明るい声で「久し振り」と喜んでいる。
これを明るく自由な時代の到来と受け止めていた高校生当時の私。同じ年齢となった娘はどのように思ったのだろうか。
言うまでもなくこの原作は野坂昭如の実体験に基づく小説である。彼は終戦を境にした人々の変容を受け入れがたかったのではなかろうかという気がする。
女たちが自由を謳歌できる時代は、主人公の少年にとっては、肉親をすべて失い、そして尊敬すべき父の命を賭した仕事への名誉も失われるという時代に他ならなかった。
おそらく軍人である父の名誉が失われていくことは、終戦を迎える前から彼には感じられていたことであろう。それは、母を失くした後に身を寄せた先の叔母から、学徒動員で勤労奉仕している自分の子供たちとの対比で「何もしない」となじられることでも感じているはずだ。
なぜなら、彼と妹の節子が叔母の家に身を寄せなければならないのは、彼らの父親が海軍の軍人として戦地に赴いているからに他ならないのに、そのことへの尊敬や同情がなく、厄介者扱いを受けているからだ。
この少年にとって終戦とは、すべての希望を失うことである。たとえ、空襲で人々が逃げ惑う日々が続いたとしても、その隙に火事場泥棒を働いて食料を確保できることのほうがありがたかった。そして、父親の働く連合艦隊が、自分とこの国を守り続けていると信じていられることが、彼の唯一の誇りだったのだ。
戦争が終わったときに喜んだ人々も多い中で、新しい時代に生きる希望を失った者もいることを忘れてはならない。これは、その時の職業や年齢、信じていたものの違いによって異なってくる。
忘れてならないのは、戦争で失われた数多の命が、敗戦によって無意味な犠牲とされてはならないということであろう。その時は、よきことと信じて死を賭けていた者たちが馬鹿を見ることのないようにしてやらねば。
そうでなければ社会には刹那主義、ニヒリズムが蔓延し、共同体のために勤める気持ちが無くなっていくだろう。
作画が表情豊かですごいと思った。 とくに涙を流すところはリアル。 ...
作画が表情豊かですごいと思った。
とくに涙を流すところはリアル。
戦時中、孤児になってしまった兄弟。
西宮のおばさんと清太がうまくいっていたら、節子も清太も生き延びられたかもしれない。両親を亡くして、親戚の家に居候して、その家の人とうまくやっていける人もいただろうし、清太のように、まだ子供であるために意地を張って亡くなってしまった人もいただろうと思う。
清太も節子も、西宮のおばさんの家に居続けたら生き延びられただろう、というのは、どうしてお金もあったのに、二人とも死んでしまったのだろう、というのも合わさって、西宮のおばさんの表面的な態度だけを見て家を出ていくことを決心した清太の子供っぽさが際立つ。
もしこの映画が、西宮のおばさんと和解して二人が生きていく、またはおばさんの家を出て二人で生きていく、という話であっても反戦映画になりえた。二人が死ななくてはならなかったのは、清太のまだ大人になりきれないところを描くためかもしれない。
全111件中、81~100件目を表示