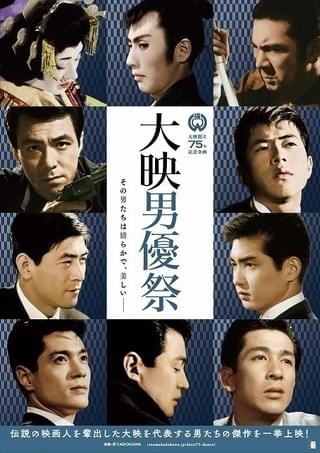地獄門
劇場公開日:1953年10月31日
解説
イーストマン・カラーによる大映第一回総天然色映画で製作は永田雅一、菊池寛の原作「袈裟の良人」を「大仏開眼」の衣笠貞之助が脚色し、監督している。撮影は「浅間の鴉」の杉山公平、音楽監督を「続思春期」の芥川也寸志、美術監督を伊藤熹朔がそれぞれ担当している。出演者は「花の喧嘩状」の長谷川一夫、「あにいもうと(1953)」の京マチ子、「砂絵呪縛(1953)」の黒川弥太郎、香川良介、小柴幹治、「夕立勘五郎」の石黒達也、「南十字星は偽らず」の千田是也、「薔薇と拳銃」の田崎潤など。
1953年製作/89分/日本
原題または英題:Hell's Gate/The Gate of Gate
劇場公開日:1953年10月31日
あらすじ
平清盛の厳島詣の留守を狙って起された平康の乱で、焼討をうけた御所から、平康忠は上皇と御妹上西門院を救うため身替りを立てて敵を欺いた。院の身替り袈裟の車を譲る遠藤武者盛遠は、敵をけちらして彼女を彼の兄盛忠の家に届けたが、袈裟の美しさに心を奪われた。清盛派の権臣の首が法性寺の山門地獄門に飾られ、盛遠は重囲を突破して厳島に急行した。かくて都に攻入った平氏は一挙に源氏を破って乱は治った。袈裟に再会した盛遠は益々心をひかれ、論功行賞に際して清盛が望み通りの賞を与えると言った時、速座に袈裟を乞うたが彼女は御所の侍渡辺渡の妻だった。然しあくまで彼女を忘れえない煩悩に苦しむ盛遠は、加茂の競べ馬で渡に勝ったが、祝宴の席で場所柄を忘て渡に真剣勝負を挑み、清盛の、不興を買った。狂気のようになった彼は刀をもって袈裟と叔母の左和を脅かす。従わねば渡の命が無いと知った袈裟は、夫渡を殺してくれと偽り、自らその身替りとなって命を失った。数日後、頭を丸め僧衣をまとった盛遠は、都を離れて苦悩の旅に出て行く。
スタッフ・キャスト
受賞歴
第27回 アカデミー賞(1955年)
受賞
| 衣装デザイン賞(カラー) | 和田三造 |
|---|




 ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 万引き家族
万引き家族 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド この世界の片隅に
この世界の片隅に セッション
セッション ダンケルク
ダンケルク バケモノの子
バケモノの子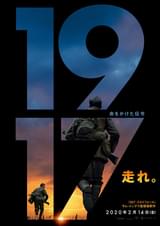 1917 命をかけた伝令
1917 命をかけた伝令