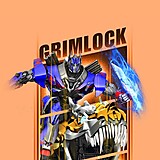ゴジラの逆襲のレビュー・感想・評価
全32件中、1~20件目を表示
アンギラスからニャンギラスを思い出すおニャン子世代
1955年公開作品
監督は『透明人間(1954)』の小田基義
脚本は『ゴジラ(1954)』『空の大怪獣ラドン』の村田武雄と『透明人間(1954)』の日高繁明
モノクロ
『ゴジラ』の続編
好評を受けて急きょ制作されたわりに前作公開から半年後に公開された
前回のゴジラとは別物
敵役としてアンギラス登場
といっても人類の味方でない
二代目ゴジラも同様
大阪の大物が東京に対抗意識を燃やし今度の舞台は大阪と強く希望したため大阪城の前でのゴジラVSアンギラスという名シーンは生まれた
アンギラスはアンキロサウルス
獰猛な肉食の設定だが実際は草食という研究結果が定着している
アンギラスが存在しなければ山吹みどり先生が住んでいるアンギラスマンションは存在しない
ニャンギラスも誕生していないだろう
それにしても酷い歌だ
あれでヒットするすごい時代
二枚目の主人公に対して三枚目の千秋実が良い味を出している
貴様が罵倒じゃない時代
支那も昔はチャイナの日本語もじりで差別用語ではなかった
今は変態やファックが褒め言葉になる時代
移り変わりについていけない真面目な人が戸惑い損をする
それが摂理か
あと何人かレビュアーが指摘しているけど娯楽映画にメッセージ性とか必ずしも必要ない
むしろいらない
高市の支持率は信用しないくせに自民党の支持率は信用する説教くさいヤフコメ老害じゃあるまいし「ウザイ」
1955年
昭和30年
それを考慮すると娯楽映画として傑作の部類
前回が最高傑作なだけ
白黒TVもまだ普及しておらず勿論インターネットなんてナンジャラホイなんだから
考慮しない馬鹿正直はどこにでもいる者だ
自戒の念を込めて
雪崩に巻き込まれて最期を迎える?二代目ゴジラ
放射能火炎があるじゃないかいうが元々ゴジラは恐竜
巨大隕石による急激な自然変化で滅びたことを思えば
テリーマンのテキサス・クローバーホールドに苦しむサンシャインのように納得がいかないことが罷り通る世の中
釈迦の教えでは生きることさえ苦しいのは当然
それも摂理
配役
海洋漁業KKパイロットで秀美の婚約者の月岡正一に小泉博
海洋漁業KK無線係で同社社長令嬢の山路秀美に若山セツ子
海洋漁業KKパイロットで月岡の友人の小林弘治に千秋実
ゴジラの専門家として東京から大阪に招かれた古生物学者の山根に志村喬
アンギラスについて解説する動物学者の田所に清水将夫
防衛隊隊長の寺沢に恩田清二郎
海洋漁業KK北海道支社長の芝木信吾に沢村宗之助
防衛隊隊員の田島に土屋嘉男
海洋漁業KK無線係の井上やす子に木匠マユリ
大阪防衛隊隊長に山田巳之助
海洋漁業KK社長の山路耕平に笠間雪雄
上陸用舟艇隊長の池田に山本廉
海洋漁業KK課長に土屋博敏
大阪警視総監に笈川武夫
囚人Aに大友伸
囚人Bに大村千吉
囚人Cに牧壮吉
囚人Dに広瀬正一
囚人Eに吉田新
囚人Fに夏木順平
海洋漁業KK北海道支社員に夏木順平
料亭・弥生の女将に三田照子
アンギラスに手塚勝巳
ゴジラに中島春雄
キャバレーの歌手に星野みよ子
囚人護送中の警官に橘正晃
大阪市のアナウンスに橘正晃
囚人護送中の警官に伊原徳
囚人護送中の警官に中丸忠雄
囚人に中丸忠雄
囚人に松江陽一
大阪防衛隊幹部に大西康雅
大阪防衛隊幹部に西條竜介
大阪防衛隊幹部に榊田敬二
北海丸船長に熊谷二良
北海丸船員に宇留木康二
北海丸船員に大江秀
北海丸船員に緒方燐作
北海丸船員に坂本晴哉
北海丸無電係に清水良二
海洋漁業KK社員に今井和雄
海洋漁業KK社員に川又吉一
海洋漁業KK社員に吉頂寺晃
海洋漁業KK社員に瀬良明
海洋漁業KK社員に松本光男
海洋漁業KK社員に光秋次郎
海洋漁業KK社員に越後憲三
防衛隊員に越後憲三
海洋漁業KK社員に由起卓也
防衛隊員に由起卓也
海洋漁業KK社員に東静子
料亭・弥生の女中に東静子
報告に来た社員の宇野に宇野晃司
海洋漁業KK北海道支社員に大江秀
テレビのアナウンサーに帯一郎
海洋漁業KK北海道支社員に帯一郎
北海道支社の来客に須田準之助
対策本部員に松下正秀
対策本部員に石川隆昭
防衛隊員に岡部正
防衛隊員に佐藤功一
防衛隊員に鈴木孝次
防衛隊員に中西英介
防衛隊員に岩本弘司
大阪海上警察官に坪野鎌之
大阪の警官に篠原正記
対策本部員に篠原正記
ナイトクラブの客に渋谷英男
ナイトクラブの客に砂川繁視
ナイトクラブの客に細川隆一
逃げ惑う群衆に奥村公延
エンタメの入り口
獰猛な暴龍アンギラス登場!! 初代は特に凶暴なツラ構えと四つ足が好きだ!大阪を舞台に敵怪獣との対決という、現在までに至る基本フォーマットが完成!
まさかのゴジラ・シアターで4K版初上映!
第一作の大ヒットを受けて制作された第二作。
東京の次は大阪、そして新怪獣登場!対戦もの、というわけで、
怪獣映画初のVSもので、怪獣対怪獣映画のパターンを作り出した画期的な作品です!
また、前作に続き、志村喬も同じ役で出演。
ストーリーにも特攻隊など戦後の影はまだあるものの、撃退作戦など娯楽性を前面に打ち出しています。
俊敏で荒々しい動物的な動き、有史以前の恐竜同士の対決を表現するために、
スロースピードでの撮影された(早回し再生に見える)特撮映像は、成功とは言い難いものの、円谷怪獣特撮映画初期の、挑戦的な試みを見ることができます。
アンギラスは、熱線も光線も吐かない、水爆実験で目覚めたアンキロザウルスですが、四足の動物的な形態と、特に凶暴なツラ構えが大好きで、見ものです。
彼には、モノクロ映像が合っています。
『怪獣総進撃』では、まったくその面影の無いクリクリ目玉の二代目が登場。
しかし、本作品での因縁がもとで、以降、ゴジラの子分になり下がってしまうので、
この作品における勇姿は貴重です。
以後のゴジラ映画では珍しい噛みつきを多用、コマ落としによる素早い動きもあいまってリアリティある肉食動物同士の野性味溢れる闘いのようで新鮮。
ゴジラ70周年記念企画としてスタートしたゴジラ・シアターもいよいよ第8弾。
本日は『ゴジラの逆襲 4Kデジタルリマスター版』(1955)を鑑賞。
『ゴジラの逆襲』(1955)
前作『ゴジラ』(1954)の歴史的大ヒットを受けて急遽半年後に公開された第2弾。
特技監督の円谷英二氏は変わらず、本編監督は本多猪四郎氏から『透明人間』の小田基義氏、音楽も伊福部昭氏から佐藤勝氏へバトンタッチ。
本作の見どころは東宝特撮映画初のアンギラスとの怪獣対決。
本作で怪獣対決がなかったら70年以上の長きにわたり30作品の長期シリーズは成しえなかったでしょうね。まさにエポックメイキング作。
ティラノサウルスを模した二足歩行のゴジラと、アンキロサウルスを模した四足歩行のアンギラスの初の怪獣対決は闘犬をイメージしたとのことで、放射熱線は少なめ、以後のゴジラ映画では珍しい噛みつきを多用、コマ落としによる素早い動きもあいまってリアリティある肉食動物同士の野性味溢れる闘いのようで新鮮。
大阪城はじめ大阪市内での対決も前作同様、70年前とは思えないほど精巧で迫力がありましたね。
しかし、この怪獣対決もクライマックスではなく作品中盤、後半は舞台を北海道に変えて、前作同様、最後は人間対ゴジラの対決で幕を閉じます。
ラストの戦闘機による雪崩作戦は『トップガン マーヴェリック』(2022)を彷彿とさせました。
前作のような反核テーマ性は希薄でしたが話のテンポも良く、主人公月岡(演:小泉博氏)の同僚・小林(演:千秋実氏)のコメディリリーフもいい味を出していましたね。
酷い出来栄え
対アンギラス戦‼️
記念すべき「ゴジラ」シリーズの2作目‼️いきなりゴジラとアンギラスの岩戸島での戦いから始まり、大阪を舞台に二体が再度対決、アンギラスに勝利したゴジラは、自衛隊のロケット攻撃で雪山の雪と氷に閉じ込められる・・・‼️一作目の反戦、反核のメッセージはどこへやら、雪山に閉じ込めたくらいでゴジラ退治にはならないとは思うけど、まぁ、実質的に今作から始まった怪獣プロレスを楽しむ作品ですね‼️特に大阪の街を破壊しながらのゴジラとアンギラスの戦いは、以降、怪獣単体での破壊シーンはあっても、対決シーンは富士山麓とか平原になってしまう東宝怪獣映画においては貴重‼️「ウルトラマン」シリーズのノリで楽しめる‼️
怪獣対決
前作と比べると音楽の力が無くなってしまった気がする。その為か、ゴジラに対する恐怖感が薄まっている。しかし、大阪城でのアンギラスの闘いは、スピード感があって何とも小気味良い。首への噛みつきで倒すという野生味溢れるスタイルは、今のゴジラに取り戻して欲しいところ。
それにしても、こんな昔から死亡フラグというものが有った事にびっくり。また、雪崩を誘発するための攻撃は、まさにトップガンマーヴェリック。
非常に残念
【第一作でゴジラを粉砕したオキシジェン・デストロイヤーと開発者芹沢博士亡き後、如何なる方法でゴジラを斃すかが焦点となった作品。】
■今作では、第一作でオキシジェン・デストロイヤーにより斃したゴジラが、”ゴジラはまだいるかもしれない”と言う台詞通りに再登場し、大阪をアンギラス(アンキロサウルス)との地上戦により壊滅状態にする。
それにしても、大阪城はゴジラに壊され、その後ゴモラに壊され、さぞや修復作業は大変だった事であろう。
今作でゴジラを閉じこめた雪崩作戦を、”そんな馬鹿な‼”と言う人もいるかもしれないが、爆薬で起こした雪崩ならば、表層雪崩ではなく深層雪崩であると思うし、威力は凄いと思われる。
ゴジラに向かって決死隊のように飛来し、雪山の氷壁にミサイルを撃ち込む特撮シーンや、大阪が壊滅するシーンなどは、製作年を考えても凄い。
但し、雪(と言うか、巨大氷)に閉じ込められたゴジラが死に至ったかどうかは、定かではないよな、と思った作品である。
いろいろなものの原型がわかるかも
ゴジラ第一作に続いてこちらを観ました。そんなに間はあいてないようですが、特撮はよくなっていました。ゴジラを遠くから観たときは相変わらず人形っぽさが出てしまいますが、近くで見たときなどは迫力があり、ほかの破壊されたり、水が溢れたりといった部分はかなりリアルになってきていました。ストーリーとしてはマイナスワンを彷彿とさせる飛行機乗りの人間関係が中心に。ゴジラ映画はゴジラを描くというより、ゴジラはあくまでも得体の知れないもので、それに対する人間達を描いたものなんだなとあらためて思いました。
で、死亡フラグが非常にわかりやすかった。これより前の映画でも死亡フラグは立っていたのかなあ。今の人たちにはわかりすぎてしまうけど、当時の人たちは気づかなくて驚いたのかも。そういうことを考えながら観るのも楽しかったです。
これは酷い
前作で死んだゴジラが再び。
ゴジラは一匹だけでは無かったらしい。そして、他の怪獣も出現。前回、ゴジラを葬った方法は考えた学者毎今は無く・・・・どうする。
ここまでは良いんだけどさぁ。
ゴジラの第一発見者とは言え、民間の漁業会社パイロットに状況説明をして貰った後、彼らを同席させたまま対策会議・・・・えぇ・・・・・。
以後もゴジラが上陸、灯りに反応する為に照明を制限した町を受刑者用護送車が走る。いや、流石に中止させるだろ。しかも、手錠もせず、受刑者同士を腰紐とかで繋げるとかもせずに脱走され、逃走に使ったガスタンク車の事故で火災が起き、沖に去ったゴジラが再び上陸。
舞台が北海道に移り、北海道支社に異動してきた最初の民間機パイロットも何故かゴジラ捜索に参加。挙げ句、元軍人だったからと言え、航空自衛隊のジェット戦闘機を操縦したり、もう一人の民間機パイロットはプロペラ機でゴジラを煽って返り討ち。最後はゴジラを雪で生き埋めしたから「やっつけた!」で完。なんじゃそれ。
新しい怪獣を出した意味も殆ど無く、一作目が受けたから急いで作ったのが丸わかりの駄作。
名作になれなかった凡作
怪獣同士のプロレス対決、航空機での応戦など怪獣映画の定番を生み出した作品
昭和シリーズの相棒となるアンギラスのデビュー作でもある
だが、人間ドラマが薄く、悲壮感も足りない
おバカな囚人のシーン、あれいる?
最後の特攻も人命軽視でたくさんパイロットが亡くなっているのに悲壮感も足りない
昔の映画だからそこまで求めてはいけないが、初代と見比べるとどうしても見劣りする
ゴジラ二作目記念すべき怪獣対決、円谷英二が特技監督というクレジットを確立した作品。
ゴジラファンからも評価が分かれている作品。初代ゴジラとは別物くらいの激しい怪獣格闘は必見!(初見で観る時は、是非ゴジラという“怪獣”の概念が無い中に公開された「ゴジラ(1954)」と、その数ヶ月後にこの作品が公開されたという事を想像しながら見ると面白い。初代ゴジラを想像していた観衆は、きっと動きの軽快さに唖然としたのでは無いだろうか)
独自採点(62):市街地ミニチュアセットスケール1/ 25(超全集)
制作田中友幸、監督小田基義、特技監督円谷英二、音楽佐藤勝
通称:逆ゴジ・登場怪獣:アンギラス・防衛:防衛隊/(クレジット無し)「海上防衛隊」・昭和30年4月24日封切り・白黒スタンダード/上映時間:1時間22分・上陸地(大阪湾此花区)・破壊地(大阪湾岸工業地帯・大阪城)・特撮爆破炎上破壊規模B(初ゴジよりは少なめ)
特徴:目線が対戦怪獣向けに正面、首のシワ覗き穴目立ち、尻尾が柔軟、背びれ3番小さい、足指4本。
特技監督というクレジットが使用され東宝怪獣映画における怪獣対決パターンを作った歴史的作品。ミニチュアセットも新設された東洋一の第8・9ステージに大々的に製作された。ただし、初代ゴジラからわずか5ヶ月後の公開だったことからも準備不足が否めない作りかも知れない(製作の田中プロデューサーも後年述懐)、途中ゴジラの被害報告する場面では前作の映像をそのまま流用、肝心のゴジラ出演シーンが・・・初代ゴジラに比べやはり物足りないというのが正直な印象。第一作目がこの出来だったらゴジラの歴史は続かなかっただろう。
出演者は志村喬・千秋実・土屋嘉男・小泉博はじめ黒澤組の名優が出演だが、全体的に暗いトーンでかつホワットした映像はクリアだと着ぐるみが陳腐に映る事やフランス映画の影響もありソフトフォーカスレンズを使用し狙って撮影したとも言われている。
対戦怪獣のアンギラスも元々は別の作品となる予定だったらしいが、前作の歴史的大ヒットによりゴジラの対決怪獣第一号として登場する事に。ただしゴジラスーツは格段の進化を遂げて格闘シーンでは驚異的な動きを見せる(スーツの進化もあるが、撮影助手のミスにより高速度撮影するものを微速度撮影=コマ落とししてしまった。結果として初代では考えられないような怪獣同士の格闘戦が繰り広げられる事となる。初代ゴジラに圧倒された人達はこの動きのギャップをどう感じたのだろうか?初ゴジ鑑賞者の感想は色々な書物にも記載があるがぜひ知りたいところだ)。
戦う舞台は大阪、前回が東京だった事もあり大阪経済界から「ぜひ大阪に」と言う中々政治的な大人の事情も垣間見える。
作品としての統一感に欠ける点はあるものの、特撮は地下鉄の天井が崩れ大量の水が流れ込むシーン(東宝の大プールは未完成だが、のちに「ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐」のために大プールを設計した井上泰幸こだわりのシーン)や大阪城破壊シーン(大スタジオ完成)など見応えは十分、以降の東宝特撮映画の地盤を築いた作品とも言える。
特撮シーンには円谷英二特技監督のこだわりや実験的な取り組みが各所に見られ、特撮班がやりたかった事が詰め込まれているだけに、本編班とのギャップが大きいというのが全体の印象。
※ゴジラの上陸は小プール(ひざ下)。
観客動員はゴジラ作品の中でも3位(観客動員数834万人)と映画が娯楽の中心だった頃の動員数は今更ながら驚異的。色々と歴史的には意義深い作品ながら、短期間で作られたこともありゴジラの登場シーンが少ないなどで評価は厳しめ。また、1953年東京有楽座・大阪南街劇場で幕を開けたシネマスコープ採用館はあっという間に広がるが本作はまだスタンダードサイズである。
時代:人口:9千万人(封切料金¥130※実勢価格約半額)、キネマ旬報(定価¥140)、団地の平均家賃は47,900円、TBS開局、後楽園遊園地オープン、都内にスモッグ発生(毎日ムック)、初のアルミ1円発行、ソニー初のトランジスターラジオ発売、平均寿命(女性68歳・男性64歳)、ラッシュアワーの押し屋アルバイト初登場、銀座交差点は都電走り銀ブラをする人の風景、日本電信電話公社が料金前納式の公衆電話機を発売、 トロリーバス池袋駅 - 千駄ヶ谷四丁目間・千駄ヶ谷四丁目 - 渋谷駅間開業(68年廃線)、物価ガソリン¥37/1ℓ・ビール大瓶¥125円/自動車保有台数16万台、前年末からの神武景気で高度経済成長著しい時期、英国が水爆製造開始、東京国際空港(羽田空港)の先代のターミナルビルが開館、ワルシャワ条約機構結成=冷戦激化、 日本住宅公団(現在の都市再生機構)設立
好きなショット:44’大阪城門越しにアンギラスと睨み合う
初の怪獣プロレスと戦後の人々のたくましさ
◯初の怪獣プロレス作品
初の対戦怪獣登場。
開幕後すぐに対戦開始。
怪獣プロレスとしては発展途上だが、
野生の狂気と荒々しさを感じる
俊敏性のある戦いが見どころ。
◯戦後の人々のたくましさ
街や仕事場を何度破壊されても
決して暗くならず前向きに立ち上がる
姿に戦後の人々の強さを感じる。
◯逆ゴジ
初代同様の不気味な目と外側に
剥き出した牙が特徴。
怪獣プロレスを意識した中の人が
動きやすい着ぐるみの造形。
◯初代アンギラス
初の対戦怪獣。
全身に生えた棘が特徴。
身体中に脳髄が分散しており、
俊敏な動きが可能。
◯花婿さんこと小林
劇中で最も愛嬌のあるキャラ。
ゴジラとの戦いで殉職する。
△展開が少し単調
アンギラスとの対決やラストの
雪崩作戦まで同じことの繰り返し
であり、単調に感じる。
△初代との作風の違い
前作は戦争も想起させる重厚な
テーマを扱っていたが、今回は
戦争の影響を感じさせながらも
人間ドラマが主体の娯楽映画であり、
前作の作風が良かった人には
イマイチかも
見直すと素晴らしさがわかった
2作目のゴジラ
おバカな囚人、大坂の陣
ゴジラ退治には有効な手段がない!芹沢博士は死んでしまったし、唯一の最終兵器オキシジェン・デストロイヤーの作り方がわからないのだ。水爆実験の影響のためか、ゴジラは光に過剰に反応することを防衛隊に伝えた山根博士。とりあえず大阪から追い出す作戦に出た。もちろんイソジンや雨合羽は通用しない・・・そこへ脱走した囚人たちが火災を起こしたため・・・
ゴジラ対アンキロサウルス(通称アンギラス)のおかげで大阪城は破壊。市内は焼野原となり、さながら戦争の爪痕の悪夢を再び経験することになった。漁業会社のパイロット月岡、小林たちは北海道支社に向かい、あろうことかそこでも逃げたゴジラを発見する。
とにかく前作の素晴らしさを踏襲し、モノクロームの効果もあって大阪決戦はかなり緊迫感、悲壮感が漂っている。アンギラスとの戦いはプロレスというより相撲のような雰囲気だったけど、何のため2匹は大阪にやってきたのか!?破壊するためか?このやろー!
この前半部分はとてもよかったのに、雪山での決戦がちょっと気になる。小林なんて月岡に恩を返すつもりだったのかもしれないが、武器も持たない民間機でそこまで追い詰めることはない。ただ、皮肉なことに雪山に激突したため、雪崩でゴジラを封じ込めるというヒントを与えてくらたのだった。
そして防衛隊の攻撃によるクライマックスとなるわけだが、これがもう特攻隊そのもの。爆撃では雪崩を誘発できず、次から次へと戦闘機が雪山に激突していくのです。なんだよ・・・こんな特攻精神なんか見たくなかった。島の名前も神子島だし、神風が吹くのを待ってたかのような。前半だけでやめときゃ良かったのに・・・
ただの怪獣に成り下がってしまったゴジラが哀れ
怪獣プロレスの始まり始まり~
①若いときは小泉博、男前だったのですね。でも声が高くて男前ではなかったのが残念。②千秋実がもうけ役。実は親友のフィアンセを好きだったことが判るのはよくある設定だがホロッとさせられる。③子供の頃に見たら信じ込んでいて成長してから裏切りただろうてど、この年になって観ると「はぁ?」が多出。先ず、何故ゴジラとアンギラスが伊良戸島でケンカしてたら説明まるでなし。偉そうな先生が、「アンキロサウルス=アンギラスで肉食の暴竜、体長は100メートルくらい」現代では絞首刑ものですな。アンキロサウルスは草食のおとなしい恐竜ですし、怪獣でもありません。④ゴジラとアンギラスの戦いは撮った写真を早送りしたのでしょうが、怪獣の闘いは本来これくらいのスピードでなされるはずで後のもったりしたやり取りに慣れた目には新鮮でした。火炎噴射で焼き殺されると聞いていたのに、本当の死因は首を噛み切られるのね。⑤結局大阪も壊滅的な被害を受けるのてすが、中之島大壊滅で御堂筋線淀屋橋駅が水浸しになってしまいました。壮観ん。桑原桑原、お決まりの大阪城破壊(これが怪獣映画最初?)ですが、この後「キングコング対ゴジラ」での小田原城破壊、まるっきりオマージュの「ガメラ対バルゴン」の大阪城を挟んでの死闘、「ウルトラマン」のゴモラによる破壊と映画的記憶は引き継がれて行きます。⑥初代「ゴジラ」も厳密に言えば映画としては傑作ではありません。が、この作といい当時の東宝が怪獣映画おいうジャンルを造り上げようという意気込みが感じられて宜しい。⑥初代「ゴジラ」に比べ、大阪があんなに壊滅したのに確かにお気楽ムードですが、それはやはり大阪人の方が明るくたくましいということで。⑦氷詰めになったゴじラは次の「キングコング対ゴジラ」で華々しく氷山の中から出現してくれます。⑧この頃からゴジラは毎年日本に上陸する台風扱いになっていくのがわかります。新型コロナウイルスと人類が共存していくか、はこれからの課題ですが、ゴジラと日本人は昔から共存していたのですね。
全32件中、1~20件目を表示