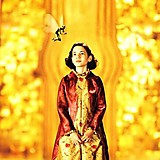硫黄島からの手紙のレビュー・感想・評価
全106件中、81~100件目を表示
クリントイーストウッド監督、ありがとう!!
加瀬さんが出るというので観ました。
アメリカ人が描く戦争
外国の監督が日本を撮ってくれる。すごいこと
日本人として勉強になる(知っておくべき)歴史作品
H25.4月、安倍首相が硫黄島を訪問し、日本兵の遺骨収容作業を視察。
との報道があったものの、恥ずかしながら硫黄島について、
歴史知識がなかったことから、歴史を学ぶ上でも本映画を観ました。
同じような人がいれば、本映画を観て勉強するのはいい方法だと思いますよ。
1.硫黄島への米兵上陸
米兵による島への上陸の様子は、ノルマンディ上陸を描いたプライベートライアンとは
異なり、ある程度島への上陸を許してから一気に銃撃といった具合。
これは栗林忠道大将の戦略。
2.トンネル(要塞)作戦
この戦争で、日本軍での状況は圧倒的不利。
日本本土からの支援(増援)はなし。戦力(軍事力)の差は歴然。
そこで栗林大将の作戦は、要塞を徹底分析しそこを拠点とすること。
3.日本兵の忠誠心
天皇陛下万歳などと声をあげる集団自決シーン。
実際に映像で見るのは個人的に初めてでした。
多くの兵士が天皇陛下万歳と叫び、銃などで自決していくシーンは
衝撃を覚えました。
簡単に映画鑑賞後気になったシーンをメモ書きしておきました。
関連映画の硫黄島の父親たちの星条旗も観てみようと思います。
かっこ良くあり、かっこ悪い日本が分かる
興味深く楽しめました。
アメリカ視点の1作目と同じくですが、両国人の人間的な優しさと残酷さをどちらも見る事が出来ると言う点がすばらしいと感じます。家族を思う気持ちや時に見せる敵兵士への優しさ(詳細は伏せますが)、といった点はやはり人間には愛があるんだなと感じますし、容赦なく人を殺したり日本の全体主義的な「お国のため精神」に関しては本当に愚かな国民だったんだなと、ある意味フェアに描かれている点が良いです。
顔は泥に汚れて、服もぼろぼろ、頭は坊主で首周りに覆いのついた帽子をかぶっている典型的な”日本兵”が描かれているところも不思議な安心感というか、ちゃんと作ってるなと言った印象です。
俳優さんもすばらしいです。
Ken Watanabeもお上手ですし、二宮さんがなぜ天才と言われるのか意味が分かりました。それにしても、ニノさんは坊主にしちゃうとなおさら幼いですね。普段はカッコいいのに、あの衣装でボーッと口開けているシーンを見ると決して”イケメン”とは言えないなーといった感じです。でもそれがリアリティを増していると言うか見てくれじゃなくて映画を作りたいんだな、と思わせてくれました。
マイナスは少しカットが多い(シーンの切り替わりが多い)のでもう少し話をまとめられないかなと思います。リアル日本男児顔が多かったのでもう少し華やかなイケメンを増やしたら何かうれしい。海外の人も見るだろうし。
とはいえ勉強になりました。
自然体を貫く二宮
二宮の大出世作ということで,前から見てみたかったのだが,戦争物は後味がどうしても悪いので敬遠していた。でも,思い切って見てみて,よかった。これが,ジャニーズの二宮?と思えるような役。アイドル的に何のメリットも感じられない。ヒーローとは真逆で,まったく格好よさはなく,むしろ弱く情けなく惨めで,これ以上の汚れ役はないだろう。けれど,それがなぜかはまるのが二宮なのだ。彼は,この映画の主役かと思えるほど光っていた。「天皇陛下万歳!」の世の中にあって,二宮はいたって普通の人間だ。体制に逆らいはしないが,決して嘘で飾りたてた言葉は使わない。友達には本音でぶちぶち不平を言うし,人一倍生への執着も強い。格好良い軍人になる気も毛頭ない。ただ日本へ帰って,家族と会いたいのだ。それが,ひしひしと伝わってきた。友達や上司の死を目の当たりにしてきても,あきらめにも似た表情を貫いてきた二宮が,ラストで感情を爆発させるシーンは圧巻だった。自然にあふれ出る大粒の涙,初めて怒りと憎しみを露わにアメリカ兵に立ち向かう姿が,目に焼き付くとともに,戦争そのものの悲惨さを強く訴えかけてきた。イーストウッド監督も本当にすごい。日本人の監督以上に,軍国主義の日本をリアルに描き,日本とアメリカを公平な目で見ている。伝えたかったのは,ただ一つ戦争のむごさと,繰り返してはいけないということだろう。そして,日本の俳優陣の魅力をあそこまで引き出す手腕もお見事である。まさにプロの仕事である。
ただ一つ,リアリティーに欠けたのが,二宮が結婚していて,子どももいるという設定。パン屋も似合っていないかな。年齢的には無理はないのだろうが,坊主刈りの姿は,どう見ても学生にしか見えない。共演した加瀬亮のように待っている母がいるとか,せめて恋人がいるという設定のほうが,見ている方がより感情移入しやすかったように思う。まあ,全編を通して言えばたいしたことではなく,減点しても満点である。
当時の日本軍人の態度や行動の描き方がいい
総合:75点
ストーリー: 75
キャスト: 70
演出: 75
ビジュアル: 70
音楽: 60
硫黄島の戦いは、助けの来ないことが最初からわかっている絶望の中で時間を稼ぐ捨石となる戦いであった。援軍も補給もなく、水や食料も乏しく、ただ洞窟の中で餓えと乾きに耐えながら侵攻してくるアメリカ軍と自分の死を待ち構える孤独な戦いだった。昔の硫黄島のドキュメンタリーで見た、敵に見つからないように外に出ることが出来ず、真っ暗の洞窟の天井から滴り落ちる水を一滴ずつコップに集めて物音を立てないように渇きを癒す孤独と恐怖。戦闘の場面やアメリカ軍に押されて後退していくような描写はそれなりであったが、そのような絶望の中での兵士の忍耐をもっと描いて欲しかったと感じた。普通の戦争ではない、硫黄島の玉砕戦とは何かという意味での独自性が欲しい。
日本の軍人や憲兵の倣岸な態度や、当時の価値観に染まりまくって命を粗末にする兵士の姿勢、理屈ぬきで自分の価値観を押し付けて上官の命令をすら無視する士官というような描写は痛々しく面白かった。本当にこのころの日本はひどい国だったと思う。最初から全滅覚悟の作戦命令、無謀な突撃、自決の強要。敵と戦って死ぬのならまだ仕方ないが、その前に自国の指導者たちの愚かさがまず目立つ。国の歪んだ教育がこのような人々を育み、それが悲惨な戦争につながり、そして必要以上に悲惨な戦闘を生んだ。戦闘の場面よりもこのような描写をきっちり入れているところがより私には興味深かった。戦争が悲惨というのは結果であって、その原因はこのような人々なんだろうと感じる。
少し気になったのが日本軍とアメリカ軍の捕虜に対する対応。日本軍は負傷したアメリカ軍兵士に貴重な薬を分け与えるのに、アメリカ軍は投降した日本軍捕虜を殺す。別にこのようなことが嘘だったとは言わないが、この映画でわざわざこんな場面を入れる必要があったのだろうか。ちょっと不公平な描き方だと思えた。
家族のために死ぬと決めたのに・・
映画「硫黄島からの手紙」(クリント・イーストウッド監督)から。
「太平洋戦争最大の激戦だったといわれる硫黄島の戦いを
日米双方の視点から描く映画史上初の2部作」との紹介に、
期待を込めて2作品を観始めた。
(「父親たちの星条旗」が第1部、本作が第2部だったらしい)
観終わった感想は、間違って第2部の作品から観てしまったが、
日本人の私にとっては、この順番が正しい気がする。(笑)
さて「気になる一言」も、出来れば「対」として選びたいと思い、
メモをとった。その結果選んだのは「戦う男たちの死生観」である。
日本人側の視点で描かれた、戦争に対する戦い方(死に方)は、
「国のため、天皇のため」と言いつつ、本音は「家族のため」。
「家族のために死ぬと決めたのに、家族のために死ぬのをためらう」
この台詞が、私の心に突き刺さった。
「靖国で会おう」「来世で会おう」の台詞を残して死んでいく兵士、
手榴弾で自爆していく光景は、涙が止まらなくなった。
日本の男たちが、戦争に突き進んでいく理由は「家族愛」
そして、アメリカの男たちが、死を掛けて戦うのは「男同士の友情」。
死に対する意識の違いをもった人種が戦っていたんだな。
綿密なリサーチの賜物
ハリウッドで日本映画。
クリント・イーストウッド監督で、日本サイドから見た戦争題材で日本語で、日本人役者を使っての映画、と聞いて、どんな偏見と台詞回しなのか、と斜に構えて観ました。
一通り観て、これが本当にアメリカ人監督で作られた映画なのか、と感心しました。
本当は、アメリカの都合の良い方に解釈され、それを強調するかのような作品になると思っていたのに、
日本人が作る戦争映画と、特に差異は見られない映画でした。
決してアメリカ兵を賞賛するような描写も無く、むしろ日本兵の良い部分もきちんと表現してくれていることに、何だか日本人として誇らしく思いました。
役者陣も素晴らしい。
確かこの映画で、二宮くんがアカデミー賞の助演男優賞にノミネートされ、
賞レースに参加しないというポリシーのジャニーズと、「辞退しろ」「嫌だ」で、事務所と一悶着があったらしいと噂。
クリント監督は、二宮くんを「ジャニーズ」のタレントとして選んだのではなく、
俳優の一人として選んでいたのなら、ジャニファンでも二宮君ファンでも無い私でも、少し良いことだなーと思いました。
彼の演技は、個人的にも好き。
このまま国際派の俳優さんに成長して欲しいな、と純粋に思いました。
救いがない感じ
戦争の悲しみ
日本的な心を持つハリウッド映画
ハリウッド作品ながら全篇を日本語で押し通した偉業に拍手!
カメラ・アングルが素晴らしい。おまけにじっとしていることがない。カメラが動かなければ絵そのものに動きがある。「父親たちの星条旗」同様、大きなメリハリをつけずとも飽きさせない展開は秀逸。なんといっても特筆すべきは、これがアメリカの監督作品かと思えるほど日本映画になっている点だ。見方を変えれば、当時の日本国民同様、日本特有のモノの考え方と思っていたこと自体が間違いで、アメリカ人もどこの国の人も、国を思う気持ち、人を思う気持ち、家族を思う気持ちはいっしょなのだと改めて痛感させられる。
日本の作品も、大和だのゼロ戦だのの雄姿や、散り逝く者への賛歌だけではダメ。結局、そんな戦争映画の根底にあるものはカッコよさであり、ワタシが子供の頃、ゼロ戦や大和のプラモデルを作っていたのと何も変わらないことになる。日本の夏の風物詩でもある戦争映画も、本作のような芯のある作品にしてもらいたい。
全106件中、81~100件目を表示