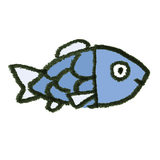ヤンヤン 夏の想い出のレビュー・感想・評価
全43件中、1~20件目を表示
繊細かつ複雑な人間関係をめぐる名作が、レストア版でより味わい深く
エドワード・ヤン監督は自らの脚本で、一つの家族をストーリーの主軸に据えつつも、家族内の関係性よりむしろ、家族を構成する各人と他者(異性であったり、仕事のつながりであったり)との関係の変化を並行して描き、群像劇のように展開させていく。
一家の構成は、小学生のヤンヤンを起点とすると、高校生の姉ティンティン、コンピュータ会社を共同経営する父NJ、別の会社に勤める母ミンミン、同居する祖母。身重の新婦と結婚式を挙げる叔父アディ。
ヤン監督の前作「カップルズ」では別れた男女がそれぞれ別の相手と付き合う流動的な関係が複数登場したが、本作で描かれるのは男1人女2人の相似な三角関係の3組。アディの元恋人が披露宴に乗り込んできて場の雰囲気を悪くする。NJは初恋の相手だったシェリーと偶然再会し、復縁を迫られる。ティンティンは隣に転居してきたリーリーの恋人ファティとデートに出かける。東京に出張したNJがシェリーと落ち合って若い頃のデートを回想する声に、台北の街をティンティンとファティが手をつないで歩く映像が重なるエモーショナルな名場面は、そうした関係の相似形を強調するとともに、恋の行く末を暗示してもいる。
今回の4Kレストア版により、俳優の表情や目の演技がより鮮明になり、人物の感情がより細やかに伝わるようになったが、それだけではない。カメラが窓ガラス越しに被写体を撮影したり、ガラス面や鏡面に反射した人物らを撮ったりする意匠を凝らした映像スタイルを一層際立たせる効果も生まれた。ヤンヤンの「僕が見るのは前だけで、後ろは見えない。だから真実の半分しか知らない」という言葉と考え合わせると、直接カメラに収める一面的で確立されたショットだけでなく、ガラス越しや鏡像、さらには写真やビデオ映像も加えて、人間という存在の多面性と不確かさを描き出す意図だろうか。
主要な登場人物の世代は、幼少、思春期、中年、老齢とバランスよく配され、結婚式、出産、そして葬式と、人生と家族の節目のイベントも描かれる。観る側もどんな世代であれキャラクターの誰かしらに感情移入しやすく、また年を隔てて繰り返し観てもそのときどきの人生のステージや状況によって受ける印象が変わってくる。観るたびに味わいが深まる、滋味豊かな傑作を最後に遺してくれたエドワード・ヤン監督に、改めて感謝の念を抱いた。
絡みもつれる群衆たち
タイトルしか知らずにずっと前から惹かれていた映画
NJ家族を中心に、ヤンヤンの視点、姉の物語、父の物語、叔父の物語、、、と想像以上に多くの人々のストーリーが広がり、絡み、千切れては再生する。群衆劇のようだった。
年齢も抱える問題もそれぞれなので誰に感情移入するかで受け取り方が変わりそう。
今回観たレストア版の「生きるということ、愛するということ。」という煽りは個人的には少し違うかな。
期待外れでも失望しても失敗しても リセットする必要はなく、ただただ続いて、ただただ続けていくしかない、という印象を受けた。
窓ガラスに映る被写体と、境目が曖昧で溶け込むような夜景を同時に撮る画がとても心に残る。
家族の体裁を保ちながらも 誰もが周囲に翻弄されて辛い思いを1人抱える中で、小さな結点となるヤンヤンがとにかく可愛くて。
片面しか見えないならその人のことを半分しか知らないってことだよね、という言葉にこの3時間のエッセンスが凝縮されていたように思う。
女子や先生からはいじめられ、でも仕返しもちょっとして、雷に打たれたように恋をして、蚊(風景)や後頭部の写真をぱしゃぱしゃと撮り、そのささやかな創作活動も学校では弄られて。
それでも小さな身体でリュックを背負って水筒をぶら下げて、言葉少なに眼を上げて。
彼がこれからどんな"見えない"世界を見せてくれるんだろうという楽しみを密かにじっと抱いた。
わたしももう年だ。
観る人を信頼した物語
「牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件」(1991) などで世界中に根強いファンを持ちながら2007年に59歳で亡くなった台湾の名匠エドワード・ヤンの遺作です。会社の経営難に苦悩する父、新興宗教に走る母、恋愛に悩む姉、そして隣人・親戚を小学生のヤンヤンから見た物語です。
これは観る人を信頼した作品だな。特に主人公が居る訳ではなく、また、人物の奥深くに踏み入る訳でもなく、明確な結論めいたものもありません。でも、或る時代の或る場所での様々な人生が鮮やかに輪切りにされます。後は皆さんで感じてねと言わんばかりの投げ掛けが決して投げ遣りではなく、観る者に委ねられるのがしっかり届きました。
また、日本も舞台の一部として描かれ、今は無き熱海のつるやホテルが登場するのが神奈川県民としては懐かしかったなぁ。
これもまた人生
台湾のお国柄と言いましょうか、あの、がなる感じのセリフまわしがキツい。
そういうシーンが多々あって結構しんどくなった。
この邦題、全然的を射ていないと思う。
これは、ヤンヤンの想い出ではない。
NJ一家のある時期を切り取ったものであり、
そこに悲喜交々があって、これもまた人生だなと、
観た人それぞれが感じる作品であろうと思った。
NJと元カノ(米国在住)、出張で日本に行き同じホテルに泊まるのに何もない。
そりゃ元カノも帰るわな、、、と思うし、
ティンティンのボーイフレンド(だった男)なんてカスだし犯罪者だし、
ヤンヤンはカメラでみんなの後頭部だけ撮っているし、
(自分では見えないでしょ?というのは気が利いたセリフだと思ったが)
幸せな家庭を切り取った作品ではなく、ある時期を切り取った作品なのだよな。
イッセー尾形さんの、時折日本語が入るセリフまわしがすごく良かったし、
彼の存在がなければ、約3時間はちょっと長いかなとも思った。
人生いろいろあるけど、生きるのって大変だけど、
自分だけじゃないよね、と、自分を鼓舞した(笑)
すごく良かった
1999年公開の台湾日本合作の、エドワード・ヤン監督のかつて大ヒットしたという映画が4Kレストア版で放映している作品。
公開当時私は「仕事人間」だったから、セミリタイアして、初めて見た。
25年経っているということで、やや古い感じは否めないが(まだスマホがなくポケベルを使ってたりとか、日本人の商談の相手イッセー尾形が若いとか)、そんなことは些細なことに感じるほど、内容は素晴らしかった。
一家を支える主人公のNJ、妻のミンミン、高校生の娘ティンティン、8歳の息子ヤンヤンを巡って、その祖母が昏睡状態に陥ったところから話が始まる。
内容は伏せるが、ティンティンとヤンヤンがよくぞこんな逸材が
という感じで、すごくよく演じていた。
特に8才のヤンヤンは、父のカメラで「人が見れないところを写す」と言って
後ろからの写真とかばかり(これが意味深)撮っていて良かった。
奥深そうなので、また見てきます。
リセットなき⼈⽣の、⾒えない”現実の半分”を想う
窓に反射する光、反射した窓から見えそうで、はっきりとは見えない風景。
逆に、ガラス越しでもはっきり見える風景。
真実が半分しか見えないこともあるけれど、
見えないものも信じて私たちは生きている。
そう考えさせる、ヤンヤンが父に投げかける言葉や、叱る先生の矛盾をつく言葉がとても深かった。
祖母に向けた言葉にも、彼が受け取ってきた愛情と、彼の受け取り方にこの上ない魅力を感じた。
希望ばかりではなく、どうしようもない絶望や理不尽さも現実として描写されていた。
それでも、半分しか見えない現実で、まだ見えていない半分に希望を託し、
やり直す必要のない一度きりの人生を大切にしたくなる。
そんな映画だった。
noteではYouKhy名義でもう少し詳しく書いています。
印象に残ったのはヒステリックな女性達
深い⋯
一期一会の映画
カンヌ映画祭への出品用として、日本人映画プロデューサー河合某がエドワード・ヤンに製作依頼したことが契機となって撮られた映画だという。最初は同じ台湾人監督ホウ・シャオシェンにお願いするつもりだったものの、たまたま台北にいたのがヤンだけだったことから白羽の矢が立ったという。河合としては前作『カップルズ』のような作品を期待していたらしいが、出来上がってきたシナリオはまったくの別物、ご覧のとおり非常に内省的な“家族群像劇”に仕上がっている。
主要登場人物の一人、コンピューター会社を経営するNJが、有名日本人ゲーム・クリエイター大田(イッセー尾形)との契約のため、台北と東京の二箇所で会談するシーンがあるのだが、おそらくヤンは河合Pとの製作打ち合わせ時のやり取りをこのシーンに生かしたに違いない。NJの息子ヤンヤンもそうなのだが、エドワード・ヤンの分身と思われるこの大田がこんなことを述べるのだ。「なぜ初めてを怖れるのか」
毎回毎回作風をガラリと変えることで知られるヤンだけに、(興行は計算しやすいのかもしれないが)『カップルズ』の二番煎じなど真っ平ごめんだったに違いない。イッセー尾形の台詞にはそんなヤンの強い想いが込められていたのかもしれない。全体としては今までとは全く違う雰囲気の映画にはなっていたが、大声で怒鳴り合ういい歳こいた大人たち、熱海つるやホテルの明滅する蛍光灯、未成年淫行が原因の殺人事件、(リンクレイターの『ビフォア・サンライズ』(95)や小津を意識したかもしれない)鎌倉?デートシーン…日本人受けしそうな(セルフ)オマージュカットが本作にも盛り込まれている。
なお本作は完成後、版権をめぐって台湾配給会社と折り合いがつがず、エドワード・ヤンの死後に台湾で初上映されたというから皮肉な話である。配給会社から172分の長尺についてなにかしら茶々が入ったのかもしれない。劇中のNJと大田の契約破棄にいたる顛末は、それを反映していたのだろうか。弟アンディの結婚披露宴で倒れ意識不明のばあちゃん(物言わぬ観客)に向かって話しかけるNJことヤンが「(観客に映画の趣旨が)ちゃんと伝わっているのか」気にかけるのも無理はないのである。
さて本作最大の問題はなんと言っても映画の原題『Yi Yi』であろう。後から誰かさんが付け加えた“1+2”なる副題は本稿では無視させていただくとして、日本語に直訳すると『一(いち) 一(いち)』である。日本人映画Pや台湾配給会社の干渉を「“いちいち”うっせぇなぁ」とヤンが感じていたのも事実だろうが、介護鬱にかかり山ごもりしていた奥さんミンミンに向かってNJがこう告白するシーンを覚えていらっしゃるだろうか。「君がいない間ぼくも青春をやり直す機会があった。でも結局あの時と同じような選択をしてしまったんだ」
名門女子校に通う長女のティンティンもまた、父親が昔の彼女にしたように、はたまた弟アンディができちゃった婚して昔の女を捨てたように、(外資系シングルマザーと同じ)尻軽娘の元カレにこっぴどいフラれ方をするのである。あの大田でさえも「私はマジシャンではない。全ての手札の並びを覚えてるだけだ」とトランプマジック(斬新な映画演出)のネタバレをするのである。『恋愛時代』製作当時からエドワード・ヤン自身の離婚問題が泥沼化していたようで、その時の暗澹たる心境を吐露したシークエンスだったのかもしれない。この映画に限らず、(アンディ叔父さん&ヤンヤンの復活劇を含め)現実の人生には同じような出来事が、世代を跨ぎなから永遠と繰り返されるのである。
「夢と現実は違うんだ」とファティはティンティンに叫んでいたが、(人間が変化を怖れるために)同じようなことが繰り返される業のような世界が現実ならば、せめて夢=映画では「ばあちゃんも知らないはじめてのもの」をみんなに見せて楽しませてあげたいと、廊下を飛び回る蚊や見ず知らずの人の後頭部に座する守護霊をカメラに映そうとしていたヤンヤン。それは、誰も見たことのない“一期一会”の映画を撮ることに生涯を捧げたエドワード・ヤンとどこか似ているのである。
この映画に惚れてしまいました
日本語タイトルが「ヤンヤン ・・・」なので映画が始まって少し戸惑った。でもわかった。とてもいい映画。3時間、だれない眠くならない飽きない、どころかドキドキして笑い胸が痛くなりながらずーーーっと見た。美しい映像が心に迫る、光、高層ビルをあんなに美しく見せることができるんだ。
登場人物の演技にとても感動した。とりわけヤンヤンの姉のティンティンの歩き方、顔のうつむき、動くテンポとか間(ま)が素晴らしいと思った。監督の指示なんだろうけれど彼女の力も感じた。ティンティンはほぼ常に制服を着ている。何でだろう?とも思った。初めてのデートで着ていた白いワンピースは可愛かった。友達のリーリーを尊敬し彼女の為なら何でもするティンティン。ティンティンは父であるNJのかつての大事なガールフレンドのような人になるのかな。
弟のヤンヤンは8才、日本であれば小学2年生か3年生。保育園とか幼稚園の頃から女の子は男の子よりしっかりして体も大きい、それはいつまで続くのかな。ヤンヤンは小柄な男の子だからでかい女の子にちょっかいされてる。でも彼は哲学的に考える男の子。カメラで写される対象は半分でしかない、もう半分(すなわち彼にとっては裏面)は見えないと言う。なんて素敵な視点だろう。ヤンヤンを父親のNJは自分ととても似ていると思っている。NJは仕事関連でイッセイ尾形が演じる日本人と羨ましいほどの友情関係を作った。イッセイはベートーベンのソナタ「月光」をピアノで弾く。その時、ティンティンのピアノもNJは思い出したと思う。
おばあちゃんの存在は孫にとってとても大切だ。だからティンティンの指に残された紙の蝶も、ヤンヤンがノートに書いたおばあちゃんへの文章も本物でキラキラしていた。NJが妻に言う言葉にどきっとした:人生をやり直そうなんて思わなくていいんだ。
そうするには人生はあまりに短い。
エドワード・ヤンの死生観を感じる傑作
3時間の尺を心配していたのですが、全くの杞憂でした。飽きることなく豊かな時間を過ごしました。
定置カメラやシルエットなど芸術的なショットの連続なのですが、中身は下世話で泥くさい日常をしっかり描くこのギャップ。
父の若き日の異性への目覚めや恋心を、息子や娘が追体験する描写の巧さ。
特に気象についての授業で、雲が絡み合い雷が生まれるといういかにも暗喩的な説明の後、息子が同級生の下着を見てしまうショット。初々しいというよりも少し後ろ暗いこの描写を入れる監督の懐の深さは凄いです。
「映画が発明されて人生が3倍になる」と言っていた、娘の初恋の青年は結局実人生でもつらい体験をすることになります。
イッセー尾形のキャラクター造形がまた素晴らしい。当初やや怪しげなカリスマ的雰囲気をまとっていますが、徐々にビジネスを超えた人間的魅力を表出していました。一方でアジア人同士が英語でビジネストークする際の、「何て言うんだっけ」とつい日本語を挟んでしまうというようなリアルさもうまかった。
エドワード・ヤン監督は本作完成の頃に癌を患い、7年後に逝去されています。等身大の人々を見つめる視線に達観した何かが感じられる気がしました。
エドワード・ヤン監督ありがとうございました!
エドワード・ヤン監督の名作と聞き、勇んで行きつけの映画館に行った。ランチでビールを飲んだこともあり、最初の1時間でちょっと眠くなり、幾つかの場面をうつらうつらで観てしまった(ごめんなさい!監督)。だが残りの2時間は目が冴えてしっかり観た。ヤンヤンより父親のN.Jや姉の恋模様が中心だったが、それぞれの心の機微が上手く表現されていて印象的なシーンが多い。弟夫婦のドタバタも含め、男と女は古今東西すったもんだするものなんだなぁ、と実感。ラストにおばあちゃんは復活したかと思いきや姉が見た幻だったが、葬式でヤンヤンが亡きおばあちゃんに投げかける言葉に家族がしんみりするところも良かったです。
人生は人それぞれで100人にいれば100通りの人生がある。そして、当たり前の日常が愛おしくなる。そんな映画でした。
2000年頃の台北もそれなりに豊かだ。台湾は独自の経済発展もあるが、日本、アメリカ、中国の良いところをうまく取り込みしたたかに強くなったんだなぁ、とも思った。高市発言で緊張も走ったが、いつでも気軽に旅行に行ける隣国であって欲しい。
ヤンヤンのように生きたい
今年最後に観た本作は、2000年に放映された台湾と日本の合作。
3時間近くもあって、とにかく長い。
座り心地の良くない椅子で鑑賞したので、激疲れです。
ヤンヤンの家族のそれぞれの事情がなかなか切なく、全てに共感できた。
その中でも特に、純粋なおとうさん…イッセー尾形演じる日本人の大田とのやり取りが特に印象的でしたね。
また、劇中の台詞「映画は人生を2倍楽しくする」にも共感。
切なく悲しくなりがちなストーリーですが、ヤンヤンを見てたら元気が出る。
8歳のヤンヤンは家族の事情を知らないけれど、少なくとも自分なりに考えて毎日を生きています。
「複雑に考えず、ヤンヤンのように飄々と生きよう、来年も…!」
…と自分も思いました。
余談ですが、手塚治虫に影響されたというエドワード・ヤン監督、ヤンヤンの部屋にアトムの人形がありましたね。
禍福は糾える縄の如し、だから大丈夫
伝説の名作と謂れのある名作を
いささか構えつつ臨みましたが、
結婚式の場面から、すべて忘れて、
あたかもわが事のように見入ってしまいました。
作品クオリティや完成度云々は、
プロの方が25年間あちこちで表明されていますから、
いまさら申すまい。
子供、若者、大人、老人
人生の四季折々のイベントが
めくるめく同時進行で
親しみやすくユーモアを交えて
展開されていきました。
見終わったあとは、じぶんのこれまでの人生や
関わってきたまわりの人々に
想いを馳せることができました。
映画を観て、それでおしまい、じゃない。
わたしの人生は、これからまた新しい。
いつもが初めてというセリフ、イッセー尾形が印象的
幸も不幸も、交互に来るけど、決して恐れないで
勇気を持って人生というプールに飛び込もう!
ヤン監督の見事な集大成でした。
とかく人生はままならぬ。邯鄲の夢の如し…
冒頭のシーンとラストシーンの対比が見事です。
ある種、もしもその選択をやり直せたら物なのですが、パラレルワールドに逃げず、現実世界でそれを成し遂げる手腕に感嘆しました。
しかも登場人物それぞれが!
やがて夢と現実が微かに混じり合うような余韻も最高でした。
それを表現するには3時間の長さこそが必要。エドワード・ヤンの鬼才っぷり本作に尽きるの感がありました。
配信されていないようなので、見逃したらこの映画を観ることは生涯無いかもしれないとの焦りでなんとか時間を作って鑑賞しました。
観てよかった。
余談ですが、制服と、お別れと、今年観た全然違う2つの映画を連想して、個人的に年の瀬感を堪能してしまいました。
そして余談をもう一つ…
山手線のホームに喫煙所があったことをスッカリ忘れていた自分に驚きました。
私こそ、思えば遠くへ来たもんだ…
既視感のある風景Familiar-Looking Landscapes
公開時(2000年)は観ていない。
今回初めて観た。
台湾の街並みは、日本とよく似ていて
2000年ごろの街並みは、
個人的には既視感がある。
そんな中で
ある家族に起こった出来事を
淡々と描いている。
インターネットはあったけれど
SNSはおろか、ブログもなかった。
メールはあったけど、
携帯電話は普及途上。
なので、人と人とのやり取りは、
距離も時間も余白がある。
家族一人一人に起こった出来事は、
伝わらなかったり、
伝わっても時間をおいて当人から語られる。
今みたいに、ネットの衆人監視ではなく
考え、行動する事に
成否も含めて一人一人の判断が
まだゆっくりとあった時代。
(書いている私は56歳です)
この映画は良くも悪くも
令和の今では成立しない。
正確には、現代の設定では成立しない。
2000年ですら
四半世紀前ですら、
大きく仕組みが、
人と人との営みが変わった事を
思い知らされる。
早川千絵監督の映画「ルノワール」で感じた
同じ事を考えてしまった。
一つじゃないと思った既視感は
おそらくこれなんだろう。
令和の今、観たからこそ
時代との
時間との距離感を
強く感じた作品になった。
I didn’t see it when it was first released in 2000.
This was my first time watching it.
The streets of Taiwan look very similar to those of Japan, and the cityscapes around the year 2000 give me a strong sense of déjà vu, personally.
Within that setting, the film calmly depicts the events that happen to a single family.
The internet existed, but there was no social media, not even blogs.
Email was available, but mobile phones were still in the process of becoming widespread.
Because of that, interactions between people had distance, time, and space to breathe.
What happened to each member of the family was sometimes not communicated at all,
or, even when it was, it was spoken about later, by the person involved, after some time had passed.
Unlike today’s environment of constant online surveillance by the masses, this was a time when thinking and acting—and taking responsibility for success or failure—were still matters of individual judgment, made at a slower pace.
(The person writing this is 56 years old.)
For better or worse, this is a film that would not work if made in Reiwa-era Japan.
More precisely, it would not work if set in the present day.
Even the year 2000—only a quarter of a century ago—already feels distant enough to remind us just how drastically the systems of society, and the ways people relate to one another, have changed.
It brought to mind the same feelings I had when watching Renoir, directed by Chie Hayakawa.
The sense of déjà vu I felt, which I didn’t think was just one thing, is probably this.
Because I watched it now, in the Reiwa era, this became a film that made me strongly aware of the distance between the era it depicts and the passage of time itself.
退屈で眠い…
「お互い何が見えているのかわからないとしたら、どうやってそれを教え...
全43件中、1~20件目を表示