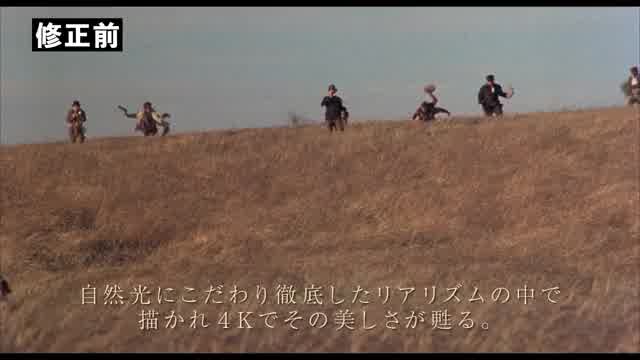天国の日々のレビュー・感想・評価
全62件中、1~20件目を表示
この内容の密度と深度でたった94分なの凄くないですか?!
この映画が、マリック監督の前作にしてデビュー作『地獄の逃避行』改め『バッドランズ』と同じ上映時間94分というのは、考えたら凄いことではないか。『バッドランズ』も神話的、哲学的な広がりと美しさを備えた作品だったが、こちらはより複雑で、より雄大で、神話性も増している。マジックアワーでの撮影が伝説化しているように、こだわり抜かれた映像美も圧巻で、正直『バッドランズ』ほど身近に引き寄せて愛でることができない、なんだか人として格上だと感じずにはいられない作品だと思っている。にも関わらず、人間関係の描写は過不足なくまとめていて、94分というほどよい短さに落とし込んだ。もちろん予算やスケジュールの都合もあったのかもしれないが、難解な長い映画を作るよりもはるかにややこしくて難しいことをマリックは本作でやってのけたように思う。
マリック監督監修の4Kレストアで、表情はより繊細に、風景はより美麗に
たまたま数年前NHK BSにてフルハイビジョン画質で放送されたレストア前の「天国の日々」の録画が手元にあったので、見比べることができた。夕暮れ時の麦畑でのシーンを日没直前の約20分間に撮影するなど、自然光を活かした映像でほぼ全編が構成されているため、従来版では表情や風景に薄暗い膜がかかったように感じられるシーンもあった。テレンス・マリック監督が自ら監修した4Kレストア(修復)により、膜がきれいにはがされて見通しが格段によくなった印象だ。リチャード・ギア、ブルック・アダムス、サム・シェパードら主要キャストの表情からはより繊細に感情が伝わり、麦の穂の黄金色が風に揺れて微妙に変化するさまなどの風景もより美麗に見えるようになった。
劇場に足を運ぶ前に4Kレストアの効果を知りたいという方は、“『天国の日々 4K』修復前・後比較映像”で検索してYouTube動画を見てみるといい。これは1080p画質だが、4Kのテレビやディスプレイが手元にあるなら、"Days of Heaven 4K trailer"で検索してみよう。やはりYouTubeで英語版予告編の1分半と2分の4K動画2バージョンが見つかるので、より高精細な映像で4Kレストア版の美麗さをチェックできるだろう。
なお、題の「天国の日々」(Days of Heaven)は聖書に由来し、「天が地を覆い尽くす日」を意味するのだそう。ほかにもイナゴの襲来などのように聖書を元にした要素がいくつかあるので、物語に込められた寓意をより深く理解するには、鑑賞後にでも関連情報にあたってみるといいだろう。
イナゴ
映像は圧巻
やればできるのに
何もない、でも美しい
イメージが機能を放棄して、お飾りに
若い頃のリチャード・ギアをみようと劇場に足を運んだが、サム・シェパ...
映像が美しい映画
リチャードギアの主役第一作だそうです。アメリカンジゴロでセクシーな大スターになる前です。上手い俳優なのにその後あまり良質な作品に恵まれずにいたのは大変残念だと思いました。この映画にはサムシェパードも出ています。個人的に大好きな二人が若くしてこんなに良い映画で共演していたのを今まで知らなかったのが大ファンとしてとても悔しいです。
リチャードギアの演じる貧しく浅はかな男に振り回される恋人が哀れです。その恋人に想いを寄せ騙される裕福な余命少ない男も悲しいです。この悲惨なストーリーを美しい自然を映像が綴っていきます。私はこの映画は間違いなくサムシェパードとリチャードギアの代表作だと思います。私は感動のあまり2回映画館に足を運びました。
圧巻の自然美&映像美!!
1978年の作品でここまで圧巻の映像美を堪能できるとは!
テレンス・マリック監督、恐るべし!というのが所感。
主人公ビル役のリチャード・ギアはじめ、アビー役のブルック・アダムス、
チャック役のサム・シェパード、リンダ役のリンダ・マンズ、
みんなカッコいいし美しい。
演技も素晴らしくて、物語から目が離せなかった。
最初は1910年代の農場での生活を、美しい自然美とともに把握。
私の思考のクセだが、トイレはどうしているのだろう?と、つい思っちゃう。無粋。
麦畑は大変手がかかりそうだが、人々が生き生きとしている。
アビーとチャックの結婚後は、
幸せそうな夫婦生活というよりは、ビルとアビーの仲をうたがうチャックの図。
昔も今も男女のいざこざは不変だな。これが人間なのだなと思う。
イナゴ🦗の大量発生からの、火事で麦畑が焼失、
そこからビルとチャックの関係性も急速に変化が!!
よもやビルがチャックを殺しちゃうとは。勢いだとしても。これも時代がそうさせたのか。
警察から追われるビル(アビーとリンダも一緒だが)が殺されるのも、まさかの展開。
そしてアビーとリンダはふたりに。
実に波乱に満ちた人生。
逞しく生きていくのだろうなというエンディング。
どこが天国の日々だったのか。
このあたりの理解は、パンフレットを購入したので、後ほどじっくり目を通すことにする。
それにしても、この時代にこの映像をつくれてしまうテレンス・マリック監督はすごすぎる。
正直、驚いたし、他作品も機会を見つけて鑑賞しようと思う。
「天国から見た、人々の日々」もあるかも
テレンス・マリック監督の、「シン・レッドライン」でとても印象に残っているシーンがある。
草むらを、片側を兵隊が通る。もう片側を、地元の人々が通ってすれ違う。
片や、死と隣り合わせ極限状況の戦闘員である兵隊たち、片や、「戦争」は目にすることはあるが他人事、日常生活をおくる地元の住民
互いに手を伸ばせば届く範囲の両者だが、内面の差は天と地ほど。
互いの世界の断絶ぶりが鮮やかだった。
これが同じフレームに収まっている。
天の高みから、人間を俯瞰していると思った。
「天国の日々」の、川岸で逃走中のビルが警官に追われ銃撃され阿鼻叫喚のシーン、対岸では、優雅にピクニックの人々。何事かと指さして見ていたりする。
この両者の断絶ぶりを見たとき、思い出したのが、先の、草むらですれ違う兵隊と地元の人のシーン。
テレンス・マリックは、こんな風に、天からの視点で人々の営みを描きたい監督なのだろう、「天国の日々」の、語り手は大人たちの右往左往を傍から見ている幼い妹であるリンダ。彼女の語りは、おとなになってからの回想なのだろうが、客観的で他人事で、人間のありさまを高みから観察しているようだった。
「天国の日々」というタイトルは、聖書由来のようだがテレンス・マリックが(無意識に?)「天国から見た人々の日々」という意味合いも含んでいないだろうか。
(リンダにとっての農場生活が、『天国にいるような日々』だったという意味もありそうですが。)
「マジック・アワー」にこだわり抜いた美術品のような撮影も、日が昇り日が沈み、イナゴの大群に襲われる、大いなる自然の当然の営みに過ぎないが、ちっぽけな人間にはそれが全世界であるというのを淡々と描いてみせる天の人の思考の一端のような気がする。
自分が子供の頃、蟻と蟻の巣を観察していたのと同じようだと思った。
蟻には大変申し訳無いが、巣に水を流し込んだことがある。
そうしたら、小さい白い楕円の球を担いだアリたちがわらわらと巣穴から出てきた。
自分が好奇心で流したバケツの水は、彼らには大災害になってしまった。(申し訳ない)
その時の私は、多分テレンス・マリックの立場にいたと思う。
「バッドランズ」はなかなか時間が合わなくて見に行けないが、やっぱりそんな感じなのではないか。大昔テレビで観た記憶があるがよく覚えていないので是非見てみたい。
アビーが、どっちかというと口角が下がったファニー・フェイスで、何人ものオトコを惹きつける魅力ある女性に見えないのと、リンダがもうちょった可愛かったら良かったのにと個人的に思いました。
若いサム・シェパードが素敵で見惚れた。
リチャード・ギアは、粗野で計算高く、実はそれほど悪い男でもないのに頭が悪くて衝動的で取り返しのつかないことをしてしまう男にぴったり(「バッドランズ」の主人公もそんな感じだったような?)
撮影と音楽が素晴らしく、映画館で観られてよかった。
観て聞いて至福のときを過ごせました。
ストーリーはちっぽけな人間のありさまを描ければそれでよし、なものだった気がする。
余談ですが、エンドロールが長くなったのはいつのどの作品からだっただろう、この映画ではまださほどでもない。特殊撮影が大きく取り入れられた頃から?スターウォーズあたり?
ダンナが最近某映画を観てきて、「『エンドロールは二次元コードを読み込んで観てください』」っていうんだよ、驚いたわ~」と言ってました。笑える。
輝かしい映像の向こうにも手前にも、世界が広がっていた
アメリカが第一次世界大戦への参戦に踏み切る前の1916年、テキサス州北部の広い農場を舞台にした物語。この映画のポイントは、リチャード・ギア扮するビルと一緒に、シカゴから流れてきた妹のリンダ(扮しているのは都会の自然児リンダ・マンズ)が、ナレーターを務めたことにあったのではと思った。テレンス・マリック監督の前作「バッド・ランズ」と同じくセリフを少なくし、その分、ナレーションとして語られる手法がとられていた。
特に気になったのは、リンダが語った予言、前半には「最後の審判」が出てきた。後半の初めでは、悪魔が悪さをしたと聞こえた。その直後、一度は農場を去ったビルが舞い戻ってくる。一体、何のために。ビル、リンダと共に農場に流れてきた美しいアビー(ブルック・アダムス)を、ビルは愛しているのに妹と偽って若き農場主チャック(サム・シェパード)と結婚させた。そのチャックに死期が迫っているためだろう。案の定、旧約聖書に出てくる災難がやってくる。ただ、ナレーションの効果だろうか、比較的さらっと描かれる。
確かにモリコーネの音楽もよかったが、農場での小麦の収穫の後、フィドルを使ったアイリシュの音楽や、黒人の労働歌が聞こえた。西部の開拓に囚人として動員された、黒人による、ジャズの先駆けになったと思われる労働歌が想い出された。
そうなのだ、このセリフの少ない映画では、深刻なドラマよりも、ネストール・アルメンドロスによるひときわ美しい映像の一瞬が頭に残り、その分、背景にあるものを思い出させてくれる。おそらく、脚本を書いた若きテレンス・マリック監督の頭の中には、第一次世界大戦の前後に、東欧や南欧からアメリカにたどり着いた移民のことがあったのだろう。一つ気になったのは、テキサス州の北部は(秋にタネをまいて、春から初夏に収穫する)冬小麦の産地ではなかったか。ロケを行ったカナダのアルバータ州だと、ずっと北方に位置しているから(春にタネをまいて秋に収穫する)春小麦の産地だと思うけれど。
この映画は、撮影のあと、編集に2年以上もかかったようだ。本作品は、発表された頃の時代(1978年)を直接描いているわけではないのに、その10年間を代表する映画と言われている。すると、映画が作られたのは、ヴェトナム戦争の終焉の後、アメリカが一番苦しかった頃であったことに思い至る。川本三郎さんが見抜かれたように「大西部のお伽話」とすることで、一瞬の映像が長く記憶に残り、背景となった第一次世界大戦当時の西部だけでなく、それぞれの人が映画を観た頃をも思いださせたのではないか。幾重にも、奥行きの感じられる映画だった。
世界一美しい映画
予告編の「世界一美しい映画」の言葉につられて鑑賞しました。
全くそのとおりです。
とにかく、舞台となるテキサスの広大な麦畑の、
いや、麦畑に降り注ぐ光線の美しさに90分間釘付けでした。
ストーリーは恐ろしくドライな恋愛ドラマです。
物語としてはちょっと感情移入しにくいキャラたちの恋愛模様が描かれるのですが
若き日のリチャード・ギアを始めとした美形キャストたちがこの上なく美しい風景の中で繰り広げるドラマは、もうストーリーとかキャラとかどうでもいいとさえ感じました。
ただただ美しさに魅了されるばかりで。
その中でも唯一の胸キュンキャラは語り部である主人公の妹役でした。
いや~彼女のウルトラドライさに萌え萌えでした。
映画って本当にいいものですね。
余談ですが、パラマウントのマークって当時はこうだったのですね。
天と地の物言わぬ相克そして融和
「光は白銀の葉にやどり、梢こずえを雲と化し、妙なる調べをつむぎつつ、行ったり来たりにいそがしい。地上の世界の欲望が、天を夢見るこの園で、たぐいまれなリラの音は、銀と緑をひびかせる。」(メイ・サートン作 武田尚子編訳 「一日一日が旅だから」より)
自然光のみを使った撮影で、微妙な色の変化をとらえきった映像はその多くが夕暮れ時に撮影されていますが、そのすべてが魔法にかけられたような陶酔感に満ち満ちています。
でも、この作品に命を与えているのは撮影の美しさだけではないように思います。
それは、地上の世界の欲望が天国を夢みたときにおこる悲劇と、それでもなお変わらず美しい光に溢れた四季を紡いでいく自然との、二つの物言わぬ相克と融和を見つめる詩的な視点なのだと思います。
地平線の彼方どこまでも続く広大な黄金色に輝く麦畑。微妙な薔薇色に染まりはじめた青空を背景に、風になびくアビーの美しい髪の流れ。青葉輝くまぶしい陽光の洪水の中での結婚式。休息の日々。天国の日々・・・・。主人公たちは、内面に不安や怒りや罪悪感を密に感じつつ、天地の静けさや、雷鳴の轟に耳をすませます。
日本公開当時、新聞で幻の名作として紹介されていて、今はなきシネマスクエア東急で初めて鑑賞。先日4Kリマスター版で久しぶりに鑑賞しましたが、その間も、LD,DVD等で繰り返し鑑賞しております。見るたびに至福の時間を提供してくれ、私にとって大切な1本となっています。
若きリチャードギアやサムシェパードの演技も光っていますが、何より監督のテレンス・マリックと撮影のアルメンドロス、そして音楽のエンニオ・モリコーネの仕事が素晴らしい傑作だと思います。
Days of Heaven の意味とは?
僕の大好きな「自然光条件下でワイドレンズで人物に寄り、背景の情景を見せる」という映像が各所に観られ、有名なマジック・アワー(日没後数十分の残照に空が映える時間帯)の美しさに魅入られる作品でした。
ただ、この「天国の日々」というタイトルが気になりました。原題も ”Days of Heaven" なので邦題の問題ではありません。さて、金色に輝く広大な麦畑を天国に例えているのでしょうか。成り上がって行く男の半生を天国の日々に見立てているのでしょうか。或いは、豊かではあるが常に孤独が付きまとう農場主の暮らしを皮肉に天国と呼んでいるのでしょうか。そこで、調べてみると、これは聖書に由来する言葉であると分かりました。そこで、聖書(我が家は無宗教夫婦ですが、聖書は「口語訳」「文語訳」「英語版」の3冊が揃っています)の該当箇所を見た所、曰く、
口語訳 申命記 11:21 (神の言葉を守ったならば)「そうすれば、主が先祖たちに与えようと誓われた地に、あなたが棲む日数およびあなたがたの子供たちの住む日数は、天が地を覆う日数のように多いであろう。」
文語訳 申命記 11:21 「然せば、エホバが汝らの先祖等に与へんと誓ひ給ひし地に汝らのおる日及び汝らの子等のをる日は数多くして天の地を覆ふ日の久しきが如くならん。」
どうやら、Days of Heaven とは上記の「天が地を覆う日」「天の地を覆ふ日」の事を指す様で、Heaven とはいわゆる「天国」の事ではなく、「空」と考えるべきものである事が分かります。つまり、Days of Heaven とは「空が地の上にある間」つまり永遠を意味するのでしょうか。
それにしても、日本語の聖書は何故こんなに分かり難いのでしょう。まるで、中学生の英文和訳の様な、日本語とは言えないぎこちなさで、分かって貰おうという気持ちが感じられません。聖書の言葉を一語たりとも疎かにすまいとするとこんな貧しい逐語訳になってしまうのでしょうか。
その点、英語版は、
DEUTERONOMY 11:21 "Then you and your children will live a long time in the land that the Lord your God promised to give to your ancestors. You will live there as long as there is a sky above the earth"
と、中学生でも分かる文章です。
さて、それではこの映画はなぜ "Days of Heaves" なのでしょう。改めて考え始めました。
光の映画
お隣席のオバさまから
「この映画て古いんですか?リチャード・ギア出てるみたいだけど・・・」
と尋ねられ
「そうですね、結構古いみたいですね」
と答えました。
マイケル・チミノ監督「天国の門」なら知っていますが、この映画の事はよく知りません。結構、昔の映画でびっくり!テレンス・マリック監督より撮影監督ネストール・アルメンドロスの方は知っていました。
「マスターズ・オブ・ライト」という撮影監督インタビュー集で、アルメンドロスがこの作品についてマジックアワーでの撮影(夕暮れから夜になるまでの時間帯)に触れていました。
当時のハリウッドでは基本、その時間に撮影しないのでカメラにブルーフイルターをかけて昼間に撮る事が多いそうです。これを「アメリカの夜」とも呼ばれています。トリュフォーの映画でもありましたよね。
その撮影方法に疑問を投げかけたのがマリック監督となるわけです。マジックアワーでの撮影は「暗殺のオペラ」でベルトルッチ監督と撮影監督ストラーロがルネ・マグリットの絵画「光の帝国」からインスピレーションを受けて青い空を再現するため夕闇の青い光をとらえた撮影を部分的に敢行しました。
「天国の・・・」場合は、ほぼ全編マジックアワーでの撮影❗️まさしくクレイジーだけど夕暮れのオレンジ色の光が美しい。
ところで隣のオバさまは時間を確かめるため、おもむろに携帯を覗いたりして映画が終わり字幕が出る前に席を後にされました。うーむ「プリティ・ウーマン」のような娯楽作を期待されたのかは謎です。
リチャード・ギア演じたビル役は「ミスター・グッドバーを探して」や「アメリカン・ジゴロ」での役と、そんなに違いはないですね。この頃のギアは攻めてるなぁ。当時の彼の演技はアグレッシブで結構好きです。
全62件中、1~20件目を表示