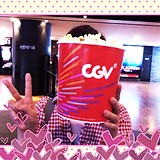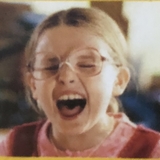海の上のピアニストのレビュー・感想・評価
全89件中、1~20件目を表示
一度も陸に降りた事の無い人生
世界の大きさ
この映画を配信で観て、劇場で観なかったことを後悔した。
劇場で観ていたら、まず音の違いで印象が変わっていただろうと思う。
ジュゼッペ・トルナトーレ×エンニオ・モリコーネ。
どうしても、ニュー・シネマ・パラダイスのことが頭にチラつく。
過去の栄光への郷愁、その栄光の象徴の破壊(爆破)、残された小さな記録。
2つの映画には共通点があるように思えてならない。同じ要素を違うストーリーで撮った映画のように思った。あくまで個人的な解釈だけど。
1900は、「陸には終わりがない」と言った。
彼が実感できる世界の広さは、客船の広さでしかない。乗客から世界中の話を聞いても、それは実体験できる世界ではない。
1900は、自分の音楽が、レコードとなって見ず知らずの人々に聞かれるのを拒んだ。
彼の音楽は、自分が奏でるピアノを聞く人々の反応を自分で感じられる、せいぜい2000人の範囲を超えない。
1900にとって、世界は自分の手の届く範囲。そうでなければ生きられない。
とても悲しい物語だと思った。
ティム・ロスが少女を観ながらピアノを弾くシーンが印象的。彼の目は少女を追っているが、観ているのは少女ではないように思える。少女に心を奪われて空虚な目をしているのではなく、その目はずっと先の何かを見ている。私にはそう感じられた。
なんとなく、エンディングがしっくりこなかった。どうしてしっくりこなかったのかを表現できなくて、言葉が浮かぶのを数日間待ったけど、何も浮かばなかった。
映画館で観ると印象が変わるのかな、やっぱり。
籠の中の鳥は、籠の外では生きられない。
戸籍の無い男の一代記であるとともに、その男とコーン吹きの友情の物語。
それを、この世の物とは思えない音楽で綴る。
音楽に酔いしれる上映時間は至福の気分に浸れます。
でも、でも、でも…。
私には、1900が、
飼育されてしまって、野生に戻れなくなった動物のように見えて…。
『ショーシャンクの空』のブルックスを思い出させられて…。
大家族の中で大切に養育されたものの、家族以外との接触がなく、社会化する機会を逸して、引きこもりになっている子どもと重なって…。
万能感に浸った少年が、現実を前に、足がすくんで動けなくなった姿に見えて…。
本来の保護者からは捨てられた1900。
でも、養い親ダニーは愛情深く、周りの船員からもかわいがられて育つ1900。
船長でさえも、下船させることや、当局に届けさせることなく、船で育つ。後1年で20世紀が始まる頃、今よりも戸籍の観念が緩く、彼らにとっては当然のことであったのだろうか。
27歳になっても、悪戯小僧。前思春期・ギャングエイジのような1900。
嵐の夜のピアノ演奏は、見ている分にはとても魅かれるシーンだが、現実的に、あんなに装飾が見事なガラスを割るのは、現実的ではない(壁や周りの家具にぶつかるであろうことは、大人なら予測がつくことだ)。
船からの悪戯電話。彼の境遇を考えれば、涙を誘う場面だが、やってよいことと、いけないことの判断がついていない。
女性の寝室に忍び込んで、寝ている女性の許可なくキス。今なら性犯罪で訴えられる。
すべて、賠償金付きの懲戒免職になってもおかしくない事案だ。
だが、映画の中では、その音楽の才能もあって、「我らが至宝」と称えられる。
1900のピアノを聞くためだけに乗船する客が多かったから、経営陣は1900の悪戯に目を瞑っていたのか?
戸籍の無い不遇な”子”として、甘やかされていたのか?
今の時代より、コンプライアンスが緩い時代だったのか?
映画は、完全に”寓話”として、1900の特異性を、それを称える人々・エピソードを、耳心地のよい音楽と共に紡ぎだす。
そして、彼の才能を大金に変えようとする人々。
単に、彼の素晴らしい音楽を多くの人に届けたいという思いからきているのだが、誘う言葉は「大金持ちになれる」。アメリカンドリームの夢を抱き、食い詰めた人々が、USAに移民に出る不景気の中では、当然の思いであろうが。
そんな欲に見向きもしない1900。
モートンとの対決も、初めは音楽で”対決”という意味が解らず、ただただ、モートンの演奏に感動するだけ。煽られて、最後は打ち負かすような演奏はするものの。
監督は世俗にまみれない純粋さを描きたかったのか?
金持ちの客にも、移民する人々にも、そして演奏シーンはなかったが、たぶん病院船の中でも、そこに音楽を愛でる人々がいれば、演奏していた1900。
「海の声」それを聞けば、自分が何をすべきかが判るという。
音楽を奏でることは息をするようなもので、その上で自分探しをしていた1900。自我の目覚め。
そんな葛藤と、1900が出した生き様を描きたかったのか。
ロス氏の演技が、そんなサヴァン症候群?と思いたくなるような、夢想した表情、いたずらっ子な表情、それでいて、思いつめた時の思慮深い様、達観した時の表情と様々な様子を見せて、魅了してくれる。
そんな1900を大切に思い、ごく一般的な幸せを願うコーン吹きの眼差しが温かい気持ちにさせてくれる。
コーン吹きの温かい眼差し、至極の音楽に酔い、素晴らしい映画を観た気になるのだが、
今一つ、映画のストーリーには乗れなかった。
足止めしてしまう1900の気持ちは判る。
でも、同じような人が側にいたら、何らかの手立てを講じられるだろうと思ってしまうのだ。
今も、親の結婚事情とその主義による無国籍児が日本にもいる。
様々な事情で、今の場所に囚われて、踏み出せない人々がいる。
最終的に、どこでどのように生きるかは、その人自身が決めるものだが、一人で悩んで一人で決めるものではないだろうと思うのだ。
養い親は、1900が8歳の時に亡くなってしまったから仕方がないとして(彼が生きていたら、1900を自立できるように育てていたはずだ)。
船員たちは、可愛がりはするものの、誰も1900の成長に責任を持たない。
コーン吹きは、なんとか1900を船の外に連れ出そうとするものの、一人で行かせてしまう。30歳の男としては、一人でできるだろうと、27歳の男との自立度を図りかねるのは仕方がないとして、実際は、援助が必要だった。だって、1900の中身は自立前の10代の少年なのだから。
そんな自立に失敗した男が自分ができることとして選択した生き様に思えてしまうから、この映画に素直に感動できない。
でも、監督はそんなことを描こうとしたのではなく、もっと芸術よりの純粋性を描きたかったのではないかとも思う。
なので乗れない。私にとっては、音楽を楽しむ映画かな。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
”芸術”という点では、
誰に、何を届けようとするのかということもテーマなのかとも思う。
ダンスホール、今ならライブハウス?1900は「2,000人」と言っていたから、コンサートホール規模までか。
オーディエンスの反応を見ながら(感じながら)、奏でられる音楽。
1900が奏でるのはそういう音楽。
だが、マス相手になれば、そうもいかない。
コロナ禍で、無観客ライブ配信もあったが、誰に、何を届けていいのか、わからなくなる。方向性が見えなくなる。
1900はそれはできないという。
この映画も、短いファイン・ライン版と、45分も長いイタリア完全版がある。
この監督の有名映画『ニュー・シネマ・パラダイス』に至っては、インターナショナル版と、映画の趣が変わってしまう3時間完全オリジナル版がある。
映画もマス相手。オーディエンスの反応を見ながら、演技や演出を変えることはできない。
その辺のジレンマが、1900に投影されているのか。
他の監督のように、第三者の編集者や制作の手が入ったもので、良しとせずに、ご自身が納得するものと、世俗受けするものを作っている監督だから、ついそんな妄想を抱いてしまった。
イタリア完全版未見。いろいろな評を拝読すると、音楽シーンが丁寧に描かれていて、ファイン・ライン版で不明な点が了解できるという。また、印象ががらりと変わるのだろうか?
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
≪以下、ネタバレあり≫
レコード?
病院船にあったピアノに隠されていたという。
1900ほどの演奏者が、自身がひくピアノに、通常無い物が入っていたら気が付かないのか。
ピアノはちゃんと調律していないと、音が変わると聞いている。何か入っていたら、響きが違ってくるから、1900は気が付くのではないか。
気が付いたけれど、コーン吹きの思いを想って、自身の青春の思い出として、そのままにしていたのだろうか?
コーン吹きとの再会。
あれ?この状況で、タキシード?汚れていない…。1900もやつれていない?髪・髭ぼうぼうでもない…。
病院船で生き延びていたとはいえ、病院船が廃止されてから、どう過ごしていたのか。爆破のために、主なものはすでに運び出されているというのに。鼠のように、床に転がっていたものを食べて生き延びたのか?水道管が壊れ、流れ出た水で、洗顔し、洋服を洗っていたのか。ものすごい数のタキシードを持っていたのか???
一瞬、幽霊が現れたのかと思った。それならば、華やかな頃の格好は了解できる。
地縛霊だから船を降りられないのでは?
レコードとコーン吹きにつられて姿を現したのでは。
なんてことも考えてしまう。
ピアノ演奏に見惚れてしまう
ラストにはどうしても納得できない
ピアニストの生い立ちは、まるでおとぎ話のように、神話のように独り歩きをして、大げさに語られていったのかもしれない。
それにしても、魅力たっぷりに、船の中の人間関係を描き出し、ピアノ対決なんかは、まるで音に優劣があるかのように、鍵盤から出てくる音が、相手を打ちのめし、拳のように叩きのめす。
ラストだけ。本当にラストだけが、「そりゃないわ」ということでした。仮にあったとして、あの爆発はもう少し何とかならなかったものか。色を消すとか、音を消すとか、スローモーションにするとか。直接的な表現を避けるとか。
とにかく、ラストシーンにがっかりした。
これも一つの生き様で、彼我に差等はないはず。
88枚の鍵盤に限られるピアノの世界とは違って、その枚数には限りのないこの世の中を生きるには、相応の困難を覚悟はしなければならなかった―。結局は、そういうことでしょうか。
本作のナインティーン・ハンドレットにとっては。
その生き様の是非を巡っては多様な意見がありそうですけれども。
しかし、困難には果敢にチャレンジするのが一つの生き方とするのであれば、それと等価の視点を持って、彼のような生き方も「あり」として、是認されて良いのてはないでしょうか。
ともすれば「頑張れ」「前向きに」「まずは最初の一歩を踏み出せ」と激励され、その激励が却(かえ)って重荷となって、心が折れそうにすらなってしまうことも、この世の中では、あるのではないでしょうか。
本作のナインティーン・ハンドレットのような生き様が共感を呼ぶのも、そういう現実社会へのアンチ・テーゼが含まれている故のことと断言したら、それは評論子の独断というものでしょうか。
ナインティーン・ハンドレットだって、豪華客船の中では乗客(富裕層)の名誉心や欲望といった醜い現実と向き合い、本船が病院船に転用されてからは、死に向かう傷病兵という戦争の苛烈な現実と向かい合っていたわけですから、彼が船を降りなかったことをさして、いわゆる「後ろ向きである」とか、「現実逃避である」との批判は、当たらないのではないかと、評論子は思います。
彼の生き様と、他の生き様との間に、差異を見出すべきではないとも思います。評論子は。
本作は、午前十時の映画祭13の一本として鑑賞したものでした。
観終わって…。
そのシリーズの一本に恥じない、深い共感が残る秀作であったと思います。
評論子は。
なぜか幸せな気持ちに
1900,1908,1927,8,1933,1933+α、
が映し出されている。
1908と1928と1930年代は客のドレスの
デザインの変遷が見れる。
🎼🎺エンニオ•モリコーネの音楽も満載♪🎹
皆がアメリカ🇺🇸だ!と叫んでいる時、一人の
女性が「音楽!」と日本語で叫んだ❗️
1900が8才で初めてピアノを弾いた時見に来た
観客の一人の女性、白塗りオバケ⁉️
と時折何かわからないけれど、何かある。
マックスと初対面で揺れる船🚢にあわせての
演奏しながらのピアノスケート滑り
お気に入り❣️
ジャズ対決の時、ジャズの発明者だかが、
2曲目終わってバーに行き、バーテンダーが
出してくれたドリンクにタバコを入れるとは?!
マナーが悪い⁉️
だから、結果も見えていると思った。
対決の時の1900、ラストに本領発揮❗️
あの心惹かれた女性の船室に忍び込み
キスするとは⁉️
1930年代だからこそだろう。
ぶら下がっていたのは?ストッキング❗️
決心して船🚢を降りる、と。
様々な手続きしてマックスに貰ったコート着て
皆に手を振って別れの挨拶したのに、
なぜ引き返したか。
本人は後にマックスに陸の生活が未知数で
怖くて自分には無理だ、と言うが、
船🚢を見捨てられなかったのだと思う。
あの女性よりも大事なんだ。
1900はこの船🚢を自身の生まれ故郷そのものと
考えていたのだと。
例として適切かどうか、
生まれ育った村がダム湖としてして沈んでしまい
運命を共にする(してはいけない)というのに
近いのでは?
船🚢をひとりぼっちで死なせるのは
忍びない、と考えたのだろう‼️
マックス、よくレコードを拾っておいてくれた。
感謝❣️
とにかく、本作数年前に初めて観た時から、
鑑賞後幸せな気持ち💕になるのです🌸
一年前から心待ちにしていた企画。
やはり映画館で観るのがいいですね💕
記:午前十時の映画祭企画
2024/3/13 ユナイテッドシネマ橿原
2024/3/28 大阪ステーションシティシネマ
過去TV視聴
限定された時間空間での満足した生涯
孤児を偶然拾った男性が育てるという話はありがちであるが、船内で育ち、無戸籍のまま一生を過ごし、才能は如何なく披露し、名人の鼻っ柱をへし折る痛快な勝負も乗り切っていくが、恋に迷い、破廉恥な行動にも踏み出し、陸に上がって常人の仲間入りをするかと思ったら、踵を返してそれまで通りの船内に限られたままの人生を全うし、命が奪われることを心配した親友の勧告も聴き入れることはなかった。本人はきわめて満足した生涯ということだったのだろう。冒頭のアメリカを発見することと女性との巡り会いの話が、だんだんと回収されていく。
ダニー・ブードマン・T.D.レモン・1900
88個の鍵盤が彼の世界
人生は壮大!肝心なのは、そこに飛び込むかどうか。
私は、時を戻したいとは今まで思ったことはない。
けれど、今作を観て、若かりし頃に戻れるなら、何か楽器を演奏できるようになりたいと心底思った。
荒れ狂う海に翻弄される大型客船内で、気持ちよくピアノを演奏する主人公は、楽しげでサイコー。
余すところなく、音楽の魅力を体感した。
農夫は、海を初めて見た時に。
主人公は、初めて恋に落ちた時に(ここ、ヒロインがめちゃ魅力的!)。
雷に撃たれたような衝撃とともに、人生の壮大さに気づく。
2人の違いは、農夫は冒険に飛び込み、主人公はとどまったところ。
最後の爆破前のシーンで、初めて主人公の変化に対する恐れを聴く。
勇気を出して新しい世界に飛び込んで欲しかったけれど、足がすくむ気持ちも分かる。
それでも。
友人とともに船を降り、人生に飛び込んで行って欲しかったな。
主人公は、親には恵まれなかったけれど、音楽の才能、職場、友人、そして恋に恵まれた。
主人公の長い人生を一緒に伴走した気分。
さて、それでは、私は。
どんな人生がいいのか、自由な発想で真剣に考えてみよう。
いつ雷に撃たれてもいいように。
その対象の世界に、飛び込めるように。
名作だが、古さを感じない。
最後の最後まで、素晴らしい演出。
すべてにブラボー!
海の上で船と共に人生を全うする
最高レベルのエンタメ映画。でも何を伝えたいのかな?
誰にでも推せるわけではないが、いわゆる午前10時の~の枠はハズレが少ない
今年111本目(合計1,203本目/今月(2024年3月度)29本目)。
(前の作品 「レッドシューズ」、次の作品「12日の殺人」)
1900と呼ばれる主人公と(この映画の主人公を誰に取るかは色々ありそうですが)、その奏でる音楽が論点になる映画です。
古い映画のリバイバル上映なので、どうしても現在(2023~24)の映画と比べると視覚面などはどうしても落ちてしまいますが、いわゆる「午前10時の~」で放映されている映画というのは不朽の名作で、多少確かに「退屈かな」というところはあるはあるとしても、よかった映画です(個人的に音楽を15までやっていた、という事情もあるので)。
今ではVODで課金できたり、ネットフリックス等ほかでは普通に再生できるらしく(4Kかどうかは知らない)、4Kであろうがどうしようがストーリーが変わるわけではなく、あれもこれも書こうとするとネタバレどころの話ではないので薄目に…。
映画「それ自体」としては実際の史実を直接、詳しく参照することはありませんが、この当時(1900年を起点として、その前後の世界史の事情)のことを知っていれば有利かなと思える部分は多々あります(この点で理解はある程度変わる。もちろんこうした事情で復刻上映されているのでパンフレットなどというものはない)。
作品の採点において特に気になる点まで見出せなかったのでフルスコアにしています。
書くまでもないですが、2023~24年の水準でアクション映画を見たいだのホラー映画を見たいだのといった趣旨の映画ではないので注意です(換言すれば、そうした事情で放映されていることから、帰宅すれば気になる点などVODで確認したりすることができるし、比較的「後追い」(後での気になる点のチェック)がしやすい映画ではあります)。
全89件中、1~20件目を表示