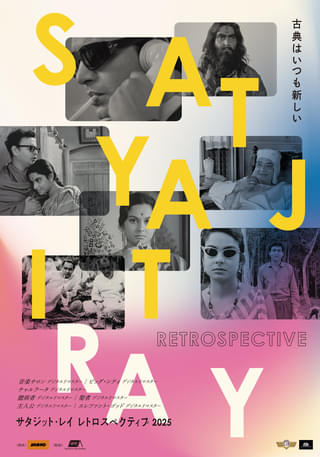1999年に米国コロラド州コロンバイン高校で起きた、同校生徒による銃乱射事件は、米国内外に大きな衝撃をもたらしました。この事件を題材にした映画はこれまでに、マイケル・ムーア監督の『ボーリング・フォー・コロンバイン』(2003)などいくつも登場しており、本作もその一つに当たります。
本作はドキュメンタリー作品ではなく、実際の事件に基づいた創作、ではあるのですが、ガス・ヴァン・サント監督は様々な試みを取り入れることで、事実と創作、そして当事者と非当事者の境界線をあいまいにしています。
たとえば、演技経験のない高校生たちを配役して、思いのままに台詞を喋らせるという作劇手法もその一つです。出演者達は、全くの架空の人物ではなく、自分たちがこの作品世界の当事者であり、言葉を紡ぐことで場に意味を与える役割を担います。もちろん大多数はプロの俳優が学ぶ「メソッド演技」の訓練も受けていないでしょう。
即興劇とも当事者作品ともつかないこの斬新な手法が、出演者に過度の精神的負担を与えなかったか、特に暴力を含めた演技をさせたことに問題はなかったのか、といった議論の余地はあったものの、本作はカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞するなど高い評価を受けました。
こうした経緯を知らなくとも、ごく普通の日常生活を送る高校生たちが、実は「あの時」に向かって時を刻んでいる、ということを観客は知っているため、最終盤近くまで淡々とした描写が続くにもかかわらず、異様な緊張感が続きます。このあたりは、山本直樹著『レッド』も連想しました。
上記の制作背景を知るとさらに個々の登場人物への感情移入の度合いが高まるので、観客によっては直接的な暴力を見せられるよりも「食らう」かも。
なお本作の特徴的な作劇は、サント監督がこれまで描いてきた人間観、死生観を色濃く反映しているものの、全くの独創ではなく、同名のイギリスのドラマの影響を受けているとのこと。この不可解な題名の由来についてはいろいろな情報があるみたいだけど、原案の題名をそのまま使っているとなると、これは元のドラマに対する作り手の誠意…と見ていいのかな?

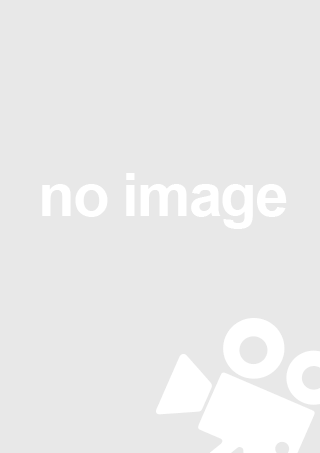

 ロード・オブ・ドッグタウン
ロード・オブ・ドッグタウン グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち
グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち 追憶の森
追憶の森 マイ・プライベート・アイダホ
マイ・プライベート・アイダホ 永遠の僕たち
永遠の僕たち 小説家を見つけたら
小説家を見つけたら ラストデイズ
ラストデイズ ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子