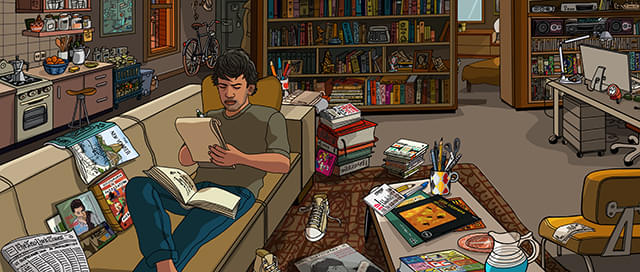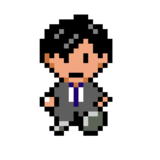ボサノヴァ 撃たれたピアニスト
劇場公開日:2025年4月11日
- 予告編を見る
- U-NEXTで
関連作品を見る PR

解説・あらすじ
アカデミー外国語映画賞受賞作「ベルエポック」のフェルナンド・トルエバ監督が、「チコとリタ」でもタッグを組んだハビエル・マリスカル監督と共同監督を務め、ブラジル音楽の伝説的ピアニストであるテノーリオ・ジュニオルを題材に、ラテンアメリカの光と影を描いたアニメーション映画。
1950年代末、ブラジルのボサノバが音楽の歴史を変え、エラ・フィッツジェラルドからフランク・シナトラまで世界中のアーティストがブラジル音楽を歌いはじめた。時は流れ、現代。ボサノバの歴史について調べるためニューヨークからリオデジャネイロへやって来た音楽ジャーナリストのジェフ・ハリスは、サンバジャズで名を馳せた天才ピアニスト、テノーリオ・ジュニオルの存在を知る。その足跡をたどると、彼はブエノスアイレスでのツアー中に謎の失踪を遂げていた。
ジャズピアニストとしても活動する俳優ジェフ・ゴールドブラムが、物語の語り部となる音楽ジャーナリスト役で声の出演。
2023年製作/103分/G/スペイン・フランス・オランダ・ポルトガル合作
原題または英題:Dispararon al pianista
配給:2ミーターテインメント、ゴンゾ
劇場公開日:2025年4月11日
スタッフ・声優・キャスト
- 監督
- フェルナンド・トルエバ
- ハビエル・マリスカル
- 製作
- クリスティナ・ウエテ
- 脚本
- フェルナンド・トルエバ
- アニメーション監督
- カルロス・レオン・サンチャ
- 編集
- アルナウ・キレス
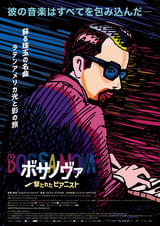


 あなたと過ごした日に
あなたと過ごした日に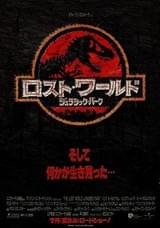 ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク
ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク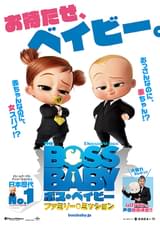 ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
ボス・ベイビー ファミリー・ミッション キャッツ&ドッグス
キャッツ&ドッグス ジョーカー
ジョーカー ラ・ラ・ランド
ラ・ラ・ランド 天気の子
天気の子 「鬼滅の刃」無限列車編
「鬼滅の刃」無限列車編 万引き家族
万引き家族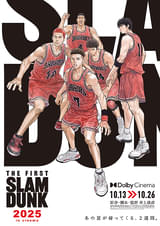 THE FIRST SLAM DUNK
THE FIRST SLAM DUNK