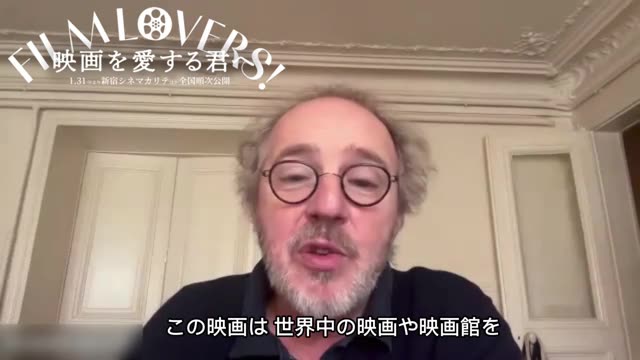映画を愛する君へのレビュー・感想・評価
全34件中、1~20件目を表示
ドラマとエッセイが融合した不思議かつ温かい手触り
本作はアルノー・デプレシャンの監督作『そして僕は恋をする』『あの頃エッフェル塔の下で』でお馴染みの主人公ポールが幼少期、少年期、青年期と歳を重ねる姿を点描しつつ、成長の傍らにいつもあった映画の存在、および映画の誕生から現代に至るまでの歴史や人々へのインタビューをも独特のタッチで絡ませた一作だ。すなわちドラマとドキュメンタリーとエッセイが一緒くたになった異色な味わいと言うべきか。そのデプレシャン流としか形容詞しようのない語り口からは、「映画とは何か」という命題をただ難解に突きつけるのではなく、あくまで温もりあるドラマや日常風景に差し込む光のように優しく浮かび上がらせようとする趣向が感じられる。きっと観る側も自ずと胸に手を当て、初めて観た映画のこと、映画館の思い出、香り、一緒に見た愛すべき人の記憶を強く蘇らせるはず。そんな観客一人一人の積極的な共感あってこそ、この映画は完成するのだと強く思う。
とある映画史
フィクション×ノンフィクション
「16歳です」
「下北沢で」
【アルノー・デプレシャン監督が、自作「そして僕は恋をする」の登場人物ポールを、様々な年齢として配し、自らの映画愛を語るドラマとドキュメンタリーを融合させた作品。】
ー 祖母に連れられて初めて映画館で映画を観た想い出から始まり、窓口で14歳なのに、16歳と偽って観た「叫びと囁き」。
女の子と、学校で映画上映をしたり、二人の女の子と映画を観に行って、鑑賞後、一人の女の子と喫茶店でキスをしたり、甘酸っぱいぞ!
ラブコメの名品「ノッティングヒルの恋人」での、若きヒュー・グラントとジュリア・ロバーツとのベッド上での面白い遣り取りを入れたり、マチュー・アマルリック本人がカフェに現れ、黒人のポールは彼を追って、映画館に行ったり。
トリュフォーの「大人は判ってくれない」を見て、映画の道に進むことを決めたり。
色んな人へのインタビューで、映画館で映画を観る席を聞くシーンも、面白かったな。一番前とか、端っことか。けれども一番多かったのは、真ん中だったな。
どーでもよいけど、私は、映画館のスクリーンによって予約する席を決めているけどね。-
<けれども、一番ショックだったのは紹介された映画の半分、いや、1/3も知らなかった事である。
フライヤーには登場する作品名が記載してあるので、少しづつ観て行こうと思ったよ。
あと、40年生きるとして、一年で1、000本観るとして、40、000本かあ。お爺さんに成ったら、時間が出来るからもっと観れるかな。
その為には、キチンと健康管理をしなきゃなあ。酒を控えめにしてね。いやあ、ヤッパリ絶対無理だなあ。映画だけ好きな訳じゃないしな。じゃーね。>
<2025年3月30日 刈谷日劇にて鑑賞>
監督が大学の講義で学んだという観客の視点の話しは面白かった
監督の自伝的シネマエッセイ。
期待もしていなかったけれど、全体としてはあまり面白くなかったです。
監督が大学の講義で学んだという「舞台劇の観客の視点」、「映画の観客の視点」「テレビの観客の視点」についての捉え方は面白かった。
今なら、「web配信の観客の視点」を新たに加えるべきかもしれません。
映画館を愛する君へ
1960年生まれというから僕と同年代の監督が、自身の映画遍歴を振り返り、映画への思いを綴る作品です。映画好きの人にしか届かない映画かも知れませんが、しみじみした語り口が僕にはしみたなぁ。
おばあちゃんに手を引かれて初めて映画館に向かう道すがら、「映画はテレビとは違うのよぉ」と語るおばあちゃんの優しい語りがいいなぁ。そして、その初めての映画が僕も大好きな『ファントマ危機脱出』だったのも嬉しい。更に、映画館で映画を見る内に「はじめて自分の居場所を見つけた」との監督のモノローグも素敵。また、十代でベルイマンの映画に打ちのめされたと言うのも凄いなぁ。僕は、居眠りしていた。「映画はいつでも敗者を迎え入れ続ける」の言葉も優しい。
そして、本作の大きな特色が、監督の映画人生を彩った作品が次々と映し出されることです。ちょっとした一場面が現われるだけなのですが、あっ、『恐るべき子供たち』だな、『白い恐怖』だ、などと言いたくなってしまいます。この辺、通ぶりたい映画ファンの心理をよく心得てらっしゃいます。
ただ、一つだけ注文が。原題『SPECTATEURUS!』は「観客」の意味ですが、邦題は「映画を愛する君へ」ではなく、絶対に「映画館を愛する君へ」であるべきでしょ。それが無理なのは理解できますが、敢えて申し上げたい。
残念ながら愛していないことを知りました。
映画を愛する君へ
このシネマエッセイ、全く面白くもなく、勉強にも、参考にもならなかった。
まあ、彼と同じようには映画を愛してはいないとして、
溜飲を下げます。
(^ω^)
映画を愛する君へ
フランスの名匠アルノー・デプレシャンが自身の映画人生を投影しながら、
映画の魅力を観客の視点から語り尽くした自伝的シネマエッセイ。
「そして僕は恋をする」「あの頃エッフェル塔の下で」でマチュー・アマルリックが演じたポール・デュダリスを主人公に、初めて映画館を訪れた幼少期、
映画部で上映会を企画した学生時代、
評論家から映画監督への転身を決意した成人期を、
19世紀末の映画の誕生から現在に至るまでの映画史とともに描きだす。
本編には映画史に功績を残した50本以上の名作が登場し、
デプレシャン監督が尊敬するアメリカの哲学者スタンリー・カベルやフランスの批評家アンドレ・バザンの言葉も引用しながら“映画とは何か”をひもといていく。
主人公ポール役には成長に合わせて4人の俳優を起用し、
マチュー・アマルリックが本人役で出演。
「ママと娼婦」のフランソワーズ・ルブランが祖母、
「落下の解剖学」のミロ・マシャド・グラネールが14歳のポール、「みんなのヴァカンス」のサリフ・シセが30歳のポールを演じた。
映画を愛する君へ
劇場公開日:2025年1月31日 88分
期待度◎鑑賞後の満足度◎ 『ニュー・シネマ・パラダイス』みたいな映画かと思っていたら大違いでした!
スタカンだ!
ナレーションは英語だった。
この映画は、「アメリカは(エジソンにより)最初の映像(キネトスコープ)を発明したが、フランスは(リュミエール兄弟により)映画(シネマトグラフ)を見出した」という言葉で始まる。この「映画の歴史」の部分で、英語のナレーションを務めるのは、フランスの俳優で監督をすることもあるマチュー・アマルレック。
50を超える映画のドキュメンタリー・タッチの紹介に、アルノー・デプレシャン監督の「個人史」が入れ子のように挟み込まれる、彼の分身であるポール・デダリュスが(4人の子役や俳優たちによって)6歳の子供の頃から、いかに映画と親しみ、学校、大学を経て、映画評論家となるが、やがて映画監督に転身してゆくかが、フランス語のドラマ(フィクション)の形で描かれる。
ポイントは、二つあるように思われた。
一つは、パリ第3大学の講義で、アメリカの哲学者スタンリー・カヴェルの引き写しと思われる「演劇では、観客の座る位置によって見えるものが異なるが、映画では、監督の(ただ一つの)視点に委ねられる」という言葉が、ドラマの一部として出てくる。講義のすぐ後、
「映画の歴史」の一部として「ノッチングヒルの恋人」でのヒュー・グラントとジュリア・ロバーツの一場面に繋がってゆく。
「映画の歴史」と「個人史」が交錯する最大の場面が、クロード・ランズマンの「ショア」。ポールに最大の衝撃を与えた映画として、ホロコーストを取り扱った9時間半に及ぶ映画が紹介された後、この映画の代表的な論客であるユダヤ人女性学者ショシャナ・フェルマンへの(テルアヴィブでの)インタヴューが出てくる。映画は、もう誰も見ることができない(あるいは隠している)情景を切り取って見せることができる、これが最大のメッセージか。映画作家には、重い責任があるわけだ。
一見すると、フランス映画らしく晦渋で、何を言いたいのか、さっぱりわからない、ということになるだろう。しかし、英語のナレーションとフランス語のドラマに代表されるように、アルノー監督は多面的で、映画を劇場で見ることだけでなく、テレビやストリーミングで観ることも許容しているのだ。彼の「個人史」が、それを示しているように。この映画の原題にそれが現れているSpectateurs(観客たち)。
タイトルなし(ネタバレ)
デプレシャン監督の分身ともいうべきポール・デダリュス。
6歳の時(ルイ・バーマン)、祖母に連れられて初めて映画館で観たのは『ファントマ危機脱出』。
テレビではヒッチコック監督の『白い恐怖』なんかを観ていた。
14歳の時(ミロ・マシャド・グラネール)には年齢を偽って、イングマール・ベルイマン監督の『叫びとささやき』を観に遠征した。
学生時代には自主上映会を開く。
映画はチェコのヴェラ・ヒティロヴァ監督『ひなぎく』。
文献で知っただけで観たことはない。
同胞の学生たちはチェコがどこにあるか、名前すら知らなかった。
大学生(サム・シェムール)になって、映画と演劇の違いを大学で学び、ガールフレンドの友だちと寝たこともある。
30歳(サリフ・シセ)、『大人は判ってくれない』を観て至福の時を過ごし、映画監督になることを決意する・・・
といった物語。
先に挙げた映画のほかにも『ヨーロッパ一九五一年』『SHOAH/ショア』など数十の映画の引用とモノローグでもって、青春時代を再現していくさまはドキュメンタリーと言ってもいいかも。
特に『SHOAH/ショア』に関するエピソードは、現在の時制で本人も出演しているので、ほぼほぼドキュメンタリー。
ある種の映画論のような映画でもある。
観ながら思い出したのは、次のような大林宣彦監督の言。
映画は1秒24コマの動かない画がスクリーンに連続して映し出されます。
それを観て「動いている」と錯覚するものだけど、コマとコマの間はシャッターで閉じています。
シャッターが閉じている間、スクリーンに映し出されているのは暗闇で、暗闇を観ているとも言えます。
暗闇を観ている間は、目を瞑って、自分自身の思いを観ているとも言えるでしょう。
と、まさに、本作を観ながら、わたし自身のことを思い出し、自分自身を観ていたような気がします。
ただし、引用されている映画のうち、先に挙げた重要作品(デプレシャンを形づくった映画)のことを観ているか知っていないと、本作は、たぶん眠くなるはず。
わたし的には、半分ぐらいはわかったので、そんなことはならなかったですが。
なお、エッセイ映画なので、デプレシャン監督作品にしてはとても短い90分ほどの尺です。
思ってたのとは違ったけど
業界全体史と個別体験史の融合
映画の草創期から歴代の代表作品を取り上げながら、監督自身の幼少期からの関わりをもドラマ化して混入させ、結末には自分自身の分身を登場させる一方で、自分自身も別役で登場している。著作権処理はどうしているのか気になった。
どうも、ピンとこなかった
途中挿入される映画館エピソードがいい感じ
正直そこまでデプレシャンが好きというわけでもないのだけど、その存在を知った時から観たかった映画。みんなが言ってるようになんとなくゴダールの映画史ではないけどもう少しカジュアルなシネエッセイ的な小品。
とはいえ、途中のコッポラの映画に並ぶふたりの女の子と関係を持つというエピソード(片方が雨に濡れてスタイルカウンシルが流れてるとこ)や、ひなぎくをシネクラブ上映するとことかの劇映画の感じが好きで無限に観ていられる。映画館で映画を観るという行為の考察とか、映画文化の真髄を探ろうとしつつ、終盤はほぼ『ショア』と私。そしてラストカットのシナリオ書いてるバックショット通り、もう誰に観てもらうでもなく映画の考察なのだけど、まったく嫌にならない。
全34件中、1~20件目を表示