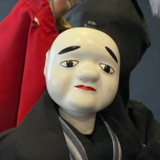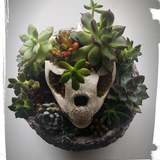どうすればよかったか?のレビュー・感想・評価
全204件中、81~100件目を表示
ひとつの答え
統合失調症と見られる症状があらわれた姉を医者に連れて行かない両親と家族の姿を映し続けたドキュメンタリー作品。
ドキュメンタリー作品は普段観ないタチなのですが、評判となっているので鑑賞。
リアルを描いているだけに、感想が難しいですね。原因を追究するわけではなく、この現実を只管にみせていく。
率直に言えば、ご両親が精神科に連れて行かなかったことが良くなかったのでは?とも思ったし、お互いにパパの意見が〜ママの意見が〜…と、どうにも煮え切らない。
しかし、そこには我々にはわからない考えがあったのかな…。或いは疲れ果てて考えることもできなかったのか。
弟さん(監督)の優しさや姉を思う気持ちはしっかり伝わってくると同時に、現実問題としていつか自分自身に降りかかるものでもあったのでしょうから…。
観ていてとても歯痒かった。
それでも、ピースサインは嬉しくなったし、その場面を映してないだけかもですが、お姉さんも弟にだけは声を荒げる様子もなく、そこに絆はあったのかなと。
タイトルでもある「どうすればよかったか?」この問いに答えることは出来ないが、これもひとつの答えだったのかなと、他人の私が軽々と言うのも恐縮ですが、そんなふうに思わされた作品だった。
「変」な家族
変。
もう全てが「変」でした。
研究者だとか頭がいいとかお金があるとかいい物食べれるとか大きな家に住むとか関係ない。
異様な空気感と距離感、両親もどこか冷静で、
なんで誰も何も言わないの?と思ってしまう。
監督が病院に連れて行くことを諦めなくてよかったです。
でも、きっと両親もとてもとても辛かったはず。もちろん、監督も。
みなさまお疲れ様でした。
こうすれば、と言える部分があっても それは、どこまで行ってもきっと...
ただただ切ない
弟さん(監督)がいてよかった
ただ淡々と家族の経過を記録したもの。
医師でも臨床医じゃない両親で、高齢ともなると正しい判断が出来ないもんなんだなぁ。
治療を受ける前と後のお姉さんの様子から、治療効果がこんなにあるんだ、と初めて目の当たりにしてびっくりした。
発症初期からもし治療を受けていたならどんな人生だったんだろう、とどうしても思ってしまう。
親って子供を守ることもあるけど、可能性を奪う毒になる事もあるな、って本当に思う。
言葉に詰まる
もっと発狂して部屋が目を覆うほど乱雑な日常を映し出しているのかと思った。カメラを回し始めたのが20年後だったのもあるのだろうか。
問題がなさそうに暮らしている様子が不気味に思えた。家族だからこその隠蔽気質は自分にも無意識にあるのだと感じた。具体的な手を打てばいいじゃないのかと問われて、病気じゃないと診断されたから大丈夫みたいな堂々巡りを母親としているのを見ていて亡くなった母を思い出した。私も一生懸命やってるのに!って言ってるように見えた。そこに家族内であれだけ踏み込めるのが凄かった。自分なら、両親も話にならないし、手に負えないよって投げてしまうと思った。
お姉さんがとにかく眼の挙動と反応が不穏で、統合失調症は千差万別ともきくのでとある一つの形ということなんだろう。入院して合う薬があるとあれほど違うのかと驚いた。対話ができることが嬉しくなることなんだと思った。
母親の認知症、姉の入院が重なったときなど、父親や撮影者の弟さんはどんな心境だったんだろう。自分だったら、とんでもない不安に駆られて寝込んでしまいそうだ。淡々と時間が進んでいって、展開上そこじゃないんだろうけど気になった。
最後に父親はそうだと思ったと言ってた?と思うのだけど、母親はどっちだったんだろう。問い詰められてる際の印象が抑圧してるようには見えなかった。とはいえ健康と思っていて南京錠とかは、やっぱり、、、。
最期、確かビートルズを聴いて亡くなって、お棺に論文とタロットとケーキが入れられていた。40年家に閉じ込めた形になっても、好きなものを知っていた人がいたのだと思ったら泣きそうになった。自分が死ぬときに知ってる人はきっといないから羨ましく感じた。
最終的に、医療を受けさせずに生きた姉の一生は、正解だったのかは不明だ。個人的には今の精神医療なら早めで改善の兆しを想像できるけど、40年前はどうだだったのだろう。そのとき、自分がその立場だったら、と思うと言葉に詰まる。
正直親は変えられないと思った
幼稚な復讐
「どうすればよかったか?」
これは内省の問いかと思いきや、違う。
両親への非難の言葉だった。
初めはドキュメンタリーならではの姉の鮮明な病状、思考停止した両親に、まざまざと恐怖を感じさせられた。
しかし、母親が亡くなってから、穏やかな父娘の日常に、父親への見方が徐々に変わっていく。
90歳近い父親が、痩せた手で娘に茶を渡し、話しかけ世話をする。娘の葬儀では、二人で論文を書いたと、無意味な人生でなかったと慰める。
30年以上、病気を持った娘を世話し続けたことに、なぜ愛がないと言えよう。
それは致命的に間違った判断であるが、愛は確かにあったのだ。
一方で、監督である弟は何をしたのか?
健常でありながら、女ひとり抱えて病院に行くこともせず、なぜか両親の説得に固執する。
娘の死後、自身も死を間際にした父に、「どうすればよかったと思う?」と、“おまえは間違えた、おまえの人生は失敗だ”と執拗に問いかけ、映画として世に出す。
インタビューにて、「姉について後悔はない。自分は25年前初めて発作が出た時に、救急車を呼ぶ正しい判断ができたから」と語る。
彼は姉を愛しているのか?
ただ自己投影の対象、同じ両親の被害者として姉を見ているようだ。両親をひたすら死ぬまで非難し、自己を正当化している。
そこには、「子は親の所有物」と考える両親と全く同じ、「親が子を導くべき」という幼稚な価値観が横たわる。
家庭という小社会を描写した点で傑出しているが、監督の立場を利用した個人的な復讐を、作品と呼ぶべきではないため⭐︎1。
貴重な記録だが…
弟さんと同じ思いで最後まで観ていた。自分自身、わりと家族であろうと淡白なので、すぐにでも医療の力を借りに動くと思うし、それをしない両親が正直理解できなかった。優秀だった娘の面影と、自分たちのプライド、社会の偏見、恥、愛…こればかりは断片的な言葉としては出てくるけど、実際のところはよく分からない。母親の存在は特にお姉さんにとって苦痛だったのでは。母親亡き後のお姉さんの穏やかさ(これは入院と薬の影響が大きいかもしれないが)に、そう思わずにはいられなかった。
弟さんも、記録をすることで向き合えた部分もあるのだろうか。両親の判断が一向に変わらないなか、弟さんが何らかの形でお姉さんを医者に連れて行くことはできなかったのだろうか。あくまで親の意思が変わるまで説得し続けることにこだわったのだろうか。それほどまでにあの両親の壁は大きかったのだろうか。とまあ他人が言うのは簡単だけど、実際はそうもいかないんだろうね。
弟さんは最終的にこの映像を公開する許可は長生きしている父親のみに取っているけど、ドキュメンタリーの中でもかなり強烈な印象を残した亡き母やお姉さんはどうなんだろう…と観ておきながらふと思った。
病気を認めないのは親のプライド、世間体なのか、何を言っても通じない...
無意味な人生をみた
ひどい言い方だが、圧倒的に無意味な人生をみた。しかも、一人の人生が親という他者に無意味にされるということ。
戦争や無差別殺人など、他者によって無意味化された人生は現実の世の中にはたくさん存在すると思うが、それを統合失調症を治療できないという特殊な状況によって無意味化された一人の人生を映像として残すことで、人生がドラマ性を帯び意味をもったかのように感じる。
人間は意味あるものに安心するし、映画なり音楽なり表現物というものは、物語や音があり、主役や旋律があり、強い意味のあるものが通常だと思いがちだ。しかし、意味不明な表現物もたくさん存在する。実はそっちの方が普通ではないか?この映画がそれだ。現実は無意味なものにあふれているということ自体を再認識させられる。当たり前のことである。ただ、無意味さは怖いし、悲しい。
両親は、娘を家で守ることが、自分たちにとって意味あることと考えていたが、自分の子供は自立した他者であるという感覚が著しく欠如していた。自分では気づいていなかったようだが、彼らからは無意味さや悲壮感のオーラがすさまじく漂っていた。
医者であれば、当然精神疾患や統合失調症というものが世の中に存在することは知っていたはずだが、見て見ぬふりをした。意味不明であるが、この意味不明さが、娘の無意味な人生となって現れた。意味不明な行動は、無意味さとつながっている。
その無意味な現状をカメラにおさめるという行為もよくよく考えて意味不明である。カメラにおさめるのでなく、無理やり病院につれていくというのが常人が考える意味ある行動であり、理解可能な行為だからだ。それをせず、意味不明にカメラで無意味な姉の人生を撮り続けた。弟の監督には、なぜ姉を病院に連れて行かず、カメラで撮り続けたのか?ぜひ教えてほしい。病院に無理やりつれていくという簡単に答えが出せそうなことに、答えを出さないという意味不明さが、映画という表現物になると売りになってしまう。なぜどうすればよかったかをとったか?と題して第二弾を公開することも可能だ。そっちには、意味がありそうだし、ぜひその意味を知りたい。
無意味な人生を意味不明にカメラにおさめたら意味不明な表現物として無意味という意味を獲得した。でもそんな意味不明なことをするとその先には無意味という呪いが待っていそうで怖い。監督はこの映画を意味あるものにしないと正気ではいられなくなるのではないか?心配である。
と、まあいろいろ思ったのですが、純粋に映画作品として観るならこういうきついこともいえてしまうのだが、他人様の家族の話であり実話という認識をもつなら、やはり単純に病院につれてけばよかったという話しではなく、他人が計り知れない事情があったと推察しなければならず、人様の家庭や人生に対しずけずけとしたことは言わないほうがいいという節度が必要な部分もあり、この映画について書くにはどうすればよかったか?となってしまう難しさがある作品である。
「どうしてほしかった?」が気になった。
この作品をみて、「考えさせられる」とはあまり思いませんでした。撮影者であり家族の長男である監督は姉を「医者に診てもらって入院させるべき」という意見を持ち続けていたが、両親は姉を家に居させる方針で納得しており、意見の異なる両者の間で監督は両親が「もっと早く病院に連れて行くべきだった」と言うのを期待して「どうすればよかった?」と問うているように見えました。
統合失調症の方の家での様子や薬を処方した後の変化、そして家族の容姿の変容から30年という時の経過をまざまざと見ることが出来たのはまさしくドキュメンタリーで、印象的でした。私にとってはこの一人一人の「老い」を観ることができたのが一番の価値でした。他の方々の感想の中には「彼女の20年を無駄にした」などあるが、そんな簡単に人の人生のある期間が無駄だったかどうかを他人が判断できるものではないと思いました。現代で精神疾患と定義されるもののうちで治療(周りと同じ状態にする)が出来うるものは治療しないとその人の人生は無駄だ、とは思いません。統合失調症の薬が開発される以前、あるいは統合失調症という症状が定義される以前に同様の様態を示していた人々あるいはその周囲の人々は不幸だったのか疑問に感じます。
強いて言えば、薬を処方され会話できるようになった姉に「どうしてほしかった?」と問うた時にどのような返答があったのか気になりました。この姉は両親を恨んでいたのでしょうか。
もし自分の姉が統合失調症を発症したらどうするか。多分病院に連れていくような気がしますが、それは「姉の幸せのため」ではなく「自分のストレスを減らすため」だと思います。
点数をつけるのが難しいくらいの心揺さぶるもの。
12月に拝見。日にちは曖昧な
もう、一旦情報を仕入れて変なイメージがつく前にご覧になってほしい。
2024年はドキュメンタリー映画が豊作で
『正義の行方』『mommy』も拝見したが、
本当に劇場で見てよかった。
どうすればよかったか。
もその一つで作品として目が離せない、
お姉さんが既に統合失調症になった後
監督が『なにか言いたいことない?』
『許せない?』など、問いかけた時の
お姉さんがジッと見つめた時に
胸に込み上げるものがある。
そして娘の物語は、母、父と物語の主軸が変わる。
最後父に真意を聞いたとき、
あれはある種のどんでん返しではないか、
どんな思いで無言をつらぬいたのか。
そして、クレジットが終わったあと、
お姉さんの笑顔に危うく泣きそうになった。
多分、最後お姉さんは決して不幸ではなかった
と思う。理屈や何が正解かではない。
こんな映画体験後にも先にもないのではないか。
本当にすごいものをみた。しつこいようですが
映画館で拝見する意味のある素晴らしい体験でした、監督には感謝ばかりです。
答えはでているのだ
どうすればよかったか?と問われたら
答えは聞くまでもありません。
異変に気づいた時点でちゃんとした病院へ行き、適切な治療をすればよかった。
ですが、この問いは、当事者である父親に向けたものだったよう。
息子(監督)の追求をはぐらかし続け、追い込まれると「そんなことをするとパパが死ぬ」と夫のせいにする母親の態度はただ腹立たしいし、最後に「どうすればよかったか」と聞かれた父は、「ママがどうしても認めたくなかったので云々」と妻に責任をなすりつける。そして、「自分は失敗したとは思っていない」と開き直る。
この家族の失敗の根源がさらけ出されている。
両親はふたりともかなりのインテリで医療関係者、娘が統合失調症であることを認めたくなかった、なので何十年も受診もさせなければ当然治療もしていない。
よくそんな気になれるもんです。虐待ではないのか。
我が子のことですよ、私だったら心配と不安で、引きずってでも受診させ適切な治療を受けさせますよ。
母が認知症になったことで両親が折れて、ようやく治療を開始した後、姉は少なくとも「人間」を取り戻していた。
もっと早くそうしていたら、姉は何十年もカオスの中で暮らさず人間らしく生きてこられたのに。
親自身も苦しんだだろうが、申し訳ないけど自業自得、自分たちのエゴで娘の人生を潰したことも多分認めたくない、反省することもないだろう。
両親は海外生活も経験したインテリらしく、両親はパパママ呼び、食事やイベントは凝った料理を食べシャンパンを飲んだり優雅なのが余計にこの両親の黒さを感じる。
会話が8割方聞き取れず、両親が何を言ったか正確にはわからない
字幕にするとか工夫はできなかったのだろうか。
こういう映画を撮ったことに、監督のスケベ心らしきものをちょっとだけ感じます。
今どきはまともな親ならもっと早く受診し治療を受けさせているはずなので、映画には、無知な人への啓蒙的な意義はあまりないと思う。
毒親を告発した映画のように感じました。
ある家族、その道のり
片付けようとも頑固に崩れない山のように
はたからみれば茂みに迷い込んだような呪縛のなかで
自分たちを信じきり祈る両親を説得する手立てはなかった
頑なに閉ざされたその道を人の〝老い〟が自然に動かし始める
滞っていた秒針がようやく少し動きはじめた
しかし同時に、それが人生だといわんばかりに容赦ない現実も襲う
タイトルは家族としての監督自身からの長い間の自問にみえた
記録は正解を求めない自答であり、監督がこれからを生き抜く為に必要な「家族の存在の証」だったのではないだろうか
目をそらしたり晒さないままにもできたはずの壮絶な家庭の内側に、固執する両親なりの家族愛のかたち、息子としての親への疑問と恨み、ひと握りのある意味での尊敬、切なくもどかしい姉への思いが隙間なく映っている
そして私には、姉が弟にみせるおちゃめなvサインやおどけたポーズがせいいっぱいの〝ありがとう〟にみえて仕方なかった
だから監督は撮り続けることができたんだと、どこかで思いたいのかも知れない
別れの際の論文のシーンで永遠に消えない隔たりを感じて苦しさがこみあげた
修正済み
全204件中、81~100件目を表示