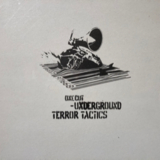どうすればよかったか?のレビュー・感想・評価
全204件中、61~80件目を表示
本当にどうすればよかったか?
観賞後、家に帰るまでの間に何回ため息をついたことか。
統合失調症を発症したお姉さんを医療から遠ざけ続けたご両親を糾弾するのは簡単だけど、いち観客に過ぎない自分がそれをするのは違う……というのは分かりつつ、でもお母さんの話が通じない様子やお父さんがラストで発したあの一言には「あーっ、なんかもう!なんかもう!」と悶えそうになる。
やっと入院したお姉さんがたったの3ヶ月で劇的に症状が緩和したのも「よかったね」と思いつつ「じゃあ、あの二十年は…」と何ともやるせない気持ちに。
ご両親に、お姉さんに対する愛情や統合失調症に対応しようとする頑張りがあったのは分かるけれども、なんか…なんか…
(病気の早期発見と早期治療)(第三者の介入)これが正解なのは間違いないんですが、もしそれを家族や本人が拒んだときは…。そして自分も当事者だった時は…
本当に「どうすればよかったか?」という問いが頭の中をグルグル回ってため息の連続でしたが、もしアベマの番組か何かで本作品が取り上げられてコメンテーターが強い口調で一刀両断したりしたら「それは違ぇだろ!」と思うのは間違いないでしょうね。
バイアスの恐ろしさ
統合失調症ではないが、発達障害+知的障害、認知症、双極性障害の身内がいるので、全編共感しながら鑑賞した。以下、感じたことを整理したい。
●専門的知識があろうと、バイアスからは逃れられない
「正常である」という認識を拡大させすぎる正常性バイアス、医師(この場合は両親も含む)の持つ知識や権威性を絶対視する権威性バイアスによって、「娘は治療など必要ない」とする両親に悲しみを感じた。両親が最終的に互いに責任をなすりつけあう姿も生々しい。医師として、親としてのプライドが目を曇らせている。
ちなみに昨今はネットの発達で医師の権威性(患者と医者の情報非対称性)は薄らいでいるし、障害や病への理解も進んでいる。そういう時代に生きている自分からすると、お姉さんが生きた時代の流れが悪かった、という点も見逃せない。
●教育虐待、「兄弟児」、ヤングケアラー、毒親、8050問題
いずれも流行りのワードであり、本作と密接に関連している。監督には、次回作でその視点から(今度はより中立の立場で)作品を作ってほしい。
●両親は娘を愛していなかった…わけではない
家父長制的な家族において、愛情とは子どもを管理し、囲い込むこと。父親はそれを忠実に実行したにすぎないのかもしれない。
●私怨を晴らすための作品か?
そういう面もあると思ったが、それが作品の意義や質を損ねているわけではない。実の弟が記録するのだから、怒りや憎しみが湧いて当然だと思う。「憎んでいないか?」と姉に問うシーンを挟んだのは英断だ(監督自身が怒りを持って撮影していることを表明しているシーンであり、観察者として偏りがあることを示している分誠実だと感じる)。
どうしようもなかったから、この作品ができた
まず、ドキュメンタリー作品というものについての個人的な前提を記載します。
これは、所謂ドキュメンタリーなのだと思うのですが、そのような映画を観るにあたり、「ドキュメンタリー=現実」ではないと思うことが大切だと思うのです。つまり、ある現象や事実を映像化するということは、製作者がそこにある物事を、「個人的な思想」に基づいて映像化しようと「思った」訳ですので、正確にいえば「ある現実を、テーマ性を持って切り取った記録作品」ということなのかな、と思います。そうなると絶対に映像の方向性は恣意的になり、製作者の思想が「編集」というかたちで自然に織り込まれて行きます。そしてもう一つ、「自分がこの人たちだったら」という考え方に取り込まれない方が良いとも思いました。単純に、自分たちはその人たちではないし、例え環境が同じになっても、その人たちにはなり得ないからです。そう思わないと、少なくとも私は「共感」ではなく「同情」(これは共感から最も離れた意味を持ちつつ、最も誤解されやすい感情だと考えます。)を抱いてしまうからです。ニュースでもそうですが、それら製作者の思想を、まるで現実そのもののように取り込むことこそが、昨今のテレビ業界や週刊誌を「叩く」という現象における原因の一つにもなっていうのかな、と思います。あくまで原因の一つだと思うだけですが。まず、こういう前提があるとこの作品は考えやすいかな、と思いました。何故なら、このようなドキュメンタリー作品は「○○が絶対に悪い」という善悪二元論か、「答えがない」という類の答えに行きがちで、モヤモヤしたまま終わってしまい、「なんかすごいものを観た。」で終わってしまうと思ったからです。もちろん、そういう「答えが出ない」系の感想が悪いのではなく、むしろ悩むこと自体が人間として大切なことだと思うので正解なのだと思いますし、善悪二元論も言うまでもなく間違っていない考えだと思うのですが、折角なら「自分なり」の答えは出せた方が良いな、と個人的には考えたため、上記のようなことを長々と書きました。
次に、わたしの感想を、わたしの中にある前提も含めて書かせていただきます。
まず、全体をとおしてわたしが思った、極々個人的な感想は、「どうしようもなかったから、この作品ができたのだろうな。」ということでした。
パッと見、このような事態には誰しもがなるかも知れない、と思ったのですが、わたしとしては、「このような事態」になるには多くの前提がなければならないと思い、自分の中にある前提を解体してみました。
結果として、わたしが最初に思った「このような事態」のほとんどは「統合失調症の家族」と「現実を認められない人間の社会性」という二つの要素だけでした。確かに、統合失調症が家族に症状としてあらわれたら、わたしは単純に「怖い」し「不安になる」し、要するに「どうしよう」と思うのです。それは、監督含め、このご家族にも当てはまると思いました。
一方で、もう一つの「現実を認められない人間の社会性」については、所謂「自分の失敗」を隠すことで周囲への体裁を整えたり、見栄を張ったりするために使うことが多く、恋愛や仕事、家族関係などで上手くいかない時に心の中で自分以外の他人や環境のせいにすることにより露呈するものだとわたしは思っています。
こう思った時に、単純に「統合失調症の家族がいる」という事象と「現実を認められない人間の社会性」というテーマは結びつかないな、とわたしは結論づけました。実際、これは全ての当事者の方々がそうであるとは思いませんが、統合失調症が家族から出て、それを家族で協力し合って治療している方々もいると思うからです。そして、そういう人たちが所謂「善人」だったから家族の病気にも向き合えたとも思いません。つまり、「致し方なかった」というところも多分にあっただろうと思うのです。
このドキュメンタリーを観てわたしが思い出したことは「座敷牢」です。「私宅監置」という言い方もあります。わたしは、その前提として「自宅に牢を作ったり、自宅である人を監置できるような環境(資金力など)がある」ことが第一に挙げられると思っています。このご家族も、お父様の海外でのお仕事に乗じてエジプトなどに家族旅行に行けたり、1950年代から記録映像を残せるほどの資金力に恵まれていることが分かります。また、中盤辺りで統合失調症のお姉さまだけでなくお母さまも、ほぼ1年間自宅から出来いない状態になっているという事実も分かりますが、これも要するに「家族が約1年間自宅から出なくても良いような経済環境」だとも思えてしまいます。監督ご自身も9年間大学に在籍できたり、お姉さまも大学合格まで4浪もできていたりします。例えバイトをして学費を稼いでいても、9年間も大学に通えたりすることはそうないとわたしは思いますし、4回も大学受験をさせてくれることもなかなかないのではないかな、とも思いました。そういう意味で、まずこのご家族は経済的に「恵まれてしまった」と思いました。これが、わたしが考える「どうしようもなかった」理由の一つです。
次にご家族のパーソナルについて、わたしが考えた前提を書きます。まず、上記のような経済状態になれたのはどうしてかというと、単純にお父様とお母さまが大変優秀なお医者さんだったからだと思います。その努力の積み重ねが社会に認められ、結果としてこの家庭を作ったのだと思いました。そのようなお父様とお母さまですので、医学の知識や関連する機器などについては大変詳しく、お年を召してからも論理的に物事をお考えになっていることが分かります。一方、そのようなお二人ですので、自分の人生についてはプライドも持っているでしょうし、「絶対に~だ。」という認知的な歪みもあったのかも知れない、と思いました。そのようなご両親ですので、基本的に成功体験が多く、大体のことは「やればできる」と考えてしまい、お姉さまや監督の言葉や普段の状態にも、ある種鈍感になっていたかも知れません。そして、お姉さまが統合失調症になってもその現実を認められず、何かしら理由や理屈をつけて現実と向き合うことから逃げていたのかも知れません。監督とのインタビューの中で(特にお母さまが)、監督からの強いご指摘に対して極端に話をすり替えようとする場面(お母さまが「じゃあパパに死ねっていうの?」と監督を責め返そうとするなど。)から、わたしはそう考えました。
次にお姉さまですが、映像記録を観たり、監督ご自身のナレーションを聞くと、大変人懐っこく、可愛がられたことが分かります。また、占いを信じたり、たった一つの不安を拡大視してしまうような(学生時代にガンで死んだ同級生を引き合いに出して、お姉さまがかつて「自分はガンかもしれない。」と言っていた、というエピソードを監督ご自身がナレーションされていました。)感受性の高さも伺えます。一方、これらの要素は「夢見がち」で「現実逃避的思考」になりやすかったり、思い込みが強すぎるという、これも一つの認知の歪みであるとも個人的には考えます。それらを踏まえて考えると、お姉さまはもしかすると、優秀なご両親のご期待に応える「べき」だと思い込んで思考的視野狭窄に陥り、占いなどが好きな自分よりも両親という「他人」を自分の人生の中心に据えてしまい自己肯定感が損なわれる要因を作ってしまったのではないでしょうか。更に、何度も受験に失敗し、その感受性の高さにより実習でも上手くいかないことで必要以上に傷付き、「みんなが自分を責めている」と現実をネガティブな方向へ拡大させてしまったのかも知れないと考えました。
そして監督ご自身について、大変家族思いで、特にお姉さまに対しては強い愛情を感じました。一方で、映像作品を志したところからも、やはり感受性が高いことも推測できます。お父様やお母さまへインタビューする際に、たまに感情が乗ってお姉さまへのご両親の所業を尋問口調で責めるところからも伺えました。わたしが気になったのは、監督ご自身がお姉さまに何度も話し掛けるある場面で「パパとママに復讐したい?」という趣旨の質問をしたことです。お姉さまは何も答えなかったのですが、これは監督ご自身がご両親に絶対的に非があることを確信するとともに、お姉さまも「絶対に」ご両親のことを恨んでいると「思い込んでいる」ように思えてしまい、個人的に認知の歪みであると考えます。しかし、それでも結局、監督ご自身が2008年まで四半世紀もそのようなご家族の状況を打開できなかったのは、当然ながらお姉さまだけでなくお母さま、そしてお父様も含めてご家族を愛していたからだと思います。それと、9年間大学で、その後は神奈川で就職するなどして、家族の抱える事実からある意味で最も「逃避していた」という事実(これは監督ご自身がナレーションで「とにかく家にいたくなかった。」という趣旨を神奈川への就職について話す件で話しているので、そう推測しました。)による罪悪感も、なかなか踏み出せなかった要因なのかも知れないと思います。
上記のようなご家族のパーソナルがあった結果、お姉さまは統合失調症になり、ご両親はそれを否定して家に軟禁し、監督ご自身もなかなか踏み出せないまま、25年もの歳月が流れてしまったのかも知れません。
これが、わたしが考える「どうしようもなかった」理由のもう一つです。
以上のことは、しかし、一つ一つはよくある状況、よくいる人たちだと思います。わたし自身も、極端な考え方をしたり、無遠慮に人の心に踏み込もうとしたり、自分本位なところの多い人間なのですが、こういう状態にはなっていません。また、上記の条件二つが「表面的に」当てはまったとしても、そうならないご家族などたくさんいるのでしょう。
わたしが考えるに、上記にある「環境」と「家族という構成員のパーソナル」は、拳銃でいうところの「銃筒」や「弾倉」、「トリガー」を構成する「誘因」でしかなく、最終的にそのトリガーを「引く」のは、言語化出来ない、その家族そのものが持つ「個性」なのではないかと考えます。ですが、逆に言えばそれらの個性を持っていても上記のような「誘因」を防いでいければ、違う未来もあるのかも知れません。
ですので、誠に勝手ながら自分のことだけ想定して考えると、「経済的環境は社会に助けを貰わないと生きていけない程度の生活をして、家族ともなるべく向き合いつつ、しっかり自分の人生を自分のものとして生きるのが大切なのかも知れない。」という結論に至りました。
作品の終盤、お母さまとお姉さまは亡くなってしまいます。もしかすると、お姉さまはずっと軟禁され、ちゃんと運動する機会に恵まれなかったことが肺がんの遠因の一つかも知れませんし、お母さまの認知症もお姉さまのお世話による心労がたたった結果かもしれません。お父様と監督が最後に対峙するリビングには家族の象徴であったソファはなくなり、一時期は汚くなった部屋も綺麗になり(寂しくもなり)ました。監督の叔母は「(お姉さまを)愛しているから閉じ込めたのではないか。」という趣旨をインタビューで語り、お父様も「失敗したとは思わない。」(成功と失敗が価値基準ということですね。)と、自分たちの半生を映像化することに意外なほどあっさりと快諾しました。そこに何の落ち度もないかのような実父の笑顔に、年を経てすっかり丸くなった監督は、疲れとも後悔とも、諦めとも分からない風情を背中に宿しながら「カット」と言い、画面が暗転します。
わたしは、この作品が「お姉さまの生きた証を残す」ための作品であると同時に「ご両親への復讐」なのだとも思いましたが、ひょっとすると、「監督ご自身が何も出来なかった自分なりの贖罪行為であり、懺悔の具現化」なのかな、と最後は思いました。なので、とても強烈な作家性が感じられ、その執念ともいえるものに呆然としましたが、個人的にはご両親だけでなく家族という構成員の一人であった監督ご自身についての心情を見せていただきたかったため、星を一つの半分除きました。
ドキュメンタリーだけどやはり映画作品
冒頭、映像はなく母親が声を荒げているシーンから始まる。この調子でずっと続くのか…しんどいな…と思っていたが、本編では概ねお姉さん以外、冷静で普通の人達という印象をうけた。
そこに監督の意図を感じた。
この映画は、もし身近な人間が統合失調症になったらあなたはどうしますか?と問われている映画だと思った。監督としては、家族を曝け出してどうすればよかったか?という答えを観客に求めているのかな。
病気でおかしくなる娘を医者に診せず、しまいには南京錠をかけ部屋からも家からも出られないようにしてしまう。正直普通ではないけど、映画ではそこまで異常に感じなかった。なぜか?父母の異常さがメインではなく、統合失調症というお姉さんの症状を観客に映し出すことを主としているからだと感じた。
25年という長い年月の中で、父母や監督自信も、冒頭の母親のように声を荒げ、精神的に追い詰められおかしくなった日があったと思う。
それこそビデオカメラを回して、誰かに見られているという意識をもっていないと、あの様に冷静に話しをすることは出来ないだろう。
もし私の親がそうだったなら、自分もブチ切れて話し合いなんてできないだろうし。。
カメラを回していつか映画にするかもという意識を持つことで、平静を保っていたのではないかな。
統合失調症という症状と長い年月、当人も周りも苦しんでいたが、合う薬が見つかればたった3ヶ月で普通を取り戻せるという事実だけが重く残る。
お姉さんの人生を救えなかった、父母の人生もそうだ…。監督の後悔が滲んでいる。
もしあなたの身近な人間が精神的な病気になってしまったらどうしますか?
答えなど出ません。
ビートルズが好きだったんです
途轍もなく長い自宅軟禁の状態から入院治療を経て「普通の状態」となってから、藤野知明監督のカメラに映るとき姉の雅子(まこちゃん)は必ず「ピースサイン」でポーズをとっていた。特にラストシーンの画像は脳裏に焼き付きます。
もっと早く病院に行っていれば、20代30代の若い時を「普通の状態」で過ごし、輝く人生があったかもしれない。誰もがそう思うが、かなりの長生きとなった父親は息子である藤野監督の「どうすればよかったか?」の問いに母の考えに従ってのことだが「間違えたとは思ってない」と話していた。本心はわからないが子どもの頃から勉強も出来て両親と同じく医学を志す娘がただひたすら愛おしく自分の手元から離したくなかっただけかもしれない。
この映画は統合失調症の原因や病気がどんなものかを目的としてないと冒頭で伝えていた。しかし、その病気は「勇気を持って」受診すれば解決の方向が見えてくることを伝えたかったのだと思う。
このようなドキュメンタリー映画も最初から「重い」「辛い」と思い、避けるのではなく「勇気を持って」観ることをおすすめします。
雅子さんは私と同学年。我々の最大のアーティストはビートルズ。彼女はいつも聴いていたようです。お見送りの時もビートルズの曲が流れていました。
部外者は簡単には言えないけれど
最後のお父さんの言葉に胸が詰まりました。
なんとも言えない気持ちになりました。家庭のビデオで日常を追っているのですが、壊れていくお姉様。それを認めないご両親。最初に診察を受けた、医師の病気でないとの言葉だけを寄り処に医療を受けさせず、大枚をはたいて、名鑑に名前を掲載させてみたり、論文を書かせてみたりして、何とか病気ではないと思い込もうとなさる両親がもどかしく悲しかった。お母様が亡くなりようやく医療につかながり、回復の様子が見え笑顔が戻ったお姉様。何故もっと早く。と思わずにはいられませんでした。最後にお父様が、間違ってなかったとおっしゃったこと。もしそう思わなかったら自分、お母様、娘様の人生の否定になってしまうので、無理にでもこれがベストな方法だったと思い込んでおられたのかと思いました。ご自分の尊厳にかけて本当に思い込んでしまったのだと思いました。どうすればよかったのか?これでよかった、これしかなかった。とお父様は思われたのでしょう。見せていただいたものとしては、もっと早く医療につなげたらよかった。とおもいますが、本当はどうすればよかったのか、、、と考えさせられました。
紺屋の白袴
どうすればよかったか?
姉は、
幼少の頃から恐れていた癌をステージ3を患いながら、それが素で統合失調症を投薬で調整しながら永らえて癌で亡くなれた。
この話は、
精神分裂症と言っていた頃から統合失調症に病名が大変更あった頃の話なんだ。
当然、
そのことは疾病に対する治療方法も社会的配慮も大変化があり、そしてその後の向上も進歩もあった。
それは、
昨今の癌死亡率と同じような向上があったようだ。
つまり、
適正な統合失調症治療をして疾病軽減していれば、癌の早期発見と治療で、今日も存命している可能性はかなり高いものと思う。
振り返ってみると、
血みどろの太平洋戦争世代の医学系御両親が、高度成長期の子女の苦悩を、臨床医でもないのに今日の進歩する臨床医療を、判断することはとんでもなく困難であったことは自明ではある。
この辺の落差、断層を理解できないのが、世相と隔離したプライド高い研究畑の人達だと思う。
父親が言った「仕方ない」のではなく、未来のためにではなく、今を、我が子を、虫の目で観る努力があのころ必要だろう。
とっても、
子供の頃、お絵描きが上手なお姉さんの絵が、病に侵されるとあんなにも稚拙なお絵描きになるのかと驚いた。
監督は、
勇気あるドキュメンタリーだったが、
インタビューではなくカウセリンをすべきだったかな。
(^ω^)
どうすればよかったか?
ドキュメンタリー監督の藤野知明が、統合失調症の症状が現れた姉と、
彼女を精神科の受診から遠ざけた両親の姿を20年にわたって自ら記録したドキュメンタリー。
面倒見がよく優秀な8歳上の姉。
両親の影響から医師を目指して医学部に進学した彼女が、ある日突然、事実とは思えないことを叫びだした。
統合失調症が疑われたが、医師で研究者でもある父と母は病気だと認めず、精神科の受診から彼女を遠ざける。
その判断に疑問を感じた藤野監督は両親を説得するものの解決には至らず、わだかまりを抱えたまま実家を離れる。
姉の発症から18年後、映像制作を学んだ藤野監督は帰省するたびに家族の様子を記録するように。
一家全員での外出や食卓の風景にカメラを向けながら両親と対話を重ね、姉に声をかけ続けるが、状況はさらに悪化。
ついに両親は玄関に鎖と南京錠をかけて姉を閉じ込めるようになってしまう。
どうすればよかったか?
とんでもない自問自答映画
何処か上品。そこが良い。
なにがしたかったのか?
見終わったところです。ドキュメンタリーであることと、主要な登場人物が高齢のため、台詞が少し不明瞭で聞き取りにくいところがあったのが残念でした。おかげでラストの父親の一言がよく分からず、少しモヤモヤが残りました。(エンドロールを見たら、整音はやってはいたようですが)
さて、こう言えば身も蓋もないないけど、あれが正解だったのでは。発症の時期が時期だけに、発症した時点で精神科にかかったら、たぶんそのまま病院で…。一緒に暮らしていた両親、特に母親への負担は大きかっただろうけど、どうも母親が通院を望まなかったようだし。(父親の弁を信じればだけど)
統合失調症の患者がどうなのかを記録した、あまりない映画なのは評価できると思います。私も勉強になりました。(一般の方々が想像しているのは、別の病態の統合失調症なのかな?)
愛を感じた
本当に本当に守りたいものは手の届くところに置いておきたい
コロナのとき国はワクチンを勧めたけど医師たちはワクチンを打たなかったって話当時はよく聞きました
昔はロボトミーがノーベル賞取るほどすごいことだったけど危ないことだということを知ってる人は知っていたかもしれないし
お父さんは我が子は病院に連れていきたくなかった
病院の治療を心から信用していなかったから
でもそれを息子に言ってしまうと自分の研究していることが間違っているということになってしまうから言わなかった
だから最後のあの言葉になったのかな、と
お金はあるのだからどこか遠くの施設や病院に預けることもできただろうに
まわりには娘は海外に行っているとでも言っておけば
でもそれをしなかった 一緒に生活をして同じ時間を過ごした
ご両親はそうせざるしかなかったのではなくそうしたかったのかな
リビングの大きな観葉植物が生き生きと育っているのが印象的だった
棚の上のポトスもツタを伸ばして元気に育っていた
ご両親は心に余裕があったのかな
幸せだったのかもしれない
娘さんご本人は幸せだったかどうかは置いておいて
娘さんが先に亡くなられて良かった(不謹慎ですが)お父様は娘さんが産まれてから最後まで一緒に過ごせたことに幸せだったのではないかと思った
それとお父様世代で料理をつくる男性は少ないと思うけど当たり前のようにキッチンに立っていた
同窓会行って欲しかったな
俺が連れていくよってなぜ言わないのだろうと思った
両親を責めるための映画
統合失調症の母を持つ身としては他人事とは思えず感情移入しすぎて見ていられなかった。
私の場合は病院に連れて行こうとしない父と、病院に行きたがらない母を無視して民間救急に依頼し、無理やり入院させたので、なぜこの息子は家を出て、自分は安全な場所で両親の説得だけなんだと終始イライラしっぱなしでした。本当に姉のことを思うなら実家に残り自分で病院に連れて行くはずです。
最初、タイトルのどうすればよかったか?は自分自身に問うているのかと思いましたが、最後にどうすればよかったか?と父にきいています。
暗に父に失敗だった。なぜ病院に早く連れていかなかったのかと責めています。
これは父を(母も)責めるための映画なんだと思います。そんなもの撮ってる間に自分で行動に移せばいいのにと思ってしまいました。
でも映画としては良い映画だと思います。
こんなに感情を揺さぶられる映画はなかなかないし、統合失調症のリアルな症状やその家族の大変さなどがわかる、家族自身が撮影しているドキュメンタリーは他にないと思います。
満席のミニシアター。上映後、全員が無言だった。
統合失調症の症状が現れた姉と、彼女を精神科の受診から遠ざけた両親の姿を20年にわたって自ら記録したドキュメンタリー。お姉さんの症状も、家族の衝突も、それぞれの認識もつぶさに残す。
「どうすればよかったと思いますか?」
息子から投げかけれた質問に対して、お父さんが
「失敗ではないと思う」と答えたのが印象的だった。
ここに当事者への介入の難しさがあると思う。
他者から見て、こうしたらいいだろう、こうすればよいのに、は当事者には関係ない。なぜなら、他者は当事者ではないから。
当事者がその時々に「どうしたらいいだろう?」と考え、時には諦め、時には保留し、時にはやっぱり「どうしたらよかったか?」と自身の選択を後悔しながら、瞬間瞬間を進めている。その瞬間が、当事者にとって答えであり、正解にするしかないというようなカルマをも背負っている。
私がこの映画を見たミニシアターは満席だった。
映画が終わり、照明が明るくなって、それぞれが立ち上がっても尚、誰も喋らなかった。誰もが頭の中で映画を反芻し「どうすればよかったか?」「こうすればよかったのに」を反復しながら、誰も明確な答えを持ち合わせていないかのようだった。
何をどうしたって、時は巻き戻せない。今の選択を振り返ると、もっとよかったであろう選択が無数に出てくる。そちらの方が当たり前によく見えて、複雑に絡み合った今の瞬間を否定したくなることがある。だけど、フィルムに残るお姉さんの両手ピースや片足立ち、花火にインスタントカメラを向ける姿は、否定したくないと思った。その姿を見れたことこそが、この映画の功績なのではないかと思った。
今月はドキュメンタリーで終わり
どうすればよかったのか。難しい作品ではあるが、自分としてはこの家族はこれで良かったのだと思う。両親、娘さん、苦しんだ決断の上の出来事には思えなかったからです。もっと早くに精神科にって意見はあると思う。だが自分のおばあちゃん辺りだと、双子は隠してたり言えない職業があったりと暗黙の差別があったりしたのを聴いたことがあります。この家族は両親が研究者で他の家庭よりは裕福に見えました。貧困家庭であったならすぐに精神科に連れて行って即入院ってなったかもしれない。そして研究者の地位みたいのが邪魔をしてバレたくない気持ちが優先しているのが感じられました。途中のお姉さんへのインタビューですが、監督自身が考えてきた事、言ってほしい事を口から発せられていて、お姉さんの返答が無い部分にとても感慨深い気持ちになりました。このような自分を曝け出す作品を作ってくれてありがとうございました。
スティグマ どうすればよかったか、そしてどうすべきか。
ごくありふれた家族の中のひとりに統合失調症の症状が現れる。その事態に家族がどう向き合ったのか、何をして何をしなかったのか。本作はどうしてこうなったかではなくどうすればよかったのか、そしてどうすべきかと問いかける。ごく私的な家族の記録から普遍的な意味を持つ本作のテーマが浮き彫りになる。
本作の監督の姉が若くして統合失調症を患う。この当時は病名を精神分裂病と言った。この病名からもわかる通り当時の精神病者への世間の偏見はまだまだ根強いものがあった。それこそ過去には病気への無知から乱心者として江戸時代から続く座敷牢に閉じ込めるなどの風習があった。そしてそれは1900年の精神病者監護法により私宅監置として50年後廃止されるまで制度としても存在した。
最初に姉が発症した時、知り合いの専門医に診せたがどこも悪いところがない健康体であり、精神病などというのは娘がかわいそうだと父は言い放った。しかしそれから姉の症状がよくなることはなく弟である監督は家にいることが辛かった。大学進学を機会に家を離れ姉から解放された。その時から二十年以上の歳月が流れる。
二十年以上もの間治療も受けさせてもらえず放置されている姉やその両親の姿を見てさすがに危機感を覚えた監督はこの家族の姿を記録に残すことを思い立つ。この家族の姿を通して社会に何か伝えるべきことがあるはずだと。
監督自ら父や母に問いただす場面がある。母は父の意向には逆らえなかったと言い、逆に父は母の気持ちを考えて治療を受けさせなかったという。あたかも責任を擦り付け合っているかのようにも、またお互いを思いやっているかのようにも見える。
母の死後妹である叔母から聞かされた話では娘がかわいそうだから守ってあげたいという気持ちが母にはあったのではないかという。
果たして本当にそうだろうか。娘のことを一番に考え、娘を守るために治療を受けさせなかったなどと。
精神病であることが世間に知れたら娘がかわいそう、本当にそうだろうか。娘ではなく自分たちがかわいそうだったのではないか。精神病の娘の親、精神病の娘がいる家、世間からそのように見られるのを何よりも恐れていたのではなかったか。守りたかったのは娘ではなくこの家ではなかったか。だからこそ娘を外に出さないように玄関に鎖をかけてまで家を座敷牢にしたのではなかったか。
いまや医学の進歩による薬物療法により統合失調症の症状は劇的に改善されるようになり普通に社会生活ができるまでに回復できるという。病名も偏見を生まないように精神分裂病から変えられたことで患者の家族の抵抗感も薄れて患者は初期症状で診察を受けられるようになった。だが姉が発症したのは80年代でまだまだ病気に対して偏見があった。両親のとった態度を息子である監督も一方的には責めることはできなかった。監督自身も姉に背を向けて逃げ出したころがあった。
母が亡くなり、姉も亡くなったあと、監督は父に問いかける。どうすればよかったかと。父はあれでよかったと答える。余命いくばくもない父をいまさら責める気にはなれない。
ただこの家族のたどった軌跡を監督は世間に公表する。なぜこの家族は誤ってしまったのか。姉の人生を無駄にしてしまった原因は何だったのか。
スティグマ。精神疾患や身体障害者に対して向けられる偏見という意味だけではなく広くマイノリティに対する偏見という意味を持つ。
精神疾患に対する偏見などなかったなら、精神疾患を患った娘を恥じることなくすぐさま治療を受けさせたなら、姉は人生を棒に振らずに済んだのではないか。
これはこの家族だけに起きた悲劇ではない。過去にも偏見から精神障害者が同じように治療を受けられずに未治療期間が長引いたために手遅れになるケースは後を絶たなかった。
姉が25年目にして初めて入院し投薬を受けたことにより回復した姿を見てどうしてもっと早くにと思った観客は少なくないだろう。しかしそれを今の時代の我々が言っても仕方ないのかもしれない。果たして本作を見ている我々が当時同じ状況に置かれてこの家族のようにしなかったと言い切れるだろうか。
さすがに今の時代これだけ精神医療が発達して偏見も薄れたからこそ精神科への受診者数は増加しているという。逆に統合失調症患者の入院者数は減少しているという。これも薬物療法の成果なのだろう。
これからは統合失調症患者の家族も躊躇なく診察を受けさせることができるだろう。今や国民の四人に一人が精神疾患を患うという。
風をひくように心も風邪をひく、内臓が悪くなるように脳も悪くなる。当たり前のことである。精神病者への偏見は薄れていくだろう。
しかしスティグマは精神病者だけの問題ではない。今の時代、性的マイノリティや移民排斥問題に見るように相変わらずスティグマに苦しめられている人々が存在する。
スティグマにより生きづらさを感じる人々。この姉のように人生を奪われる者は後を絶たない。
仮に自分の家族に性的マイノリティの人間がいたとしてその時この家族のように世間体を気にせずにいられる人間がどれだけいるのだろうか。
本作はどうすればよかったか、そしてどうすべきかと我々見る者に問いかける。スティグマによって人生を奪われた姉のようにいまも人生を奪われる人々を前にして我々はどうすべきかと本作は問いかける。
誰が、「どうすればよかった」のだろう?
子供の頃から成績もよく医学部に進学した姉が、在学中に突如奇声を発し訳の分からぬ事を叫び始めた。現在ならば統合失調症と名付けられるその症状を医学研究者の両親は病気と認めようとせず、家に軟禁状態にして25年間放置したという経緯を弟である監督が記録し続けたドキュメンタリーです。
医師に診せるべきという監督の勧めを両親は頑なに拒み続けます。それは、「こんな娘が居る事を世間に知られたくない」という古い村社会的な思いからなのか、「医師の家からそんな子供が出たのは恥だ」といった歪んだエリート意識からなのか、本作中で叔母さんが語る様に「その子にとって良いと思うから隠した」のか、或いは本当に「娘は病気ではない」と信じていたのか。そんな重圧に耐えきれずに監督自身は高校卒業と共に家を出て、帰省の度に家族の変化を見続けたのでした。
タイトルの「どうすればよかったか?」に対する答えは明らかで、「娘(姉)の発症時に医師の診断と治療に直ちに当たるべきだった」に違いありません。しかし、もう一歩踏み込んで、自分が父だったら・母だったら・弟だったらと考えた時、その判断が揺らいで来るのも事実です。
そして、もう一つ気になる事。「どうすればよかったか?」には主語が記されていません。「父母はどうすればよかったか?」なのでしょうか、「私(弟)はどうすればよかったか?」なのでしょうか、「家族はどうすればよかったか?」なのでしょうか。恐らく、監督自身も含む「家族全員」の選択を問うていて、それを意識して撮っているのでしょうが、僕にはそこが曖昧に感じられました。
「監督は、弟である自分自身にもカメラを向けているのだろうか」
確かに、映像内に監督自身も映る事があるのですが、監督は本当にカメラの前に立っていたのだろうか、安全なカメラの向こうに居たのではないのかな? それは、映画館で観る第三者の無責任な問いかもしれませんが、映像が映し出すものの残酷さ、映像制作が制作者に突き付ける苛烈さを改めて感じたのでした。
劇場を出て最初に目に入った物は奇しくも「籠の中の乙女」のチラシだった
全204件中、61~80件目を表示