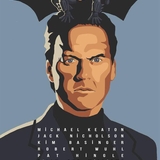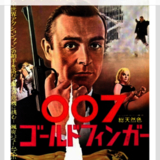スオミの話をしようのレビュー・感想・評価
全446件中、1~20件目を表示
ご結婚、おめでとうございます!
それはさておき.....
いやぁ驚いた。
ビックリする程つまらなかった。
まず謎解きとして話が破綻している。何処をどう見ても誘拐は狂言、自作自演と丸わかりでしょうよ。こんなのネタバレにもならんわ。
さらにコメディとしてもキッツイなぁとしか。今どき急に中国語で話し出すのが面白いかなぁ?あと逆探知だとか無言電話かけてやったぞ、だとか誰が金の入ったバッグを落とすかで揉めるところとか。三者面談のくだりに至っては要らないんじゃないの?あれで笑う?
四半世紀前なら受けたかもしれないけど。
なんせ苦痛でした。
久部劇団向き素材
面白かった〜
寒くてとてもつまらない
失踪した妻を探す夫と元夫たちの話。
とんでもなくつまらなかったです。
途中で観るのやめようかと思ったレベル。
真犯人が分かりやすすぎる。
ヒントが見え見えでミスリードを狙ってるのかと
思いきやそうではなく予想通りの結末。
素敵な俳優さんが揃ってるのに
脚本がだめなのか演技がとても寒い。
瀬戸さんの役にはもはやイライラするレベル。
極めつけはラストの歌。
ここまで観たし最後まで観ないという気持ちで
頑張ってふんばりましたけど、なんだったんだ、、
長澤まさみさんが綺麗だったのだけが救いでした。
舞台劇として再演希望
ダイワハウスの宣伝のようなキャスト
何となく流し観しみ的な
長澤まさみさん、良かったです。
が、
宮澤エマさんが更に良かったです。
お二人共、コメディエンヌとしても良いですね。
映画館でも観ましたが、WOWOWで放送したのを録画し、お風呂上がりのお手入れタイムなどで何となく流して観ています。
それくらいが丁度良い感じでしょうか。
軽いコメディです。
なんかミステリーのような宣伝の仕方でしたが、違いますね。
劇場で観て、印象に残ったというより良く覚えていたのが、いきなり始まるミュージカルのようなヘルシンキ、長澤まさみさんは堂に入っていますが、男性陣の慣れてない、ちょっと不器用な感じもご愛敬です。
相手事にキャラを変えるまさみさんとエマさんが
面白かったです。
俳優陣が豪華、話は薄い気がした
天才三谷映画!面白かった!
眠気との戦い
長澤まさみ100点、オチ10点。でも本当は…?
全446件中、1~20件目を表示