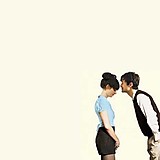A.I.のレビュー・感想・評価
全83件中、61~80件目を表示
結局作品は自分自身なんです
夢
エクスタントの原点?
主人公の子供の縁起が凄い
ストーリーも先が読めずに引き込まれる
2000年経過は転けたけど、、、
CGもこれ見よがしではなく、自然に盛り込んでおりあくまでドラマが主なのも良い
ひたむきな愛をもつロボットに涙
二人の巨匠の"共同作品"
これは"スピルバーグ監督作"とも"キューブリック監督作"とも括ることはまずできない。これは二人の偉大な巨匠が"共同監督"で作ったものだから。実際はスピルバーグ監督だけど、スピルバーグ作品にしては本編全体がどこか冷たい。この当たりはキューブリックの『シャイニング』に通じるかも。あとどこまでも冷酷に、誰かと別れるその瞬間と誰かと出会う瞬間もどこまでも反らさず描いてて、しかも心が通じたのかも最後幸せになれたのかも見終わっても不明瞭で、引用するならモヤができた。そこは同じキューブリックの『2001年宇宙の旅』的で、実際僕は『2001年~』を初めて見たときモヤだらけだった(苦笑)
ただ僕は押井版の『攻殻』が結構好きな身なので、哲学的なSF好きには本作は絶対たまらない。長いし結構重いから相当の体力は必要だけど、その時間を耐えられるぐらい話にひたすら見入ってた。僕の中では『ブレードランナー』『AKIRA』と初めて出会った以来の、イマジネーションが大きく広がった魅力溢れる未来映画だった!
最後の展開に感動した
全編哀しい雰囲気で切ないだけの映画だったが、最後に人類が滅んでから進化した宇宙人が出てきたのには、死んだ頭が突然覚醒したかのように感動・感激してしまった。この展開で、評価が普通→良いに変わった。単に、ロボットに対する同情をかう映画ではなかった。「2001年宇宙人の旅」、「スターウォーズ」、「ET」等のエッセンスも盛り込んでいる。さすがスピルバーグ、最高の演出効果に大拍手したい。最後の数分間のために、長かった前哨戦があったんですね。
ライオンが涙するところ
SF作品の中では最も好きな作品。
今まで観たスティーブンスピルバーグ監督の作品の中で最も切ないと感じる。
プログラムされた「愛」の中、デイビッドは母にもう一度愛されたいという一心から、人間になるためおとぎ話のブルー•フェアリーを探す旅に出る。
この作品の中で私がとてつもなく惹かれるのは言葉だ。
母モニカがデイビッドに愛をプログラミングする時の7つの言葉
「巻き雲 ソクテラス 分子 音波 ハリケーン ドルフィン チューリップ」
や、デイビッドの作り主であるホビー教授の「ロボットから人間へ」からの
「人間の子よ
坂立つ海の彼方へ
フェアリーと共に
嘆きに満ちたこの世を後にしよう
危険な旅路だが 得る物は大きい」
(Come awway O human child
To the wters of wild
With afairy hand in hand,
or the worl`s more full of weeping
Than you can understand,)
さらにマン・ハッタンの事を「ライオンが涙する地の果て」
「海に沈んだ地の果ての都市」`夢が生まれる その場所´
と呼ぶなど、詩的でなぜか惹かれる言葉の数々にとても胸が苦しくなる。
おそらくインタビューでスティーブン監督も言っていたが、
この物語は「現在、そして未来のおとぎ話」がテーマであるためこういった曖昧で詩的な文が多く出たのではないかと思う。
明確な言葉よりもこういった言葉を使うことで観客たちに想像の余地を与えているのではないだろうか。
そういった夢物語なのに、一方でルージュ・タウンといった性と欲に満ちた世界や、ジャンク・フェアのような残酷で身勝手な人間性も織り交ぜてくるギャップもいい。
また、この作品は元はスタンリー監督(シャイニングの方)が撮る予定だったが、亡くなってしまったため懇意だったスティーブン監督が一度断ったこのオファーを受けた形となっている。
スタンリー監督を偲んでのこともあり力の入った作品となったのではないだろうか。(そのような経緯がなくともスティーブン監督は良い作品にする事ができただろうが)
〈舞台美術について〉
これは私の好みだが、SF作品ではこういったあり得ない世界を撮るとき、CGに頼りすぎずある程度までセットや小道具など人が現実で作った物を入れている作品が好きだ。(フィフス・エレメントや、スターウォーズⅣ、ザ・セルなど)ほぼ全てをCGに任せる作品がこのところとても多い。だがそれだとあまりにも奇麗すぎる映像に、現実感が無く(それが狙いなのかもしれないが)感情移入がしにくい。(アバターで強く感じた)
観客が想像できる範囲内の素材や想像物を使って、いかに未来的に新しく作るかが監督に求められる難しいさじ加減なのかなと思う。
その点ではこの「AI」はとても美しいと感じる事ができる作品のひとつである。
〈キャラクター〉
・デイビッド(ハーレイ・ジョエル・オスメント)
「君は2つとない特別なメカだ」という言葉を信じ、人間を目指す彼。仕組まれた旅と知らず進み、人間になりたい彼は、不思議とこれだというセリフが思い出せない。
それは彼が「無知」「純粋」「子ども」であるためあまり言葉が達者ではないことからなのかと思う。
行動が彼を物語る。
特にラスト近く、自分と同じロボットを目の前にして嫌悪するシーン。
「ママは渡さないぞ ママは僕のだ ママの子は僕だけ 僕がデイビッドだ!ぼくは特別でユニークなんだ!!僕がデイビッドだ!僕がデイビッドだ!」
と自分を殺す(壊す)シーン
ヘンリーの「人を愛すことができるなら憎むこともできるはずだ!」という言葉が頭をよぎった。
私はあのシーンが一番人間らしさを感じた。
そして自殺。その少し前の自分を大量に吊るされている所をみて「自分は特別じゃない」と知り、絶望する彼の表情には悲しみを感じずにいられない。
2000年の時を氷の中待ち続け、夢を叶える。
そしてようやく`夢が生まれる その場所´にたどり着く。
ハーレイ少年の演技はすごいとしか言いようがない。
・ジゴロ・ジョー(ジュード・ロウ)
「彼女も僕と同じさ 君のサービスを期待している。
愛してるのとは違うんだ 愛するわけがない。
君は人間の子でもなく 犬や猫やカナリアでもない
僕らと同様仕えるために造られたものなんだ。
君に飽きたから捨てたのか 新型と交換したのか
あるいは気を損ねるようなことを君がしたか
彼らは利口なメカを造りすぎた その間違いがツケを呼んでる
生き残れるのはメカだけ!
だから憎まれる
どこにも行かず 僕と ここに!」
愛を囁き売り歩く彼だからこその、この言葉に彼の全てがあるように感じる。キザなセリフすら様になる。
彼は「人間をよく理解したロボット」としての役、デイビッドとは対照的な存在として際立っていた。
「僕は生きた! そして消える!」
ロボットであり、あれほどメカと人間の区別をしっかりとつけていた彼が、最後の言葉に選んだのが「生きた!」と「消える!」である。「生」を全うした、だが「死」を人間とは区別していた所に惹かれた。
脇役では一番好きなキャラクターである。
・テディ(ジャック・エンジェル)
「壊れるぞ」
マーティンに対抗してほうれん草をほおばろうとしたデイビッドを止めた彼。
おとぎ話ピノキオではジミニーの立場にある彼はデイビッドの最後までひたすら彼の側にい続け、見守る。
古い玩具である彼は無知なデイビッドに代わって賢者のように助言をくれる。
またラスト近く、モニカを蘇らせるために必要な髪を持っていたり、彼無しではこの映画はもっと殺伐としていたと思う。
あんなに可愛らしい外見なのにおじいさんのような声なのがまたいい。私も欲しい。
・モニカ・スウィントン(フランセス・オコナー)
「世の中に無知な あなたを…」
デイビッドを捨てるシーン。突き飛ばしたことに自らも傷ついていた。このセリフがとても苦しかった。デイビッドはまだ何もわからないのだということを実感させる。
「愛してるわ…本当に愛していたのよ」
最後のシーン。愛していた、と表現する彼女は本当は気がついていたのではないかとドキリとした。
・ホビー教授(ウィリアム・ハート)
「君の選択を知りたくてね ブルーフェアリーを人間の`ないものねだり´の一例と思うか それとも人間だけの特質 `夢を追う能力´を君が持つか こんな意思を持つ機械は存在しなかった」
デイビッド「僕だけ特別なのかと…」
「息子も特別だった 君は新種の第1号だ 本当の親に会わせよう 君を造ったチームだ 本当によくやった」
ゼペットの立場にいる彼。作り主であるのにデイビッドのことを何も理解していない。デイビッドに絶望を教え、トドメを刺したのは他でもない彼だと思う。
ちげーんだよ!デイビッドが望んでるのはそんな事じゃない!と思わず殴りたい衝動に駆られる。
亡くした息子にもう一度会いたいと願った彼が生み出したロボット。それ故に人間になりたいとデイビッドが望んだのは必然だったのかもしれない。
にしてもこんな残酷なことはない。
亡くした息子との再会を望みながらデイビッドのことを息子としては接しない。
傲慢だ。
メモ
原作「スーパー・トイ」
衣装(ボヴ・リングウッド)
音楽(ジョン・ウィリアムズ)
いい映画なのに…
スティーブン・スピルバーグの作品ということで、とても期待してみました。
小さい頃に見たことのある作品だったですが、内容を覚えていなかったのでまたみました。
まず、ラストシーンに迫る人類が滅んでから母親と仮再会するラストの30分で作品をブチ壊しにされました。
主人公が母親に捨てられ、残酷なショーの見世物にされそうになったり、そこで出会ったロボットと協力して、人間になって母親に愛してもらうために本当に存在しないブルーフェアリーを探しにいく…
そして、ブルーフェアリーに会うが、それはただのアトラクションの飾り…
それを本物だと思い、人間になりたいという絶対に叶わぬ願いわし続けて悲しい終わりにすればよかったのに…
実際僕はそこで泣いていました。
いままでみたスティーブン・スピルバーグの作品で面白くなかった作品でした。
劇場でみたかった
人工知能
母親への愛情をただただ求めて。
でも、その想いはつくられたもので。
少年の一途さと葛藤などいろいろ考えさせられます。
ラストは悲しいながらに幸せかな。
すごく切なく、すごく印象に残る作品です。
全83件中、61~80件目を表示