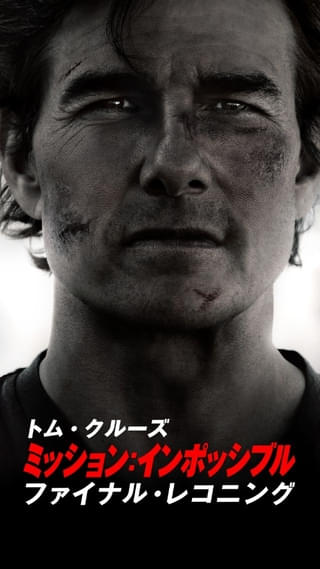コラム:若林ゆり 舞台.com - 第105回
2022年3月8日更新

第105回:原作映画へのリスペクトが、舞台でしか表現し得ない創意工夫に結実した「千と千尋の神隠し」の奇跡!

提供:東宝演劇部
スタジオジブリ、宮崎駿監督の名作アニメーション「千と千尋の神隠し」を舞台化するなんて、並大抵の覚悟ではできないことだろう。しかし、相当の覚悟と国際規模の並外れた才能が集結し、心をひとつにして、それは見事に成し遂げられた。すごい。さすが、「東宝創立90周年記念」「世界初演」と銘打つ大作だ。期待を裏切らない、奇跡のような、魔法のような舞台である。ここまで来るにはギリギリまでたいへんな試行錯誤が必要だったようで、ダブルキャストのうち、千尋役が上白石萌音のチームは公開ゲネプロを行うことができなかった。ここでは観劇が叶った千尋=橋本環奈チームのゲネプロをレビューしたい。
まず原作映画を見れば、誰しもが頭に「これをどうやって舞台化するんだろう?」という疑問を浮かべると思う。なにしろアニメーションでしか、映像でしか表現し得ないシーン満載のファンタジーだ。だが、演出家ジョン・ケアード(とパートナーの今井麻緒子)には勝算があった。この映画を愛してやまない彼らは、作品へのリスペクトと自らの想像力&創造力、そして舞台演出家のプライドを総動員、優秀なスタッフとキャストを集め、舞台でしか表現し得ない方法に答えを探り出したのだ。それは、特殊効果やLEDやプロジェクション・マッピングやワイヤーフライイングなどは一切使わず、すべて人の肉体と手製の小道具で表現する、という潔い選択だった。この選択と、数多の難関を見事にクリアしたスタッフ・キャスト全員に熱い拍手を送りたい! 原作映画ファンであり、舞台ファンである筆者は、両方のファン心を満たしてくれる舞台の完成度にコーフンしっぱなし、なのだった。

提供:東宝演劇部
まず、オープニングから映画の追体験がバッチリできる。お父さんとお母さんのドライブする車の後部座席にいるのは、引っ越しに気乗りしない、寂しげな千尋だ。ドライブ中の流れる風景は幕に映し出されているが、映像(アニメーション)が使われるのはここと、続いてのタイトルバック(なんとスタジオジブリ製!)、そしてラストのみ。これ以外はセットと人力で、しっかりと世界観が立ち上げられていく。ストーリーの流れもシーンも細かいディテールも、舞台の上で驚くほど忠実に再現される。とはいえ映画をそのままなぞっているわけではない。舞台で、演劇で、映画と同じ感覚を味わわせようとする演劇的工夫に満ち満ちて、異世界へと入り込んでいった千尋と同じような(ときには上回る)驚きと没入感をこれでもかと味わわせてくれるのだ。

提供:東宝演劇部
その世界観を担う大きな舞台は、もちろん神々が湯浴みにくる「油屋」。そのセットが現れたときは「うわぁー」と声が出そうになった。さすが、ミュージカル「レ・ミゼラブル」で帝国劇場の回る盆(回転舞台)を使い、ダイナミックなバリケードのセットを巧みに使ったケアード、今度はダイナミックに油屋を回す。ジョン・ボウサーが手がけるセットはまるで能舞台のようで映画の建物とはかなり違うが、この舞台には最高に適していると言える。美しく幻想的で、この作品が実現している表現と完全にマッチし、違和感がないのだ。
この作品は絶対、映画を見てから観劇した方がワクワクできると思う。初見でも間違いなく楽しめるが、小さなキャラクターの表情などは、やはり遠い席からでは伝わりにくい。映画を見ていればストレスなく補いながら楽しめるからだ。それに、「その表現、舞台でどうやってやるんだろう?」という疑問への「そう来たかー!」という答え合わせもすこぶる楽しい。たとえば釜爺の長い6本の手は、手のマペットをアンサンブルキャストが操演し、黒子のような操演者たちはその表情も見せてくれる。これは劇団四季でも上演しているミュージカル「リトル・マーメイド」のタコ魔女、アースラを思わせるが、それもそのはず、今回のパペットデザイン・ディレクションは「リトル・マーメイド」を手がけたトビー・オリエによるものなのだ。千尋の足下にわらわらいる小さなススワタリたちも同様に、操演者たちを見せることで表情がより立体的に伝わってくる。

提供:東宝演劇部
また、湯婆婆は人間が演じているが、彼女が怒ったときには大きな顔のパーツが操演者によって寄せ集まり、大きな怒りの表情がパペットによって表現される。青蛙や坊ねずみもパペットだ。操演者の演技を見せるこうした方式が「ライオンキング」でジュリー・テイモアがやった、革命的で多彩な表現手法から大きな影響を受けているのは明らかだが、実はそのテイモアも、日本の文楽にヒントを得てアイデアを膨らませたという。つまり、この手法は文楽や歌舞伎の黒子といった日本伝統芸能の“進化形”とも言えるのではないか。だから能舞台がしっくり来るのかもしれない。しかも、場面転換も役者たちによる人力。そこにも、「観客の創造力によって完成される」演劇の魔力がある。

提供:東宝演劇部
表現手法はパペットだけではない。そのキャラクターごとに最適な表現手法が選ばれており、「おしらさま」は完璧な再現度の着ぐるみだし、ひとりで3つの顔を表現する「頭(かしら)」、汚れきった身から変身する「オクサレ様」、鯉のぼりと新体操を合わせたような「白龍」など、その創意工夫にいちいち「わあ!」と心で(このご時世、発声は控えなければならないが)叫ばずにはいられない。そして、面白かったのが「カオナシ」。ダンサー・菅原小春による人並み外れた動きが、このキャラクターが持つ得体の知れない雰囲気を最大限に伝えてくれるし、暴走するときは「口」のパペットが現れて、食らう。こんな表現は凡人には思いつけない、でも見れば、これ以上の「3Dカオナシ」は考えられない、という仕上がりだ。千尋とカオナシが電車に乗るシーンには、「詩情」のようなものまで感じられる。これが痺れずにいられようか。
コラム
筆者紹介

若林ゆり(わかばやし・ゆり)。映画ジャーナリスト。タランティーノとはマブダチ。「ブラピ」の通称を発明した張本人でもある。「BRUTUS」「GINZA」「ぴあ」等で執筆中。
Twitter:@qtyuriwaka