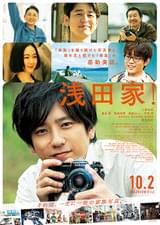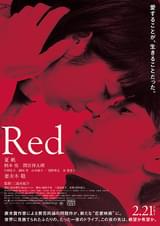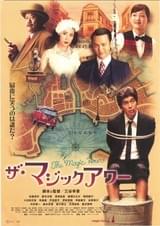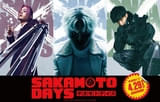妻夫木聡×大友啓史監督、不退転の決意と覚悟「たかが映画されど映画」【「宝島」インタビュー前編】
2025年9月18日 19:00

妻夫木聡が主演を務める大友啓史監督最新作「宝島」(9月19日公開)の“熱波”が、日本列島を駆け巡ろうとしている。その立役者である妻夫木と大友監督の胸にあるのは、「この作品をただの映画で終わらせたくない」という一念。作品の舞台である沖縄を皮切りに全国キャラバンをスタートさせた2人は、北海道まで20都市以上も訪れ、観客1人ひとりに熱い想いを直接届けてきた。そこまで衝き動かす原動力はどこにあるのか、その真意に迫るべくロングインタビューを敢行。全2回に分けてお届けする。(取材・文/大塚史貴、写真/間庭裕基)
第160回直木賞を受賞した真藤順丈氏の傑作小説を映画化する「宝島」の舞台は、戦後アメリカ統治下の沖縄。混沌とした時代を全力で駆け抜けた若者たちの姿を圧倒的熱量と壮大なスケールで描いている。
 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会当初は沖縄本土復帰50年となる2022年に公開すべくスケジュールを組んでいたが、コロナ禍で21年夏、22年春とクランクインが延期に。大友監督は何度も心が折れそうになりながら、その都度、原作を読み返して撮影への想いを募らせていったことを明かしている。それだけに、原作が放つ熱量の再現度には並々ならぬ想いを抱き撮影に臨んだ。

大友監督「脚本化に際してその都度、原作には目を通してきたのですが、何度読んでも心揺さぶられたのは、『諦めるな、生きろ』という登場人物たちからのメッセージでした。アメリカ統治下という特殊なコンディションの中で、様々な苦難にも諦めずに立ち向かい生き続けたという、ウチナンチュたちのとんでもない熱量が原作からブワーッと、まるで熱波のように届いちゃうわけです。その源は、時代そのものに抗いながらも、愛するものを守り、希望を捨てることなく真っ直ぐ生きようとした登場人物たちの“生きる力”なんだと思います。それが時には僕自身への叱咤激励のようにも思えて。それで、絶対に諦めちゃいけないと。映画としてその熱量を再現できたか……という意味では、手応えは凄くあります」
一方の妻夫木は、撮影時から「ただの映画では終わらせたくない」と口にし、オールアップ後に東京で顔を合わせた筆者に「この作品を携えて全国を回りたいんです」と熱く語っている。

妻夫木「沖縄で撮影中、ふと『映画が完成したらどういう宣伝をしていくんだろう?』と思ったんです。これだけの想いを詰め込んだ作品ですから、実際に自分たちで届けるべきじゃないかと感じて……。その時に『ウォーターボーイズ』で各地を巡ったことを思い出しました。
『ウォーターボーイズ』で色々な土地へ行き、そこで観てくれた方々にとって、自身の映画になっていく。『わたしも皆に広めます!』って。それぞれの想いを胸に広げてくれて、その口コミのおかげでヒットに繋がりました。『ヒットした』というよりも、『愛された作品』になったという意味合いが強くて。『宝島』もそういう作品であって欲しいという想いから始めました。
映画は観てもらって完成するものだと思っていましたが、実際はそこが完成ではなく、作品自体が成長していくものなんだと最近は感じています。映画って育っていくんだ、劇場で働く皆さん、お客様たちが育ててくれるんだって。映画の力を信じたいと思って始めましたが、逆にパワーをもらっています」
 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会そう語る妻夫木の表情は気負うことなく、あるがまま受け入れているように見える。全国キャラバンでは、妻夫木が鑑賞後のファン1人ひとりに名刺を手渡しするなど、コミュニケーションを大切にしている。その中で勇気づけられ、奮い立たされたファンの声を聞いてみた。
妻夫木「『ありがとう』ですね。『ありがとう』という言葉って、その人自身の人生の一部になった証なんじゃないかという気がするんです。『素晴らしかった』『いい映画だった』『泣けた』という感想ももちろん嬉しいのですが、『ありがとう』って映画を観ただけでは言葉として出てこない気がして……。
その人の中でまだこれからストーリーが続いていくんだろうなという思いや、命のバトンを受け取ってくれた証なのかなと感じています。それは、僕の中で『ただの映画で終わらせたくない』という想いが形になった瞬間。その人にとって映画が映画を超えた瞬間でもあり、作り手として本当に幸せなことですよね。何のために役者をやっているのだろう? と悩んだこともありましたが、このためだったんでしょうね」

大友監督「『ありがとう』率は本当に高かったですね。沖縄以外の土地でも、『作ってくれてありがとう』『諦めずに届けてくれてありがとう』『知らなかったことを教えてくれてありがとう』って。これは、驚きを禁じ得ませんでした」
全国キャラバンでは、本編を観賞した直後の観客に感想を紙に書いてもらい、貼り出す試みも行っていた。これは、前述の「ウォーターボーイズ」宣伝時の成功体験があったと妻夫木が明かす。
妻夫木「『ウォーターボーイズ』では、ファボーレ東宝(現・TOHOシネマズファボーレ富山)が観客動員全国2位を記録したのですが、その時に感想文の掲出が凄く多かったんです。それを今回もやるべきだと思って。最初に訪れた沖縄キャラバンで、那覇市立那覇中学校をサプライズ訪問した際、生徒さんたちが僕らへの質問や感想を真剣に書いてくれたんです。
知らないことを恥じる年代でもないので、本当に素直に映画を観て感じ取ってくれました。これからどう生きていくのかを考え抜いて書いてくれた感想文が、本当に胸に響いたんです。これを読んで、さらに新しいストーリーが生まれるんじゃないかと感じて、なるべく劇場でも掲示していただいています。僕らも、まだまだ成長していける気がするんですよ」
今作の舞台は戦後の沖縄だが、沖縄の人々に起きた想像を絶する出来事は時代や場所を問わず、誰にでも起こり得ることだと本編を観て気づかされる。だからこそ、傍観者ではなく当事者意識を忘れてはならないというメッセージを、眼前に突き付けられた人は少なくないのではないだろうか。
 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会妻夫木は、今作でグスクとして生き、作品を世に届けるうえで肝に銘じていることとして、「覚悟」と言い切る。「背負える覚悟があるかどうか。僕も監督も、他の多くの出演者にしても沖縄で生まれ育ったわけではない。でも僕たちがこうして作品を届ける意味は確実に存在しています。ドキュメンタリー映画を作りたいわけでも、戦争映画・反戦映画を作りたいわけでもない。ただ、その部分は切り離すことはできないので向き合わなければならない。そういう覚悟は全員が持っていたし、今も当然あります」。
「言うは易く行うは難し」という言葉があるが、妻夫木と大友監督は言葉の重みを噛み締めながら、長年にわたる沖縄との縁を大事に、大事に育んできた。妻夫木は「涙そうそう」の撮影で今作の舞台でもあるコザを初めて訪れてから約20年、大友監督は沖縄を舞台にしたNHK連続テレビ小説「ちゅらさん」の演出で滞在してから約25年が経過したことになる。
妻夫木「『涙そうそう』でコザという町に出合い、たくさんの人と出会って親友もできました。それ以来、コザには何度も遊びに行ってますが、『宝島』に出演するにあたって改めて勉強していくなかで、『見て見ぬふりをしていた自分』がいたことに気づかされたんです。
 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会僕には宮島真一さんと金城諭さんという親友がいるのですが、役作りで沖縄に行った際、金城さんに『ガマへ行きたい』とお願いしたら、チビチリガマとシムクガマへ連れて行ってくれたんです。チビチリガマは集団自決もあった場所なので、色々なことが伝わってきて……。『ごめんなさい、もう来るなと思われているかもしれないですが、こういう映画をやらせていただきます』と挨拶させてもらいました。
シムクガマへ行った後、金にぃ(金城さん)から宮島さんにバトンタッチして、『どこへ行くのかな?』と思ったら、『連れて行きたい場所がある』と言われ、(宜野湾市の)佐喜眞美術館を訪れました。宮島さんからは『とりあえず何も言わないから見てくれ』とだけ言われ目にしたのが『沖縄戦の図』でした。『沖縄戦の図』にチビチリガマ、シムクガマが描かれているとも知らずにその絵を見たのですが、絵から自分に入ってくるものの大きさに動けなくなり、涙が止まりませんでした。絵から、『見て見ぬふりしていた自分がいたんじゃないか?』『分かった気になっていないか?』と言われた気がしたんです。
『学ぶ』『知る』ことはもちろん大切なことだからやってきましたが、初めて戦争というものの声を聞いたというか、感情がスッと入ってきたんです。僕は『感じる』ということを、どこかで忘れていたんでしょうね。この体験があったからこそ、初めて本当の意味で覚悟を持てたようなところがあります。そこに導いてくれたのは親友の2人だし、僕を信じて連れて行ってくれたのだと思うんです。そこで何も感じない人間だったら、そこまでの映画なんだろうと思われていたんじゃないかな。動けなくなった僕に『妻夫木、ありがとうな。ちゃんと想いを汲んでやっていかなきゃな』と声をかけてくれました」
大友監督「いい友だちだね」
 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会妻夫木「ほかにも、宮島さん一家とカフェで過ごしていたら、上空を戦闘機が3~4機通過したんです。その時に『妻夫木、これが沖縄よ』と言われて、ハッとさせられました。戦争は終わっていないんだって。これが当たり前にはならないよって。宮島さんは押しつけがましいことは一切言わず、生活の中で教えてくれるんです。宮島さんはコザで映画館(シアタードーナツ)を経営していますが、どこか映画、ドラマを作る側の想いや作品の力を信じてくれているところがあるので、それがまた嬉しいんです」
大友監督「あの時代に沖縄で生きていた人たちのことを思うと、ノイズをなるべく排して作らなければと思うんです。『サービスしなきゃ』とか『受け入れられたい』とか、自分の中の、作品を作り上げるための計算や打算、そういった余分なノイズが本当に邪魔に思えてくる。そんなことよりも、この題材には、それ以前に真正面から向き合わなきゃいけないことがたくさんある。皆で覚悟を決めて、自分たちは『何も知らないのだ』ということを自覚しながら、それでも覚悟をもって、一つ一つこういう方向性で創るんだと決めていかなきゃいけない。その結果、作るプロセス自体がどんどん純化されていくんですね。

改めてアメリカ統治下の沖縄について、私たち日本人にとって知らないことがあまりに多いと感じます。さらに、日本では当時高度経済成長の繁栄を享受していただけに、そして今でも基地の7割を沖縄に負託していることを考えると、知らなすぎるのではないかと思うんですね。現地の小さな図書館や公民館などへ行くと、私家版の元刑事の自伝みたいなものや、当時を生きた人々の証言録が残っていて、それを1日こもって読んでいると、聞き書きされた膨大な言葉の中の数行に、直接話を聞くだけでは分からない『言いたくなかったこと』や様々なディティールが書き残してあったりして、ハッとさせられます。
人は誰しも嫌な記憶は遠ざけようとするし、例えば大切な人を守れなかった自分自身に負い目を感じて、口を閉ざしてしまうこともある。当時、人に言えなかった想いや声なき声が無数にあったということが、それらの記録から浮かび上がってきて、直接語りかけてくるんですよね。
そういうことを重ねていくと、ますます純化していくことが大事なのではないかと、そう思えてくる。余計なことは考えず、自分たちに出来得る限りの最大限の努力を尽くし、あの時代を再現するのだと。僕らが知らない沖縄のあの時代を、当時の人々の喜びも悲しみも、無念や悔しさなどの思いも出来得る限り共有し、ほんの少しでも背負いながら、一つ一つ再現していかなければならないのだと。“知らない”だけに美術、衣装、装飾含めて嘘をついてはいけないという気持ちが常に付きまとっていました。作り手としてはそこが、最も覚悟が問われた部分かもしれませんね。クライマックスのコザ騒動のシーンも含め、自分たちの『ここまでやるんだ』という覚悟、それを表現するすべてに宿らせて、当時生きていた人々の思いや熱量を、僕ら自身が“発見”していく。ひとつひとつOKを出すときにも、覚悟の問われ方がこれまでとはかなり違いましたね」

1970年12月20日未明、沖縄県コザ市(現・沖縄市)で数千人に及ぶ群衆が米軍関係者の車両を次々と襲い、焼き払った事件。被害車両は約80台、負傷者は88人(うち沖縄住民は27人)。背景にあるのは、アメリカ統治下での圧制、度重なる人権侵害に対する不満が爆発したもの。直接の契機となったのは同年9月18日、糸満で酒気帯び運転およびスピード違反の米兵が運転する車両が主婦を轢殺する事故を起こしたが、同年12月7日の軍法会議で証拠不十分として無罪判決が下されたことにある。さらに騒動当夜に米兵が運転する車両が住民をひく同様の事故が起こり、事故処理をするMP(米憲兵)が取り囲んだ人々に向かって威嚇射撃を行ったことが民衆の怒りを買い、騒動へと発展した。
 (C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会
(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会大友監督の「純化」という言葉が強く印象に残るが、クランクイン前に取材を通して聞いた、それを象徴するようなエピソードを披露してくれた。
「この題材には、“作品にきちんと反映させていかなければならない”ことが、いっぱいあるんですね。ある方に聞いたのですが、戦果アギヤーの方が亡くなる前に、基地から物資を盗んだことに触れて『俺たちはしょせん盗人だ』と、そのようなことを言ったそうです。ですが、枕元で看取っていた方が『そんなことはない。あなたがいなかったら私は今ここにいないし、私の子どもも、孫の未来も、あなたのおかげで救われたのだ』と感謝の想いを伝えたら、その方は柔和な表情を浮かべて亡くなられたそうです。
生きるために様々な覚悟を背負って生きていた戦果アギヤーの方々のそうした想いも含め、沖縄という土地は、死者の魂が人々の日常生活の中で今も一緒に生きていると、そういう感性が強く残る島です。そうしたことを知れば知るほど、そして感じれば感じるほど、声なき声に一層耳を傾けなければいけない題材であることが分かってくるんですね。その声に耳を澄ましながら、ぼくたちは取り組まなければいけないのだと」

妻夫木と大友監督が抱える「想い」について話題を振ると、終着点がまったく見えぬほど語り続ける姿は容易に想像できるのではないだろうか。後編では、本記事にも登場したコザ在住の妻夫木の親友・宮島さんから聞いたエピソードもお届けする。
フォトギャラリー
執筆者紹介

大塚史貴 (おおつか・ふみたか)
映画.com副編集長。1976年生まれ、神奈川県出身。出版社やハリウッドのエンタメ業界紙の日本版「Variety Japan」を経て、2009年から映画.com編集部に所属。規模の大小を問わず、数多くの邦画作品の撮影現場を取材し、日本映画プロフェッショナル大賞選考委員を務める。
Twitter:@com56362672
関連ニュース


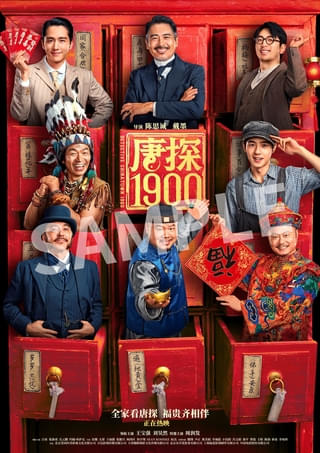

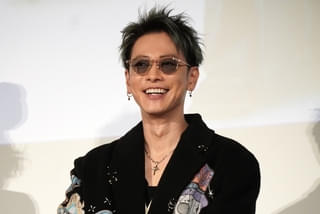

映画.com注目特集をチェック
 本日公開 注目特集
本日公開 注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!
【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!
提供:ツイン
 本日配信開始 注目特集
本日配信開始 注目特集 辛口批評家100%高評価
【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。
提供:Hulu Japan
 本日公開 注目特集
本日公開 注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
 注目特集
注目特集 映画は、ここまできた。
【配信を待つな!劇場で観ないと後悔する】戦場に放り込まれたと錯覚する極限の体験
提供:ハピネットファントム・スタジオ
 注目特集
注目特集 エグすぎる…面白すぎた…
【とにかく早く語り合いたい】だから、とにかく早く観て…そして早く話そうよ…!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント