窪塚洋介、どん底時代を救った詩人の言葉「漫画の1ページ目やん」 「Sin Clock」牧賢治監督とのシンクロも語る
2023年2月16日 15:00

窪塚洋介が18年ぶりに長編邦画単独主演を務める「Sin Clock」が、2月10日から公開された。窪塚が演じたのは、どん底の人生を生きるなかで、偶然の連鎖に導かれていく主人公・高木シンジ。本作で商業映画デビューを果たした新鋭・牧賢治監督と共に、撮影や自身のどん底時代の経験を聞いた。

高木シンジ(窪塚)、驚異的な記憶力を持つ番場ダイゴ(坂口涼太郎)、裏社会に通じる賭博狂の坂口キョウ(葵揚)らタクシードライバーたちが、幻の絵画をめぐる一夜の人生逆転計画に挑むさまを描く。米ヒューストン国際映画祭短編部門のゴールド賞を受賞した「japing」、仏ニース国際映画祭の新人監督賞を獲得した長編第1作「唾と蜜」などで知られる牧監督がオリジナル脚本も手掛けている。
インタビューを行ったのは、公開直前イベントが行われた日。このイベントで自身のどん底の経験を聞かれた窪塚は「某マンションから某落っこちたことがございまして」と、窪塚らしい言い回しで、2004年に起きた自宅マンションからの転落事故に触れていた。
「その瞬間が一番絶望的だったけれど、それ以降も一気にではなく地味に復活していったので、その過程で纏っていた空気感や目の色だったり、目の光だったり。自分としては向かい合いたくないし、もう二度と体験したくない、箪笥の奥につっこんで忘れないようにしていた感覚が、今回シンジを演じるにあたって役に立った」(窪塚)
このインタビューでは、このどん底時代に見えた復活の兆しについても語っている。

 (C)2022映画「Sin Clock」製作委員会
(C)2022映画「Sin Clock」製作委員会 (C)2022映画「Sin Clock」製作委員会
(C)2022映画「Sin Clock」製作委員会当時は本当につらかったですが、1番復活の兆しをもらったのは、三代目魚武濱田成夫さんという詩人の言葉でした。子どもの頃に本屋で「君が前の彼氏としたキスの回数なんて俺が3日でぬいてやるぜ」っていう本の表紙を見て、なんだこれって思って開いたら中の言葉がむちゃくちゃ強くてかっこよかった。一発で好きになって、そこから何冊も買うことになるんだけれど。
それで、俺がマンションから落っこちた数年後にたまたま三代目魚武濱田成夫さんと初めて会う機会があったんです。紹介してもらったとき、俺が事故について話そうとするよりも先に、向こうが「窪塚君、ほんまえぇよな」って言ってきた。「まぁまぁ嫌ですよ、この感じ」って返したら、「いやだって、自分それ漫画の1ページ目やん。自分の人生が1冊の漫画になるとするやろ、そしたら1ページ目の1コマ目、落ちているところの空中の絵から始めたら最高やんか。ほんま羨ましいわ」って言われて。この人は本気で羨ましがっているっていうのが伝わったのと、大好きな詩人にそう言ってもらって、なんだか雷を打たれたような気分でした。本当に頑張ろう、頑張ろうって思っていいんだって背中をバーンって叩いてもらったような。そこから気持ちがだいぶ楽になりました。これも不思議なんですが、牧君とシンクロするんだよね。牧君もこの詩人が好きで。
(C)2022映画「Sin Clock」製作委員会
関連ニュース




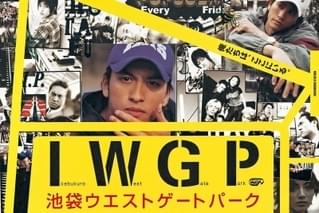

映画.com注目特集をチェック
 注目特集
注目特集 メラニア
世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?
提供:イオンエンターテイメント
 注目特集
注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!
【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!
提供:ツイン
 注目特集
注目特集 辛口批評家100%高評価
【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント







































