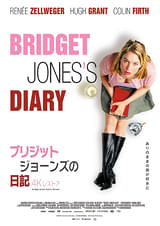コリン・ファースの“相棒”プロデューサー、「アイ・イン・ザ・スカイ」リアリティに太鼓判
2016年12月22日 15:00

[映画.com ニュース] ソニー・ミュージックUKの元会長兼CEOという異色の肩書きを持つプロデューサー、ジェド・ドハーティが来日し、初めて製作を務めた映画「アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場」の裏話を映画.comに語った。
ヘレン・ミレンや故アラン・リックマンさんら演技派が結集した軍事サスペンス。軍事用の無人戦闘機(ドローン)を使い、ナイロビでテロリスト捕獲作戦を実行中の英米軍は、ターゲットの自爆テロ計画を突き止める。だが、ミサイルでテロリストを一掃しようにも殺傷圏内には民間人の少女がおり、政府高官や軍人たちは「テロで奪われる最低80人の命」と「目の前の無関係の少女の命」をはかりにかけざるを得なくなる。「ツォツィ」のオスカー監督ギャビン・フッドがメガホンをとり、緊迫感あふれる物語を生み出した。
2011年にソニー・ミュージックUKを去ったドハーティは、翌年には「映画界の唯一の知り合い」コリン・ファースと映画製作会社レインドッグ・フィルムズを立ち上げる。本作はその記念すべき第1作で、米批評サイト「Rotten Tomatoes」では95%の高評価を記録(12月16日現在)するなど成功を収めた。ドハーティによれば、本作が遺作となったリックマンさんやポールの起用は“相棒”ファースのアイデアだという。両者は続くプロデュース作「ラビング 愛という名前のふたり」(17年3月公開)でも第74回ゴールデングローブ賞で2部門ノミネートと結果を残しており、映画界の注目コンビといえる。
本作で目を引くのは、“ドローン戦争”という身近ではない題材ながら、綿密な取材に基づき徹底してリアリティを追求している点だ。ドローンをはじめとする兵器はもとより、当事者それぞれの心情が細やかに描かれ、臨場感や緊迫感の底上げに付与している。ドハーティは「脚本の執筆段階でも、すごく調査しているよ。米軍のドローンパイロットや元英軍にいた人物、政治家に対しても“もしこういった事態が起こったらどうするか”というのを詳しく調査した上で書いているから、ほとんど現実に基づいているんだ」と語り、あるエピソードを挙げ、本作のリアリティの高さを証明する。「15年の9月、本作がトロント映画祭でプレミア上映される前日に(英国のデービッド・)キャメロン首相が、英国人の一般市民がシリアでドローンの空爆によって亡くなったという発表をした。この脚本は06年に書かれたんだが、その時点で(事態を)予測していたんだよ」。
本作には“虫型”“鳥型”といったドローンが登場し、テロリストの特定に大活躍する。これらが実際に使用されているのは驚くべき事実だが、ドハーティはさらに「最新型のドローンの映像を見せようか」とスマートフォンを取り出し、ドローン開発の現状について講義を開始。「これは蚊型のドローンなんだ。飛んできて人間のDNAを採取して戻っていき、人物を特定する。そして今度は別のドローンが飛んできて、毒を刺して殺害するんだよ。爆発するものも今後開発されるだろう。恐ろしいよね」。こういったドローン戦争の恐怖や問題点を伝えるためにも「観客が共感できる形で提供しないと、影響を及ぼせない」と見せ方にはとことんこだわったという。
「本作はとてもリアルだが、エンタテインメント性にもあふれている。ドローンという新しいものについて学べるし、戦争映画だけれども、敵や味方だけでなく犠牲者の視点からも描いている。英国人が優柔不断に、米国人が好戦的に描かれているところなどユーモアのセンスもちりばめられているね。ただ、1番大きいのは、すべての登場人物の視点で見ているから、色々な見方ができること。“私ならどうするだろう?”と考えさせられるんだ。私自身、何百回と見ているんだが、毎回見方が違うんだよ」。
「アイ・イン・ザ・スカイ 世界一安全な戦場」は、12月23日からTOHOシネマズシャンテで先行公開後、17年1月14日から全国で公開。
関連ニュース






映画.com注目特集をチェック
 注目特集
注目特集 メラニア
世界中がさまざまな出来事に揺れ動く今、公開される――あなたにはこの作品が、どう映る?
提供:イオンエンターテイメント
 注目特集
注目特集 ジャッキー・チェンだよ全員集合!!
【祝・日本公開100本目】“あの頃”の感じだコレ!!ワクワクで観たら頭空っぽめちゃ楽しかった!!
提供:ツイン
 注目特集
注目特集 辛口批評家100%高評価
【世界最高峰】“次に観るべき絶品”を探す人へ…知る人ぞ知る名作、ここにあります。
提供:Hulu Japan
 注目特集
注目特集 なんだこの“めちゃ面白そう”な映画は…!?
【90分のリアルタイムリミット・アクションスリラー】SNSでも話題沸騰の驚愕×ド迫力注目作!
提供:ソニー・ピクチャーズエンタテインメント