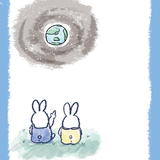「藤竜也の陽二の魅力とラストの願望的考察…。そして謎について」大いなる不在 TMさんの映画レビュー(感想・評価)
藤竜也の陽二の魅力とラストの願望的考察…。そして謎について
とてもとても良かった。
演技の事など何も分からない私でも、スクリーンの中の藤竜也に圧倒された。
名優を精巧な機械に例えるなら、彼は老練な機械のように精緻で大胆で狂いなく、時折接合部から滲み出るオイルのような人間味が、唯一無二の個性を醸し出していた。
なんと表現したものか難しいのだけれども。
親に向き不向きがあるならば、恐らく陽二は後者で。
他者の目線に合わせられない陽二は、常に他者を自分の目線まで登らせるか、下から呆然と見上げさせるかの二択しか与えない。
幼い子にとっては背伸びしても届かぬ存在。必死の訴えも甘えたい想いも、彼の顎先を掠めるだけで、彼の視界に入ることはない。関心を得ることは無い。
父との埋められない距離感は今も卓に付き纏う。擦り寄るか、拒絶するか。どちらも健全な親子関係とは言い難いが、卓は拒絶を選んだ。そもそも陽二が妻子を捨てたのだけれど。
とは言え陽二は不義理な人間ではなく、むしろ義理堅く一貫して誠実に努めていて。
実子の結婚式に参列していない事を理由に、継子の式にも参列せず。直美との関係を再開させるにあたって、己と相手方の家族関係を精算して。卓と結婚した夕希に対し、事後報告だったが両家顔合わせをしなかった不義理を詫び。卓に対し、幼少の頃に奮ってしまった暴力と暴言を詫びる。
固すぎる程に、義理を通す人間として描かれていた。”気持ちさえこもっていれば形は拘らない。”という現代の風潮とはっきり隔絶した、気持ちいい程の男気ある人物だ。
愛に対しても一直線で。熱烈な恋文と、決して口だけで終わらせない行動力。
偏屈で高慢で配慮に欠け、論理的思考で他者を批判する嫌味な側面もありつつ、愛と義理を全身で体現する雄々しさが、とても魅力的だった。
こういう人物はとても狡いと思う。他者に媚びず、自分を生きて、それでも愛されるのだから。
私も途中から陽二という人間の魅力に呑み込まれて行った。親族にはいてほしくない。けれども恒星のように輝き、燃え上がる存在感には見蕩れる。教え子の鈴元が陽二を尊敬し、慕っていたのにも納得する。(チョイ役だったけれど、鈴元役の人の演技大好きだった)
直美は陽二に対し、一抹の苛立ちや呆れを抱きつつ、それでも根底にある強い愛と尊敬の念で支えていた。それが垣間見える夫婦のやり取りが素晴らしかった。
直美は深く陽二を愛していたからこそ、認知症による彼の変容に耐えられなかった。
あの熱烈な恋文と、陽二が自分に向ける確固たる愛があったからこそ形作っていた夫婦が崩壊し、愛の矛先と供給先を失った直美も崩壊する。
”無かったことにされた” ではなく、本当に無になってしまった。その悲しみと苦しみは想像がつかない。
愛し合った記憶を自分だけが有した状態で、最早別人の伴侶と共に生きる孤独は深くて暗い。
時折元に戻り、変わらぬ愛を向けられても、いつかまた病の海に沈むと考えたら…そしていずれ、二度と浮上することのない暗黒の日が訪れると考えたら…目を背けた方が楽かもしれない。
愛あるが故に、共に居ることは耐えられないのかもしれない。
『大いなる不在』 は、直美の不在を指しているのだと思っていたけれど、直美にとっての、かつての陽二の不在も指しているのだろう。
ラストのシーンには様々な憶測がある。故郷の海へ向かい歩を進める直美の姿。かつて陽二が表した通り、彼女は故郷の海そのものになってしまったのだろうか。燃えたぎる恋慕に心を爛れさせながら、陽二が眺めることしかできなかった故郷の海に。
街を徘徊し、妻の名を叫ぶ陽二の溢れる想いは、宛もなく直美の故郷の地を彷徨ったかつての陽二の姿と重なる。
二人はまた会えるのだろうか。これが悲劇の愛の物語ならば、在りし陽二との幸福な日々を護るため、直美は死を選び、何も知らない陽二は病が見せる世界の住人になってしまうのだろう。
希望のある考察をするならば、直美は生きていて、また陽二の元へ戻ってくる。病の世界へ徐々に囚われていく陽二を見守りながら、彼の魂に交信し続ける。次は直美が、熱烈な恋文を送り続ける。
私の願望は勿論後者。
最後に、序盤に繋がるシーンにて。陽二は誰も受信していない無線で、あたかも息子の卓と交信出来ているかのように語りかける。
今から行くと告げた後、彼は矍鑠と身支度をし、身なりを整え、直美の日記を携えて外に出る。その目には強い決意があった。その決意とは何だったのか。なぜ彼は、無線で息子を呼ぶ時、幼少期の愛称である『たっくん』と呼んだのか。
彼があの時交信していたのは、かつて彼のプライドにまみれた心を揺るがし、彼の執着する美徳とエゴを陳腐にさせ、アイデンティティに亀裂を生じさせた、幼く無垢な息子だったのだろうか。
直美への愛さえくすませる純な脅威に、かつては拒絶する事しかできなかった陽二であったが、何故この期に及び、会いに行こうとしたのか。
あの無線のシーンで語りかける相手は、当然直美だろうと思っていたから、とても驚いた。
男女間の燃え上がるような愛とは異なり、胸を奥底から温めていくような父子の愛。その感覚は今も陽二を翻弄させ、困惑させ、希望を与えているのかもしれない。
そうであるならば、卓が数十年間離れていた事も、陽二にとっては大いなる不在だったのだろう。