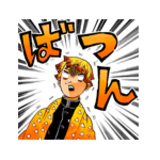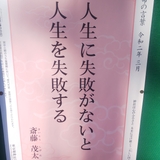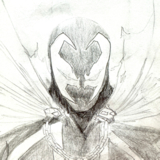マエストロ その音楽と愛とのレビュー・感想・評価
全75件中、21~40件目を表示
演奏場面の圧倒的な説得力
監督・脚本・主演のブラッドリー・クーパーから目が離せなかった。完成までの間、どれだけバーンスタインを自分に乗り移らせてきたのだろう。
比較するのもおこがましいと思うが、これまで自分が観てきた邦画やドラマで指揮者やクラシックが扱われていた時に感じた嘘くささが、この映画には微塵もない。
例えば、終盤近く、学生に指揮を指導する場面など、彼の手の動き一発で、観客の誰もが納得させられたのではないか。
映画の序盤から中盤まで、演奏場面は必ずしも多くない。それがある意味フリになって、クライマックスである、後半のオーケストラの演奏場面の長尺が生きてくる。
ここが本当にすごい!
この演奏場面の圧倒的な説得力により、我々観客は、それまで、夫と共に歩み続けることから降りようとしていた妻が、改めてバーンスタインに引き寄せられていくその変化を納得させられてしまう。
妻役のキャリー・マリガンも素晴らしい。プロミシングヤングウーマンの彼女だと後で知り、印象の振り幅に驚いた。
若い頃から、晩年までが違和感なく感じられる、カズ・ヒロの特殊メイクの自然さも指摘したい。
加えて、回想シーンを、時代に合わせて白黒からカラーへとスタンダードサイズで表現する手法もよかった。ワンカットワンカットが、まるで一枚の絵の様に美しく見えたのも、まるで人の思い出というもの自体を表しているかのようだった。
ところで、
余談だが、登場人物たちが余りに喫煙するので、つられて自分も久しぶりに一本だけ吸ってしまった。禁煙中の人には、ツラい映画です…。お気をつけ下さい。笑
愛に包まれている
人間味あふれるガチャガチャ人生
Netflixはチラシないし、いつのまにかチラッとだけ上映するから観れないかと諦めてたら、有楽町で観れた、小さい方ではあったけど満席。
タイトルと写真から妻への一途な愛の物語かと思っていたら、意外にも複雑で奔放。
まあ偉大な芸術家というものは、私生活がエキセントリックだったりするから分からなくもない。
すごいタバコ吸うし。
音楽パートは流石に素晴らしい。セーラーでのダンスシーンは、クラシックのミュージカル映画を彷彿とさせ、教会で指揮をするシーンは鳥肌もんだった。
欲を言えばモノクロパートのエピソードをもっと観たかったかな。モノクロ写真のイメージで観に行ったから、カラーパートがいろいろありすぎて、前半がわりと駆け足だった印象。
冒頭とトミー登場のパーティーシーンのカメラワークが好き。
役者の演技を堪能
2024年劇場鑑賞2本目。本当は元日に観る予定でしたが地震で上映中...
2024年劇場鑑賞2本目。本当は元日に観る予定でしたが地震で上映中止。正直3日に観に行くのもしんどかったのですが、今週しかやってないということで、これで観るのやめたら地震に負けた気がして意地でも行きました。
ネトフリの作品なので当然パンフレットなくマイナス0.5。
年末から実話かドキュメンタリーしかほとんと観てない・・・。
実話と知らずに観に行ったのですが、なんとなく名前は聞いたことのあるレナード・バーンスタインの伝記映画。原題はマエストロだけなので、その音楽と愛は邦題で勝手につけたのですが、確かに愛の映画でした。音楽の部分はちょっと分かりませんでしたが。愛といってもその男女のスキャンダル的な一元的な感じではなく、家族愛も含まれた広い意味で、色々あった奥さんとの晩年の話は泣いてしまいました。
若い頃はモノクロで、過去編はずっとモノクロかと思いましたがそうでもなかったので、CGで若返らせるのがその方がやりやすかっただけかもしれません。
音楽好きなら推せる一作。
今年7本目(合計1,099本目/今月(2024年1月度)7本目)。
元ネタありの映画のためドキュメンタリー映画のような様相になりますが、そのために展開が読みやすいという一面もあり、小説(自伝記など)で読むか映画を見るかは分かれるかなと思います。
音楽好きならおすすめといったところでしょうか。
主人公の妻(フェリシア)に思う心遣いなどは「少し前の時代」のことではありますが普遍的にあることですし、こういった描写があったのは良かったです。
採点上、ややわかりにくいかな?と思った点はあるものの、音楽映画という性質上そういう語句が出るのはある程度承知済み(エレクトーンにせよピアノにせよ合唱にせよ、何らか音楽に触れているのが前提という字幕は一定数出ます)ということなので減点なしにしています。
人間を観る
冒頭から心をつかまれた!
レオナード・バーンスタインは、あふれるような音楽的才能を背景として、五つの側面を持っていた。作曲家、指揮者、演奏家(ピアノ)、舞台芸術家(ミュージカルの作曲)、教育者(音楽番組の企画・進行)。映画のなかで外向的と捉えた指揮者の仕事に比べ、一番難しいのは最も才能を要し、年齢を重ねると必ず衰退し、内面に引き籠って取り組む必要のある作曲家の仕事。彼と知りあって、最大の理解者となり暖かな家庭を共に築いた舞台芸術家の愛妻フェリシアは、作曲の仕事から逃げて、不眠から薬物に依存する彼のことを「クソしかしない鳥の下に立つな」と言われてきたのにと非難した。必ずしも、バイセクシャルだけが彼の問題であったわけではない。しかし、彼女も舞台の仕事に戻ると、彼を許すことができた。イングランドのイーリー大聖堂でのロンドン交響楽団との歴史的なマーラーの交響曲第2番「復活」の最終楽章を演奏した舞台の袖がその場だった。彼の心には「憎しみ」はないと言い切っていた。
この映画で、最も心が震えたのはどの場面だったろう。耽美的な彼の録音が流れたマーラーの交響曲第5番の「アダージェット」の演奏、マーラーの第2番の再現、それから映画の冒頭、取材カメラの前で彼がピアノで弾いた晩年のオペラ「A quiet place」の一節の演奏だった。その時、彼は自分自身の作品の数が少ないことを述懐していた。この映画では、彼が作曲した曲は、どれも少し演奏する時間が限られていたように思う。
でもバーンスタインだって没後30年を超えた今、若い皆さんには本当はなじみは薄いのかも知れない。それでは、彼が私たちに一番伝えたかったことは一体、何だったのか。最近の科学の進展によってはっきりしたのだが、音楽は演奏する音楽家と聴き手の心の動きがシンクロした時に、それぞれの心に最も響く。世界で一番それができたのが、指揮者レオナード・バースタインではなかったかと思う。実際に指揮をして、音楽が変わって行くところを若い学生たちに示した、タングルウッドで撮影したと思われるベートヴェンの交響曲第8番でも、それは明らかだった。教育こそ、双方向性に違いない。
そうだ、私たちにできることは、コロナ禍以降、すっかりご無沙汰している演奏会場に直接、足を運んで、音楽と心がシンクロする場面にめぐり会うことなのだ。バーンスタインほどの音楽家に出会うことは容易ではないだろうけど。立ち上がって上半身を揺らしたり、手を挙げたり、大声をあげたりすることはできなくても、ラップ音楽とクラシック音楽は、実は同じこと。それを想い出させてくれた良い映画だった。
この映画は、監督および主演の二人、バーンスタインを演じたブラッドリー・クーパー、フェリシアのキャリー・マリガンともに、ゴールデングローブ賞(2024)にノミネートされている。オスカーにもきっとノミネートされるに違いない。
--
この映画が、第96回アカデミー賞の作品賞、主演男・女優賞をはじめとする7つの部門賞にノミネートされたことが伝えられた。我が国でも、もっと多くの人たちに、この映画を見てほしかった。喫煙、バイセクシャルなど今日的な視点のみに捉われることなく。これは素晴らしい映画だ!(2024.01.23)
フレンチフルコース並みのボリューム感
師匠であるクリント・イーストウッド監督から急遽引き継いだ「アリー/スター誕生」で俳優から監督として大成功を収めた弟子のブラッドリー・クーパー。
そしてブルーノ・ワルターの代役を務めたレナード・バーンスタインの数奇な運命に近いものを感じた。
そして、今の映画界の大巨匠であるスティーブン・スピルバーグとマーティン・スコセッシがプロデューサーとして全面バックアップするなど、大きな期待を背負ったブラッドリー・クーパー監督の第二作目。
なんて立派な映画を作ってしまったんだ!そしてNetflix配給ということもあってか、斬新なカメラワークやシーン繋ぎ、ロングショット等挑戦に満ちた映画だった。イーストウッド監督譲りの自然でラフなセリフやカメラワークが冴え渡った前作「アリー/スター誕生」とはまた違った境地に達したような気もした。
さすが、ダーレン・アロノフスキーの元鍛え上げられた撮影監督マシュー・リバティーク!
モノクロとカラー映像、画角の切り替え、20代から60代までを演じる為の特殊メイク、豪華な舞台、豪華なオーケストラ。まさにフレンチのフルコースのような映画だった。
今年公開された「TAR」の師匠でもあったレナード・バーンスタイン、同性愛の傾向もあり人好きの彼の人柄なのか、中々一つの場所に落ち着くことはなさそうだった。いかにも成功者のライフスタイルといった感じだ。
本作は妻であるフェリシアの視点、立場も丁寧に拾い上げ、才能ある彼女の女優人生からいつの間にか夫バーンスタインを影で支える妻という裏方に回っていく姿をとてもスムーズに変化させている。
特にマスコミに囲まれるレナードに耳打ちし、去っていくフェリシアの後ろ姿と、誰1人女優である彼女のことに振り返らずバーンスタインに注目し続けるマスコミと観客を正面から捉えて対比させたロングショットには痺れた。なんて悲しいロングショットなんだろう。
そして他の男へ色恋に走ろうとするも他の女を紹介するように近付いてきた男だったとわかるなど、とても切ない。
そして、その音楽の素晴らしさで日頃の行いを全てチャラにするバーンスタイン笑
ブラッドリー・クーパーが本当にバーンスタインに見えてくる。
しかし、一つ一つが素晴らしい要素でありながら、映画としてのドライブ感に欠けるストーリーで、他人の人生なので仕方がないのだが、もっと脚色しても良かったのではないかと思う。メインがハッキリしない豪華フルコースメニューであった。
やにだらけ
子供のころ指揮者という職業に疑問をもっていました。
でたらめにタクトを振っても大丈夫な気がしたからです。
たとえばシンバルを鳴らすところでシンバルに向かって合図しなくても奏者はシンバルを鳴らすのではないだろうか。
楽譜もあるのだしシンバルを任されたからにはシンバルを鳴らすところがわからないということはないと思ったのです。
無教養なわたしにとって指揮者はなにがすごいのかわからない人でしたがTAR(2022)を見たときTAR(ブランシェット)が曲を克明にスコアしているのを見ました。
オーケストラを指揮するための解釈がファイルに綴じてありTARにそれを見せてくれるように再三懇請してくる人物をマークストロングが演じていました。
おそらく指揮者とは、作曲家がつくった曲を自分のものとして指揮するために、自分用に書き直すような作業をする人なのでしょう。
後半で、業界を放逐されたTARが質素な生家に戻って過ごすシーンがあり、そこで彼女はレナードバーンスタインが音楽の意味を語るコンサートのVHSを見て涙します。(TARは架空の人物ですが)天才のTARにとってさえバーンスタインは神なのかもしれません。
このことからわかったのはクラシックとは作曲家の曲を聴くというより指揮者の“解釈”を聴くということです。
熟達した聴き手であれば、オーケストラを聴いて「あ、バーンスタインだ」とわかる──ということです。
この映画は「あ、バーンスタインだ」とわかる──ほどまでにバーンスタインをわかっているなら、興味深い映画だろうと思います。
逆に、クラシックをあまり聴かずバーンスタインの偉大さとその理由がわかっていないとつらい映画かもしれません。
TARのようにサスペンスやミステリーの要素もなく、延々とバーンスタイン(クーパー)とフェリシア(マリガン)の日常が描かれます。
表現主義の撮影で、構図も角度も仕草もがっつり決めます。衣装もヘアスタイルもしっかり監修し、Bombshell(2019)でシャーリーズセロンを別人に変えたKazu Hiroが特殊メイクを担当し、クーパーは見た目もバーンスタインにそっくりです。
オーソンウェルズのように喋っている人を間断なく繋いでいくような饒舌なタッチで、愛憎の山と谷を活写していきます。
最初は陰影を活かしたモノクロですが、時代が進むとカラーに変わります。カラー処理も60年代映画のようなヴィヴィッドな色みを使ってシーン毎しっかり絵になるように撮っています。
もっとも時間を割いているのは教会の演奏で、概説によると1973年イギリスのイーリー大聖堂で演じたマーラーだそうです。撮影のマシューリバティークはアロノフスキーの右腕で、そりゃもうみごとな絵でした。
これらの映画的こだわりは一目で解りますが、バーンスタインを解っていないと、じょじょに彼の放恣に苛立ちをおぼえてくるでしょう。
天才が放恣なのはよくあることですし彼の浮気癖に目をつぶったとしても目に余るのは喫煙の描写です。
正直なところ、この映画でもっとも特徴的なのは禁煙ファシズムへの反発のようにすら見える煙草です。
いま世の中は喫煙者に対してはどんなに弾劾してもいいという風潮になっていて公共での喫煙は縮小の一途を辿っています。
喫煙者は今世でもっとも迫害されているマイノリティと言っていささかも過言ではないでしょう。
その過激な学会活動に対して映画は全編で反抗しているように見えます。なにしろレニーもフェリシアもタバコを口にくわえているか、人差し指と中指の間にタバコが挟まれていないショットを探すのが難しいほどです。
壇上でも、ピアノ弾きながらでも、運転中でも、子供の眼前でも、まばゆいほど鮮やかな新緑の野原でも、ぜったいに煙草を離しません。
結果レニーもフェリシアも肺がんで死にます。ふたりは芸道人生を貫徹し、好きに生きて死ぬわけです。煙草をすいすぎると肺がんになりますよ──に対して「それがどうした」と言っているわけです。
喫煙にたいする現代社会の冷遇をガン無視しているのと同時に、肺がん撲滅を意図した啓蒙映画にもなり得るでしょう。
すなわち映画マエストロのつらさとは、そのへんで(煙草吸うの)やめとけよと言いたくなるつらさでもあります。
バーンスタインは再三の浮気でフェリシアを悲しませましたが業界やファンにとっては情熱的で活発で後進の育成に熱心な人でした。
TARのワンシーンを前述しましたが、実際に──
『音楽解説者・教育者としても大きな業績を残し、テレビ放送でクラシック音楽やジャズについての啓蒙的な解説を演奏を交えて行った。マイケル・ティルソン・トーマス、小澤征爾、大植英次、佐渡裕など多くの弟子を世に送り出したことでも知られる。』
(ウィキペディア、レナード・バーンスタインより)
──とあり、バーンスタインの技術や魂が現代に受け継がれていることをうかがい知ることができます。最晩年の1990年も含め7回来日しており、フェリシアが病に臥すと献身的に看病にあたりました。
したがって後半のつらさは、前半のつらさとは異なり、病でしだいに弱り狭窄していくふたりにたいする同情心です。
それに、何より、キャリーマリガンが悲しでるの見るのがつらいんですよ。
というわけで、この映画が技術的に高度な次元に達しているのはよくわかりますが、ぜんぜん晴れない映画だったのです。
imdb7.0、RottenTomatoes80%と81%。
演技力
クソしかない鳥の下に立つな
愛ってなんだろうと考えると荒涼感にさいなまれる。けれど、夫婦愛ってなんだろうという問いかけはありでは?
そう思わせる天才マエストロ、バーンスタイン夫婦の愛の軌跡を描いた作品。
ふたりの壮絶な夫婦喧嘩のシーンが印象的だ。
ここまで妻に罵倒されるバーンスタインは、ただの身勝手でわがままな自己中の男。
特に、チリ生まれの妻が言う、「クソしかない鳥の下に立つな」というチリの格言が辛辣。
鳥はもちろんバーンスタイン。
ウソをつき続けて愛を偽り、難なく指揮する姿を見せて、聴く者がいかに下等か思い知らせたいだけ、あなたの真実は偽りで、自分だけ勇敢に見せて人の気力は吸い取る真実よ。
男もここまで言われたら、うーん完全にぐーの音も出ない。バーンスタインでなくても、男なら皆へこむ。
自分のいままでの人生観の全否定。
天才で同性愛者で世間ずれしたバースタインだから、言われてもしょうがないじゃなくって、夫婦ってそう
やって罵り合いながら、愛か破局かの壮絶なデッドヒートを演じる関係だってことだと思う。
男の奢りと女の興ざめという危うい均衡。でもそれが夫婦。
ブラッドリー・クーパーとキャリー・マリガンの絶妙な掛け合いが堪能できる。
米史最高のエンターテイナーの一人。
レナードバーンスタインは、個人的にはヨーロッパ偏重なクラシックの世界から、アメリカなりにクラシックをやって解釈し直し、エンターテインすることで全世界が認めた、かつてない、そして不世出のコンダクター。今回の作品を観ても、その思い込み?先入観?は間違いなかったと思う。
その中でも、刮目に余りあるほどの演技は、英イーリー大聖堂で振ったマーラーの交響曲第2番「復活」。私の先入観通りの彼そのもの。指揮台で笑い、歌い、仰け反り、そして跳ねる。それに呼応するかのように、ボーイングは変わらずだけど、バイオリニストたちがどこぞのロックライブかと思わせるほどのヘッドパンキング。そりゃ盛り上がるよ。更に更に、このシーンがキャリーマリガンの’I miss you’からの舞台袖でサンドイッチされていることの演出の憎らしさたるや。だからこそ、この後の展開が沁みるわけで・・・。
今後ブラッドリークーパーから目が離せないのは間違いないな。
天才の故の焦燥なのか??
超有名マエストロ、レナード・バーンスタインの
半生を映画化した本作。
この映画、お馴染み町山智浩氏の解説によると
バーンスタイン氏の実の娘さんが監修に入っており
天才バーンスタインの外向けの姿ではなく、
家族に見せる生身の男性として描かれているため
有名な「ウエストサイド・ストーリー」などを
作曲するシーンなどはありません。
でも、要所要所の場面転換時に、
有名な曲を編曲した音楽が流れ
ああ、この頃にあの曲を作っていたのだなあ〜〜
と、分からせてくれてます。
この映画の見せ場となるのは6分間にわたる
バーンスタイン指揮シーンの完コピ!!
ここ、本当に胸熱シーンでした。
名演技でした。
バーンスタイン氏に興味のある方は楽しめるでしょうし
それほど関心の無い人でも
「天才とそれを見守る妻の生き方」として
感じるものがあるんじゃ無いかと思います。
で、
月に8本ほど映画館で映画を観る中途半端な映画好きとしては
前出の町山氏の解説によると
映画の中のバーンスタイン氏は常にお酒や薬物を
身近に置いていつも、結構なハイテンションを保っている。
そういう人って言うのは、常に何かから逃げている
何かから目を背けている。
冒頭、朝のベッドには男性の恋人がまだ寝ているシーンがある。
バーンスタイン氏はゲイであったのですが
女性の奥さんと結婚して三人の子供がいる。
演奏旅行の合間に若い男性の恋人とイチャ付いて
奥さんを怒らせたりしている。
でも奥さんが病気になった時は心の底から
心配し、看病し、その死を恐れている。
奥さんが完全に許している訳ではないが
ゲイであることを隠そうともしていないし
恐れている訳でもない。
ならばバーンスタイン氏は何から目を背けていたのだろか?
天才の頭の中は凡人の私などは想像も付かないけれど
天才は天才なりの焦燥を抱えていたのか〜〜
モノクロの中に生々しい天才のあがきを観たような
そんな気がする映画でした。
今年一番
ドキュメンタリータッチの佳作と思いきや、
スピルバーグやスコセッシがプロジューサーに名を連ねる
ハリウッド超大作でした。
監督・主演のブラットリー・クーパーは、ありとあらゆる
レニーの写真・映像を研究しており、各シーンは、Lifeや
Magnamのカメラマンが撮影した写真から飛び出したようで
アメリカ写真・映画芸術の王道を踏襲したものでした。
(ちょっと古臭い感じするかも)
白黒の前半部分は、古き良きハリウッド映画の夫婦愛を
彷彿させる。(ジューン・アリソンとジミー・スチュアート
が出てきそうだ?)
しかし、カラーの後半部分は、自由奔放(自堕落?)な生活を
謳歌するレニーと家庭を守ろうとするフェリシアに亀裂が
生じる。
とてつもない才能に、魅了され、時には戸惑った、比類
ない人生を送った夫婦の愛情物語なんだろう。
レニー役のブラットリー・クーパーは、ルックスをかなり
研究しているが、クライマックスのLPOと「復活」を
振るシーンの指揮は、実際のバーンスタインの演奏に接した
ものにとっては、正直、ヘタクソである!!!
フェリシア役のキャリー・マリガンは申し分ない立派
演技である。でもチリ人だからスペインなまりじゃないの
フェリシアは・・・
フェリシアの看病のために、コンサートをキャンセルされた
ものより
今明かされるレナード・バーンスタインの素顔
アメリカが生んだ20世紀を代表する大指揮者
レナード・バーンスタインの伝記映画です。
カラヤンと並び称されるほどの大物指揮者です。
20代から60後半まで一人で演じ切ったブラッドリー・クーパー。
監督も勤めているが、その極似ぶりに驚き、彼以外のバーンスタイン役を
思いつかない程成り切っています。
バーンスタインの精力的でカリスマ性のある姿はクーパーと、
とても似通っています。
良く言えば、ブラッドリー・クーパーのバーンスタイン憑依演技・・
熱演にに尽きる映画。
逆に言えばドラマらしいドラマがかなり薄い映画でした。。
バーンスタインに同性愛傾向があった事と、
妻のフェリシア(ケリー・マリガン)が、
60代で乳癌に罹り闘病して、
バーンスタインが愛妻家ぶりを見せるシーン。
それ以外に山も坂も谷もエピソードも少ない平板さである。
晩年にも美青年には弱い人で、教え子の青年と熱いキスを交わす
シーンがある。
バーンスタインの同性愛嗜好など、知りたくなかったのが、
私の本音です。
バーンスタインさんは北海道ゆかりの人で、1980年にスタートした
札幌コンサートホールKitaraと芸術の森・野外ステージを拠点にして
世界各国の若手音楽家をオーディションで集めて養成講座を
夏の三週間開催されるPMF
(パシフィック・ミュージック・フェスティバル)の
言い出しっぺで、第一回の総監督。
そしてそれを見ることなくバーンスタイン氏は亡くなったのです。
KitaraのPMFには毎年何回も行きました。
ヴァイオリンの五嶋みどりや弟の五嶋龍もゲストとして出演。
聴きに行きました。
ゲストのオーケストラも世界的な布陣でした。
23年経った今も開催されています。
バーンスタイン氏の遺産が日本に、北海道に、今も残って
息づいています。
ゆかりといえば世界的指揮者である佐渡裕氏の師匠としても、
日本では有名です。
「この一本でタバコはやめる」が口癖で、遂に肺癌で亡くなったのも
14歳から1日100本のヘビースモーカー・・・故のことですね。
映画でも殆どのシーンで煙草を手にしています。
一番の名演奏はエンディング映像でバーンスタインさんご本人の映像で
流れる、1973年、イーリー大聖堂でのバーンスタイン指揮、
ロンドン交響楽団演奏の「マーラーの交響曲第2番」
これぞクライマックス。
本当にダイナミック素晴らしい名演です。
大感動でした。
エンディングこそが一番の見所で聴きどころ。
身体全体の動きで楽員を鼓舞して乗せて実力以上を引き出す
「見せる指揮者」のお手本ですね。
レナード・バーンスタイン(1918年〜1990年)享年72歳。
フェリシアの死後は気落ちして後を追うように2年後には
後を追うように亡くなっています。
やはりフェリシアを深く愛していたし心の拠り所だったのですね。
バーンスタインの代名詞は「ウエストサイド物語」作曲者。
クラシック愛好家以外の世界の人々に愛されるミュージカルナンバー。
ジャズの要素も取り入れた現代的な名曲がズラリ。
バーンスタイン、その輝きは不滅です。
音楽ファン、特にクラファンやミュージカルファンの方のために
結構いろんな感想・評が多く、まだ観てない方たちを躊躇わせてるように思うので、音楽ファン、特にクラファンやミュージカルファンの方のためにひとこと書きます。
ネタバレになるかもしれないですが、この映画の全編にわたってバーンスタイン自作の有名曲が適所に使われていて、マーラーなどの楽曲も効果的に出てきて、音楽好きにはとても素晴らしいです。特筆すべきは、ブラッドリー・クーパーがバーンスタインになりきって指揮するマーラーの第2交響曲”復活”、第5楽章フィナーレの場面です。レニーの1970年代頃のコンサートを、英国のどこかのカテドラルで再現しているのですが、延々約6分間にわたって終曲まで聴けて思わず拍手したくなるほど。それとバーンスタインとフェリシアが”オン・ザ・タウン”の世界に入り込んで、ブラッドリー・クーパーがジーンケリーばりに踊るところも良かったな。またレニー自作のミサ曲の”平和:聖餐式(シークレット・ソング)”の練習シーンも良かった。
楽曲の詳細をお知りになりたい方は、Deutsche Grammophonから出ているサントラの紹介を見てほしい。それによると基本ネゼ=セガンとロンドンSOの演奏だけども、一部はバーンスタインがウィーンフィルやNYフィルに遺した音源も使われているようです。
なお、この映画はフェリシアとの愛の軌跡を中心に描いているので、バーンスタインの様々な業績や活躍を具体的に見せてくれる場面は多くない。インタビューを受ける場面で語られる方が多いようです。いわゆる伝記的な部分がもう少しあったほうが、音楽ファンには嬉しかったかもしれない。また、レニーの奔放な生き方とかフェリシアや子供たちとのかかわりの場面で、物語の説得力とかフェリシアやレニーへの共感も増したかもしれないかな。
なお、以上は私の感想です。これからの方は、惑わされず、あまり拘りなくフラットな気持ちで観てほしいです。また、NetFlixだけども映画館の音のよいところで観たほうがいい。
まあまあだった
若い指揮者がどんな評価でどのようなパフォーマンスで出世していくのかと思ったらそこはばっさり端折られて、奥さんとの出会いが描かれる。それがとても普通でつまらない。裏に同性愛があるくらいだ。
後半カラーになって、奥さんと猛烈なけんかをする。うちでそれをやったら一発で離婚だ。余程の理不尽がない限りこっちは平謝りなので、あんなふうに対等に言い合えるなんてすごい。関係が壊れることが怖くないのだろうか。本当の信頼関係で結ばれているのか。一方で男性との浮気は暗に認められているような、芸術家だから仕方がないという理解を奥さんがしているのだろうか。すごい場面だったけど、別にこの題材で見たいのはそれじゃない。偉大な指揮者だって人間だみたいなことかもしれないけど、もっともっと偉大さを見せて欲しい。
終盤に素晴らしい演奏が見られる。また、後輩への指導も指揮で演奏が見事に変わるのがすごい。そういうのがもっと見たかった。音楽や指揮の分量が3倍くらいが望ましい。
全75件中、21~40件目を表示