オッペンハイマー : 特集
【公開直前】アカデミー賞®7部門受賞、ノーラン監督の
最新作――実際に観た人は何を語るのか?「巨大な映画
だ」「これは注目すべき荒技」「IMAX®の巻き込まれ感に
圧倒」≪映画を語る“プロ”のネタバレなしレビュー≫

第96回アカデミー賞では、作品賞を含む最多7部門を受賞した「オッペンハイマー」(3月29日公開)。この受賞結果からも、本作が“注目に値する作品”であることがわかっただろう。
前回の特集では、本作の基礎情報となる“重要なポイント”を紹介したが、今回はさらに作品の深部へと迫っていこう。

第2回特集では、「オッペンハイマー」をいち早く“目撃”した人々のレビューを<ネタバレなし>でお届けしよう。さまざまな場所で映画を語り継いできた“プロ”は、本作の鑑賞体験で何を感じとったのだろうか? 心の底からから生じた“言葉”によって、「オッペンハイマー」の魅力を徹底的に解説してくれているので、ぜひ一読を(※レビュー掲載は、執筆者五十音順)。
日本公開を待ちきれず、オーストラリアに飛んで鑑賞
大島育宙が全身で体感した“異様な3時間”

まず語ってくれるのは、映画・ドラマの考察をメインとしたYouTubeチャンネル(登録者数11万人超)などで人気を博し、お笑いコンビ「XXCLUB」のメンバーでもある大島育宙氏。「オッペンハイマー」の日本公開が決定する以前、彼は驚きの行動に出ている……日本公開を待ちきれず、なんと既に封切られていたオーストラリアでの鑑賞を実践したのだ。
大島氏が全身で体感したのは“異様な3時間”。一体、何を“目撃”したのだろうか。
【「オッペンハイマー」の目撃者①】大島育宙~天才科学者の脳内に、血中に、潜り耽る……3回鑑賞しても飽きなかった~
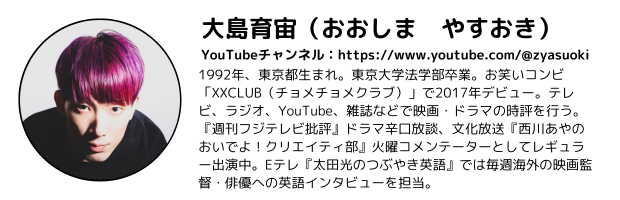
●これは“巨大な映画”――そして、クリストファー・ノーランの人間宣言だ
天才科学者の脳内に、血中に、潜り耽るために作られた巨大な映画だ。私は日本公開を待ちきれず、昨秋にオーストラリアに飛び、巨大なIMAX®シアターで観た。オッペンハイマーの頭の中に広がる量子空間の美しいイメージと原爆実験のシーンは筆舌の及ぶ余地もない映像の暴力だ。日本公開でご覧になる方も、足の届く範囲で可能な限り大きな画面と音の映画館を選んでほしい。
同時に、この映画はクリストファー・ノーランの人間宣言だ。人間の心理描写が課題と言われ続けた映画作家が1人の人物の内面だけに意地でしがみつく異様な3時間。
●「ダンケルク」との比較、これまでのノーラン映画にはない“濃密さ”にも注目
ノーランが史実を扱うのは「ダンケルク」以来、2回目だ。陸、海、空の3つの空間にいる人物の1週間、1日、1時間が恣意的にシャッフルされる「ダンケルク」には画面に映る全てをコントロールする完璧主義者・ノーランのプライドと満足が見えた。
対して、「オッペンハイマー」の時系列は尋問によって思い出させられる半強制的な回想シーンであり「ダンケルク」のようなリミックス的楽しさはない 。戦後、主人公が予想外の外圧によって、死ぬ時まで整理・直視できなかった事実を悔恨し検討させられる、苦しい時系列シャッフルだ。これまで楽しませるために時系列を入れ替えてきたノーランが観客を追い詰めるために時系列を入れ替える。

ノーランらしくなさはレイティング(※)にも影響している。本作がノーラン映画には珍しく各国で年齢制限がかかったのは、オッペンハイマーが不倫の恋に落ちるシーンのためだ。キリアン・マーフィも 「感情的に最重要な場面」と語るように、フローレンス・ピュー演じる医師との関係はこれまでのノーラン映画にはない濃密さだ。彼女はオッペンハイマーの弱点を初対面から看破していることが会話で示され、彼女の退場とともに彼の純粋さは手綱が外れたように加速する。
それほどノーランはオッペンハイマーに自身を投影している。科学の地平が広がる可能性があるなら、道義的是非はさておき突き進むしかなかった科学者に、映画の世界を開拓している自負が重なる。
※編集部註:日本では「R15+指定」
●観るたびに異なる機微が浮かび上がり、飽きない――キーとなるのは「世界の脆さ」
これまでのノーラン映画はどれもそれなりに体験型アトラクションだった。今作はどう頑張って解釈してもアトラクションではない。実在の負の歴史だから爽快でない。懊悩を追体験するが、一方通行なダウナー映画でもない。恋も嫉妬も愛憎も使命感も、感情の起伏はドラマチックに溢れる。私は帰国後も試写に二度通ったが、観るたびに異なる機微が浮かび上がり、飽きない。

ノーランの映画には「世界は脆い」という気分が漂う。個人にとって世界を世界たらしめるのが記憶だが「世界なんて、編集と認知の順番次第で簡単に覆るぞ」と言わんばかりにノーランは記憶をシャッフルする。「ダークナイト」のジョーカーは観る者の世界を倫理で揺さぶる。その時に持てる予算と影響力に応じて手を替え品を替え「世界の脆さ」を見せつけてきた。そんなマジシャンが円熟期に世界を破壊し得る兵器の開発を題材に選んだのは偶然ではない。「我は世界の破壊者」だから。
歴史的名作の主人公との比較、ノーランの荒技に刮目
芝山幹郎が紐解く“オッペンハイマー”の実像とは?

続いて、言葉を紡いだのは、これまで数々の映画の魅力を圧倒的な知識量・鋭い考察で論じてきた評論家・翻訳家の芝山幹郎氏。本作を鑑賞し終えた瞬間、映画史に燦然と輝く“名作”を思い浮かべつつ、ノーラン監督の“あるテクニック”に着目せざるを得なかったようだ。キーとなっているのは「蓄積」という言葉。果たして、これが意味するものとは……?
【「オッペンハイマー」の目撃者②】芝山幹郎~「蓄積する力」で難物に挑む~
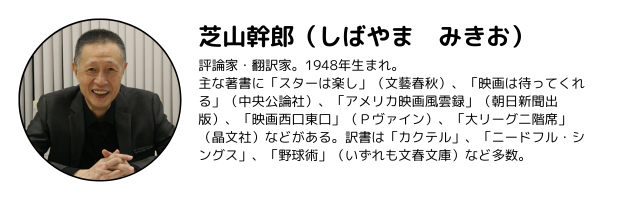
●オッペンハイマーに“解放”は訪れない 生きた世界、直面した状況の“息苦しさ”
「オッペンハイマー」を見終えた直後、私は反射的に「アラビアのロレンス」(1962)を思い浮かべた。業績の評価をめぐって世に物議を醸し、みずからも震え続けてやまない生涯を送った人物の伝記映画。デヴィッド・リーンもクリストファー・ノーランも、主人公の複雑な二面性に心惹かれたのだろうか。
ただ、T・E・ロレンスには砂漠というカタルシスがあった。彼はラクダの群れを率いて剣を振りかざし、奪った貨車の屋根で優雅な悪魔のように舞い踊っていた。
オッペンハイマーに、その解放は訪れない。彼が生きた世界は、そして直面した状況は、もっと息苦しそうだった。
●“不吉な化学記号”のような人物の肖像を立体的に描き出す
災害や疫病と並んで、核兵器は人類最大のオブセッションだ。どれもおびただしい死をもたらす。最終兵器という動かしがたい定義の前では、戦争抑止力の側面は、どうしても霞みがちだ。根底には恐怖がうずくまる。
そのオブセッションを、世界に送り出してしまった人物の伝記映画は、どんな形を取るのか。根源的な恐怖を作り出した者は、自身も根源的な恐怖にさらされて震え続ける。われわれは、「オッペンハイマー」の名を不吉な化学記号のように口にしてきた。彼のファーストネームは、意外に知られていない。

ノーランは、そんなオッペンハイマーの肖像を立体的に描き出す。まず彼は、渋い性格俳優のキリアン・マーフィを主役に抜擢した(やはりアイルランド出身のピーター・オトゥールを連想させる部分がある)。加えて、ロバート・ダウニーJr.やマット・デイモン、さらにはゲイリー・オールドマンといった名優たちをアクの強い役に配し、オッペンハイマーの不安や苦悩を浮き彫りにした。すると、どうだ。映像で何度か示唆される核分裂と核融合の反応が、登場人物同士の間でも起こりはじめるではないか。
●積み重ねる力が図抜けている――ノーランの注目すべき“荒技”とは?
これは注目すべき荒技だ。ことにノーランの場合は、積み重ねる力が図抜けている。組み立てる力というより、蓄積する力。土台をがっしりと固め、強靱な骨格に支えられた躯体を入念に築き上げていく。
イメージ、音響、情感、オブセッション。どれも蓄積されることで効果や深みを増す。描かれる世界が拡大されようと、細部の密度は落ちない。建物が大きくなっても、壁や天井がゆるんだり、たわんだりすることはない。
ノーランは、そこに勝負を賭けている。曲解を恐れぬ気概が、画面から伝わってくる。対象を凝視し、感情を抑制し、覚悟を定めて、彼はこの難物に挑んだのだろう。
IMAX®→通常スクリーン…異なる“体験”の気づき
立田敦子が断言「IMAX®で観るという選択肢以外はない」

最後に感想を述べてくれたのは、映画ジャーナリスト・評論家の立田敦子氏。大島氏と同様、海外のIMAX®シアターで「オッペンハイマー」を体感し、そこから通常スクリーンでの鑑賞も行っている。本作のIMAX®鑑賞ならではの魅力を解説してもらった。
【「オッペンハイマー」の目撃者③】立田敦子~IMAX®で伝記映画を“体験”することの意味~
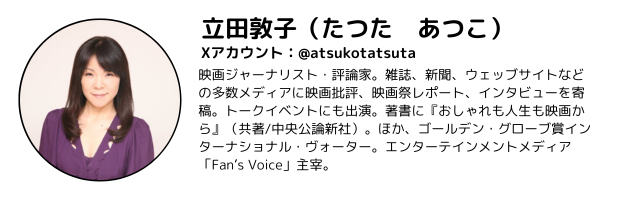
●IMAX®ならではの没入感 観客に提供されるのは“数奇な心の旅の追体験”
クリストファー・ノーランは、IMAX®カメラによるフィルム撮影による卓越した没入感を誰よりも追求している監督だ。天才物理学者ロバート・オッペンハイマーの伝記映画「オッペンハイマー」は、この基本コンセプトをさらに推し進めた野心作である。IMAX®65ミリと65ミリのラージフォーマットフィルムカメラを使用、さらに本作のために65ミリカメラ用のモノクロ・フィルムも開発している。実際、本作の最大のチャレンジのひとつはSF大作でも戦争大作でもなく、伝記映画でこのフォーマットを試すことにあるだろう。

オッペンハイマー(キリアン・マーフィ)は、第二次大戦下における原子爆弾開発を目的とした「マンハッタン計画」を主導し、「トリニティ実験」を成功させたことで雄となるが、戦後は原爆とは桁外れの威力を持つ水素爆弾の開発に意義を唱え、その結果、赤狩りの対象となった。
原作である、カイ・バード&マーティン・J・シャーウィンによる評伝『オッペンハイマー』の原題は「American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer」。プロメテウスとは、ギリシャ神話で天界から火を盗んで人類に与えた為、罰せられた神の名である。ノーランは、顔のクローズアップを多用したカメラワークとIMAX®ならではの没入感によって、複雑かつアンビバレントな葛藤を内に抱えた科学者の視点にどっぷりと浸って、その数奇な心の旅を追体験することを観客に提供する。決して、核爆発のインパクトだけを期待して、IMAX®フォーマットを選択しているわけではない。
●「オッペンハイマー」の物語が、実は今日と地続きであることに気がつき震撼する
ストーリーはふたつの公聴会(聴聞会)が基軸に構成されている。ひとつは、オッペンハイマーが政府の公職から追われに至る1954年聴聞会である。観客は、この圧迫感のある陰湿な小部屋と、過去を行き来しながら、オッペンハイマーの数奇な半生を巡る心の旅に帯同するのだ。もうひとつの公聴会は、オッペンハイマーと確執があるアメリカ原子力委員会の創設委員でルイス・ストローズ(ロバート・ダウニー・Jr.)の1958年に上院で行われた公聴会である。このパートはモノクロ・フィルムで撮影されている。

東部の裕福なアカデミックエリートと靴のセールスマンから銀行家として成り上がり政府の要職を得るまでに至った叩き上げ。米国の原理力政策のふたりのキーマンの「転換」をそれぞれ“核分裂と“核融合”というキャッチをつけて対比させる。キリアン・マーフィら俳優陣は準備のために「アマデウス」を観たというが、モーツァルトとサリエリと同様の対立構造を軸にすることによって、平凡な伝記映画を回避し、3時間という長さを感じ捺せない緊張感を保ち続ける。歴史の局面として捉えていた彼らの物語が、実は今日と地続きであることに気がつき震撼する。
●IMAX®体験では“巻き込まれ感に圧倒”された IMAX®言語で語られていることを確信
筆者は本作をまず海外のIMAX®シアターで鑑賞したが、まずその巻き込まれ感に圧倒された。ノーランの意図はまさにそこにあったのだろう。その後、通常のスクリーンサイズ(シネマスコープ)で鑑賞し、確信した。本作はIMAX®言語で語られている。ストーリーではなく、この作品の核に触れるにはIMAX®で観るという選択肢以外はない。
【まとめ】日本公開まであとわずか――“目撃者”となったあなたは、何を感じるだろうか

以上が、本作を“目撃”した3人のレビューとなる。第1回特集を経て、彼らの“言葉”に触れてみると、「オッペンハイマー」という映画の輪郭がより鮮明に見えてきたのではないだろうか。
映画「オッペンハイマー」は、3月29日に日本公開を迎える。封切りまで間もなく――本作を鑑賞するか否かの判断は、あなた自身に委ねられている。もしも“目撃者”となることを選んだ場合は、その目で観て、感じたことをぜひ“言葉”にしてみてほしい。
※映画公開後に掲載する本特集3ページ目では、作品の理解度がさらに深まる解説・考察をご紹介します。
公式サイト:https://www.oppenheimermovie.jp







