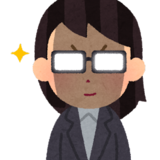ほかげのレビュー・感想・評価
全120件中、41~60件目を表示
「もはや戦後ではない」から70年近く経とうとしている
2024年映画館鑑賞9作品目
2月24日(土)チネラビィータ
会員料金1500円
監督と脚本は『鉄男』『ヒルコ/妖怪ハンター』『双生児 -GEMINI-』『野火』『斬、』の塚本晋也
粗筋
売春婦の家に転がり込んだ復員兵と戦災孤児
それぞれが大東亜戦争のトラウマを抱えていた
3人の同居生活はしばらく続いたが発砲音で戦地の恐怖が蘇った復員兵は発狂し暴れ追い出されることに
こうして女と孤児の二人暮らしになった
女は自分の子供のように孤児を可愛がった
帰りが遅い孤児を叱り危険な仕事を断って来いと指示した女は戻って来た孤児に嫌いになったと言って追い出した
テキ屋の男と汽車に乗り田舎にやって来た孤児は元上官への復讐を見届けることになる
帰りの汽車賃を渡された孤児は女の家に戻って来た
女は重い病に罹っていた
女と別れる日がやって来た
孤児は幼くして再び自立しなければいけなかった
映画の出来として悪くない
むしろ傑作の部類
若干不満点はあるがほぼ星5の評価をつけたい
出だしも良い
ラストも好き
反戦のメッセージについて特に改めてレビューに書くつもりはない
野火などで既に書いたつもりだ
ガザ地区もウクライナもそろそろ停戦してもらいたいと願ってはいるが決定的な価値観の違いに虚しいばかりだ
俳優陣の熱演がとても素晴らしかった
朝ドラの方も悪くはないがやっぱりこっちの方がいいな趣里は
私娼の役だがヌードにはならない
ヌードになる必然性はなかった
着衣でも充分だから
それを思うとあの映画でヌードになった意味が今でも不明だ
子役の塚尾くんの表情や眼差しが天才的
主演は趣里のようだが実質的に主役なのは彼だろう
かわいい
名前はあまり存じ上げないが復員兵を演じた河野もなかなか良い
森山未來の芝居にケチをつけるつもりはないが汗出すぎ
あれじゃまるで漫画だ
下手くそだけどどっかで観たことがあるなと思ったら大森監督だった
弟の足元にも及ばない大根ぶりだった
妻?役の唯野未歩子は随分と歳を取ったなと感じた
彼女は自分と最も共通点が多い芸能人なので親しみは感じている
思わせぶりな不安を煽る効果音の多用は塚本晋也の世界
だが焼夷弾の焼け野原の映像直前の地鳴りがするような音とテキ屋と孤児が乗った汽車の音は大きすぎる
びっくりしたというか迷惑だ
それにしても『首』は戦争の悲惨さとか反戦映画と言われずましてやあろうことか最も尊敬する武将は誰かとランキング形式で称えられる始末
かたや大東亜戦争がらみなら例外を除けば反戦映画とモテ囃される
これが日本の教育の成果なんだろう
朝日新聞の社員はみんな優等生
自分は劣等生
ほかげさまです
いやおかげさまです
配役
大東亜戦争で夫と息子を亡くし自宅兼居酒屋で売春をしている女に趣里
戦争孤児を連れて復讐を果たす片腕が不自由なテキ屋に森山未來
手提げカバンの中に拳銃を忍ばせている戦争孤児に塚尾桜雅
かつては教師だった復員兵に河野宏紀
女の店に日本酒を仕入れる男に利重剛
大東亜戦争でテキ屋の上官だった男に大森立嗣
上官だった男の妻?に唯野未歩子
戦争で家族を失った女と戦災孤児が出会い一緒に生活を始める…という話なのだが
戦後間もない日本。疲弊した人々、瓦礫の中の闇市、そんな中で半分崩れかかった小屋のような家で居酒屋を営み、時には身体を売りながら生きる戦争未亡人と盗みをしながら生きる戦災孤児、この二人が出合い、生活を共にし始める。そんな二人が肩を寄せ合い生きていく心暖まる話なのかと思って観ていたのだが…。
この二人に絡む男たち、元教師の若い男、そして謎の男アキモト、戦争を何とか生き延び日本に帰ってきたものの心的外傷に苦しむ男たちの話でもある。
戦争によるPTSD。これをテーマにした名画は多い。「ディア・ハンター」「タクシードライバー」「アメリカン・スナイパー」などなど。アキモトの下りでは「ゆきゆきて、神軍」(これは凄まじいドキュメンタリー映画で僕は途中から震えが止まらなかった)を思い出していた。「ゴジラ-1.0」もそこにテーマがあったと僕は思っている。
僕たちは先人の灯りの中で生きている。
「ほかげ」
・・・知らない言葉なので調べたら「火(特に灯火)の光」だそうで。
この題名はラストの少年に芽生えたであろう気持ち、
感情を言い表したのではなかろうか?と思います。
さらに文字は「火影・灯影」と書くそうで・・・。
塚本監督作品「野火」の「火」が落とした影の世界(後の世界)を描く
という意味も兼ねているのかな?
さて、本作。主演の趣里さんはじめ、俳優陣の圧倒的かつ確かな演技で
最初から引き込まれ一気に観てしまいました。朝ドラとのギャップを
感じたのもつかの間でした。いやぁ、すばらしい女優さんですね。
これだけでも鑑賞の価値があるとおもいます。
「野火」では戦争を、本作では戦後を描いていますが、共通するのは
「生々しさ」です。
きっとこうだったんだろう戦後の風景と人々。
戦争の傷で人間の大切なものを失ってしまった者たち。
生活のすべてを失い生への渇望のみで生きている者たち。
戦時をいまだに続けざるを得ない人。
そこには明るい未来なんてものは存在せず、勝手に背負わされた
負に対してなんとか抗っている人々が居るだけです。
けど、、だけど、心にくすぶっている「希望と願いの灯り」はあるわけで、
体内に取り込んでしまいどうしようもなくなってしまった者の中には
「繰り返してはいけない戦争の火」がくすぶり続けているわけで、
でも、多くの人には幸せだった「戦前の記憶と人間としての感情の灯り」はあるわけで、
それらは他者と関わることでちょっとずつ手から漏れて光るのです。
それこそが「ほかげ」であり。それに照らされ未来に導かれるのが戦後を
生きていく子供たちだったのではないでしょうか?
救いは基本的になく、ただただ絶望を感じ続ける本作ではありますが、
クライマックスの描写と、遠くに聞こえる刹那の音が、
次代への願いのようであり、渡されるバトンのようでもあり、
新たな時代を始めるスタートの合図の様でもあり。
雑踏の先に明るい場所があることを願わざるをえないし、それは僕らが
つくっていくものなんだろうと思います、改めて。
・・・やっぱり忘れちゃいけないことなんだよね。
目を背けてはいけない
映画『ほかげ』地味な作品なんだけど、その作品創りには敬意を評したい。先の大戦からまもなく百年近くが経とうとしている。喉元すぎれば暑さを忘れ、そんな言葉が頭をよぎる。大戦の経験者の証言もめっきり減ってしまった。また過ちを繰り返すのだろうか。
先の大戦から百年近く
ややもすると美化するような風潮と作品群。
ここ十年ぐらいの傾向のように思えてならない。
あんなむごたらしい戦いの中にあっても、こんな素敵なことがあったとか。
日本のために戦い、命を失った英霊のおかげで今日があるとか。
そうだろうか。
英霊、つまり戦死者。
これは、たんに戦争の犠牲者でしかない。
戦争は、不条理の極みであり。
そこに、真実や正義などない。
ただの国家間の殺し合いでしかない。
そんな暗い時代にもこんな素敵な出会いと恋があったとか。
それが事実でも、それはそれでいい。
ただ注意しないと、いつのまにか大戦自体も肯定的にとらえようとすり替えられること。
『ほかげ』出だしは、まるで一幕劇でも見てるかのよう。
一件のボロ居酒屋。
そこに夫と子供を失った一人の女性。
居酒屋は、表の看板。
体を売ってその日その日を生きてゆく。
息が詰まりそうな空間と芝居。
ああ、戦争の傷跡とはこういうものかと。
誰も目をそむけたくなる。
そう、戦争の本質とはそうなんだろうと。
あえてそのことから目をそらさず映像化したことに、拍手を贈りたい。
丁寧な作品創りと、俳優陣の演技がいい。
後半は、打って変わって動的に
このあたりは、上手だなと。
闇市の喧騒。
傷痍軍人の物乞い。
そして、なによりも戦争によって心を病んでしまった者の傷跡。
薄暗い路地裏にたむろする帰還兵。
あてどもない彷徨と絶望。
森山未来の帰還兵がいい。
拭いきれない罪の重圧。
なんとか過去を清算しようとする姿。
清算などできないのだが。
作者は、繰り返し戦争の不条理を訴えてくる。
そんな時代に翻弄される人間。
正義はどこに行ったんだろう。
そう戦争に正義などない。
嫌というほど伝わってくる。
だから見ていて、決して心地良いものではない。
心地よくなる戦争映画があるとしたら、そっちのほうがおかしいのだと。
戦争という出来事に、真正面から向かい合った製作陣に頭が下がる。
戦後の実相は底知れぬ漆黒の闇だった
1 戦後間もない頃の闇市で、一人生き抜く少年の姿を通じ、戦後の実相を描く。
2 あらすじは次のとおり。
何処とは特定できない町の闇市。一人の女性が青線的な商売をしている。そこに恐らく壮絶な体験をした孤児が出入りする。孤児はその女性と兵隊上がりとともに一時の家族ごっこをしたかと思えば、金を稼ぐために市中で出会った男の危ない用事を手助けすることに。果たして彼は・・・。
3 戦禍で焦土と化した中から日本人の戦後がはじまった。戦争から解放された喜びはほんの一瞬、その後は明日のない現実のみが残る。多くの人は身近な人や住む家を失い、希望が見つけられないその日暮らし。人々の心は荒み、なりふり構わず自己の欲望のまま行動する。何も持たない女は体を売り親のない子供はかっぱらいで生きていく。男は体に血や硝煙の臭いを残し、まだ戦場の記憶を引きづっていた。戦後まもないころは、まさに暗黒であった。本作は、そうした時代背景の基で日本の何処にでもあった戦後の実相が描かれた。全体的に救いのない映画となった。
4 映画のなかで印象的だったのは、疑似家族として繋がったエピソード。微笑ましさを通り越し狂気を纏っていた。そして、バイタリティー溢れた子役。それにしても画面が暗くおどろおどろしいのには参りました。
それぞれに強くのしかかる戦争
ほんの数十年前のことなのに、戦争当事国であっだ、戦争当時社会であったことのリアリティがなくなって久しい。気がつけば失われた30年というけれどお金、経済や政治的な立場、グローバル化と言いながらグローバルとは反対の方向にいく失われた30年は戦争のリアリティ当事者性も失われ無惨な歴史修正や反知性が跋扈している。
そんなことを強く感じざるを得ない作品。
役者さんたちは渾身で素晴らしい。渾身すぎて力強すぎてかえってそのことかわからなくなるくらいだ。
大人たちは皆モノローグだ。人との関わりを最低限避けたり自らの体験した戦争の地獄にうなされたりそれでも目的があったりなかったりで人に近づき近づかれ、でもこの作品に出てくる女も帰還兵も皆モノローグ。子どもに話しかけ関わりを持っても彼らの世界はもうモノローグから出ていけない。子どもと戦災孤児となり子どもも自らの戦争体験身内の死や恐怖孤独にうなされるが、彼は対話する。1人で言葉少なく、目を見開いて世界と向き合わざる得ないから、良い人が悪い人か嗅覚で判断し経験値を高めていく、彼は対話し他人と呼吸する。
モノローグに人を押し込める戦争は、被害者も加害者も一重だと思う。
覚悟をもって観なければならない作品
反戦映画と言ってしまうのは簡単だけど。戦争に奪われ傷ついた人達の重い暗い物語である。
趣里が演じる女は焼け跡の中の居酒屋の建物で暮らしている。そこに戦災孤児と復員兵がやってきて奇妙な共同生活を始める。ほかげとは、狭く暗いこの居酒屋の壁に映る彼らの傷ついたこころに他ならない。復員兵は戦場の恐怖に怯える。戦災孤児はおそらくは空襲の恐怖に怯え夜な夜なうなされる。そして女は身体を売って生きなければならない運命を嘆き恨む。彼らの想いはほかげのようにゆらゆらと揺れ繰り返し彼ら自身を苛むが彼らは居酒屋の闇に囚われ出ていけない。特に女は。この居酒屋には奥の間があり女の心の闇、そこには戦争に奪われた夫と子への想いが潜む。そこにはもはや火影すら届かない。途方もない暗闇である。
映画の後半は森山未來の演じる復員兵と戦災孤児の旅が描かれる。あらすじを読んだときはなぜ復員兵が二人出てくるのか、前半の居酒屋の復員兵が後半の復員兵と同じであっては何故いけないのか疑問に思っていたが旅の目的が分かることにより理解できた。この復員兵は戦争の被害者であるとともに加害者でもある。
彼はある妄執に囚われている。その意味では、彼は女の住む暗い居酒屋に同じく住んでおり、壁に映る火影を見つめているのである。
私は、もちろん塚本晋也の人となりを知らない。でも恐らくは心やさしい人なのだと思う。この映画では、女にも復員兵たちにも孤児にも、希望の光がみえる瞬間が描かれる。凄まじい情念をもって生きていく女の暮らしにも一瞬ホッとする情景があるし、復員兵にもやろうとしていることを躊躇する場面がある。こういったシーンを置いたことは塚本の本質的な優しさによるものだと思う。でも結局、彼らは暴力や病気などにさらされ、他人を拒否し過酷な宿命に突き進んでいく。
私には、こころ優しい塚本が歯を食いしばってこのドラマをつくっているように思える。戦争の過酷さを描くということはそれだけの覚悟がいることなのである。塚本は表現者としてその責務を果たそうとしているようにみえる。だから観客である我々も受け止めなくてはならない。受け止めたからといって何が出来るかはよく分からないけど。
【今作は、戦争終結後も、心に痛みや闇を抱える人たちの姿をシビアなタッチで描いた、ワンシーンも戦闘シーンが無いが故に強烈な印象を残す、見事な反戦映画である。】
1.女(趣里)は半焼の小さな何もない居酒屋で独り暮らし。襖の向こうは誰にも見せない。ある日、そこに泥棒をした男の子と、元教師と言う男が転がり込む。
男の子は拳銃を持っているが、女は”そんなものを持っていては駄目”と言って茶筒にいれてしまう。
男は初日こそ金を持ってきたが、居座る。だが、ある日男の子により、彼が働いておらず町の片隅でボンヤリ座って一日を過ごしている事が告げられ、女は男を追い出す。
そして、男の子も真っ当な仕事をしていない事が判り、女は男の子も追い出す。
- 襖の向こうには、線香とご飯が添えられた位牌が二つある。-
2.男(森山未來)は、男の子と一緒に歩いている。川で魚を取ったり、トウモロコシを食べたり。
そして、ある日。男は頭がオカシクなった男が閉じ込められた建物に行って、窓から手を入れ、その男の頭を撫でてやる。男の子が”何をしたの?”と聞くと男は”皆、面白い奴だったんだよ。”と答えるのである。
更に別の日に、男は立派な邸宅にコッソリと忍び込み、裕福そうな老夫婦の姿を見た後に、男の子に”夜に成ったら、あの男を呼び出してくれ。俺の名前を出せば来るから。”と言う。
そして、夜。初老の男が着物姿でやって来る。”久しぶりだな。腕は残念だったな。”と語りかけ、男も敬礼をしながら男に対峙する。軍での元上官である事が判る。
男は、男の子から拳銃を貰い、且つての戦友たち(上官の男の命令で、捕虜の処刑をした後に、精神がオカシクなってしまった者。処刑を拒否し、殺された者。)の名を叫びながら初老の男の身体のあちらこちらに銃弾を撃ち込む。
そして、”お前はその痛みを抱えたまま、生きていけ。”と冷たく言い放ち、”これで戦争が終わった!”と夜空に腕を差し上げ叫ぶのである。
3.男の子は久しぶりに女の家に戻って来る。女は”病気になってしまったよ。近づいちゃ駄目だよ。この間は酷い事を言ってごめんね。”と襖越しに謝り、男の子に”真面目に働くんだよ!”と叫ぶように言葉を掛ける。
男の子は、その言葉を聞いて且つて、盗み食いをした路上の雑炊屋で働き始める。そして、暗い防空壕に入って行く。そこには、教師だったという男が、虚無的な顔をして座っている。男の子は、その姿を見て男が大事に持っていた教科書を置いて去るのである。
ー 戦争孤児の男の子の表情が、序盤から徐々に大人びてしっかりとしていく過程を、その瞳と共に見事に描いている点が、素晴らしい。-
<今作は、戦争が終わっても心に傷や痛みを抱えながら生きる人々の姿を、シビアなトーンで描いた見事な反戦映画なのである。>
<2024年2月3日 刈谷日劇にて鑑賞>
灯された救いの火の頼りなさと、その影の深さ
ほかげ(火影)と聞くと、NARUTOのイメージが浮かんでしまう自分もどうだかなぁと思いながら、改めて意味を調べてみた。すると、「火の光、灯火」と「灯火に照らされてできる影」どちらも表しているらしい。なるほど、映画を観終えると、塚本監督がこのタイトルに寄せた思いのようなものが少しわかった気がした。
趣里演じる女が暮らす居酒屋に転がり込んできた、孤児と復員兵。それぞれが身寄りを無くした3人にとっては、お互いは束の間の救いの存在だったことだろう。けれど、その救いも、復員兵が灯した火のように頼りなく、影はそれぞれが抱えている闇のように深かった。
生きるために体を売りつつ、けれど決して奥の部屋は覗かせないことでかろうじて自分を保っている女。教科書をお守りにして、かつて教師だった記憶にすがる復員兵。拾った拳銃を肌身離さない孤児。
一時は、それぞれの闇を抑えて、うまく行きかけるのだが、闇市から聞こえてきた発砲音をきっかけに、あっという間に関係が崩壊していくところが切ない。
とりわけ、教師だったはずの復員兵は、女を殴り、孤児を投げ飛ばして、お守りだったはずの教科書に目もくれない。
兵士として、戦争という暴力の真っ只中に緊張と共に置かれ続けた結果、心が完全に壊れてしまったのだろう。
それに対して、森山未來の登場後に出てくる旧上官は、潤沢な恩給をもらって、優雅な戦後を暮らしている。その対比がやるせない。
個人的に、女が孤児にかける言葉に少し違和感を感じる場面がいくつかあって、この点数にしたが、全体としてはまとまったいい映画だと思う。
敗戦後の女性の生き延びていく道
主演の趣里氏の目つきは、岸井ゆきの氏とも見紛うほど鋭いものでした。敗戦後の混乱期に男手を頼りながら生き延びていこうとすれば、『ゴジラ-1.0』の浜辺美波氏の演じた女性よりも、こちらの役柄の方が実態に即しているであろう。ただ、塚尾桜雅氏、河野宏紀氏、利重剛氏の演じるそれぞれの出入りする男性への態度が、そのときの気分によって違うのには戸惑いを感じた。
森山未來氏が演じた男性が、上官に復讐したいという気持ちはわかったけれど、それで戦争が終わったと言って良いのかという疑問は残った。
塚尾桜雅氏はもちろんのこと、報復を受けた上官を含むすべての登場人物の行く末に、少しでも喜べる生活が訪れてほしいものである。
終わらない戦争
薄暗い部屋でひっそりと息をひそめるようにして暮らす女、闇市で食べ物を盗んで暮らす孤児、PTSDに苦しむ復員兵。映画前半は彼らが織りなす疑似家族のドラマとなっている。
戦争のトラウマを抱える者同士、身を寄せあいながら慎ましく暮らす光景に、戦争の”傷跡”が嫌というほど思い知らされた。
どこからともなく聞こえてくる大きな物音にパニック障害に陥る復員兵。戦火の悪夢にうなされる孤児。生きる屍のように体を売る女。戦争は終わっても彼等の中ではまだ戦争は続いているのだ…ということが実感される。
物語は女の視点を軸に展開されていくが、後半から孤児の視点に切り替わり、カメラも薄暗い部屋から屋外に出ていくようになる。重苦しいトーンから解放されて、ここからは孤児とテキ家の男の旅を描くロードムービーのようになっていく。
ここでは何と言ってもテキ屋の謎めいたキャラクターが出色である。彼もまた戦争の傷を抱えて生きる孤独な男で、その顛末には原一男監督のドキュメンタリー「ゆきゆきて、神軍」が連想された。
製作、監督、脚本、撮影、編集は塚本晋也。
本作は「野火」、「斬、」に続く戦争三部作の最終章ということである。「斬、」は江戸時代末期を舞台にしているため若干趣を異にするが、戦時下を描いた「野火」と戦後を描いた本作は姉妹作のように並べて観ることが出来る。いずれも反戦メッセージが強く押し出されている。
印象に残ったシーンは幾つかある。
例えば、テキ屋の最後の”選択”と、その後に続く孤児の自律には、平和への祈りとかすかな希望が感じられた。
また、女が切り盛りする居酒屋は一種異様な雰囲気に包み込まれており、まるでホラー映画のような禍々しさで切り取られている。とりわけタイトルシーンにおけるヒモ男と女のスリリングなやり取りは出色の出来で、一気に映画の世界に引き込まれた。
また、塚本作品の特徴と言えば過激なバイオレンスシーンである。復員兵がPTSDでパニック障害に陥るシーン、テキ屋の男の復讐を描く緊迫感溢れるシーンに目が離せなかった。
俳優の肉体描写も如何にも”塚本印”という気がした。女を演じた趣里のふくらはぎに対するフェティシズム溢れるカット、テキ屋の男を演じた森山未來の鍛え抜かれた裸体を克明に記したカット等にそれを強く感じる。
とにかく本作における趣里の存在感は圧倒的で、同時期に放映されている朝ドラのイメージとは真逆で驚かされてしまった。森山未來はもちろん、孤児を演じた子役の澄んだ眼差し、復員兵を演じた俳優の説得力のある造形も素晴らしかった。
戦争が終わっても人々の戦いは続く
終戦直後の闇市を舞台に戦争に翻弄された人々の姿を描いヒューマンドラマ。半焼けの居酒屋で暮らす女と片腕が動かない男、そして戦争孤児の子供が必死に生き伸びる姿を見事に描いている。特に印象的なのが孤児を演じた子役の表情が素晴らしく引き込まれた。戦争が終わっても人々の戦いは続くことを改めて実感しました。
2024-11
面白かった
塚本監督には頭が下がる
全120件中、41~60件目を表示