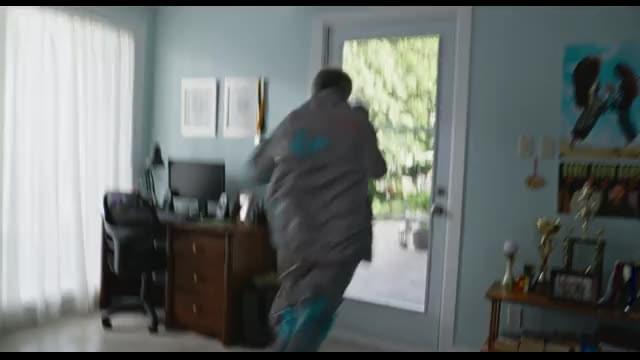ボーはおそれているのレビュー・感想・評価
全364件中、221~240件目を表示
不快な三時間
精神を病んだ主人公ボーの見ている奇妙奇天烈な世界を3時間もみせられた
もう少し短くてよくない?
みる前に予想した通り不愉快度120%
ミッドサマーや継承よりはまし
吐き気をもよおさなかったので
不愉快な時間の長さはナンバーワンかも
精神を病んだ息子を心配して見守る母親の仕組んだ壮大なドッキリ大作戦
ドッキリにはめられてどんどん妄想膨らむ主人公
彼の見る現実と過去と絡みあう異様な妄想
そこにストーリーはほんの少し
かあちゃん死んじゃったから葬式に帰る
実際は見守るレベルじゃなくて異常な監視
こんなモンスターペアレントがいたらどんどん頭おかしくなっちゃうよね
モンスターペアレント通り越して精神異常者
頭おかしいやつしか出てこないし、ヒステリックに叫びまくって発狂するやつ多数
本当に不愉快な3時間
こんな映画他には存在しないし見事な世界観なサイコパスホラーだけどさ、やっぱ二度と観たくないな
A24ホラーって2度と観たくない映画ばっかり
トークトゥーミーは良かったけどね、それ以外は二度とみないよ
で、結局屋根裏に父親監禁してたって事でOK?
すぐに妄想入って奇妙奇天烈炸裂してたけどね
最終的に被害妄想裁判にて自爆
あんな母親いたら誰だってね
同情します
ホアキン・フェニックスの病み芝居は最高です
ボーの見る奇妙奇天烈な妄想世界をみて、彼と世界を哲学的に分析しましょう
その前に、どれが現実でどれが妄想かだけ教えてもらえすか?
自分で判断しろって?
そうですよね
無理です
まず強烈なオープニングから察するにボー君は生まれた時から精神異常あり
オープニングに爆発音。戦争?
いや、でも水の中っぽいし
戦争中に水の中に潜ってるのか?
と思ったら出産シーン
泣かない赤ちゃん
そしてヒステリックに叫ぶかあちゃん
思い返すとお腹の中にいる時から母親との戦争が始まっていたって事でしょうか
そして精神異常な子供が生まれたのは父親のせい!
と屋根裏監禁の流れでしょうか?
ボー家の周りは最悪な環境
そこも妄想なんだろうけど、最初は気づかずに最近のアメリカの荒み具合やばいねって勘違いする
アメリカでオピオイド中毒者が蔓延している番組を見たばかりで、ボーのマンションの入口にいたホームレスが番組に映っていた中毒患者そのものだったんですよね
オピオイドを作った会社を母親の会社にたとえて風刺をいれてるんだろうな
ボーが半監禁?の手下の家の子供も朝ご飯が、そのお薬だったし
ドア下から投げ込まれるメッセージ
うるさい隣人
母親に会わなければならない恐怖
恐怖が生みだす妄想のオンパレード
妄想なのかと思ったけど、身体に傷跡あったから全裸のシリアルキラーは現実ですよね
路上のホームレス軍団も妄想かと思ったけど、部屋荒らされてたから現実?
部屋荒らされてたの妄想の可能性だとしたら‥
やっぱりパンフレット買って読まなきゃだめかな?
妄想が表現する彼の過去のトラウマなど、またWOWOWで放送した際に録画してじっくり分析してみます
いや多分しない、だって二度と観たくないから
奇妙奇天烈ぶっ飛び映画としては
哀れなるもの
の方が俄然好きです
変な映画
めっちゃ眠い
観てて眠すぎる。
主人公がかなりの心配性。
主人公目線で描かれるから誇張された出来事が連発。
コメディでもなくホラーでもなく中途半端。
ストーリー自体微妙なので叫び声や音響でインパクトを出している感じ。
合わない人はひたすら眠いです。
二度ある事は三度ある?三度目の正直?
二度ある事は、
三度ある。
か、
三度目の正直になるか。
内容は、
前前作、前作、
以上でも以下でもない。
が、
両作品以下と、
評価される可能性がある主な理由3点。
1.何故予告編であのシークエンスを披露しないのか。
『ヘレディタリー/継承』も、
『ミッドサマー』も不穏な設定一発の予告効果は内容よりも強いインパクトがそれなりに効いてなかったか。
2.あの人とあの部屋を、
中盤からでも何故もっと入れないのか、
プロット、編集の問題、追加撮影は不要。
『ヘレディタリー/継承』のツリーハウスと同じ役割、無理矢理だけど、それだけで何とかしていた(私の記憶では)。
3.言ってもしょうがない事の最後は、
不要なシークエンスが多い、
例えば、父とのシークエンスを全オミット。
以上。
【蛇足】
もしも、
ボウうしろうしろ!
歓声、応援、声出し、コスプレOK、
うちわ、タオル、ペンライト、サイリウムの持ち込みOK、
火器類の持ち込み、クラッカー・笛などの鳴り物の使用までOKなら、
やっぱり行かないかな・・・
ホラー・コメディの傑作!
この作品が、ホラーでありながらコメディであることを俯瞰できないと、チンプンカンプンな作品に観えるかも知れません。評価がイマイチなのは、そのツボのようなところが分からない方だと、私は勝手に思います。現実の世界があって、そこに抽象的な表現が差し込まれると、作品でも取り上げられている迷子状態になりそうです。あと、母親と息子の確執という、男性であれば誰もが経験するベースを、実にうまくエピソード化しているところは、この作品の真骨頂だと言えるでしょう。ホアキン・フェニックスは中年でありながら、子供のように不安症に苛まれよく劇中で泣き出します。その気持ちがヒタヒタと伝わってくるので、とても可哀想になるのですが、反面、私たちを笑わそうとしている名演だと感ずると顔が緩みます。この作品は15歳以上指定の映画ですから、当然エロいシーンもありましたが、何故か初恋の人と結ばれるシーンに、不思議な感動がありました。あと、母親が亡くなって、実家にたどり着くまでの、難行、苦行のような時間は、茨の道になるのですが、その中に込められた比喩や箴言は、学ぶことが多いです。それにしても、子供から見たら、普通は母親は完璧な存在に見えるものですが、この作品では、その母親の未熟ささえも白日のもとに晒しているのですから、考えさせられること多しです。最後に、水の中にホアキン・フェニックスは沈み、浮き上がってきません。母親が水のような存在であるとしたら、きっと母親の愛に抱かれたのかも知れないと思うと、静かな感動が押し寄せてきました。
やりすぎアスター
アリ・アスター節が全開過ぎた
アリ・アスター監督の才能はスピルバーグ以来のものと感じている。これがホラー以外のジャンルで炸裂したら本物だと思うが、今回のこれはホラーではないので、その才能が如何なるものかという興味がまずあった。
結果から言うとやはり本物。3時間の上映時間は全く飽きる事無く、グイグイとスクリーンに引き込まれて行く。
以下は少々ネタバレあり。
描写は主人公であるボーからの視点のみ。そしてボーは難産のせいか少々発達障害のきらいがあるのがポイントで、腐乱死体の転がるスラムやペニス怪物などは、何かがデフォルメされた描写だろう。これはアンソニー・ホプキンスの「ファーザー」を思い出した。
ボーはおそらく無職で、母親の仕送りで暮らしていると思われるが、全ての出来事は母親の監視下による仕掛けなのだが、森の劇団のエピソードは一見不要にも見えるけど、ボー自身の願望なのだろう。だから元兵士はそれを破壊したと思う。
色々と深読みすると面白いけど、でも今回はちょっとやり過ぎで、母と息子の対立が無駄に難解で長いと言わざるを得ず、バランスを少々欠いた映画になってしまったと思う。
しかし次回作が楽しみで仕方ない。
不快という爽快感
まず、この映画の3時間をあっという間に感じる人と長いと感じる人で分かれるだろう。一種のカルト映画なのは間違いない。なので、ハマる人にはとにかくハマる。私はハマった。観てからずっとボウの事を考えている。
この監督の作品は精神的に不安定な人間が多いが、ボウはその中でも図抜けているし、痛くなるほどそれを描写してくる。内面がすでにボロボロなのに、周囲にはチラチラとボウに迫る危険を見せて来て、不意に爆発を起こして殺意を向けてくる。そしてそれが現実なのか非現実なのかはわからない。
もう一度書く。ハマる人にはとにかくハマる。私はハマった。観てからずっとボウの事を考えている。沢山の人に観てほしい気もするが、大半の人には理解されないだろうから人には勧められない。誰かに「実はあの映画が好きで・・・」とひっそり言われたら嬉しくなって話し込んでしまうだろう。そんな映画。
ブニュエル的プロットとデ・パルマ的悪趣味が炸裂する「地獄めぐりでマザコン・セラピー」映画!
まあ、たしかにこんなの見せられても、
ちょっと途方に暮れるよね(笑)。
扱いに困るというか。
何が何だか意味がわからないとはいわないが(むしろ何がやりたいかはわかりやすい映画だと思う)理屈の通った筋らしい筋はまるでないからなあ……。
でも個人的には、あちこちで大笑いさせてもらったし、何が起きるかわからないので、ずっとわくわくしながら退屈もせず、寝落ちもしないで最後まで楽しむことができた(嘘。ちょっとだけ森のコミューンのシーンは長すぎて一瞬気が遠くなったw)。
ここでは、アリ・アスターが「何をやりたかったか」の話をする前に、
まずはこの映画が「何に比較的似ているか」の話をしたい。
なお、公開三日目なのにもう調布ではパンフが売り切れていて(!)、すべて今から書くことは己が脳内での勝手な決めつけであり、いろいろウソを並べ立てているかもしれないのでそこはお許しください。きっとみんな観ても訳わかんないから、せめてパンフで情報を補完したかったんだろうなあ(笑)。僕も欲しかったよ……。
一見して、僕がこの映画が何に似ていると思ったかというと、実はルイス・ブニュエルにとてもよく似ていると思ったのでした。
ルイス・ブニュエルといえばまさに「不条理映画の王様」みたいな巨匠監督だけど、
「●●をやりたいのに、どうしても●●ができない」
これこそは、ルイス・ブニュエルが得意とした黄金プロットだ。
部屋から出たいのにどうしても出られない『皆殺しの天使』。
峠を越したいのにどうしても越すことができない『昇天峠』。
料理を食べたいのにどうしても食べられない『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』。
『ボーはおそれている』は、明らかにこの路線を引き継いでいる。
“実家に帰省したいのに、どうしても帰省できない”不条理映画。
ルイス・ブニュエルとの類似点は他にもある。
女性に対する若干気持ち悪いフェティシズムの発露と、毒のあるセクシャルなシーンの挿入。ブニュエルといえばなんといっても脚フェチだが、本作ではマザコンを拗らせた男の赤毛への執着が描かれ、騎乗位プレイが繰り返される。
街に一歩出たら危険がいっぱいという感覚に関しても、非常にブニュエルに近しいものがあると思う。ブニュエル映画では『アンダルシアの犬』の頃から、道を歩いているだけでいきなり車に撥ね飛ばされるわ、路上にふつうに死体が転がってるわの剣吞な描写が続いていたが、後年の映画になると、何かと街角でテロリストが銃を撃ったり爆弾を爆発させるシーンが唐突に挿入されるようになる。ボーが住んでいるアパートの不条理なクレーマーと、一歩出た街角の悪夢的なデンジャラスさは、まさにブニュエル譲りの世界観だといえる。
じゃあ本作の不条理劇としてのテイストが、誰の作品にいちばん近いかというと、僕は初期~中期のブライアン・デ・パルマにとてもよく似ていると感じたのだった。
もちろん、デイヴィッド・リンチっぽい部分も出てくるし、前述したブニュエルやら、ホドロフスキーやら、オーソン・ウェルズの『審判』やら、さまざまな既存の「不条理劇」からテイストを受け継いでいるのはたしかだろう。
しかし、この全般的に「人を食ったような」「あまり笑えない悪ノリの勝った」「ひたすら品のない露悪的なネタを連発する」テイストってのは、やはり僕にはデ・パルマのクセの強いホラー・サスペンスにいちばん似ている気がしてならない。
とくに『ボディ・ダブル』とか『レイジング・ケイン』とか。
だいたい、頭のおかしい支配的な毒親と心を壊された子供の内的闘争が全体の大テーマってのは、そのまんま『キャリー』だもんね。明らかにパイパー・ローリーとパティ・ルポーンの演技プランにはある種の共通点があるし、どちらもイニシャルが「P.L.」なのだって、もしかしたら意味があるのかもしれない(多分ないけどw)。
多重オチや夢オチがどんどん肥大して収拾のつかないことになっていく悪趣味なつくりや、唐突に下卑たセックスシーンが入って来る下世話感、突然豹変するように狂気を噴出させる女性の怖さの描写、決め所でかかるメロウで通俗的なダサい曲など、端々にデ・パルマっぽい「バッド・テイスト」が漂っている。
これにアリ・アスターが大好きなホラー映画のエッセンス(『エルム街の悪夢』の風呂シーンとか、チャールズ・ブロンソンの『殺人鬼』に出てくる全裸殺人犯とか、『ミザリー』における献身的な介護とか、『ハロウィン』の背後への殺人鬼映り込みとか、ダリオ・アルジェントの三原色とか、初期ピーター・ジャクソンのテイストとか……)を加えたうえで、さらにアートアニメや劇中劇の要素までぶち込んで、ラストではルキノ・ヴィスコンティの『ルートヴィヒ』に目配せなんかもしつつ、この雑駁なシネフィル的不条理映画は成立している。
では、こういった諸々の「クセもの不条理映画」の成果を徹底的に注ぎ込んでまで、アリ・アスターがやりたかったことというのは一体何なのか?
言い換えれば、この映画はどんなジャンルの映画なのか?
答えは比較的簡単だ。
これは、いわゆる「地獄めぐり」の映画なのだ。
そんなジャンルあるのかって?
ジャンルとしては、たしかにないかもしれない。
でも「地獄めぐり」は、欧米の小説・映画において様々な形で何度も採用されてきた、西欧文化の核心を成す重要な「型」である。それは間違いない。
その源流は、ダンテの『神曲』煉獄篇、および地獄篇だ。
さまざまな「悪」を見て回ることで「魂の浄化」へと至るというこの構図(キリスト教の「贖罪」の思想と深く関連する)は、たとえば『時計じかけのオレンジ』や『キラー・インサイド・ミー』では、前半で悪行の限りを尽くした主人公が、後半で因果応報の拷問を受けることで自らの「悪」と向き合うという形で援用されている。悪夢の連鎖がそのまま「地獄めぐり」として機能している映画としては『ブレインストーム』や『ジェイコブス・ラダー』があるし、もっと古い映画だと『ベン・ハー』などもそうだ。
近年の地獄めぐり映画で出色だったのが、チェコ映画の『異端の鳥』。フィル・ティペットの『マッドゴッド』も、絵に描いたような「地獄めぐり」映画だった。
「地獄めぐり」映画は、ひどいことが起こり続けた挙句に、主人公が追い詰められて死に至るような映画ではない。
本人にとって経験したくないような事象、直視したくないような内容。
そういった「ひどいこと」の連鎖によって、主人公の「業」が「浄化」され、オブセッションから解き放たれるような、「再生」と「復活」の要素が含まれてこその「地獄めぐり」である。
その意味では、『ボーはおそれている』はまさに、「地獄をめぐることで」自己と向き合い、その根幹で自らを縛り上げているマザー・コンプレックスと正対し、そこからの解放・浄化に至るという道筋を持っており、まさに「地獄めぐり」映画と呼ぶにふさわしい。
たしかに、あんなことになって話は唐突に終わってしまうわけだが(笑)、少なくとも彼は悪夢的体験を経て、長年苦しめられてきた毒母による呪縛の正体を解き明かし、実際に反撃を加えるところまで「成長」することには成功しているのだ。
『ボーはおそれている』。
いったい何をおそれているのか?
もちろん、母親だ。
彼の神経症も、対人不安も、挙動不審も、元をたどれば母親との関係性に起因している。
もともと「帰りたくても帰れない」のは母親に極度のプレッシャーを感じていて、内心は「帰りたくない」からだ。
そんなボーも、幼少時の自らの記憶と対峙することで、母親への執着と性的な抑圧の淵源にたどり着き、それを言語化し、母親との関係を相対化することができた。
ラストシーンは、洞窟という「女陰」の象徴たる場所の奥へと至って(いわゆる「子宮回帰願望」というやつで、冒頭の「産み落とされる」シーンと実は呼応している)裁判の形で生前の因果が端的に表現されるわけだが(日本でいうところの閻魔様のお裁きの場)、そこで彼は今までの「偽りのセラピストによる偽セラピー」ではなく、「本当のセラピー」を経て「自分を知る」ことになるのだ。
あまりこの映画を理屈で語っても仕方がないと思うけれど、普通に考えれば、最初に部屋に戻ってきたシーンで本当はもう蜘蛛に刺されていて、あとの展開は「すべて」そこから死に至るまでに見た悪夢だと考えた方が辻褄はあうだろう。
だって、あんな危険すぎる街角とか、あるわけないんだし(笑)。
少なくとも、天井にへばりついてるオッサンから涙がぽたぽた落ちてくるシーンで、すでに「夢」の領域に入っていないとどう考えてもおかしいわけで、結局は「ほとんどのシーンは実際には起きていない脳内妄想」だと考えるべきか。正直、あまり理屈やつながりは重視しないで、のんびり刹那的に愉しんで観ればいい映画だと思う。
あとはとにかく「悪夢の鉄則」である、「起きてほしくないこと」が起き続けるという唯一のルールに従って物語は展開していく。
●●しようと思ったら●●できない。
隣人に脅迫的ないちゃもんを受ける。電話がつながらない。出かけようとしたら鍵をパクられる。薬を飲もうとしたら水が出ない。水を買おうとしたらお金が少したりない。部屋に戻ろうとしたら戻れない。朝になってやっと戻ったら死体が待ち受けている……。
人生、うまくいかない嫌なことばかりだ(笑)。
ボーの身に起き続ける「嫌なこと」の芸術的な連鎖は、まさに「悪夢のロジック」としては完璧である。あと、話が行き詰まって来ると、死ぬような衝撃的なシーンで暗転していったんリセットしたあと、なんとなく適当に「次の別の悪夢が始まる」というのも、いかにも悪夢らしい。
こういった「悪夢」の法則にのっとってとりとめもなく紡がれ続ける物語を、いったいどういう形で閉じるつもりだろうと思って観ていたら、きわめてミステリ的な仕掛け(身●●●殺●とか『トゥルーマン・ショー』的なオチとか)が用意されていたのにはちょっと驚いたが、これとて「夢のなかで観ているときは超クールに思えたミステリ的などんでん返しだけど、目が醒めてから冷静になって考えてみたら、あんまりたいしたことなかった」ネタっぽい感じがあって、個人的には笑えた。
なんにせよ、「地獄めぐり」を経てマザー・コンプレックスをセラピーする物語としては、あらゆる出来事が「自分探し」と「母性の探求」につながっており、意外に「ロジカル」な映画なのでは、とも思う。
これを観て面白いと思わない人がいるのもよーくわかるが、個人的にはこの手のバッド・テイストも不条理展開も基本、大好物なんで、星四つとかつけてみました。
その他、ふと思ったことなど。
●冒頭、赤ちゃんの視界がぼやけているのは、実際にそうらしい(視覚で得た情報を形として認識するのには経験と訓練が必要)と昔、大学の心理学の授業で教わったのを思い出した。
●アホっぽい通俗曲を終盤かけまくっていたのが印象的だが、ところどころでクラシックの楽曲をアレンジして使っていたのは面白かった。
冒頭流れる女声スキャットは、バッハのアリオーソとして知られるチェンバロ協奏曲第5番の第二楽章。続く尺八を用いた劇伴は武満の『ノヴェンバー・ステップス』を思わせる。最後の海に乗り出すシーンでかかる曲の冒頭のハープは、マーラーの交響曲5番のアダージェットと同じ音型でどきりとさせられる。
●ボーの寝ている部屋のガーリーな色調が宣伝写真として用いられ、『バービー』みたいなノリの映画なのかと思って観に行ったら、まるでそんな映画じゃなかった(カラフルなのはあのシーンだけ)。非常に悪意のある引っ掛けである(笑)。
●全編のなかで一番完成度が高いのは、冒頭の「出られない/戻れないアパート」と、中盤の「謎一家」のシーンだろうが、後者はシットコムのパロディなんだろうね。
●正直あのチンコ怪人は爆笑したけど、よくわかりませんでした(笑)。「誰」の男根恐怖なんだろう?
●『バッド・ルーテナント』に続いて、なぜか二作連続で中年男優の全裸を観てしまった。俺のガンはでかいぜ!
反出生主義?
個人的にはすごく好みの映画でドはまりしたけど、たぶん万人向けではない。現実か夢かあいまいな世界が3時間も続く。こんな長い時間、幻想の世界に浸れるなんて最高だ…、と僕は思ったが、これが拷問のような時間に感じる人もいるだろう。
「ミッドサマー」では新しい恐怖の開拓に成功したけど、この映画も従来のホラーとは一線を画す、新しい恐怖を描いている。それは、普通の日常がとてつもなく怖い、という恐怖だ。
主人公のボーは、異常な怖がりで、うがい薬を飲み込んだだけでも、それが原因でがんになるかを心配するほど。実際に恐怖性障害、不安障害、強迫性障害といった神経症は存在する。あとの展開を考えると、ボーは統合失調症ももっている可能性がある。
神経症を患っている人の恐怖感や見えている世界がどのようなものか、当該者でなければどうしても理解できないものだと思うが、この映画はもしかしたらそれを体感させようとしているのかもしれない。
この映画は、さんざんな目にあうボーを笑い、超現実的な展開を理屈抜きに感性で楽しむのが正しい鑑賞法なのだと思うが、展開がひどく思わせぶりなので、どうしてもいろいろと意味を解釈したくなってしまう。
<世界観>
この映画の世界は現実なのか、夢なのか。わざと曖昧にし、意図的に混乱させようとしている。たとえば、寝るシーンや気絶するシーンがたびたび挿入されることで、観客は無意識に合理的に辻褄をあわせようとしてしまう。しかし、おそらく「現実か夢か」を考えることに意味は無い。どちらかはっきりしない、混乱した状況こそが、ボーの感じている不安の一部なのだから。
しかし、この映画の世界がひどく「夢」的であることは確かだ。
(1)夢によく出てくるシチュエーション(家の中に見知らぬ他人が侵入する、全裸で街に出る、敵味方が反転する、追いかけられる、など)がある。これは原初的な不安が表現されたものともいえる。
(2)水、森、ジプシー(的な人々)、演劇、凪の海、洞窟など、深層心理学的(特にユング的)な象徴に満ちている。
(3)主観・客観の逆転、辻褄が合わないことが起きても主人公が疑問に思わない、時系列の混乱と同時性(監視カメラに未来のイメージが映る)がある、という夢の特徴がある。
<ストーリー>
起承転結に分けると、「起」では、肉体的な安全が脅かされる恐怖が描かれる。危険に満ちている不潔で不愉快な外界と、かろうじて守っている自分のテリトリー。そのテリトリーを侵害されむちゃくちゃにされる恐怖。
「承」では、人間関係(社会性)の恐怖が描かれる。自分が本来居てはいけない場所に居て、他人に激しい悪感情をもたれている、といういたたまれなさや、明示されない人間関係の中に放り込まれる寄る辺なさの恐怖。
「転」では、一転変わって、はじめてボーは信頼できそうな人たちのコミュニティの一員となり、恐怖から解放される。演劇の世界の中で精神的癒しを受け、成長を促される。
「結」では、ボーが最も愛し、かつ最も恐怖している存在である、母親との対決が描かれる。
<テーマ>
母親からの歪んだ利己的な愛により、精神的な「去勢」をされてしまった主人公の悪夢のような精神世界、だろうか。
母親は愛に飢え、子供からの愛を要求する。そこには相互の愛の交換は無く、一方的な愛の搾取があるのみ。母親にとって子供は愛の飢えを満たすための道具でしかない。無条件の愛を知らない子供は、母親の意に反してしまうことを極端に恐れ、自分の意志を封印する。自分の意志をあらわすことを恐れ、What do you mean? や Why? を繰り返す。
ボーは、無条件の愛を知らないが故に、他人を信頼することができない。ボーに親切にする人や、セラピストを信頼していない。
この「毒母親」のテーマの裏には、「父性の欠如」「男性性の否定」という現代の普遍的なテーマがあるように思う。母親の家の屋根裏には、「やせほそり監禁された自分の半身(男性としての自分)」と「醜い怪物のような男性器(父親)」が隠されていた。これは、現代において(この映画では母親にとって)、「父性」や「男性性」が忌むべきものとみなされていることを意味しているのではないか。
「承」のボーが滞在していた家で、「兄が戦死している」というのは、過去の時代においては、「父性」や「男性性」の価値が認められていたことの象徴ではないか。
ボーが「兄」の代わりにはなりえないのに、「兄」の代わりをさせられそうになるいこごちの悪さは、男が必要とされない社会で、男であることの申し訳なさを表現しているように思う。
「男性性」が否定されているから、恋愛対象に自分の思いを伝えることができないし、男性である自分自身を肯定的に見ることができない。
そういえば、精子バンクを利用する人の中には、「結婚はしたくないけど子供は欲しい」という女性が相当数いる、という話だ。
また、この映画で「反出生主義」を連想した。反出生主義というのは、人間は生まれてこない方が良い、という考え方のことで、近年この考え方がじわじわ広がっているという。
映画の冒頭、ボーの視点で「苦しみに満ちた世界」に生まれてこなければならない恐怖が描かれる。彼が世界を肯定的に見ることができないのは、そもそも生まれた瞬間からだ。
<ラストの解釈>
終盤では、この映画はどういう決着になるのか、ということを気にしながら観ていた。果たしてハッピーエンドになりうるのか?
母親に対する愛情と憎しみの葛藤を、「母親殺し」をすることで超克し、平穏な精神状態を象徴するような凪の海に船出し、産道を象徴するような洞窟をくぐり、ときたところで、「これはハッピーエンドに向かっているのでは?」と感じた。
しかし舟のエンジンの不調が不穏な兆候を示す。エンジンは心理学的にはリビドーか? なぜうまくいかなかったのか? 素人考えだが、本来のエディプスコンプレックスは、母親を手に入れるために父親に憎しみを抱く、というものだが、それとは異なる過程を経たためか?
最後、何もかもうまくいきそうになりながら、急にアンハッピーエンドにして突き落とすところは、「未来世紀ブラジル」みたいだ。
もし、洞窟が産道、弾劾裁判みたいのが行われた球状の空間が子宮なのだとしたら、そこで死んだボーは、「生まれる前に還った」ということになる。
これは、「生まれたくなかった」というボーの願いの物語ということになり、冒頭につながる。
<劇中劇の意味>
「転」の森の中での劇中劇は、かなりの長尺だった。この映画の評価を低く考える人は、たぶんこのパートの長さを挙げるだろうな、と思うほどに長かった。
でもそれだけに、ここに最も重要なメッセージがこめられているようにも思う。
劇中劇は、「夢の中の夢」とも考えられ、深層心理の奥の方、ユングのいう「集合無意識」を表しているのではないか。
集合無意識は個人的体験に由来するものではないので、ボーの個人的体験に影響されず、ここには彼が生まれてから経験した恐怖のイメージが入り込めない。
とても神話的な物語である。自分を支配する鎖を自らの手で断ち切ること(2回も!)、何十年にも渡る愛する家族の捜索、スープと演劇の二者択一で演劇を選ぶことで家族と再会できたこと。劇中劇の中にさらに劇があり、無限の入れ子構造になっているのも幻惑的で良い。
印象的だったのは、この劇中劇では、ボーは困難に苛まれても、意思と工夫によって成長していき、自分自身の人生を歩めていたこと。現実のボーが優柔不断で受け身にしか行動できないことと対照的である。
この劇中劇で、ボーは仮想的な一生を体験し、なんらかの精神的成長を遂げたはずである。母親のために買ったマリア像は、おそらく母親への執着を象徴しているのだと思うが、これを手放すことさえしている。
映画全体の中で、劇中劇のパートは物語としては省いても何ら問題ない。では何のためにこれがあるのか? それは、「観客とこの映画の関係」を示唆するためではないか。
とりとめもなく続く悪夢をずっと観させられている感じ
アリは恐れている、ファンに飽きられてしまうのを!
2月なのに異常に気温が高く、何処もが暖冬。
半袖でウロツク外国人旅行者も出るくらい街中は暖かいよ。
そんな中、毎作異常熱を発した作品をだす アリ・アスター監督の最新作「ボーはおそれている」を観に行った。
本編179分の時間無駄使い作品、ココに見参です!
2018年ヘレディタリー/継承
2019年ミッドサマー
2023年ボーはおそれている
どれも観て来たけども、今回も想定してた通りヤッちまッてたね。
今作は家族の愛がテーマとか言ってたけども その通りの作品でした。
---
あらすじ(※一応あるようだ)
精神科クリニックに通う中年男(ボゥー)の話。彼はとても心配性でその日常は大変な様だ。住まいは荒んだ街中にあるオートロック式マンション。何故か浮浪者(変人・狂人)に追いかけられ隠れおびえて暮らしてる。ある日、
実家に帰る電話を母にしていたが 2度目に連絡入れた時から向こうの様子が変。どうやら、直前まで電話で話していた母が突然亡くなった模様。彼は慌て急いで帰ろうとしたが部屋の鍵を盗まれ、挙句に浮浪者たちに部屋は荒らされ・・・とにかく実家に戻り母の葬儀に立ち会おうと、それだけを目指す目的の流れです。この道中が奇想天外、摩訶不思議で~そして支離滅裂。分けわからんこの上ない事に~です。
---
まぁ、こうなるだろうとはほぼ思ってました。よってガッカリ感は感じません。
だろうな・・・的な思いが強いです。
そろそろ 皆さん気が付いてるだろうし、ファンも今作で彼の醸し出す味付けに飽きて来るでしょうね。
主演のボゥー:ホアキン・フェニックス氏は 我慢し良く演じたと思います。
流石です、大御所俳優なのによく局部を晒したなと思います。
今作で一番の場面は、ボゥの自分部屋のバスル-ム天井に男が必死に張り付いてて、毒蜘蛛が顔に付いたことで落下し、風呂入ってたボゥーと 抱き合いながら格闘するところでしょうか。
慌ててボゥは全裸で外の道路へ飛び出し、ポリスに撃たれそうになるわ、全裸の変人爺に狙われるわ、挙句にトラックに引かれるわ・・・。
ここのシーンは腹抱えて声出して笑いましたわ。(*´ω`*)
そもそも 真面目で心配性な彼が 色々な事に巻き込まれながらも とにかく家へ戻りたい。その一心で有った思いは良く理解できました。
そこは凄く良いんですが、とにかく周りの奴等、出てくる場所、繋がりがとっても変で、精神科に通う彼の頭の中が悪夢の状態なんだろうと察しは付きます。しかしそれでも 現実の繋がり現象がオカシク・・・終盤迎え駄作判定にせざるを得ない状況に成ってしまってます。そこが残念極まりないかな。
大体、2時間エンドで1回目、2時間半エンドで2回目、そして3時間エンドで3回目のエンディング風な構成展開を持ってきてます。しかし 終わりそうに見せておいてまだ続きを遣るという しつこさ。
監督なりに考えたのでしょうけども。最終展開流れと最後はダメっすね。
地獄のエンマ様の裁きってやつでしょうか?? アレは。
この作品みて素直に思った事は
”君たちはどう生きるか” の実写版にはアスター監督が相応しいと
ちょっと感じましたねww
時間がアリ余ってる方は
どうぞ劇場へ!
3時間は長くない
マスコミの映画評ではそれほどでもなかったけど、ホラーを見たかったので、あまり期待せずに見たら予想外にパンクな感じで面白かった。現実なのか夢なのかよくわからないような光景が多いが、それが面白い。それぞれの細部がよくできているので、ストーリーを忘れてそれぞれの場面がすごく面白かった。
映像だけではなく、音楽や効果音もとてもよかった。目をそむけるような衝撃的な場面があるわけでもないが、怖がらせる演出の中にユーモアや余裕がある。遊園地のジェットコースターみたいな感じで、安心して怖がれる感じで、楽しい。
だけど、成功した実業家の息子がなぜスラム街に住んでいるのか?勘当されたわけではなく、母親と普通に電話しているので、そこが気になった。優柔不断の性格なので、母親から快く思われていないのはわかるが、普通のところに住めばいいのに、よりによって無法地帯に住んでいる理由がよくわからなかった。でも、理由は多分、単純で、「その方が面白いから」。実際、その無法地帯は秩序が崩壊してしまった近未来の都市みたいで、すごく面白かった。森の中で暮らす劇団も世界核戦争で生き残った人たちのような感じで、近未来SFみたいで面白かった。
サスペンス+ホラー+SF+ファンタジー+お笑いと言ってしまえば身も蓋もないが、細部に凝っているので、何度も見たくなる映画だと思う。チープな感じを意図的に出しているところもあるが、それは演出なので、面白い。私としては屋根裏の父親のシーンが最高だった。なぜ、屋根裏にいるのか?理由は簡単で、「その方が面白いから」。よくこんなシーン考えるなあと感心した。
嫌な気分にさせてくれてありがとう
私はいったい何を観させられてるのか・・・・
全364件中、221~240件目を表示