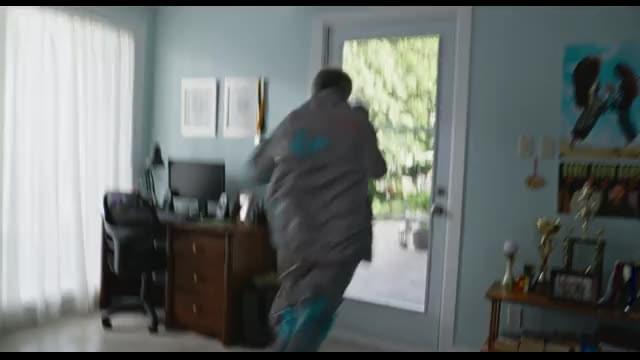ボーはおそれているのレビュー・感想・評価
全364件中、1~20件目を表示
誰も殺していないボーの罪悪感は殺人より大きく愛より小さい
ボーは罪悪感により自分を一番許せないにも関わらずそれを認めることができず、また罪悪感が生まれた背景を深く考えたり客観視することができずまたその勇気が持てないため精神を病んでいると解釈しました。
思春期に誰しも一度は思いませんか?母(あるいは母なるもの)が憎くて今ここで首絞めたらどうなるかな、など。ボーは母の首を絞める妄想をしたことがあるのかもしれません、女の子とキスする妄想も。一人暮らしをする妄想や、他の家族の息子になることや、女の子と悪いことしたり、別の家庭をもつことも想像したこと、少しの体験もあるのかも。
そして母が大好きすぎるあまり、母からの愛をきちんと返そうとするあまり、それら全てはボーにとっては大きな罪悪感となって肥大してしまいます。さらに罪悪感の理由に気付いていないながらも、自分が罰を受けることだけは受け入れているため、シーンの終わりは全て、理不尽で謎な出来事として時に残虐に降りかかります。
(例えば、他人の家で目覚めた、まるで違う家の子になったみたい!けど、お母さんが悲しむだろうな、ごめんなさい。そんなことを楽しんでしまって。この気持ちは、考えは罪だった、僕が罰を受けるに違いない→けど誰が罰を下す?お母さんはそんなことするわけない→捏造された罪としての青ペンキ→殺人鬼に罰を受けるみたいな流れ)
歪んだ親子愛、という評も多いですが、ボーは母のことが大好きで、逆に母も、表現は束縛過多で不器用ながらもボーを愛しており、ボーの方は定型発達ではなかったため互いにバッドトリップになってしまい、その不幸が生んだ愛のホラーになっています。愛が生んだ美しく華麗な物語は多いですが、愛が生んだ妄想ホラーを描き切った作品はそれに比べると少なく、作り切る挑戦もまた素晴らしいと思います。
どんな考えや妄想も本来はギルティではなく、母の愛を裏切ろうとも自分を愛しても良いと、ボーにどこかで力強く言ってあげたくなるのですが、言う隙がないし作中の誰も言わないので可哀想なボーにせめて寄り添う長い時間になります。愛が作った複雑なホラー世界を長時間観客に浴びせる暴力でさえ、罪にはならないというメッセージで、私は残念ながら途中休み休み配信でみましたが上記をふまえるとぜひ映画館鑑賞で暴力されたかった作品でした。
毒親に支配された子の心象風景……みんなどん底になあれ
アリ・アスターとホアキンのタッグで3時間、と聞いただけで、面白さとしんどさのどちらが上回るか早くも不安になる。今回、私の苦手なグロはかなり控えめだったため割と耐えられた。ただし、ラストの救いのなさは容赦がない。
本作は端的に言えば、毒親持ちの息子・ボーの心象スケッチ、である。どこまでが作中で現実に起こったことかはわからないが、彼の妄想が少なからず紛れ込んでいることは間違いない。荒唐無稽かつシュールな展開でありながら、毒親に支配された心のありように関しての解像度は高い。
序盤、セラピストにかかっているボーが住む街のあまりの治安の悪さに笑ってしまう。実際にあんなとこ住んでたら健常者でも精神を病むでしょ。これはあくまで神経症のボーから見た外の世界ということなのだろうか。薬を服用する描写が、現実との境界線を余計に曖昧にする。終盤で、このエリアは母親が作った更生地区であることが示唆されるが、それでもあの極端な状況は解釈の余地がありそうだ。
置き引きや生活騒音のトラブルなど、出来事の一部のパーツは単体で見れば現実感のあるもので、その不安を生々しく想像できるだけに、余計にうわあ嫌だなあという気分になる。
なんだかんだで車に轢かれたボーが担ぎ込まれたのは、彼を轢いた外科医の家。結論から言うとこの外科医家族は束縛的なボーの母親と通じているという設定で、バイタルの測定器と称してボーにGPSを装着し、病院や警察には連絡しない。夫婦は表面的には明るく親切で理想的な家族だが、彼らの息子が戦死した悲しみにとらわれており、向精神薬を常用し、娘には構わない。隣人は戦争のトラウマで精神に異常をきたしており、監視を察知して逃げ出したボーを追ってくる。
逃げ込んだ森の中で劇団と出会い、劇中劇のシークエンス。「オオカミの家」を手がけたレオン&コシーニャ監督が描き出す風景は、素朴なタッチの中に不気味さを内包していて、アリ・アスターの世界観によく合っている。その風景の中で、ボーはかりそめの堅実な人生を体験するが、自分には息子はいないはず、と気づいて現実に戻る(きつい)。追ってきた精神異常の帰還兵が劇団員たちを射殺。
何とかたどりついた実家でエレインと再会、セックスするも彼女は腹上死(さすがに妄想かな)、壁の写真から自分の出会ってきた人間たちが母の会社の社員であることがわかり(これも陰謀論的な妄想かも)、生きて現れた母親にボーは掴みかかって首を締める。倒れた母の元を離れボートで漕ぎ出してみたら……はい、トゥルーマン・ショーでした。
いやはや、どこからどこまでが現実かはたまたボーの妄想なのかわからないが、少なくとも言えるのは、ボーの目に母親は、中年になってもなお彼の人生全てを支配し得る存在に見えているということだ。毒親によるトラウマの根深さよ。
回想シーンで、バスタブに入ったボーの視界に少年が映る。彼は屋根裏部屋に閉じ込められる。ボーは一人息子のはずである。閉じ込められたのは、いわばボーの分身、彼の魂の伸びやかな部分であるようにも見えた。
終盤、昔腹上死したはずの父親と称して屋根裏にハリボテのような男根が登場するが、あれは母親のミサンドリー(男性嫌悪)の生んだ亡霊のようなものではないだろうか。そもそも、一族の男性が代々腹上死というのも、母がボーに性行為への恐怖を植え付けて男性としての成長を妨げ、いつまでも子供として支配するための嘘かもしれない。父親とは実際は憎しみあって別れたのでは? でなければ、パパは男根ですはないだろう。
ラストシーンの個人的な解釈だが、あれは「毒親の精神的支配を受けた子供は、物理的な束縛を逃れた後も毒親の価値観の呪縛を受け続ける」ということを表しているのではないだろうか。スタジアムはボーの心の中であり、幼い頃から彼を支配してきた母親が原告として内在している。スタジアムの観客は、ボーの受難の傍観者でしかない世間か、あるいは母親の会社の社員たちかもしれない。脳内にこのような状況が形成されると、もはや物理的に母親の元を離れても無駄である。
ボー自身のおこないについて、母親の考えに沿って批判する検察官と、ボーの自我の側に立って抗弁する弁護士が争い続ける。どちらもボーの心が作り出した声だが、最後に弁護士は強制排除され、自分の心の中にさえ味方のいなくなったボーの自我は崩壊する(ボートの転覆)。
支配的な親に抑圧された子供の心の最悪な結末。
さまざまな解釈を呼ぶ要素は多いが、どう考察しても結果としてどんよりした気分になる。とりあえず、アスター監督の「みんな、どん底気分になればいいな」という狙いは実現できているのではないだろうか。
もしかしたら、毒親からの自立に成功した人は、アスター監督に共感を示されたような気がして、過去の苦しみが昇華されたようなある種の癒しを得られるかもしれない。現在進行形で毒親に支配されている人は……ラストがラストだけに、見ない方がいいかも。
不安症にとっては居心地のいいファンタジー。
個人的には冒頭のパートがコメディとしてべらぼうに面白く、そこから先は3、40分ごとにスタイルを変えていくこともあって、振り落とされないように、ほどよく刺激的かつときおり退屈を感じながら最後までたどり着いた。明らかに、観客を戸惑わせ、右に左に振り回すのが目的の映画だと思うので、まんまといい観客をやりました!とアリ・アスター監督に報告したい気分。
ただ、大好きな映画かと自問するとそこまででもないのだが、アリ・アスター作品では一番しっくりと身近に感じられる作品でもあった。というのも、不安症のあり方に非常に親近感が湧く描写が続き、とにかく最悪のことを想像し、実際に起きることを想定して覚悟することが人生を無事に生き抜く方法だと思っている者として、この映画の心配性は他人事ではなく、でも1/1000くらいの確率でしか起きないはずの最悪の事態が、ここではほぼ100%の確率で発声するのだから、むしろカタルシスを感じて気持ちいい。
この映画は「イヤな想像はすべて映画の中に置いていけ!」というアリ・アスターなりの親切なのかもしれない。たぶん違うと思うけど、そういう効能は確かにある。
尽きることのない悪夢的イマジネーションの連鎖に心酔
生きることは悩ましくおそろしい。どうやって生まれたのか、いかに毎日を生きるか、家族の問題にどう向き合うか。そんなことを考えだすともう頭がおかしくなりそうだ。過去のアスター作品からやや趣向を変え(でもやっぱり”家族”が関係するのだが)、本作はホアキン扮する中年男が抱える”おそれ”をじっくり我々に突きつける。ある意味、カフカ的でもあるし、フロイト的、ギリシア悲劇的とも言いうるだろう。序盤のアパート生活のカオスな日常描写には勢いがあり、声を上げて笑ってしまうシュールさに溢れ、目が離せなくなる。そこからいざ帰郷というモチーフが起動するも、案の定、不条理の鎖が足に絡まりボーはなかなか帰れない。この一連の物語をどう解釈すべきか。私は途中から意味に囚われすぎるのをやめた。水辺の小舟に揺られ、アスター流の”おそれ”巡礼を体験するかのように、悪夢的ながら美しさに満ちたイマジネーションの連鎖を心から楽しんだ。
ずっと浸っていたい、妙に笑える悪夢のような旅
アリ・アスター監督作品については、長編第1作「ヘレディタリー 継承」の独創的な世界観とホラー描写に震撼し驚喜したが、カルト教団の閉鎖的コミュニティーを訪れた若者たちを描く2作目「ミッドサマー」はストーリーの独創性という点でやや期待外れだった。そんな経緯もありこの3作目は期待と懐疑が相半ばする気持ちで臨んだが、結論から言えば「ヘレディタリー」を超える一番のお気に入りになった。
不安症の主人公ボー(Beauの発音は「ボウ」と表記するのが正確で、字幕もそうなっているのになぜタイトルと不一致なのだろう?)に次から次へと災難が降りかかり、母親の葬儀に出るための旅もトラブル続きでなかなか目的地にたどりつけないのだが、展開が予想外すぎて笑えてしまう(特にバスタブと屋根裏の両シーンで爆笑した)。「ミッドサマー」にもユーモア要素はあったが、本作は格段にいい。ホアキン・フェニックスによる不安と困惑と恐怖と苦痛の演技が絶品で、アスター監督の演出との相乗効果もあり、地獄めぐりでありながらドタバタ喜劇のようにずっと楽しめる、飽きることのない2時間59分。監督の次回作「Eddington」にもホアキンの出演が決まっているようで、今から楽しみでならない。
難解だな。
ファンキンフェニックスの怯える姿は、まさに病的 不思議な感覚 エエ加減な世の中を映しているのか?
ペンキを飲まないこと。ゴムが破れるほど凄いのか?
配信なんで細切れで観たよ。
生まれてきたんだ、もう怖いものなんてねぇよ
劇中9割が主人公であるボーの妄想と言っていい。映画の序盤でわかる「ボーが恐れているもの」は母親であるが、ストーリーが進むにつれ、それは恐怖の一部に過ぎないことが明らかになっていく。
ほとんどすべてが妄想であり、疑惑であり、恐れであるこの作品は、極端に振り切れた心配性のボーが見ている世界がいかに危険で生き難い世界であるかを描く。
ある人にはホラー、またある人にはコメディ。それが「ボーは恐れている」だ。
ほとんどのシーンがボーの妄想なので、わけがわからないと感じてしまうのも無理はないのかもしれない。
そんな時ヒントになるのは観る人自身の妄想である。例えばドライブに出かけようと路上に出た途端にトラックが突っ込んで来たら?と想像したことは無いだろうか。みじん切りの最中にうっかり指を切断してしまうかも、とふと頭をよぎったことは無いだろうか?
どんな日常の中にも、特別なひとときの中にも、不幸はすぐそこで大口を開けて待っている。
もちろん、ほとんどの場合そんなものは杞憂に過ぎず、起こる確率の低い不幸に怯えて予定をキャンセルする人はかなりの少数派だ。だが、ボーはほとんど起こらない恐ろしいことに怯え(しかも実際には単なる自分の妄想)、恐怖を回避しようともがき続けているのだ。
浴室の天井にへばりついている見知らぬ男なんて、その最たる例。確かに可能性はゼロじゃないよ?何らかの事情で、たまたま自分の家の浴室に逃げ込んで、必死で天井にへばりついていた男と出くわす可能性はあるかもしれないよ?でも限りな〜くゼロに近いでしょ、そんなこと!
だから観てるこっちは「どうしてそうなった?!」って思うし、あまりの荒唐無稽さに笑っちゃうんだよね。
こうなると、ボーの不安が具現化したカオスな状況に「次はどんな不安で来るか?」というワクワクが生まれてくる。わけがわからなければ、わけがわからないほど最高だ。意味不明なほど滑稽さが増し、じっくり考えると「なるほど、この状況はこういう不安が具現化した妄想なのか」という理解にもつながる。
森の中で演じられる舞台はある男の一生の物語だが、その中で語られる不安とは「自分の子どもたちが実は自分の子どもじゃない」可能性だし、母親への恐怖は第三者に自分の人生を決められてしまう不安であると同時に、庇護下から脱して自力で生きていく途中で「自分は大したことのない、至極低能力な人間」という事実に直面したらという恐れでもある。
つまりボーの恐れることとは生きていくことそのものであり、究極には「生まれること」そのものが最大の不安なのだ。
醜かったらどうしよう?愚かだったらどうしよう?鈍かったら、弱かったら、貧しかったら、誰からも愛されなかったら…。
最終局面、己の一挙手一投足をあげつらっては非難される孤独。生まれることへの恐れが最高潮に達した時、謎の施設から排出されたボーはこの時本当にこの世界に生まれたのだ。つまり、今までの不安妄想に彩られたボーの世界は、生まれる前に抱え込んでいた「生きていくということ」への恐れであり、泣きながら生まれてくる赤ん坊というのは不安という名の悪夢から目覚めたんじゃないか、というのがこの映画で描かれる世界観と言える。
悪いことばかり妄想し、泣きながらこの世に産み落とされた存在。それはボーであると同時に、私たちも同じ。
だが、生まれてしまえば何のことはない、生まれる前の、可能性の低い不幸に漠然と怯えていた頃に比べたら、生まれるという大仕事を果たした我々は、不幸の可能性に対処しながら生きていける。
実際生きてみたら、そこまで悪いことばかり起きなかったでしょ?そんなわけわからん状況にはそうならないって!
そんなポジティブなメッセージを「ボーは恐れている」から受け取ったのだが、あまりに能天気すぎるだろうか。
そんなに悪くなかった
初公開時にXで結構叩かれていたこの作品・・・
しかも3時間の長尺。
挑むつもりでIMAX版を鑑賞いたしました。
うん、結構面白かったですよ。
ユダヤ人であるアリ・アスター監督の自伝的要素が強いのでユダヤ教による戒律やキリストを理解していないと分かりづらい箇所があり、そういうのに無縁な私達には不評だった原因かもしれません。そもそも欧米でも興行的に失敗しているので、やっぱり宗教を題材にした映画は難しい事ですかね。
ボーが住んでいる街が「ウォーキング・デッド」にも出てきそうな終末感漂う一角。しかし、これは彼の脅迫的妄想が絡んでるので、どこまでが現実か話を分かりづらくしているんですね。鍵を盗られたところで観客のイライラ度はマックス(←はぁ、いつまでこんな事続くの・・・)これて夢で、これから出かけようとしているのに財布を忘れたという夢あるあるですね。
事故でボーを介抱したキリスト教の外科医師家族も人が良さそうだけれども、どこかしら変・・・。
「ヘレディタリー」の家のように喪失を抱えています。(長男が戦死)娘はグラハム家の長男ピーターのような役回りで兄の幻影に悩まされます。大麻を吸って気を紛らしたりします。ボーを介抱するのに娘の部屋を使い(彼女はソファーで寝る)兄の部屋は大事に手つかずのまま・・・
この映画はB・ワイルダー「サンセット大通り」のパロディなのかな?船上でのプールのショットが“あっ”と思ってしまいました。(そこで記念写真て・・・この映画で唯一可笑しい場面)
D・リンチ「マルホランド・ドライブ」が女優側(スワンソン)の視点なら、
この映画が脚本家(ホールデン)の視点で描かれているのか推測してしまいます。
母親の支配から逃れられないボー。
それにしても船上シーンは晩年のフェリーニ映画のように美しいです。
お風呂のシーンが2度も出てくるのが気になる。どちらも水溢れてるし・・・欧米の人は、もっぱらシャワーで湯船に浸からないと聞いたけどボーは入浴するんですね、その後思わぬトラブルが起こるんですけど。
まぁ、この映画はポリスのアルバム「シンクロニシティ」に収められているアンディ・サマーズ作曲「マザー」を聴いた時の衝撃ですね。うーむ、なんだかよく分からないんですが曲の圧だけ覚えてます。
母の邸宅に飾ってあった祖母の肖像画は作家
エドガー・アラン・ポーにそっくり!?
それにしても、この監督は屋根裏部屋が好きですね。
わけがわからず夢を見てる気分に。
IMAXリバイバル上映で初鑑賞。
3時間の長さで終始、わけがわからん状態だった。
感じたのは、ボーの自分で決断ができないところ、狼狽えるばかりの彼をみてイライラしてしまったというところ。
急で奇想天外な場面がいくつも続いているのは、精神疾患?知的障害?的な彼の見ている世界を追体験したような感じなのか。そんな印象を受けた。
母親は母親でボーに常に強く当たっている。毒親的に子供を支配していることを風刺しているようにも見えた。
ただ、ラストの裁判で行ったボーの過去の行動は「あちゃー…」と頭を抱えてしまった。
意味深なシーンも沢山あり、アリアスター監督のメッセージを完全に受け取れていないな…と思わされたのは確か。
意味が分からなくていいのかも
タイトルなし(ネタバレ)
厳しい母親の影響でパニック障害?になってしまったボー目線で描かれる悪夢のような映画
行き当たりばったりで悲惨な目に遭う流れはまるで炎628に似たような流れだけれど、途中たちよった劇団の演劇に自分の過去が入り込みその中でまた演劇が始まる入れ子のような演出は不思議だなと感じた。
「ナイフ投げ」「厳しい母親の影響」これはホドロフスキー監督のサンタサングレの影響じゃないのかなと思う。
サンタ~は最後、母親の幻影の影響で殺人に手を染めてしまった主人公が警察に出頭するところで終わる。その後を非情に描いたのが本作の裁判~ボートが爆破し溺死する、衝撃的なラストなのだろうか。
親子関係って難しいよなあとなりました。 赤ちゃんと親は必然的に主従の関係になってしまうものだろうがそこからどのように関係性が変遷していくのか?その中で互いの要求や期待に答えられないのは悪なのか?
中盤の
強迫神経症の映画・・・かと思いきや
この作品に流れる時間を共有する気になれない。映画に入れない。首をかしげる・・・。この手法に共鳴も共感もない・・このまま見続けるのは不可能ではないかと言う息苦しさも途中からの映像の変調でまるでオズの魔法使いの世界へ・・思い込みの世界と言われるオズの世界は何かの暗示か・・。そしてその答えは終盤に用意されていた。重層的に夢と現が折り重なるが薄い雲母のような意識の幕を丁寧にはがしていくと・・・この監督のただならぬインテリジェンスが顔をのぞかせるのである。全てが監督の用意した装置の中で我々は映画とう舞台を見せられる。この作品を見ると言うより、この監督の作品をある程度の解釈に沿って一元的に見ていく必要がありそうだ。それでも十分楽しめる期待感もある。
アリアスターの想像力
ホラーコメディにホアキンフェニックスの演技で3時間の長尺も全く気にならない。どうしようもない親子の話しを現実と妄想を入り混じらせ、家に帰りたいのに帰れない奇妙な旅の話しにしてしまうアリアスターの想像力を思い知った
気狂い映画
突拍子もない、奇妙な行動や場面はヌーヴェル・ヴァーグの手法だが、全体のちゃんとしたストーリー構成の一シーンだけ異常なので、あれは成り立っている。
この映画の場合、全編を通して奇妙な場面や行動ばかりで、理性の範疇に無いため疲れてしまう。
精神異常者の世界観ってこうでしょ?という作り手の傲慢さが感じられる。映画として、何が面白いのか分からない。何か意味ありげに、観る側が考察したり深読みするのをほくそ笑んでバカにしている作り手のいやらしさが透けて見える。本当は意味なんてないのに。
こういう感じの夢を見ることがある。もどかしく思い通りにならない。おそらく誰もが経験するような夢を映像化して見せることに何の意味があるのか。
これをお金を払って観た気持ちはどんなだろうな、と思う。眠かったし少し寝落ちしたが、時間のムダだった。
これ、真面目に良いものだと思って作ったなら作り手は気狂いだし、ありがたがって観る方も気狂いに違いない。主張もセンスも無く、駄作で悪趣味。
こんなふうに見えているのか…
新時代のホラーの名手が放つ難解作
【イントロダクション】
『ヘレディタリー/継承』(2018)、『ミッドサマー』(2019)のアリ・アスター監督・脚本・製作によるコメディ・スリラー。主演に『JOKER/ジョーカー』(2019)のホアキン・フェニックス。極度の不安症を抱える中年男が、事故死した母の葬儀に向かう過程を時に滑稽に、時に幻惑的に描く。
【ストーリー】
実業家の母を持つ中年男、ボー・ワッサーマン。ヒステリックで抑圧的な母の元を離れ、極度の不安症を抱えながらも、カウンセリングを受けつつ極端に治安の悪い地域で一人暮らしを営んでいる。
ある日、父の命日に母の自宅へ帰省しようとするも、忘れ物を取りに行った際に、玄関ドアに差しっぱなしにしていた鍵と荷物を盗まれてしまう。飛行機に乗り遅れ、母に電話を掛けるも、ボーの話を信じてはもらえずに失望される。更に、カウンセラーから「必ず水と一緒に飲むように」と渡された処方箋を水なしで飲んでしまい、不安感に駆られた彼は向かいにある商店に水を求めて走る。しかし、ボーが目を離した隙に自室をホームレスに占拠され、1人屋外で一夜を明かす事になってしまう。
ホームレスが立ち去り、再び母に電話を掛けると、見知らぬ男性が出る。話によると、男はUPSの配達員で、母の自宅を訪ねた際に、シャンデリアの下敷きとなって亡くなっている母を発見したという。狼狽えたボーは、浴室に残っていた侵入者と鉢合わせ、慌てて外に駆け出す。しかし、運悪く目の前には巷を騒がせる連続殺人鬼。警官に助けを求めるも、入浴中に飛び出した事で全裸状態のボーは、警官に銃を向けられてしまう。逃げようとしたその時、彼は車に跳ねられて意識を失ってしまう。
目を覚ますと、彼は自分を跳ねたグレースとロジャー夫妻の自宅にて、彼らから手当てを受けていた。娘のトニと戦死した息子の親友ジーヴスも同居しており、傷が癒えるまで住まわせてもらう事になる。ボーは母の弁護士に電話すると、遺言によりボーの立ち会いなしには遺体の埋葬をする事が出来ず、一刻も早く帰るよう伝えられる。焦りながらも、予定より出発が遅れたある日、トニがペンキを飲んで自殺を図り、グレースは側にいたボーを犯人として責めたてる。彼女はジーヴスにボーを殺害するよう指示し、ボーは森へと逃走する。
森の中を彷徨うボーの前に、妊婦が現れる。彼女は旅回りの劇団の一員で、ボーは舞台へと案内され芝居を観劇する。しかし、芝居の内容が自分の人生と酷似していると感じたボーは、いつの間にか芝居の役者に自らを重ね、幻想の世界へと足を踏み入れる。現実に意識を取り戻したボーの前に、謎の男が現れ、ボーの父親がまだ生きている事を告げる。しかし、追ってきたジーヴスの襲撃により劇は中断され、ボーは再び森の中を逃げ回る。
森を抜け、ヒッチハイクで母の自宅へと帰宅したボーは、葬儀が既に終了している光景を目にする。夜になると、1人の女性が葬儀の時間を間違えて訪れた。その女性は、ボーが10代の頃に恋に落ち、再会を約束していたエレインだった。彼女は母の会社の従業員だったという。再会を喜び合い、母の寝室で2人は交わる。しかし、オーガズムに達した瞬間、エレインは亡くなってしまう。次の瞬間、亡くなったはずの母親が現れ、エレインの遺体を召使いに処理させる。
母はボーをずっと監視していた事を明かし、カウンセラーもグルだったと判明する。カウンセリングの内容を録音したテープを再生し、ボーの自分に対する愛情の希薄さに激怒した母は、彼を責め立てる。しかし、ボーは棺に入っていた遺体の手の痣から、亡くなったのが母ではなく、メイドの女性だと知っており、母の生存を確信していた。ボーは、父の生存が真実かと母に問いつめ、母に屋根裏に案内される。そこには、鎖で繋がれ痩せ細ったボーの双子と、父が居た。父の正体は、巨大な男性器の姿をした怪物であり、母はその真実を隠してきたのだ。直後、ボーを追ってきたジーヴスが窓を突き破って押し入り、父に銃を乱射する。ジーヴスは怪物の鋭利な腕で頭を貫かれ死亡する。
驚愕の真実を知り、ボーは母に謝罪し、赦しを請う。しかし、自らを恨んでいると語る母にボーは激昂し、母を絞め殺そうとする。我に帰り、手を離すも、母は倒れ込んで亡くなってしまう。
気が動転し、湖のモーターボートで逃げ出したボーは、暗い洞窟の果てで闘技場の様な円形の空間に辿り着く。大勢の観衆に取り囲まれ、ボーの裁判が始まった。母と弁護士がボーのこれまでの母への仕打ちを責め立てる。ボーの側にも弁護士がおり、彼と共に弁明するが、母の部下に殺害されてしまう。ボートのモーターが故障し、火を吹き始めた。逃げ出そうにもボートに足が嵌ってしまい、抜け出せない。全てを諦めたボーは、ボートの転覆に巻き込まれ水中に落下。やがて、ボートはその場に浮かんで静止した。
【考察】
本作は、所謂“毒親問題”と、人生における様々な“不条理”を描いているのではないかと思う。アリ・アスター監督は、これまでも「悪魔崇拝」や「カルト宗教」といった、“現実に根差した恐怖”を描いており、それは、監督自身の家族や周囲で起こったリアルな出来事から着想を得ているそう。
冒頭、ボーが母の産道を通って誕生した瞬間から、彼は「子供は親を選べない」という最初の不条理な世界に投げ出されたのだ。母は「落としていない」と否定する助産師の話を聞かず、ボーを落として頭を打ち付けたとヒステリックに怒鳴り散らし、これだけで彼女が厄介な人物である事が見て取れる。
タイトルバックが明け、成長したボーはカウンセラーと母親について話し合っている。カウンセリングの様子から、やはりボーは母とは上手く行っていない様子だ。
そして、一度外に出れば、息子を無闇に叱り付ける母親、他人の自殺すら笑って動画撮影する大衆、都合の良いことばかり謳う広告と、現代社会の病理がそこかしこに展開されている。
ボーの住むダウンタウンでは、退廃的で暴力や殺人、ドラッグによる廃人化が当たり前の光景が広がっている。
ボロアパートで眠ろうにも、毒蜘蛛が居るから注意しろという張り紙や、(恐らくドラッグによる副作用で)幻聴を聴いて怒鳴り込んでくる隣人、留守中に大挙して押し寄せるホームレスと、あらゆる「こんなの嫌だな」という展開の連続だ。
母の死を悼もうにも、浴室には侵入者と毒蜘蛛。慌てて全裸で表に駆け出すと、同じく全裸で「Fuck!Fuck!」と言いながら通りで人を刺す殺人鬼。余談だが、この一連シーンには、思わず声を上げて笑ってしまった。最悪な出来事も行き過ぎれば笑うしかなくなってしまうかのようで、本作一のお気に入りシーン。
堪らず逃げ出そうとした瞬間、ボーはロジャー夫妻の車に跳ねられて大怪我を負う。手厚く手当てを施し、温かく迎え入れているが、要は自分達の罪を隠蔽しようとしているも同じである。また、会社の重役のグレースと医師であるロジャーは、裕福な家庭を築いているが、その空間の言いようのない“気持ち悪さ”は、一つの恐怖ですらある。ボーの育った抑圧的で支配的な母親の居る環境とは違うが、ロジャー夫妻の家庭もまた異常なのである。
森を彷徨い、旅の一座と遭遇した彼は、彼らの芝居に自らの人生を重ねて行く。この辺りから、起こっている事が現実か妄想かの境が曖昧化していく。
母の自宅を訪ねてからの展開の数々は、その全てが妄想、虚構であるかのように感じられた。まるで、昨年亡くなったデヴィッド・リンチの『マルホランド・ドライブ』(2001)を観ているかのような感覚だった。
しかし、エレインの突然死や異形の姿をした父といった点を除けば、幼いボーを取り巻いていた環境が如何に歪であったのかを読み解ける。支配的な母に反抗する双子は、屋根裏に監禁されるというネグレクトを受けているし、そのトラウマを封じ込めるかのように、ボーはその光景を夢だと認識する。
母は、自らが母親から愛されなかった屈辱から、ボーに対して異常なまでに愛情を注ぐ。しかし、それは一方的な「これで良い」という親のエゴの押し付けであり、誤った愛情表現なのは間違いない。また、自らが与えた愛情と同程度の返しがないと、それを不満に思い、自らが被害者であるとして責め立てる。
こうした歪んだ認知の再生産は非常に現実的。
そして、クライマックスでボーがボートに乗って夜の湖へ逃げ出す様は、母を殺した事で、ようやく自分の人生を掴んだ。ある意味で、ようやく“生まれる事が出来た”瞬間なのかもしれない。しかし、ボーの中には強い罪悪感が付いて周り、それがラストの裁判の様子に繋がるのではないかと思う。彼が幼少期から母に対して行ってきた罪(罪と言える程の事ではない気もするが)に対する罰を、ボー自身が無意識に求めていたのではないかと思う。だからこそ、彼は最後には命を落としてしまう。
「子供は親を選べない」。そして、たとえ不条理の権化のような親であっても、手に掛けてしまえば罪の意識が芽生えてしまう。少なくとも、ボーはそういう性根の人物だったのではないかと思う。それは不幸であると同時に、紛れもない“恐怖”だろう。
【感想】
主演のホアキン・フェニックスの体当たり演技が素晴らしく、だらしない中年男の体型になりながら全裸で駆け出す姿は、最早天晴れとしか言いようがない(本作が日本公開時にR-15指定だったの、間違いなく、彼と殺人鬼のフルチンだろう)。
事あるごとの表情の演技も抜群で、さすがベテラン俳優。
母親役のパティ・ルポーン(若い頃はゾーイ・リスター=ジョーンズ)のヒステリックで支配的な母親像も説得力に満ちており、自らを息子思いの良き母として疑わない姿勢にはゾクッとさせられる。
3,500万ドルの製作費に対して、世界興収は役1,200万ドルと惨敗。評価も賛否両論といった具合で、これまでの作品と比較しても難解なストーリーは確実に観る人を選ぶ。しかし、個人的には、本作のテーマの扱い方、幻惑的な中盤以降の展開と様々な真実が明かされていくクライマックスの展開は非常に好みであり、アリ・アスター監督作品の中では最も娯楽性のある作品だと評価したい。
全364件中、1~20件目を表示