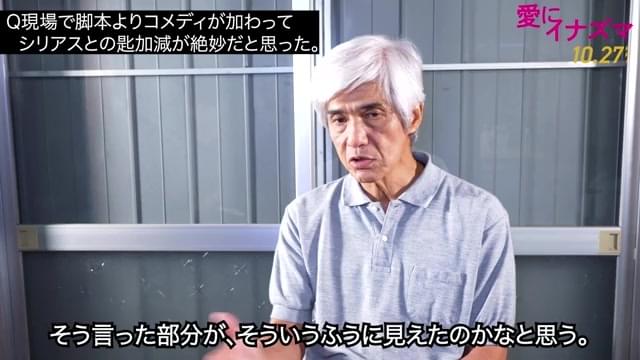「松岡茉優だけでなく、佐藤浩市の親子が素敵な一本」愛にイナズマ talkieさんの映画レビュー(感想・評価)
松岡茉優だけでなく、佐藤浩市の親子が素敵な一本
<映画のことば>
「負けませんよ、あたしは。」
花子監督は、念願の監督デビューを飾るべく、映像作品を通じて実母の出奔の秘密を探ろうと試みるのですけれども。
しかし、製作に大きな発言力を持つプロデューサーの意向(横暴?)で作品を取り上られてしまうー。
それでもめげない花子監督は、偶然に知り合った(頼りなげな?)彼氏・正夫に触発されて、十数年来も行き来のなかった家族に突撃取材を敢行することで、自分なりの映像製作を続けようとは試みるのですけれども。
結局は、花子監督の剣幕に、ついに押し切られた父・治がしぶしぶかけた一本の電話で、その真相は明らかになるー。
いずれにしても、花子監督のこの「突撃体勢」は、正しく「イナズマ」そのものであり、そのエネルギーが、バラバラだった治、誠一、雄二を、家族の絆で(再び)まとめ上げたのではないかと思います。
そして、「猪突猛進」の言葉のとおり、イノシシの如く真正面から突進してくる娘を受け止めかねて、たじろぐ父親役の佐藤浩市の好演ぶりも見逃せなかったと、評論子は思います。
彼の演技は、まさにそんなイノシシ娘をどう受け止めるのか、扱いに困る父親の姿そのもの。
実際、爆弾のような娘と対峙していた心当たりの評論子には、百も二百も合点できる名演技でもあったとも思います。
そして、その娘=花子監督を演じた松岡茉優の演技が秀逸だった一本としても、充分に佳作としての評価に値する一本だったと思います。
(追記)
血を分けた実の家族ではあっても、携帯電話の解約など、公的(?)な手続きでは「紙」で、その家族関係を証明しなければならなかったことが、治・誠一には、もどかしかったように見受けられました。
個々の家族の関係など知る由もない携帯電話会社としては、無理からぬ対応でしょうし、ほんの「はじっこ」とはいえ行政機関に職を得ている評論子としては、日々、同じようなことをしているとも言えそうです。
反面、そのことは、書類面(づら)さえ整えば「家族」として通用してしまう「危うさ」も含まれていることを忘れてはならないとも思います。
(追記)
プロローグのタイトルが「あり得ないこと」になっていましたけれども。
上記のとおり、製作側の判断で、花子監督は、その監督としての立場を勝手にすげ替えられただけでなく、タイトルはそのままに、自分の構想(理由もわからずに出奔してしまった自分の母の物語)を勝手に取り上げられてしまったわけですけれども。
そんな「ありえへん」ようなことは、映画の世界では決して「ありえへん」ことではないのでしょうか。
本作が時代背景としていたのは、ひと頃の「コロナ禍」。
中世ヨーロッパの黒死病(ペスト)じゃああるまいし、もともと保健衛生には「これでもか、これでもか」と言わんばかりにうるさかった令和のこの日本で、大規模な感染症(COVIT-19)が流行することだって、本当は「ありえへんこと」だったのかも知れません。
その一方で、食品衛生一つとっても、やれ賞味期限だといい、消費期限だという。しかし、どっちにしても細菌の繁殖具合とかいった客観的な指標で常に常に判定されているわけでもなく、官能試験といえば聞こえはいいのですが、要するに人=判定員が、言ってしまえば、その主観で判断している。
一皮剥いてみれば、そんな不安定さ。
往時は、何でもかんでも二言目には「コロナ禍だから」という修飾語句で一括りに括られていましたけれども。
しかし、そんなこんなに対する痛烈な皮肉が本作には込められていると言ったら、それは穿ちすぎというものでしょうか。
(追記)
もう一つ、コロナ禍の特徴は、マスク姿ということでしょう。
顔の半分が隠れることで、そのぶん素性も隠れる(隠しやすい?)ということで、本音が前に出やすかったということもあったのでしょうか。
本作でも、正夫が、飲食店での詐欺グループに堂々とケンカを売ることができたのも、素性が(半分)隠れていたことと、無縁でなかったと、評論子は思いました。
(洗濯後の彼のアベノマスクに、洗っても落ちないほどの血痕が、しっかりと付いていましたから、相当の「返り討ち」に遭ってしまったことは、想像に難くありませんけれども)
(追記)
お話が戻りますが、「ありえへん」といえば…。
評論子が住む北海道では、大地震の影響で全道的な停電(ブラックアウト)があり、三日三晩、電気のない生活を強いられてしまいました。
「ほんま、ありえへんわ。」
映画フアン殺すにゃ刃物はいらぬ。
電気の三日も来なきゃいい。
(追記)
更につまらないことなのですけれども。評論子が気になったのは、フェリーから亡母の遺骨を撒くシーン。
実際の海洋散骨では、遺骨を薬剤でジェル状に固めてから、それを海中にポトンポトンと落とすやり方だそうです。
本作のような方法では、風向きによっては、撒いている人の目に入ったりもするそうですし、第一、他のお客さんも乗っているフェリーでというのは、論外でしょう。
基本的には撒くだけなので、節度をもってやる限りはOKというのが厚労省筋の見解ではありますけれども。
一方では、その地その地によってローカルルールもあるようですから、地元の葬儀屋さんをかませることは、実際問題としては、必須のようです。
共感ありがとうございます。
今作の佐藤浩市と言えば、娘が連れてきた男に対する視線がどんどん優しくなっていたのが印象的でした。
石井裕也監督は汚い、えげつない描写をちょいちょい入れる監督でしょうが、前半丸々はちょっとキツかったですね。