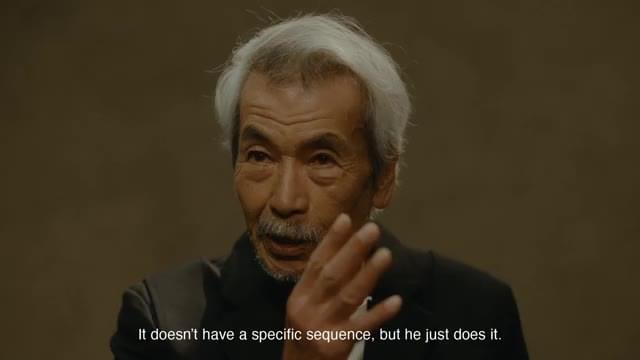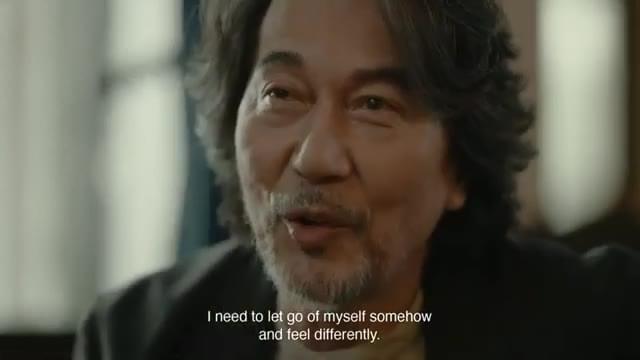「“日常”の有難さを知った2020年代に響く人間賛歌」PERFECT DAYS 高森 郁哉さんの映画レビュー(感想・評価)
“日常”の有難さを知った2020年代に響く人間賛歌
昨日と今日、そして明日もだいたい同じ一日が繰り返される。当たり前だったそんな日常が、コロナ禍で一変した。職場や学校に通い、人に会って話をし、店で飲み食いする、そんな普通のことでさえも困難になったあの時期を経て、日常の有難さが世界中で認識された今、この「PERFECT DAYS」が世に出るのはまさに完璧なタイミングだ。
成立過程はかなりユニーク。2018年に「THE TOKYO TOILET」プロジェクトがスタートし、渋谷区内17カ所に著名な建築家やクリエイターらが設計した公共トイレが順次設置された。そのPRの一環としてまず短編映画の企画が立ち上がり、役所広司とドイツの名匠ヴィム・ヴェンダースの参加が決まってから長編劇映画として再構想されたという(おおよその経緯はWikipediaの「THE TOKYO TOILET」と「PERFECT DAYS」の項で確認できる)。
小津安二郎への敬愛をドキュメンタリー「東京画」で示したヴェンダース監督らしく、本作の主人公であるトイレ清掃員の平山は実直で心優しく日常を大切に生きる男で、物語はさほど大きな事件が起きることもなく淡々と進む。近所の老婆が通りを竹ぼうきで掃く音で目覚め、仕事道具を積んだ車で担当する渋谷区の公衆トイレに向かい、丁寧に便器や手洗い場や床を清掃する。樹木を好み、木漏れ日をフィルムのカメラに収め、銭湯に通い、馴染みの飲み屋に寄り、文庫本を読んで寝落ちする。そこには、平山というひとりの人間の生きざまをそっと見守り讃える温かなまなざしが確かに感じられる。
寡黙な平山の心情を代弁するかのように、彼がカーステレオや自室のラジカセで流すカセットテープの60~70年代の洋楽が、夜明けと朝日の美しさ、一日の始まりの高揚や感謝、日曜の午後の気分などを歌い上げる。どの曲もシーンに合っているが、とりわけラスト近くで流れるニーナ・シモンの「Feeling Good」と役所広司の表情の相乗効果が抜群で、ヴェンダース作品としてだけでなく邦画史においても屈指の名場面として大勢の観客の心に残るはずだ。