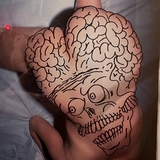落下の解剖学のレビュー・感想・評価
全330件中、201~220件目を表示
3セットマッチにたとえるなら
ケンカの録音を聞く前、"サンドラが優勢"。
録音を聞いた後、"夫が優勢"。
決まりかけた試合のタイムアウト直前、"ダニエルが決めたのなら、それで良いよ"
サンドラは頭が良く才能に溢れ、周りの人々は彼女に惹かれずにはいられない。
一方で、仕事ができる人間にありがちな、周りの人々を利用する事を厭わない面もある。
そんな彼女の夫が、才能のなさや境遇を克服する強さを持ち、妻の不誠実さをなじることでしかプライドを保てないほど弱くなければ起こらなかった悲劇。
事実はどうあれ、頭が良く眼の障がいという自分の境遇に向き合える、ダニエルが出した結論だもの。
壊れてしまった夫婦、あるいは家族の物語
スヌープの演技力ならラップもできそう
夫の死をめぐる裁判で、徐々に明らかになる夫婦間の確執を見つめつつ事件の真実に迫るという設定はおもしろそうなんだけど、実際には夫婦の痴話を長々とうまくないセリフ回しで見せられる感じ。話のポイントじゃないこともあってミステリー的要素も薄くて、こっちは傍聴席で意識が飛びそうになった。
裁判もなんか論破合戦的というか「朝生」っぽい軽い感じで、 検事がやけにフランク。あちらでは公判中にジョーク言ったりすんのだろうか? まあ、母親があんまし子ども好きじゃないのはよくわかった。
しかし、飼い犬のボーダーコリーの演技がめっちゃすごい。アスピリンで目を開けたままぴくぴくなったり、人の心を見透かすような三白眼で見つめるところなど、ヘタな役者よりもうまい。今作の主役ザンドラ・ヒュラーがトニ・エルドマンで唐突にマッパなったときぐらいの驚きがあった。
関係ないけど、本作の紹介欄で「さようなら、トニー・エルドマン」って。校正ぐらいした方がいいよ…。
ガチ
真実は結局なんなのか
正直想像していた内容とは違った。
結局真実がなんなのか明らかになっていないような感覚になり、急に出てくる新たな証言に翻弄され、確信に近いことなのかよくわからない事柄を議論しまくっている印象だった。
痛ましいケンカシーンや白熱した裁判の議論が見せ場だったとしたら少し期待外れであった。
息子の揺れる表情が切ない
家族の絆と裂け目「落下の解剖学」に見る社会の断面と深淵
『落下の解剖学』はただのヒューマンサスペンスに留まらない、深遠なメッセージを秘めた作品です。人体の構造を探求する解剖学のように、この映画は、雪山の山荘で起きた謎の転落死を通じて、家族の秘密や社会の問題を解き明かします。監督ジュスティーヌ・トリエの手によって、第76回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞し、さらに第96回アカデミー賞で5部門にノミネートされるなど、世界中から高い評価を受けている事の意味を深く感じました。すごい
この映画は、視覚障がいを持つ少年とその家族を中心に展開し、夫婦間の複雑な関係、社会問題、そして人生の不条理について深く掘り下げます。高額な医療費、外国で暮らすことの難しさ、性的マイノリティ、ネット社会による情報の拡散や誹謗中傷など、現代社会が直面する様々な問題を、一つの家族の物語を通して浮かび上がらせます。
サンドラ・ヒュラーが演じる主人公サンドラの迫真の演技は必見。彼女の演技を通して、観客は家族の愛、秘密、そして嘘が複雑に絡み合いながらも、それぞれの真実が明らかになっていくのかを目の当たりに。深い作品でした。
#落下の解剖学#カンヌ受賞作#ヒューマンサスペンス#サンドラヒュラー#ジュスティーヌトリエ#アカデミーノミネート #社会問題を考える#家族の秘密 #現代社会の挑戦 #真実の探求#映画レビュー#三度の飯より映画好きシェフ聡
味わい深い映画‼️
フランス法廷劇
予告だけ観て鑑賞、意図せずして良い法廷映画を引いた。
作中の「重要なのは事実ではなく、君が周りからどう見られるかだ」というような台詞、まさに参審制や陪審制の曖昧さを表現しているのかな。
後半に出てくる口論シーン、
あ、なんか旦那さん可哀想かも、いややっぱり奥さんが可哀想かも、いやでも、やっぱり……客観的に見ているつもりの自分の判断がいかに曖昧で主観的なものかを突きつけられる感じ、本当に嫌になる、上手い。
他の弁論シーンも同様、家族のストーリーを一部見せられている我々には検察官がめちゃくちゃ嫌な奴に見えるんだけど、傍聴席から聞いてみればむしろ馬鹿げた弁論を繰り広げているのは被告人側なのかも、客観性ってなんなのか…。
元々フランス映画の独特なテンポに苦手意識があったのだけれど、この作品を観て私が苦手なのはフランス語のテンポなのかもと思い直しました。
アカデミー賞ノミネートがこれ…
宣伝ミス
恩と仇は紙一重
法廷ものにありがちなラストではない
ケンカって双方の言い分を聞かないとどちらが悪いなんて判断できない。そもそもどちらかが一方的に悪いってこともあまりないように思える。しかも男女間の諍いなんていろんな事情や思いや今までの積み重ねが絡まった上で起こるんだから判断が難しい。
夫殺しの容疑で逮捕された妻の裁判を中心に描かれるこの映画。物的証拠と言えるのは遺体と血痕のみ。その科学的な分析は前半の方で議論されるが、あとは夫婦仲が悪かった、妻が夫を憎んでいたんだろうという印象や推測の話が法廷で飛び交うものだった。フランスの警察や検察はあれで大丈夫なんだろうか。クソほどに意地が悪いし、ついでに頭も悪かった。
最後の方でアッと驚く展開があるのかと思ったが、意外とあっさり終わっていった。ここらへんがフランス映画っぽい。ハリウッドならもう一波乱起こしていたはず。ただ、最後に犬のスヌープ(ラッパーからつけた名前?)の行動は何かを暗示しているような気がしてしまう。あんな仕草したのを初めて見せられたから。
でも、夫が亡くなった真相がどうなのかってことはメインに伝えたいものではないのだろう。あの法廷で責められるサンドラと、夫との諍いや周りの証言で家族の関係性が変容する様がメインのような気がした。男女間の諍いって本当に面倒だと感じる。上映時間が長いのにそれほど退屈にはならなかった(前半は少し退屈)。なかなかの秀作だと思う。
どんでん返しや複線のてんこ盛りに頼ることなく物語に引き込む、上質な語り口の作品
ジュスティーヌ・トリエ監督、サンドラ・フューラー主演の本作は、作中英語とフランス語が行き交う状況が示すように、フランスを舞台としたフランス映画です。だからこそなのか、トリエ監督の持ち味なのか、謎と衝撃的な展開がてんこ盛りになりがちなサスペンス映画とはまた一味違った展開、余韻が楽しめます。裏返せば、ジェットコースターのようなドキドキ、ハラハラな展開を期待すると、ちょっとあれっ、てなるかも。
物語の基本的な筋は、山荘から転落死したサミュエル(サミュエル・セイス)の死因が事故なのか他殺なのか、そしてその妻サンドラは無実なのか、を法廷闘争を通じて追及していく、というものです。この基本線が明確であるため、夫の死因に無罪を主張する妻の物語、として観通すことは当然可能だし、それでも十分面白いんですが、この件の背後には、仕事上の二人のいさかい、息子ダニエル(ミロ・マシャド・グラネール)の視覚障害の問題、サンドラの個人的な問題、果ては彼らの国籍の問題(サンドラはドイツ系、サミュエルはフランス系)などが浮かび上がってきます。
このように主筋を明確にして、一見わかりやすい物語に見せつつ、実際には様々な要素をそれとなく忍ばせているため、一度観通しても、再度見返したくなる魅力があります。派手さはなくとも間違いなく良質な作品なので、今回のアカデミー賞でどれだけ内容が評価を受けるのか、今からとても楽しみな作品です!
かわいくない
とても深みのある作品
評価4.3
ジュスティーヌ・トリエ新作のサスペンス。
と思って観たのですが、とても深みのあるヒューマンドラマでした。
ほぼ会話劇で、迫るようなカメラが印象深位です。
前半は緩く少し眠気さえも伴ったものの、裁判に入ってからの張り詰めた空気に引き寄せられました。
とてもリアリティのある作りで、先にあげたカメラもですがマイクも良かったです。
リップや吐息など細かい音を拾っていて、とても身近に感じられました。
またとても練られた脚本で、段々と明るみになっていく真相は見事でしたね。
それは事件そのものというよりも、その背景に隠れていた夫婦の秘密。
それが少しずつ露わになっていく様が実に見応えがありました。
主人公役のサンドラ・ヒュラーの芝居もすごい。
その表情からは犯行に関わっているのかいないのか、最後まで拭いきれない気持ちが付き纏ってました。
あとスヌープ役の犬。どうやったらそんな演技ができるか不思議すぎます。あれは天才レベルですね。
そして視覚障がいの少年ダニエル。
彼は最初からずっと物語の中心にいるのですが、常に影を落としていました。
間違い(嘘)の証言。
何度も差し込まれるひとりでピアノを弾く姿。
あれは、彼しか知り得ない真実に苦しんでいるように見えるんですよね。
ただそんな中でも、彼は自分で真実を決めました。
そうしてやっと二人が向き合うことができ、家族の再生の一歩となったのでしょう。
謎は謎のまま、とても深みのある作品でした。
全330件中、201~220件目を表示