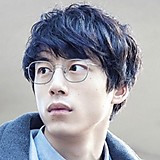関心領域のレビュー・感想・評価
全441件中、1~20件目を表示
精神や体調に支障がでていることを祈る
・新しい効率的な焼却炉の商談 ⇒ それはゴミではなくユダヤ人を焼却する炉
・好きな服を選んでいい ⇒ それはユダヤ人から剝ぎ取った毛皮や服
・歯で遊ぶ子供 ⇒ それは恐らくユダヤ人の歯
ここまで麻痺するのか。いや麻痺しうるな。そういう空気、ご時世、雰囲気になっても人間らしさを見失わず正しいことを全うできるか?恥ずかしいことに100%の自信がない。だからこそ自戒し続けなければ。
最初から最後までずーっと叫び声や怒声や銃声がバックに流れる。
これが音響のいい映画館で観た方がいい「これまでにない理由」だ。
あの音をBGMに暮らすのは、いくら裕福でも精神に支障を来すはず。
そういえば、妻も子供も少しずつそういう兆候(ヒスなど)があったような。
また、裕福とはいえ、幸せそうにも見えなかった。「自分は恵まれている」と無理に思いこもうとしているように見えて仕方がなかった。
いや、きっとそうであって欲しい。
人間として、全く平気であって欲しくない。人間はそうじゃないと思いたい。
※リンゴを挿していくシーンは何なんだろ?そういえば塀の向こうでリンゴで争いになっている(と思われる)シーンもあったな。このリンゴなんだな。
※よく分からなかったシーンがたくさんあった。川に流れてきたのは何?とか。あらすじを書いたサイトや考察を早く読みたい。
※A24っぽさ全開。しかし、なんかパターン決まってきたな。
音と映像の関係について批評的な作品
予想以上のヒットになっているようだが、これは確かに観ると「何か言いたくなる」タイプの作品だし、鑑賞後に他の人がどう思ったのか気になるタイプの作品だろう。考察要素もかなりあるので、意外と現代の観客の嗜好にあった作品かもしれない。
僕自身は、この作品はカメラのあり方に上手さがあったと思う。定点観測的に据え付けられたカメラで観察する態度を徹底させて、のぞき見の視点を持っている点が多様な解釈を生み出す。そして、家の敷地の向こう側に決してカメラがいかないで、音だけでアウシュビッツの惨状をほのめかすという点が本作の優れたポイントだが、音と映像の関係について考えさせられる。映像はフレームが決まっているが、音の空間的な拡がりは映像よりも広い。映像が洩らした情報を音が拾っているわけだ。音の表現力を突き詰めて考えているからこそ出てくる発想だと思う。音はただ映像を補完する存在ではない。音の空間表現力は映像を凌駕することがある。画面だけ見るとひとつの家の中だけしか情報を提示していないが、音はより広い空間を表現している。音が良い作品は映画館でこそ本当の力を発揮する。その意味で、これが劇場でヒットするのは、必然とも言える。
“関心の壁”を可視化した鋭い眼差しが、時を超え現代人を射抜く
ナチスドイツとホロコーストの歴史に明るい人なら、映画の題名の元になった用語に聞き覚えがあっただろうか。ドイツ語でInteressengebiet、英訳でZone of Interestは、第2次世界大戦中のナチス政権が占領下ポーランドのアウシュビッツに建設した強制収容所群を取り囲む一帯を指した呼称。interesseとinterest(どちらもラテン語から派生)には「関心;利権;重要」などの意味があり、この地域で農地を接収し農作物を販売して利益を得ることや、住民と囚人の接触を減らすことを目指す「重要な地域」というニュアンスがあったようだ。
英作家マーティン・エイミスは2014年に発表した小説「The Zone of Interest」で、登場人物らの関心と無関心を重要な要素として描いており、interestの語義のうち「関心」をより強く題に込めたのは明らか。なおエイミスは、初代所長ルドルフ・ヘスとその妻をモデルにした架空の2人と、妻と親密になる将校、ユダヤ人ゾンダーコマンド(労務を担う囚人)を主要なキャラクターにして物語を構築した。
ジョナサン・グレイザー監督はこの小説の映画化権を獲得し、自らの脚本で所長夫妻を実名に戻したことをはじめ、原作から大幅に改変してより史実に近いドラマとして再構成(原作小説の将校とゾンダーコマンドは映画には登場しない)。ルドルフ(クリスティアン・フリーデル)と妻ヘートヴィヒ(ザンドラ・ヒュラー)ら家族が、収容所から壁一枚隔てた敷地に建てた邸宅で過ごす“幸福な日常”を、淡々と観察するかのようなカメラワークで描いていく。
ホロコーストを題材にした映画として画期的なのは、強制収容所内の出来事を一切映像で描写しない点。ただし銃声や叫び声などの音と、高い煙突から上がる煙などの背景映像によって、すぐ隣でユダヤ人収容者の虐殺が延々と続けられていることを示唆する。そして、そんな煙や音を見聞きしながら意に介さず楽しげに暮らすヘス一家と来訪者らの姿が、観客を戦慄させもする。
人間の関心の範囲には限りがあり、その範囲を越えた先のことは、たとえ情報が五感を通じて体に入ってきても意識にほとんどとどまることすらなく通り過ぎてしまう。そんな関心の限界、言い換えるなら“関心の壁”を、グレイザー監督はヘス邸と収容所を隔てる壁で可視化してみせた。
そして、映画の眼差しは、単に80年以上前のドイツ人家族に向けられるだけでなく、ロシア・ウクライナ戦争とイスラエル・ガザ戦争で大勢の兵士と市民が日々戦死し犠牲になっている世界に生きる現代の私たちをも射抜く。そうした世界の悲惨な状況をニュースやSNSで見聞きしても、すぐに意識が日々の衣食住や身近な人間関係などに移っているのなら、ヘス一家に恐怖したり批判の目を向けたりする資格はないのかも。あなたの関心の領域はどこまでか、関心の壁は今のままでいいのかと、映画が問いかけてくるようだ。
怒りや衝撃を超えて込み上げてくるもの
数年に一度、こんな類稀なる怪作と出会うたびに私の体は硬直する。アウシュヴィッツ収容所に隣接する邸宅という極めて象徴的な場所を使って、そこで何食わぬ顔で暮らす家族をまるで実験観察のように見つめるこのひととき。すぐ間近で起きているおびただしい人々の地獄のような日常はいっさい映り込まない。だがそこには、けたたましい音、衣服、立ち上る煙、灰塵など、何が起こっているか想像するのに十分な悲鳴や痕跡があふれている。歴史を知る我々はその一つ一つを意識的に受け止めうる。しかし、どうやらあの家族は、耳を塞ぐでもなく、聞こえないふりをするでもなく、そこでの暮らしを「手に入れた幸せ」として受容しているようだ。あたかも別世界の住民のような態度を見ていると、怒りを超えた衝撃と恐怖が込み上げてくる。が、翻って、戦争や災害などの苦しみが世界を覆う現代において、あの家族は他人事と言えるのか。あらゆる意味で、映画は写し鏡だ。
戦争や差別や殺戮を許す無関心の罪
壁を隔てたすぐ隣にある施設からは、強制収容されたユダヤ人たちが何らかの肉体的危害を加えられていると思しき"音"が聞こえる。目には見えない分、"音"が伝える恐怖は計り知れない。それは、観客が想像力のレベルを検査される時間でもある。一方、壁のこちら側では、ナチス将校一家が豪華な邸宅に住み、家庭菜園で土を耕し、子供たちは水泳や釣りに興じている。
ドイツ映画はこれまでも様々な形でホロコーストを描いてきた。しかし、イギリス人監督、ジョナサン・グレイザーはアウシュビッツの司令官、ルドルフ・ヘスとその妻、ヘドウィグの生活にスポットを当てた小説を自ら脚色し、近年発表されたほぼ全ての同ジャンルのドイツ映画にも勝る、強烈な反戦映画を外国人の視点で作ってしまった。
本作の怖さは壁を隔てた2つの空間の対比よりも、むしろ、無関心を装うことがいかに戦争を放置することになるかという、現代人への警告だ。ヨーロッパやイスラエル、ガザ近辺だけではない、地球上の全ての場所に住まう人々への。戦火が止まる気配を見せない今、見逃してはいけない1作だ。
Infernal Audio Trip
An eerie pitch black overture unwinds you into a diabolic abyss, tuning your ears for a score to ungodly torment. Nixing a substantial percentage of story from its source, the film sticks to the daily life of a family's dream home perched by Hell, of which the breadwinner is a senior manager. A well-staged historical reenactment with the sounds of machinery and suffering saturating the atmosphere.
関心領域
後半の盛り返し具合エグイ
現代を生きる人達も、この映画と同じかもしれない
途中寝てしまう
権力者が生まれると“思考停止や凡庸さ”の者たちが支配する世に…
アウシュビッツ関連映画は
これまでも随分と鑑賞してきたが、
この作品は少し視点の異なる作品だった。
ある意味、
その“思考停止や凡庸さ”が重大な犯罪を
引き起こしたとするアドルフ・アイヒマンに
関する映画
「スペシャリスト~自覚なき殺戮者~」や
「ハンナ・アーレント」と
根っ子は同じ“無関心”がもたらす悲劇
を描いているのだろう。
そんな“無関心”を象徴するシーンとして、
自宅からチョイ見えする監視塔や
焼却炉の煙突と煙などを背景に描かれる
ルドルフ・ヘス宅での家庭的日常描写は、
制作側の意図が明白な見事な構成に感じた。
但し、この作品で残念だったのが、
せっかくヘス家族の“無関心”日常を
淡々と描くことにより、
それが強制収容所内の地獄絵図を
逆説的に想像させるスゴ技になっていて、
その地獄の匂わしは、収容所からの音声や
使用人と妻の母親の行動の描写で充分な
はずにも関わらず、
私には勇み足的に見える最終盤での
ヘスの精神への寄り添いや
現在のアウシュビッツのシーンで
締めくくってしまった編集だ。
ヘス夫婦の、ある意味トンチンカンな悩み
が、この映画の肝なはずなのに、
多分に、この結果がこれだけの犠牲者が、
と言いたいのだろうが、
最後の最後までヘス家族の
日常生活で終えてもらった方が、
より犯罪への人としての“無関心”さが
浮き出たように感じる。
さて、現在においても、
プーチンロシアを見ても分かるように、
我々が最高指導者に間違った人物を
置いてしまったら、
異議申し立ても不可能な中で
その権力に従属せざるを得ない社会を
生んでしまうとの教訓を得るべきで、
アイヒマンやこの作品でのヘスが
どうのこうの言う以前に、
権力者が生まれると、彼を信望する
“思考停止や凡庸さ”を兼ね備えた者たちに
我々は支配され、
悲惨な社会状況になってしまうことを
肝に銘ずるべきなのだろうと思った。
強制収容所所長の日常
こう聞くとゾッとするかもしれないが。
"彼"とその家族の目線から見ると、実に平和な日常が広がっていた。
ホロコーストを実行していたのは残虐な殺人鬼でもなければ悪魔でもない。
紛れもない人間。
それも我々と何一つ変わりない普通の人間だと言うことが分かる。
逆に言えば誰でも加害者にでも被害者にでもなりうるという事。
そして人々の無関心がそれを助長しうると言う事。
この普遍的事実をセリフや映像ではなく"音"で突きつけてくるアプローチは実に新鮮だった。
これはかつて被害者であったユダヤ人達が、今や虐殺する側になった現代にも非常に重なるものがある。
正直な所、映画としては実に退屈だ。
眠気を誘うシーンばかり。
しかしその"無関心"こそ危険だと言う事に後から振り返り気づくとゾッとするのだ。
決して面白い映画ではない。
でもこういった映画も必要なのだと思う。
無関心でいる人々に関心を持たせる為に。
面白くは、ない
今までにないタイプの映画
この映画を事前知識なしで見る人はほとんどいないと思いますが、この映画は説明0の状態で始まり、最後まではっきりとした説明がないまま終わります。
なので本当に事前知識0で見ると面白くないのではないでしょうか?
最低限「アウシュビッツ強制収容所の隣で暮らす一家の日常」という知識は必要です。
通常の映画は目に映るものを楽しむ・耳で聞こえるものを楽しむということが基本ですが、本作では「目に見えない塀の向こうを想像する」「聞こえてくる音声からそれが何の音か想像する」という通常の映画とは全く違う楽しみ方をする映画です。
正直娯楽作品としては楽しみにくい作品ですが、考えさせられる作品としてはめちゃくちゃ素晴らしい映画だと思います。
「関心領域」という邦題も素晴らしいですね。「あなたは塀の向こうに関心がありますか?」という問いかけにも思えます。
無関心であることの恐ろしさを容赦なく暴(あば)き出す
<映画のことば>
「現実を受け入れて、ここを離れよう。」
「嫌よ。あなた一人で行けばいいわ。
あなたは、オラニエンブルクで仕事を。私はここに残って、子供たちを育てる。今までどおりに、アウシュビッツでね。」
「まさか君が来ないなんて。思いもしなかったよ。」
「あれが、私たちの家なのよ。」
世にも恐ろしい虐殺行為が白昼に堂々と行われていたというアウシュビッツというその土地柄…壁一つ隔てた隣では、ユダヤ人に対して歴史に残る大虐殺が行われている、その土地柄で、無邪気にも(?)住まいに固執する、ヘス収容所長の妻・ヘートヴィヒの言動が、評論子にはむしろ不気味にも思われました。
自宅の、ほんの隣では世界史に残るような大量虐殺が行われているというのに…(絶句)。
しかも、ヘス家に集う彼・彼女たちは、ヘス家から塀ひとつを隔てた、すぐ隣では何が…どんなことが行われているかは、知らないわけではなかったようにも見受けられます。
そのことは、家政婦から嫌がらせをされたと思い込んだヘートヴィヒが家政婦(おそらくは送られてきたユダヤ人の中の一人)に向かって「夫に頼んでお前を灰にして、あちこちに撒き散らしてやるから」と悪態をついていたことからも明らかだと、評論子は思います。
無関心でいることの「本当の恐ろしさ」は、ここに極まったとも言うべきでしょう。
本作を観終わって、まず真っ先に評論子の脳裏に浮かんだのは、ドイツの神学者で、反ナチス活動家としても知られたマルティン・ニーメラー(1892-1984)の次の言葉でした。
「ナチスが共産主義者を連れさったとき、私は声をあげなかった。私は共産主義者ではなかったから。/彼らが社会民主主義者を牢獄に入れたとき、私は声をあげなかった。私は社会民主主義者ではなかったから。/彼らが労働組合員らを連れ去ったとき、私は声をあげなかった。私は労働組合員ではなかったから。/彼らが私を連れさったとき、私のために声をあげる者は誰一人残っていなかった。
人は、自らの「関心領域」の外側で行われていることには、まったくを以て無頓着であるという箴言としては、本作の標題は、まさに「そのものズバリ」というべきだとも思います。
そして、そのようなストーリーをドラマ仕立てや劇映画タッチで描くのではなく、ドキュメンタリータッチで、ただ淡々と事態の推移を描いていた点も、構成としては、高く評価できる…否、むしろドキュメンタリータッチで淡々と描かれているからこそ、無関心でいることの本当の恐ろしさが、容赦なく暴き出されていたとも思われます。
本作は、評論子が入っている映画サークルが、毎年選定している年間ベスト作品として、2024年の公開作品として選ばれていた作品になります。
地方都市に住まう評論子にはなかなか鑑賞の機会がありませんでしたが、ようやっと宅配レンタルで観ることができました。
年間ベストに相応しい、重厚な作品で、充分に佳作としての評価に値する一本でもあったとら評論子も思います。
(追記)
先程は「人は、自らの『関心領域』の外側で行われていることには、まったくを以て無頓着である」と書きましたが、これはもちろん、自分の関心領域外で行われていることは知らない(無関心)ということで書いたのですけれども。
しかし、他面では、ヘートヴィヒは「何が行われているか」は知ったうえで、その「知っていること」を意図して関心領域の外へ押し出しているとしたら、それは、まったくの「関心領域」外よりも、数十倍、いや数百倍も空恐ろしいことと思います。
本作のタイトルには、実は、そのダブルミーニング(?)も隠されているのでしょうか。
(追記)
音だけ聞こえてで、映像がないシーンから始まるという本作の構成も、作品の組立てとして、秀逸だったと、評論子は思います。
音がするので、上映が始まっていることはわかるのですが、「絵が出ないということは上映機器(DVDデッキ)の不具合だろうか」と、観ている方を不安にさせる手法は、作品全体に漂う不気味さを、いやが上にも盛り上げる演出として、当たっていたのではないかと、評論子は思います。
(追記)
作中で言及されているヘンゼルとグレーテルの寓話…パン焼き窯でグレーテルを焼こうとした魔女は、ガス室で殺害したユダヤ人の遺体を焼
却炉で焼却したドイツ軍の暗喩だったと、評論子は受け取りました。
(追記)
本作に登場する人々の「関心領域の狭さ」は、取りも直さず彼・彼女らの「心の闇」ともいえると、評論子も思います。
そして、当時のナチスの「エリート意識」「独善さ」「近視眼さ」ということは、別作品『ヒトラーのための虐殺会議』にも描かれていたとおりで、彼らの心にはそういう「闇」が根深く巣くっていたことには疑いがありません。
的確なレビューでそのことを再認識させて下さったレビュアーNOBUさんに感謝するとともに、末筆ですが、ハンドルネームを記してお礼に代えたいと思います。
全441件中、1~20件目を表示