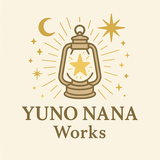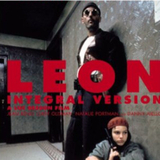映画 窓ぎわのトットちゃんのレビュー・感想・評価
全188件中、1~20件目を表示
親子で見るのもオススメできる作品
はるか昔に原作を読んだ以来のとっとちゃん。
あの頃は自分も10代だったので、やはり大人になって見ると感じ方が変わってくる。
10代の時は、自分らしさを大切にすることや、自分だけじゃなく、周りの子の自分らしさも理解して接していくことを学んだけれど、今は子供たちに大人はどう接していくことが大切か、という目線で見ている自分がいた。
子供の頃とっとちゃんを読んで大人になった人たちには、ぜひ私のように、自分の変化も感じながら見てほしい。
全体的に淡い色合いと可愛らしい絵柄で、全体的に優しい雰囲気がすごく良い。
そして、子供たちの声を実際子供たちが演じている点がすごく良かった。大人が子供の声を出して演じるのとは違う、リアルさや純粋さを感じた。
この優しくてあたたかな雰囲気だからこそ、戦争に向けて進んでいく不安さや、平和な日常が壊されていく感じが際立ったように思う。
大人でも十分楽しめる作品だけれも、子供たちと一緒に見るのもオススメな作品だった。
「あなたはあなたのままそれでいい」
私は黒柳徹子さんが好きだ。人として好きというよりも、なにか天然記念物をみるような興味深さに近いといった方が適当かもしれない。年齢を感じさせず、いつまでもパワフルで活動的。決して人に媚びないストレートな物言いがまた潔い。テレビが白黒の時代からスマホで見れるようになった現在までの歴史を全て知る人。そんな黒柳さんが、書いた自叙伝が満を辞して映画になった。
これは、観るしかないでしょ。
恥ずかしながら原作本は読んだことはなかったので、真っ白な気持ちでスクリーンに向かう。観終わって感じたのは、この映画は子育てに奮闘する世代のお父さんお母さんに観て欲しい、子育てバイブル的映画なのだということ。
「あなたはあなたのままそれでいい」と優しく背中を押してもらえる映画です。
人と違うのは悪いことじゃない、違いを個性として受け止めて、その個性を輝きにまで昇華させるには、多くの周り人たちの理解と応援が必要だ。そういう意味では、黒柳さんはとても周りに恵まれた人であったに違いない。今の黒柳さんの活躍があるのは、トモエ学園の校長先生との出会い、小児麻痺の泰明ちゃんとの出会い、そして何よりいつもありのままのトットちゃんを受け入れてくれたご両親の愛があったからだと思えます。
SNSなどの発達により、ひと昔前より人とは違う個性を持った人が生きやすい時代にはなってきたのかもしれない。けれど、まだまだ現実社会においては、人と違うことは生きづらさの原因にもなる。
今そんな生きづらさで苦しんでいる人たちにこの映画を是非おすすめします。
「あなたはあなたのままで十分いいのです。」
今年の最重要作
これはすごい。内容レイヤーでも映像や芝居のレイヤーでも圧倒的なものがある。とにかくモブの一人ひとりにいたるまできちんと芝居させていて、誰一人「背景」になってしまっていない。非常に労力がかかっていることは間違いない。子どもたち1人ひとりの動きにも個性があって、描き分けられているのがすごい。
戦前から戦時へと移り変わる様が日常描写の中に挟まれていき、いつの間にか日本は戦火となる。子どもの視点で描かれる市井の変化を捉えている。
「へいたいのうた」を最後まで歌わせないで騒ぎだしてしまうトットちゃんのシーンが序盤にある。とても示唆的だ。戦争プロパガンダが小学校教育に入り込んでいるが、トットちゃんはそれを遮ってしまう。そういうものには与したくないという制作の意思が強くでている。終盤、出征していく兵士たちと真逆に駆け抜けていくトットちゃん。言葉よりも動きで伝える姿勢が徹底されている。小林先生のキャラクターも非常に奥深い。あの狂気の時代に教育を守るためには、ある種の狂気を宿さなければいけなかったのか。
冒頭と最後に、夢の光景のように出てくるちんどん屋だけがそうした戦争の狂気から隔絶された、特権的なものとして登場する。人を楽しませるちんどん屋だけは戦争に侵されずに住んでいる。これも強烈なメッセージだ。
2023年の最重要作だと思う。後年に残すべき一本だ。
窓ぎわのトットちゃん
トモエ学園て今もどこかにあるのだろうか?
トットちゃんがのびのび育っていくのがよくわかる。
ご両親や校長先生、友達、学校と環境が素晴らしい。
決して自然にできあがったもので無く登場人物それぞれが戦時中とは思えないほどいっしょうけんめいに真剣に生きているのが伝わってくる。劣悪な環境に負けずに明るく生きている。それだけで感動ものだ。
物語はトットちゃんのエピソードの連続だが泰明ちゃんとのエピソードはトットちゃんらしさが一番出ていたのではないだろうか?
そして泰明ちゃんのおかあさんが汚れた服をみて涙ぐむシーンにおもわずこちらも嗚咽した。
その後の悲しい結末もこのシーンで深い悲しみも少しは救われたのではないか?
戦時下にもかかわらず、みんなの個性が尊重され、違いを認め合うことでいじめも無いトモエ学園はなぜ、もっと広まらなかったのだろうか?
私の世代からは少し昔の時代だが氷を入れる冷蔵庫や黒電話など昭和レトロ満載。
(残念ながらあのパン焼き器は観たことは無い)
お祭りのさかなの絵を削る板菓子、それになんといってもひよこ。
自分も親に買って貰いこたつの中で暖めたのを覚えている。それでも1週間そこらで死んだので悲しかったのを思い出した。
色んなエピソードが流れる中で戦争はダメということが根底に流れていて見終わった後もすがすがしく感じられた気がする。
そういえば「窓際のトットちゃん」途中までしか読めてなかった。
続きを読んで再度、トットちゃんワールドにひたってみよう。
たくさんのメッセージに溢れた映画
期待通りに感動的
国際線の映像サービスで鑑賞。
映像化してくれたおかげで、本を読んだがでけでは知り得ないことが分かって、面白かったです。
トットちゃんの両親がとても心の強さを持っていて、だからこそ問題児トットちゃんを暖かく育てたこと、その背景にはかなり裕福で洋風の生活スタイルがあったのだなあと思いました。見たことのない形のトースターがあって印象的でした。
ポスターにある木登りのシーンは、本で読んだ時に号泣した記憶がありました。映像で見ると、かなりリスキーな挑戦で、頑張れという応援の気持ちはあるものの、やめた方が良いという気持ちも感じました。
逆に、映像で観て特に感動したのは、二人三脚のシーンで、観戦している親が感激しているのに共感し、もらい泣きしました。
また全体として、校長先生がただ優しいだけでなく信念を持って教育していることも伝わってきて、じわりと感動します。この映画の重要なテーマがトモエ学園の理念の素晴らしさを伝えることなのだと思いました。
御免なさい、全く舐めていました
原作も読んでいないし、予告編を見ていても鑑賞リストには全く入っておらず、「どうせ、奔放なトットちゃんの明るく正しいお話なんでしょ」と期待もしていませんでした。しかし、一足先に観た我が家の妻の評価が高かったので、恐る恐る映画館に向かいました。
申し訳ありませんでした! 全く舐めていました。本作は、素晴らしい映画です。
トットちゃんは主役ではあるのでしょうが、作品の視線はその背景となる時代とその時代を生きねばならなかった人々に据えられ、更に現代へそしてその先へとしっかり届いています。戦争は降って来るものではなく自分の足許からジワジワと広がり、それを自ら広げる人さえ居るという認識も際立っていました。原作発刊時の40年前以上に、新たな戦前が足許から広がりつつある今観るべき映画です。
泣かせ映画には極めて強い僕も何度かウルッと来てしまいました。これはお子さんと一緒に観て欲しいなぁ。
2023/12/21 鑑賞
トットちゃんをトットちゃんたらしめるもの
<映画のことば>
さぁ、今度はどんな学校を作ろうか。
テレビ旭日系列で長く放送されていた「徹子の部屋」で知られていた黒柳徹子さんには、子供時代にこんなエピソードかあったのかと、初めて知りました。
独自の音楽的手法による教育を実践した学校のようではありますけれども。
しかし、子供たちの個性を、こんなにも尊重する教育をしていた私立小学校か実際にあったことも、初めて知りました。本作を観て。
(子供の個性を大切にし、管理教育=文部省(文部科学的省)が決めた学習指導要領どおりの画一的な教育をしない教員を、徹底した懲戒処分で教育現場から排除してきた、どこぞの国かの義務教育学校とは、大変な違いだとも思いました。)
しかも、「きな臭さ」を増して、戦争への道をまっすぐに突き進もうとしていた、それこそ「挙国一致」が声高に喧伝されていた、まさにその時代。
(皆が同じ考え方をし、同じ行動様式をとることを強制され、その考え方に従えない者は「非国民」として、社会からのけ者にされた時代)
その時代に、こんなにも子どもの個性を大切にする学校があり、そういう教育が実践されていたということは、正直なところ「驚き」以外の何ものでもありませんし、そして、こんなにも
個性豊かな子供時代を過ごしたことが、ゲストから多彩な話題を引き出して、長く長く、さらに長くトーク番組を続けてこられた秘訣なのかも知れない。否、それこそが、トットちゃんをトットちゃんたらしめたものに違いない。
その一端が窺われるのだとも思いました。
佳作だったと、評論子は思います。
(追記)
本作で、泰明君の死は、大きな意味があったのではないかと思いました。
トットちゃんについては。
それまで、天衣無縫、純真爛漫(らんまん)に生きてきたトットちゃんにも、世の中の摂理は無縁でないことを、トットちゃんは彼の死で思い知ったと思うからです。
トットちゃんにとっては、未曾有のエポックメーキングな出来事だったのではないでしょうか。
(追記)
まったくの余談ですけれども。
評論子も親に、お祭りの夜店でヒヨコを買ってもらったことがあります。
「カラーヒヨコ」ということで、全身に蛍光色の染料を付けられて売られていたヒヨコでしたけれども。
(言うまでもなく、その着色は、羽の生え替わりで、すっかりなくなってしまった。)
そしてやはり、評論子の両親も(トットちゃんの場合と同じ理由で)反対した記憶がありますけれども…。
しかし、最後には折れて買ってくれたときは「一羽では寂しがるだろうから」ということで、なんと二羽も買ってもらえました。
評論子が買ってもらったヒヨコは、運よく(?)二羽とも成鶏にまで育ちましたが、お
祭りの夜店で売られているくらいですから、それは卵を産まない鶏(つまり雄)。
とにかく、元気で勇ましい鶏だったことを記憶しています。
ちなみに…鶏は「飛べない鳥」といわれていますが、我が家の鶏は、屋根の高さくらいにまでは飛び上がることができていたようです。
(養鶏場で飼われている鶏は、飛ばないように羽の一部を切り取っているとか。)
亡父の転勤で飼えなり、手放すまで大切に飼うことができましたが、今でも良い思い出になっています。
それにしても、二羽も買ってくれた両親ー。
トットちゃんのヒヨコは、一羽だけだったので、寂しくて死んでしまったのでは…というのは、評論子の勝手な心配ということで、およそ間違いはなかろうと思います。
卑しい歌を歌うな
タイトルなし
最高の作品
原作は発刊当時に読了。
当時小学生で読書はそこまで好きでなく人並みだったが、テレビ等で馴染みのあった人物ということで読んでみた。
それまでテレビの人だった徹子が身近に感じられ、巻末の徹子の幼少時の写真に恋した。
その後も原作本は大切に保管。
お陰でいわさきちひろを知りこちらもファンに。
今回それがアニメ化で一も二もなく鑑賞することにした。
映画など年に1本観るか観ないかの小生が。
しかし本作を観ようという同志が周囲におらず劇場に足を運ぶのを躊躇していた矢先、職場の30代部下女子が観たいと言うので遅れ馳せながら年明けに鑑賞。
原作未読という部下には小生のを貸して事前勉強してもらった。
エンディングで目の前がボヤけるも、隣の部下は涙ぐむどころか鼻水垂れ流して号泣。
外に出てもしばらく泣き止まないほどだった。
ともかくも良作との評価をしたい。
作品の寸評だが、既存の寸評・感想に反論めく記述があることをお許しいただきたい。
■周囲の評判
小生の周囲では残念なことに話題にも上っておらず評判もなにもない。
小生の職場には前述の部下の他にパート従業員が30名ほどおり、しかも多くが原作世代で徹子本人や著作のことを知らない筈はない。
中には原作は読んで感銘したという40代や映画好きを自称する30代がいるが、興味は示すものの作品は結局観ていないようだ。
小生が分析するに、やはり宣伝の方向がよろしくなかったのではないか。
原作を読んだにしてもほとんどが数十年前のことであり、内容に関してよく憶えていない者も多かろう。
そしてそれがアニメ化となるも、黒柳徹子というタレントのおてんばな幼少期を描いたコメディとでも捉えられてしまったのではないか。
そしてそれは子供向けであろうとの憶測を生む。
加えて、その子供ら若者には原作を読んでいる者が少ないため、そもそも興味を惹かない。
つまり、大人は子供向けと思い、子供は大人向けと認識、結局鑑賞したのは原作に特に思い入れを持つ一部の大人と、その薦めで観た者に限られてしまったのではないか。
聞けば興行成績は10億に届かなかったとのこと。
その割に評価は高いことがこの作品の立ち位置を如実に物語っている。
非常に残念ではある。
■絵柄のこと
今更述べるまでもないが、賛否両論あった本作のキャラデザイン。
これに抵抗感を覚えて観なかった者も少なくないのではないか。
小生は何をおいてもそもそも観るつもりであった訳だが、客観的に見て違和感があるのは否めない。
しかし本来、人間を描くのに唇がないのはおかしいのである。
戦後日本でアニメやイラストが盛んになる際に写実的な部分(鼻の穴や口唇や爪など)が省略され、それに慣れてしまった我々の感覚が間違っているのだ。
小生としてはキャラデザインも含めてこれほど美しいビジュアルは観たことがないと称賛せざるを得ない。
観れば観るほど愛らしく思える、大変魅力的なキャラデザインと評価したい。
■反戦映画か?
本作は反戦映画なのだろうか?
そう見ることもできるが、小生は反戦映画ではないと捉えている。
原作を読めば解るが、著者は作中で反戦を訴えてはいない。
戦争を生きた者として徹子にも反戦の意思は勿論あろうが、原作に関しては少なくとも反戦を意図して著したのではないだろう。
原作に記した著者の幼少期がたまたま戦時と重なったまでのことであり、戦争に関する記述も著者に関係する事柄以外はことさらない。
従って、それをアニメ化した本作も反戦映画ではないと小生は考える。
しかし、トットが過ごした幼少期の背景としては戦争を外しては語れない事柄であり、中盤以降の戦争に関する描写はある程度必要で、「戦争の描写は不要」・「もっと必要だった」などの賛否があるが、「トットの知らないところで忍び寄る戦争」という視点から、この程度が適切ではなかったか。
もしこれ以上多く、さらに解説など付けようものならたちまち反戦色を帯びてしまうし、なければないで作中の背景描写が薄くなってしまう。
しかし、「火垂るの~」のような深刻な反戦映画を期待して観ると今一つに感じるとの意見も散見されるが、それも無理はない。
主人公は確かに戦争の影響を知らず知らずとはいえ受けたり疎開したり思い出の学校が焼けたりを経験するが、空襲で焼け出されたり両親が死んだり飢えに苦しんだりと自らが悲惨な経験をするわけでもない。
本作では戦争はあくまで背景でしかないことの理解が必要ではなかろうか。
このあたりも原作を読んでいないと伝わりにくい嫌いはあるかも知れない。
■説明のない描写の妙
本作には説明がされていない描写というかシーンが幾つか存在する。
これも原作を読んでいないと理解できない、または伏線として後の下りと併せて理解する必要があろう。
駅の改札口の男性やロッキーがいなくなったことなどは解りやすいが、他にも小生が気になったのは、トットの弟が誕生した経緯である。
弟は誕生した描写がなく終盤で突如登場するが、実はこれには伏線があったと小生は捉えている。
それは、トットが初めてトモエに登校する日の朝、トットの両親が寝室で目覚めるシーンである。
両親がただ眠っている(いた)描写であるが、これがなぜか横楕円の鏡に映されている。
両親を囲んで引き立てるように映す鏡を通してその姿を見ると、その夜に弟が生を受けたのではないかと捉えることができると思うのだが、小生の下衆な深読みだろうか(弟が実際に産まれたのはその数年後であり実際には違うのだがそれを象徴することとして描かれているのではないか)。
それはともかく、作中であえて説明をしない場面は、親子で鑑賞しながら親が子に教えてやることを製作側が意図していたのではないだろうか。
そう言えば筆者も幼少時に戦時を過ごした祖父に当時のことを色々と聞いたものである。
■原作はハッピーエンドだが本作はどうなのか?
原作を読めば解るが、時代背景が戦時中であるにも関わらず、登場人物で戦争に関連して死んだ者はいない。
泰明は不幸にして旅立ったが戦争とは関係がないし、トットの周囲では両親も小林校長も戦後に名を残すほどの人生を各々送ってさえいる。
まして主人公のトットは現在も存命の誰もが知る著名人である。
終盤で産まれた弟は幼くして他界した可能性はあるが、その描写は少なくとも作中にはない。
つまり、戦争がここまで背景にありながら、戦争によっては誰も死んでいないのである(クラスメイトに関してのその後は判らないが…)。
従って、原作を知る我々にとってはハッピーエンドと捉えることができる(否、著者本人は元気で活躍中なのでエンドにもなっていないか)。
しかし、本作だけを観れば、ハッピーエンドというには余りにも悲しむべき結末に終わっている。
ラストではトットが成長した姿が描かれており、そこはこれからを期待させる部分であろう。
ただ、終盤では泰明の死、忍び寄る戦争、そして疎開により先の見えない明日…ハッピーエンドと捉える方が無理だ。
だからこそ、原作やその続編を事前に読んでいていただきたかったし、本作のその後を描いた続編(主人公の年齢的にもアニメでなく実写の領域となろう)を期待したい。
ともかくも、小生にとっては生涯忘れ得ぬ良作となったことは事実である。
前述の通り世間の評判が少ない(評価が低いのではなく観た者が少ない)のが残念でならないが、地上波でテレビ放映でもされれば多くが観るところとなり再評価されるのではないか。
地上波での早期の放映が待たれる。
それにしても、本作のDVDを早速予約して手に入れたは良いが、観るとまた号泣確実なため封を未だに開けられないでいる小生である。
「あのね」をおいそれと聴けないのもまた同じ。
GHQ前の學校
子供の戦争映画NO1
アニメ版トットちゃん
単行本が出たときは、買って読み、とても面白かった記憶がある。
その後は黒柳徹子のテレビ人生を眺めながら、歳を重ねてきた感じ。
やはりトモエ学園の素晴らしさに拍手、今もこのような学校はあるのだろうか。
何にでも興味を持ち、天衣無縫な少女は、周りからは変な子と思われ、これは今も変わらず、みんなが優しい眼差しで見ていけばいいのだが。
ノスタルジーを除いても、とても感動的なアニメーションだった。
彼女を変えた小林先生との出会い
全188件中、1~20件目を表示