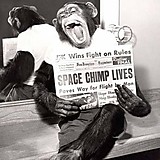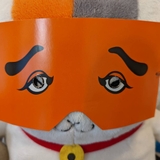私、オルガ・ヘプナロヴァーのレビュー・感想・評価
全32件中、21~32件目を表示
衝動
思っていたものとは違いましたが、映画として、1人の女性の最期を見る物語として楽しめました。
同性愛が認められていなかった70年代、レズビアンだったオルガはそれを公の場で言うことはできず、それを抱えながら生きていました。
暗殺者になりたい衝動から、トラックに乗って大量殺人に移行し、今後誰も殺人を起こさないために自分が死刑になると言う宣言のもと、実際に絞首刑に処されるます。
死刑される直前、やはり生きていたいという想いが強くなって泣き叫ぶシーン、人間味がドバッと飛び出ていました。ここまで基本的には感情を表に出さなかったオルガがこれでもかと感情を出すので、なんだか愛おしくも思えてしまいました。
事件の前後を色濃く描く映画なのかと思いきや、オルガ・ヘプナロヴァという1人の女性の半生を描く物語でした。7年前の映画がこのタイミングで入ってくるというのもなんだか珍しい縁があるもんだなーと思いました。
鑑賞日 5/21
鑑賞時間 20:25〜22:20
座席 G-4
タイトルなし(ネタバレ)
1970年代にチェコスロヴァキア・プラハで実際に起こった事件をモノクロで映画化した作品です。
ローティーンの頃からうつ病に悩まされていたオルガ・ヘプナロヴァー(ミハリナ・オルシャニスカ)。
自殺未遂の末、精神病院に入院するが、そこでも異質の存在として扱われ、集団リンチを受けていた。
退院後は世間から逃れるように、トラック運転手として働きつつ、森の中の粗末な小屋で暮らしていた。
ある日、職場で出会った少女イトカ(マリカ・ソポスカー)に同性愛傾向を感じ取ったオルガは、イトカと肉体関係を持つが、その関係も長くは続かない。
徐々に心の内に澱(おり)のようなものが蓄積していく中、オルガはプラハ市内のトラム停留所にトラックで突っ込み、多数の死者・重軽傷者を出してしまう。
オルガは、それは社会に対する復讐だと法廷で語る・・・
といった内容で、自暴自棄になった若者が悲惨な事件を引き起こすのは洋の東西を問わずだが、オルガの心底にたまっていく澱のようなものは痛いほど感じ取ることができます。
70年代前半のことなので同性愛者に対しては大きな偏見があった時代。
かつ非社交的でうつ病の傾向もあるがゆえ、社会から疎外されている感は徐々に強くなり、社会もオルガを拒絶するが、オルガも社会を拒絶する。
すこしでいいから認められたい。
承認欲求は、人間としての本能であろう。
本能としての欲求を満たされないときの苦しみは、いかばかりか。
だからといって、オルガの行為を許すわけでもなく、映画は劇伴もなく淡々と撮っていく。
感心したのは、裁判後、死刑執行を待つオルガの描写で、独房生活だったオルガは、社会から断絶されることで心の平安を得る。
ここにきて、承認欲求よりも生存欲求の方がはじめて上回る。
泣き叫び、刑から逃れようとするも刑は執行される・・・
淡々と撮り続けた映画は、最期まで淡々とした描写で貫き通す。
エンドクレジットは無音。
無音のクレジットを観るあいだに、心に去来するものをいま一度思い返してみるが、さて、なにが心の底に溜まったのか、それとも払拭されたのかわからないが、澱のようなものでないことを祈りたい。
監督・脚本は、トマーシュ・ヴァインレプとペトル・カズダの共同。
ミハリナオルシャンスカ様が観たくて
ストーリー展開は淡々と進むしほぼセリフも無いし場面展開も結構急なので、かなり集中して観ていないと理解が難しい作りになっている。しかしミハリナオルシャンスカ様の美貌のおかげで観ていられる。
正直オルガに感情移入するのは難しい。オルガという人の人物像が見えづらいためだ。彼女が人と接する場面が極端に少ないし、オルガ以外の登場人物の名前もほとんど明かされない(彼女が他人の名前をほとんど呼ばないため)。オルガの住環境や職場環境の変化も突然起こるので、ほとんど説明がなく、彼女が何を経て今こうなっているのかは彼女の独白でしか読み取る術がない。無愛想で非社交的なレズビアン、それ以上のオルガの情報が観客にもわからない。
そしてこの「オルガのことが側から見てよくわからない」ことこそが、彼女が周りから孤立した要因、ひいては大量殺人を起こした要因なのではないか。誰かひとりでも彼女を理解しようとして寄り添っていればこうはならなかったのではないか。あの医者はオルガのために色々手を尽くしてくれていたようだが、結局肉体関係を持ってしまったようだし。
そんなことを考えながらの鑑賞中、安倍元首相を射殺した犯人や京アニに放火した犯人のことを思い出さずにはいられなかった。社会から孤立し、自分の中で危険思想を育ててしまい、おかしなところにその矛先を向けた犯罪者たち。もちろん絶対に許されることではないが、彼らを生み出す一因として社会そのものがあることを忘れてはいけないと感じた。
社会不適合な自分と重ねた
観たい度◎鑑賞後の満足度△ 「頭のおかしい女がこんな事をしでかしましてな」という描き方をしていないのは宜しい。が、映画としては生煮え。
①同情するでもなく糾弾するでもなく、一定の距離を取って対象を描こうとする映像にはある程度の力が感じられる。
ただ演出力の未熟さからか、脚本の構成力の未熟さゆえか、煮え切らなさ・物足りなさが残る。
②“心震える実話”“チェコスロバキア最後の女性死刑囚”という宣伝文句に惹かれ、予告編での同級生達に虐められるシーンや、「あなた達に死刑を宣告する」という独白、暴走する車の映像から、耐えきれなくなった主人公が同級生たちを牽き殺す『キャリー』みたいな話かと思い“面白そう”と思っていたら全然違っておりました。
まあ、勝手に思い込んだ私が悪いのですが。
③よく考えみれば、実話と云っても事件の有り様や本人の告白というのは事件の後で知るようになったことで、主人公の事件以前の部分は云わばフィクションに近い。死刑の前でも悟ったように粛々と刑場に向かったとか、本作の様に泣き叫びながら看守に引き摺っていかれた、とか数説あるようだし。
原作を書いた人は丹念な取材をいたかもしれないけれども、本人に取材した訳ではないので何処かにバイアスが掛かっていないとま限らない。
“最後の~”というのに簡単に心を惹かれてしまうが、考えたみればチェコスロバキアという国はもう地球上から無くなっているので、単にチェコとスロバキアに分かれる前の最後な女性死刑囚というだけかも知れない。
④と、御託は置いといて、
それがし、透明人間に非ず... 世間の規範に従うことの困難な風来坊女性が異分子の声に無関心な家族に,そして社会に爪痕を遺さんと怨嗟の念を滾らせるマイノリティーの絶望映画!!
1973年、チェコの首都プラハで群衆にトラックで突っ込み、多数の死傷者を出して翌年チェコスロバキア最後の女性死刑囚となったオルガ・ヘプナロヴァーを巡るクライムドラマ。
事故当時22歳のうら若き彼女の、裕福ながら家庭の世間体のために存在を否定され続けた少女時代、そしてようやくありつけた職場と精神病院を行き来する中で世間の無理解と冷笑に苦しみ、被害妄想も相俟って内在する憎悪を先鋭化させていくその姿・・・・・・同性の愛人達との刹那的な享楽に身を委ねつつ幼子のように孤独に打ち震える主人公の姿を主演のミハリナ・オルシャンスカが全身全霊で体現し、モノクロームで寒々として生気の感じられない画造りと劇判並びに劇的な展開を排して淡々と空疎な日常を描くシュールな世界観は観る者の心を鷲掴みにすること請け合いです。
"犯罪映画"といえばギトギトした油ギッシュなものを想像しがちですが、その対極に君臨する一本として好事家にも苦手な人にも観てもらいたいこの静かなる狂気…。
"Collegium Musicum"
確かに『レオン』でマチルダを演じたナタリー・ポートマンのようで『ナイト・オン・ザ・プラネット』のウィノナ・ライダーみたいにお気楽ではないがトラヴィス・ビックルの女性版に思えてしまう、本来なら自己中で胸糞悪くなる物語が演じたミハリナ・オルシャニスカの魅力とボブヘアが似合い過ぎるキュートさに魅了されながらもオルガのキャラクターには理解不能で彼女の人間性に難解で知的な物をゴチャ混ぜに面倒臭さを感じてしまう。
雨が降る中で洗濯物を外に干す、同じく雨の中でテントを張る、布団を掛けてあげる場面と印象的ながら、観ている側の準備が整わない呆気なく起きてしまう顛末に意表を突く展開にすらならない、最後は食卓を囲む家族が映し出され、名も無き自殺者にならない為の行動を選んだ彼女を救える術は何だったのだろう。
プリューゲルクナーベ
1973年、22歳の時にトラックで路面電車の停留所に故意に突っ込み翌年死刑となった女性オルガ・ヘプナロヴァーの話。
家族から孤立している様に感じ、精神安定剤を大量摂取し、と始まっていくけれど、いつの間にか入院し退院し、家を出てて一人暮らししたい?場面転換が急過ぎて、序盤は少々判り難いし、冒頭の件は13歳らしいけど…。
当時は多様性が受け入れられる様な世情ではなかったであろうし、承認欲求とか被害妄想とかそういうものを拗らせた統合失調症なんだろうけど、描かれ方を見るに狂っているという様にはあまり感じられず…まあ、やったことを考えたら狂っている訳だし、収監されてからは本格的にイってしまっていた様だけど。
自殺願望はずっとあった様だけれど、感情が無な訳でもなく、拗らせた思想を加速させていく感じでもなく、なんだか突然の犯行に感じてしまいどう受け止めるべきなのか難しく感じた。
オルガは今なお存在する
鬱病に悩まされ、父親からはDV、母親からは事務的な愛情をそれぞれ受けてきたオルガ・ヘプナロヴァーは、居場所を求めて自立し、自分が同性愛者である事を自覚する。しかし、旧ソ連の傀儡的存在だったチェコスロバキアで暮らす事は容易ではない。
もし彼女がチェコ以外の国で生まれていたら、もし彼女が生まれたのが社会的弱者への施しが70年代よりも手厚かった(完璧とはいえないものの)現代だったら、もし彼女の事を心から理解してくれる人物が1人でもいたら…そんな様々な“たられば”が重なっていたら、彼女はトラックで町の群衆に突っ込む事はしなかったのかもしれない。
華奢で猫背体型のオルガを演じたミハリナ・オルシャンスカは、そのヘアスタイルもあってか『レオン』の少女マチルダ(ナタリー・ポートマン)を彷彿とさせる。マチルダはレオンのような暗殺者になろうとするが、オルガは暗殺ではなく大量殺人への準備を進めていく。
「殺人をしたのは、今後このような事が起こらないようにするため」、そう言ってオルガは絞首刑に処された。しかし現実ではトラックの代わりに銃や刃物、毒ガスを使った無差別大量殺人が繰り返されている。彼女は今でも存在している。
劇伴を一切使わずにドキュメンタリータッチで捉える構成は、近作の『母の聖戦』同様、観客を主人公と同化させていく。つまりこれは、事情は十人十色あれど、人は誰しもオルガになる素養を持っているという事実を体感させる狙いもあるのだろう。
本作を日本配給したクレプスキュール・フィルムは、配給第1作『WANDA/ワンダ』(この作品も劇伴未使用)といい次作『ノベンバー』といい、観客に“問い”を与える作品ばかり。実に骨があるというかクセがありすぎる。
全32件中、21~32件目を表示