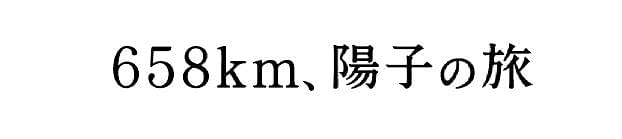658km、陽子の旅 : 特集
【2023年“本当に観て良かった1本”に確定しました】
コミュ障引きこもり女性が東京→青森658kmを旅する
しかもヒッチハイクで!? 菊地凛子の“化け物級演技”
を堪能できる――海外映画祭3冠を達成した珠玉の一作

鑑賞後に「これ、最高だったな」と呟いて、自分の得た感情や言葉を“誰か”に共有したくなる。
そう感じる映画には滅多に出合うことができません。ところが、7月28日公開の「658km、陽子の旅」は、そのハードルを易々と飛び越えてきたんです(この記事を書きながら「やっぱり最高だったなぁ」と言っているほど!)。
「#マンホール」「私の男」の熊切和嘉監督と「バベル」の菊地凛子が“22年ぶりに再タッグ”を組んで描いたのは、心を閉ざした女性の東北縦断ロードムービー。「さて、どう魅力を伝えていくか」と思案にくれていると、とんでもない吉報が……!
なんとアジアを代表する映画祭で最優秀作品賞を含む最多3冠の快挙! そこに含まれていたのは「最優秀女優賞=菊地凛子」。この結果、納得せざるを得ないといいますか……端的に言い表すのであれば、菊地凛子の芝居が“本当に凄まじかった”。
世界的評価も受けた“陽子”の素晴らしさ、観ればきっと心震える。映画.com編集部が実際に観た感想を交え、隅から隅までお伝えさせていただきましょう! この映画、何が何でもおすすめです。
↑あらすじは予告編でチェック!
【レビュー①】菊地凛子の化け物級の演技に震撼――
アカデミー賞候補俳優の本気→この“傑作”見逃し厳禁

試写で鑑賞してからというもの、筆者の頭の片隅には“陽子”が生き続けています。彼女との出会いは、それほど強烈で、忘れ難いものになりました。要因のひとつとなっているのが“初の邦画単独主演”をこなした菊地凛子の存在。
ほぼ出ずっぱりの113分――これってめちゃくちゃ“贅沢な時間”だと思うんです。このパートでは、本作最大級の見どころである“菊地凛子の芝居”について、魅力を紹介していきます。
[“菊地凛子=陽子”から目が離せなくなった理由]
悲哀に心抉られ感情を乱され…“変化”にも圧倒される

彼女の本作での芝居を目撃したら、「凄いものを観た」と声を発したくなるんです。このすさまじい気持ち、早く誰かと分かち合いたい……!
物語は、人生を諦めてなんとなく日々を過ごしている陽子が、父の訃報を受けて“過酷な旅”に身を投じるところから始まります。撮影は物語と同様、東京から青森まで北上しながら行われ、菊地は陽子をリアルに体現するため全シーンノーメイクで参加。不慣れな状況に戸惑い、時に傷つきながらも、彼女は前へ、前へ進む――こうした心情をわずかなセリフと表情、身体の所作で表しているのだから、いやはやマジで凄すぎる。
陽子は長い間引きこもっていたため“寡黙&対人スキル皆無”というキャラクターであり、それをまっすぐに表現するのは実は相当難しいこと。にもかかわらず「雄弁に語らず、多くを動かず」という制約のなかでも、哀しみや苦しみをしっかりと滲ませつつ、徐々に“陽子の中身”を露出していくんです。
陽子がシームレスに変貌していく姿は確実に圧倒されるはず。菊地凛子の演技力はよくわかっていたつもりでしたが、本作の彼女の芝居は、そうした筆者の想像や予想を大きく超えるものでした。これこそが「658km、陽子の旅」を観てよかったと心の底から思い、頭から離れなくなった最大の理由なのです。
[世界に認められた俳優・菊地凛子の経歴]
「バベル」でオスカー候補に アジアの映画祭で快挙

菊地凛子の本作での存在感に魅了されたのは、映画.com編集部だけではありません。アジアを代表する「第25回上海国際映画祭」で、最優秀主演女優賞に輝いたのです! これもまた凄まじいことです。
日本人俳優の最優秀女優賞獲得は、7年ぶり。審査員の講評がかなり的を射ているので、ここで紹介しておきます(審査委員長は、ポーランドの名匠イエジー・スコリモフスキ!)
【講評】映画の中の菊地凛子の表情豊かな目と震える手は審査員たちの心を捉え、キャラクターを内面化する彼女の演技力は“俳優”の存在を忘れさせます。彼女の演技はキャラクターに命を吹き込みました。
「バベル」で演じたろう者の女子高校生役が話題となり、アカデミー賞助演女優賞を含む多数の映画賞にノミネート。そこからは「パシフィック・リム」等の主要キャスト、近年では超大作ドラマ「TOKYO VICE」にも参加した菊地。そんな“世界レベル”という評価を、第25回上海国際映画祭での快挙が改めて強固にしたといえるでしょう。
[菊地凛子はケイト・ブランシェット級]
数多のスターと同じ“スーパーエージェント”が担当

もうひとつだけ、菊地のすごさがよくわかる事実をご紹介しておきましょう。菊地は、米最大手タレントエージェンシー「クリエイティブ・アーティスツ・エージェンシー(CAA)」と契約中。彼女のマネージメントを務めているのが、ヒルダ・クアリー。実はこの人物、業界では敏腕として知られる“スーパーエージェント”なんです。
例えば、オスカー女優のケイト・ブランシェット&ケイト・ウィンスレット&ジェシカ・チャステインだけでなく、ジョニー・デップの娘リリー=ローズ・デップ、日本でも人気のクロエ・グレース・モレッツ等々“超大物”ばかりを担当。つまり菊地への期待値は、彼女らと同等と言っても過言ではありません。
そんな“世界が認めた”俳優の芝居をたっぷりと堪能する“113分の旅路”。同行しないなんて考えられませんよね?
【レビュー②】設定の面白さにも注目! 物語、演出、
“陽子の旅”をさらに魅力的にする重要な要素を紹介

まだまだ感想をお伝えします。「菊地凛子がとてつもない」という点を大前提としながらも、設定、物語、キャラ、演出、そのどれもが語り合いたくなる高クオリティの代物! ここでは作品全体の完成度を底上げしたエッセンスを取り上げます。画面の端々に目を凝らせば、得も言われぬ映画体験が味わえる――。
[絶妙な設定]誰とも関わりたくないのに…
奥手な主人公がヒッチハイクせざるを得ない状況が◎

他人との関わりを遠ざけてきた陽子が、目的地に向かうための手段――それが“ヒッチハイク”。何故そんな、他人に話しかける勇気が超必要なチャレンジを? そう思う方もいますよね。実は、こんな事情があります。
・旅の始まりは、従兄が運転する車に同乗→予期せぬ事態でサービスエリアに置き去りにされる!・従兄に電話をすればオール解決! あ、前日にスマホが故障していた……。・所持金は2000円弱。別ルートで移動する金もない。お金を借りる相手も思い浮かばない。・翌日正午の出棺に間に合わなければいけない=悩んでいる時間がない!追い詰められたコミュ障が、見知らぬ人に声をかけまくる。その光景はクスっと笑えて、時折胸が締め付けられる。この意外性がめちゃくちゃ面白く、初っ端からグイグイと物語に心引かれていくのです。
[刺さる物語]“1日の旅”を通じて描く
陽子の心の揺れ&徐々に芽生えるシンパシー

本作の時間経過は、たった1日。その短いひとときのなかで、陽子の大胆な成長を描くという点も見どころ。他人から心配されていた彼女が「他人のことを心配する」ようになる。言葉を内に溜め込んでいた彼女が「言葉を自ら発信する」ようになる。これまで避けてきた“人との出会いと別れ”によって、陽子の凍りついた心が溶かされていくんです。

物語序盤における陽子には、きっと“とっつきにくい”という印象を抱くはず。もっというと“共感しにくい”人物です。それが徐々に変わっていき、最後には親密さまで感じるようになる。
そして人によっては、こんなことを思うかもしれません。「自分の心の中にも陽子がいるのかもしれない」「知人や親族にも陽子がいるかもしれない」と。たった1日で人間はそんなに変わるのか――はい、陽子は見事に変わります(顔つきさえ違ってみえるほど!)。
[魅力的なキャラ]陽子が出会う人々の存在感が抜群
オダギリジョーは“幻影の父”として登場

“陽子の旅”に現れ、そして去っていく人々のことも忘れられません。「男と子どものいない人生なんて無理」と吐露するシングルマザー、人懐っこいヒッチハイカーの少女、かつての取材地を巡っている怪しいライター、人の良さが滲み出ている老夫婦。口下手な陽子への態度や言葉から、それぞれの“人生”が垣間見えてくるという点も注目ポイント。
とりわけ特異なのが、オダギリジョーが演じる“若き日の父の幻”。陽子の旅に同行しながら、こちらは一切喋らない。そのため、父の幻の前では、陽子は饒舌にならざるを得ないんです。幻という曖昧な存在に対して、とつとつと言葉を紡ぎ続ける菊地。セリフを排しても、確かな存在感を示すオダギリ。エモくて仕方がない。この奇妙な掛け合い、何度も反芻したくなる仕上がりです。
[巧みな演出×必聴の音楽]菊地凛子の“奇跡の瞬間”が
熊切監督の“手腕”×国際的ミュージシャンの“音”で誕生

熊切監督の劇場デビュー作「空の穴」(2001年)にヒロインとして起用された菊地。長い歳月を経て再タッグを組んだ本作について「自分にとっては奇跡の瞬間ばかりを収めた宝物のような作品」と語っています。この“奇跡の瞬間”めちゃくちゃ多いんです。指折り数えてみても、両手では収まりきらないほど――!
印象深かったのが、冒頭&終盤のくだり。両パートともに、熊切監督が“菊地凛子”という才能を信用しきっていることがわかるはず。冒頭では、陽子の仕事や生活の様子、趣味趣向を“セリフ無しの5分間”で説明。そして終盤には、それと呼応するかのように“5分間の長台詞”が差し込まれているんです。
これが圧巻の一言。“心震わすカタルシス”を、劇場の空間で味わってほしい……!
さらに付け加えるとしたら、本作の“音”は必聴。音楽を担当しているのは、国際的ミュージシャンのジム・オルーク。熊切監督とは「海淡市叙景」「夏の終り」「私の男」に続き、4作品目のコラボ! しかも、エンディングテーマ「Nothing As」では「ドライブ・マイ・カー」の音楽を手掛けた石橋英子とタッグを組んでいるんです。
奇跡的瞬間の数々を彩る“音楽”は、映画館の環境で味わえば、その音圧を一層に感じられるはず。本作は“目”だけでなく、“耳”でも堪能できる逸品なのだ!
【“今”観るべき理由は?】“声なき女性”を主人公に
オスカー受賞作に連なる女性映画としての側面に着目
これが本記事で最後の項目です。「658km、陽子の旅」には“ロードムービー”という大枠のジャンルに加え“女性を描いた映画”という特徴があります。ここで「陽子をヒロインに据えた」ということに焦点を当ててみましょう。そこに込められていたのは、製作陣の“熱き思い”。知ればもっと、本作が興味深くなる――。
●陽子に反映したロスジェネ世代 “声なき人”を可視化する試み

熊切監督、菊地、原案・共同脚本の室井孝介、そして陽子は、同年代の就職氷河期世代。本作では、いわゆる“ロスジェネ”とも呼ばれる世代が背負うリアルを表現することに苦心しています。つまり“これまで見えにくかった存在”を映画という装置を用いて、あえて白日の下にさらす。それによって、彼らが内に秘めていた“声”を現実社会へと届ける……という試みが行われているのです。
陽子の背景となっているのは「就職氷河期世代/非正規雇用/独身者」。面倒で解決できないものを心に仕舞い込み、自分で自分を見て見ぬふりをしてきた人物です。そんな彼女が過酷な旅に身を投じることで、過去の確執と対峙し、自分自身を見つめ直していく。一見荒療治にも見えますが、これは“癒しの物語”ともとらえることができます。映画終盤の陽子の姿は、確かに“殻を破った”という印象を与え、それゆえ観る者の心も確かに癒やしてくれるのです。
●「ノマドランド」「エブエブ」の系譜に連なる作品 邦画としては“新しい主人公像”

近年のアカデミー賞作品賞を受賞したタイトルには“名も無き中年女性”を描いたという共通点がありました。「ノマドランド」に登場した“現代のノマド”として生きるファーン、「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」の平凡な主婦・エヴリン。社会の片隅でひっそりと生きていた陽子にも、彼女たちの姿がダブって見えることでしょう。
さらにいえば、陽子は邦画として“目新しい主人公像”だと言えるんです。他人との関わり合いは苦手だが、ひとりの時間を楽しむという余裕はある。陽子のような人は“今の世の中”のどこかに必ずいます。社会が注目していなかった(=見て見ぬふりをした)だけなんです。そんな存在に光を当てる――これが「658km、陽子の旅」の功績であり、唯一無二の作品へと昇華している重要なポイントです。
【結論】二重の発見を味わえる!滅多にない鑑賞体験
映画館で“陽子の旅”に同行しませんか?

筆者は既に作品を鑑賞した身ではありますが、公開日当日、映画館へ“陽子”に会いに行こうと考えています。それほど大切な作品なんです。だからこそ、最後に改めて猛プッシュしておきます。
本作は世界で大きく羽ばたき、上海国際映画祭で激賞された“菊地凛子の才能”を再発見し、知らず知らずのうちに見過ごしていた“声なき人”の存在を改めて見つめる作品です。つまり“二重の発見”ができる。そんな貴重な体験、映画ファンであればスルーするわけにはいきませんよね? ヒッチハイクをしてでも、映画館へ向かう価値がある作品です。