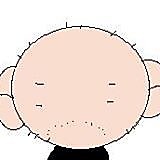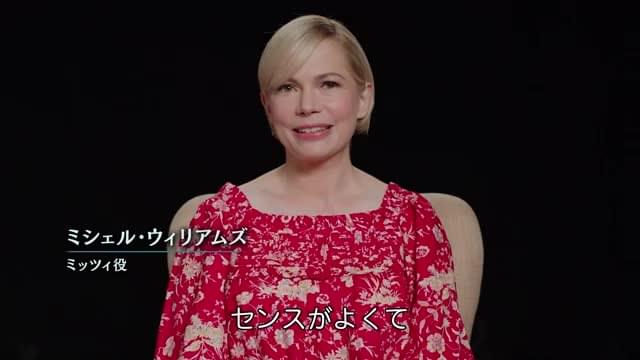フェイブルマンズのレビュー・感想・評価
全390件中、321~340件目を表示
少年の未来を信じた家族の物語
成長期の少年と、それを支えた続けた家族。
家の中では太陽のように明るいママ
時に、月のように透き通ったママを
「ママは泣かさない」と守る少年。
一方、映画へのアイディアは少年を熱狂させた。
「あれはETの場面だ」と思うシーン。
また少年の演出に一変、涙する俳優役のシーン。
キャメラを覗き込み走り回る少年の姿に見た未来。
しかし、少年は悩んで、悩んで、すごく悩んだ。
「映画は事実と違う」それは分かっている。
自分には才能はないのか?と全てを諦めかけた。
そして、あの人の言葉。
ぶっきらぼうだけど、その言葉は少年の心に光を与えた。
、、、終わりはあっという間 !!
「えぇ〜! もっと観たいのに」と心の中で叫んだ。
でも、この後の物語は、少年の未来は、
すでに世界中の誰もが知っている。
この映画の続き、何百倍もの映画の時間をくれた
スティーブン・スピルバーグに感謝したい。
※
【”寓話を語る男。”映画に魅入られた青年の半生を、彼を優しく育てる両親や父の友人、そして級友達との関りを通して人生の痛みや、映画の持つ力や魅力に青年が気付き、更に映画道を究める決意を描いた作品。】
ー ご存じの通り、"fable"は、寓話を意味する。
つまり、主人公、サム・フェイブルマンとは、”寓話を語る男”となる。
スピルバーグ監督の今作への想い入れが伝わって来るタイトルである。-
◆感想
・物語は幼きサム・フェイブルマンが有能なコンピューター技師である父(ポール・ダノ)と優しくピアノを弾く事を愛する母(ミシェル・ウィリアムズ)と3人で映画”地上最大のショー”を観に行くところから始まる。そして、サミーは、映画の中で列車と自動車が正面衝突するシーンを見て、家に帰ってからも”衝突ごっこ”にふける。
ー あのシーンは、どう考えてもスピルバーグ監督の初期傑作の「衝突」に繋がっていると思う。-
・映画に嵌ったサミーは、トイレット・ペーパーをフル活用して、妹たちにミイラ男に変身させる。そして、その姿をサミーは父の8ミリカメラで映して行くのである。
ー 今作では、常にサミーは映す側に立っている。-
■フェイブルマン一家には、常に父の親友ベニー(セス・ローゲン)がいる。そして、父が腕を買われてGEに会社を変わる時にも、妻の進言で、ベニーも一緒に付いてくる。そして、ある夏の日にサミーが何気なく撮っていたフィルムに映っていた母と、ベニーが親しそうにしている姿。
ベニーは家族にはそのシーンをカットして見せるが、徐々に母に反抗を始める。
そして、理由を問う母に、一本のフィルムを渡し、自分の衣装が掛かっている小さな部屋で母に見せる。
このシーンは、サミーの母に対する優しさと、遣る瀬無さが伝わって来て、胸に沁みる。又、母を演じたミシェル・ウィリアムズの”貴方が考えているような事はしていないのよ‥。”と涙ながらに訴える姿も。
母は、父を愛しながらも、ベニーにもプラトニックな想いを持っていた事が分かる。
だが、このことにより、父がIBMへ再び職を変えた際に、ベニーはついて来ないし、両親の関係もギクシャクし始め、離婚してしまうのである。
・サミーは、転校前の高校では、戦争映画なども、級友達を集めて取っている。
ー 彼が一人生き残った兵士役の青年に言った言葉。”部下が皆、殺されたんだ・・。その想いを映したい。”そして、青年は涙を流しながら、倒れた兵士たちの間を、ゆっくりと歩いて行くのである。彼の映画センスや、戦争に対する想いが表現されているのである。-
・サミーが慣れない土地で、ユダヤ人である事を級友ローガンやチャドに揶揄されるシーン。そんな彼は、高校の卒業記念映画を撮影する。
ー 海岸で燥ぐ級友たちの姿を映す様も、例えばカモメを取った後に、級友たちの顔にアイスを落とすシーンを入れたり、一工夫している。
そして、自分に嫌がらせをしたローガンが、砂浜でのリレーでトップでテープを切る様を撮ったりもする。そして、彼の映画がプロムで流された際に、ローガンとチャド(彼は記念映画では散々な様で映っている。)は、サミーを呼び出す。が、ローガンはチャドを殴りつけ、自分はロッカーに背を預けながら座り込み涙するのである。
サミーが映画でローガンに訴えたかった事。それは、人種差別はイケナイという事だったのである。サミーは心に痛みを覚えながらも、映画が持つ力にも気付いて行くのである。-
・サミーは大学生活に馴染めず、主にTV映画を製作する会社に、メデタク入社する。そこで、彼を待っていたのは・・。
ー ビックリしたなあ。「駅馬車」「怒りの葡萄」などのポスターが額に入れて飾られている部屋で待つようにと言われたサミーの前に現れたのは、ジョン・フォード監督であり、それを演じているのはデイヴィッド・リンチ監督である。
1900年代の前半から中盤のアメリカの大監督を、1970代から2000年代に掛け、カルト的な映画も含め数々の傑作を制作した監督に演じさせるとは・・。-
<今作は、御存じの通りスティーヴン・スピルバーグ監督の半生を描いた自伝的作品である。
そして、今作は幼き時に観た”地上最大のショー”で、映画に魅入られた少年が、青年期に映画製作を通して、人生の痛みや喜びを学んでいく様を、見事に描いた作品でもある。>
夢を追う少年の苦悩と成長の物語
人並みではいられない
スピルバーグの生い立ちを
家族の物語ですね。
文句なし!スピルバーグの作品への思いが伝わる
スピルバーグの自伝期を作品にしたが、全然違和感がなく、フェイブルマンの成長期を垣間見る事が出来た。彼の成長期での出来事をもとにヒット作のヒントとなっているのかと肌で感じた。シーンはネタバレになるので省くが、一つ一つのシーンに作品のヒントがある。これを見つける楽しみが本作品にはある。また、作品を通じて家族との愛、絆、人種差別についてもう一度観客に考えてほしいとのメッセージも含んでいる。スピルバーグの半生期ながら色々考えさせられた映画。見事でした。
普遍的な家族の物語
スピルバーグが自伝的映画を作ったと聞いて、一体どんな映画になるのか、もしかしてあの作品やあの作品の裏話が見られるんだろうかと楽しみに、公開日初日に鑑賞。
結論から言うと、本作はスピルバーグのアバター、サミー少年が映画作家として歩きはじめるまでを描いた物語だった。幼少期両親と一緒に見た初めての映画に衝撃を受け、プレゼントの鉄道模型とミニカーでそのシーンを再現するところから、映画製作に夢中になったサミー。
最初は妹たちと、やがて友人たちと8㎜映画を作り続けながら、サミーは成長し、映画の娯楽性と残酷さの両方を知っていく――というストーリー。
スピルバーグの自伝というと、映画作りに物語がフォーカスされていると思ってしまうけど、本作はもっと普遍的な家族の物語なのできっと多くの人の心に刺さると思うし、ほぼ3時間と長尺な映画なのに、体感ではあっという間に終わってしまった。おススメ。
"映画"を巡るある家族の日常
感想
現在の"巨匠"と呼ばれるに至るまでの半生を、鮮烈なサスペンスパートを取り込みつつ描いた、愛と抱擁の作品だった。
・物語構成
スピルバーグ監督の半生を取り入れた自叙伝作品。幼少期に両親と映画を観た事で、映画の魅力に取り憑かれ、母親から貰ったカメラで日々自主制作映画を撮るサミー。ある日、カメラに映っていたある場面が家族の絆に亀裂を入れる...。といったあらすじ。
スピルバーグ監督が映画業界人になるまでの経過をフィクションの設定と物語ベースの中でも随所に感じられる細やかな脚本だった。特に親の視点主軸で進む本作は、無垢な少年と、仲の良い家族を形作る事に常に徹する親の視点の違いを描き分けられていると感じられた。
個人的には、幼少期の頃から本格的な映画づくりをしていて、家族やボーイスカウト、学校のプロムパーティなどの多人数の環境で披露して生活してきたという部分に現在の"巨匠"となる部分の片鱗を感じられて嬉しくなった。
意外だった要素にサスペンスパートがある。家族のある秘密に気づいてしまう、往年の昼ドラ的展開。この展開は予想していなかったので、素直に驚かされた。
この事実を知った後の家族への接し方についても、スピルバーグ映画らしさを感じられて感動した。
他にもユダヤ系出身である事に対する迫害についても、監督自身の経験から描かれていると思われるイジメ描写に生々しさを感じられた。
・スピルバーグ印
スピルバーグ監督ならではの、美しい場面作りは今作で健在で観やすかった。
総評
スピルバーグ監督の原点を垣間見れる傑作。監督自身の物語としてだけではなく、観客も共感できるメッセージ性の強い物語に没入できた。
映画監督とは
芸術を取るか家族を取るか
スピルバーグの自伝、といっても、映画監督になってからのキャリアの話ではなく、青年期までのスピルバーグとその家族についての映画です。
夢を持つ子供とその一家の物語として楽しみました。
「芸術を取るか家族を取るか」という問いが、この映画の一つの主題のように思います。
科学の道を極める父親や、ピアノを弾いたり踊ったりと「表現者」な母親。
家族それぞれに芸術肌な一面があり、よく言えば個性的、悪く言えば収まりの悪い家族に見えます。
芸術を極めることと、家族の一員として生きることは相反することで、夢を追う人はいつでも、どちらを選ぶかという選択を迫られているのだと思います。
夢を追う人だけでなく、その家族にも見てほしい映画だなと思いました。
最後のワンショットがとてもいい!
映画の時間から何十年も経って、今も生き生きとカメラを持っている「少年スピルバーグ」が最後に出てきてくれたように感じました。
他の作品をもう一度見かえしたくなった。
劇中のサムの体験のひとつひとつがスピルバーグのの作品に影響を受けているのではないかと思えた映画でした。まだまだ話は続くので、ぜひ続編を期待したいです。
表現者へのエール
良い意味で思ってたのと違った!
勝手にノスタルジックな映画愛に溢れる作品だと思っていましたが、自分らしくあることへの犠牲と覚悟…スピルバーグ監督から、今この時代に“表現”しようとする全ての人たちに向けてのエールでした。
そして、観客の私たちにも…ラストショット。カメラを覗く作り手の目線に「これから作られる映画たちをお楽しみに!」と言われた気がしました。
全編、光と影がとても印象的です。
映画は光と影の芸術だからですね。
映画の持つ光と影、良い影響があれば悪い影響もある。
そして人間の持つ光と影。
光だけのものはない。両方あるから複雑で美しい。
自分自身に正直に生きること、自分自身を表現することは、誰かを犠牲にしたり、傷つけてしまうこともある。
「でも、それを怖れないで。」
同じくアカデミー作品賞にノミネートされている『イニシェリン島の精霊』にも通じるテーマだと感じました。
世の中には自らを表現せずには生きられない人間と、表現しなくても生きられる人間がいる。どちらも良くてどちらも悪いけれど、自己表現や自己主張には区別と選択が伴う。
何かを選ぶということは、何かを捨てるということ。
『イニシェリン島…』はかなりストイックに突きつけてきますが。笑
女性問題から多様性ダイバーシティへ。環境問題からSDGsへ。
この数年で社会は成長した。
お互いに認めあう世の中で、自分の思いを表現することは、時として配慮が足りないと指摘されることもあるだろう。
「でも、それを怖れないで。」
『フェイブルマンズ』は悲しんでいる家族を前にカメラワークを考えてしまうような…どうしようもなく表現する側の人々を勇気づける作品だったと感じます。
映画がもたらすドキドキやワクワクに魅了された少年は、映画でメッセージを伝えることができることに気づきます。
役者の演技はもちろん、編集や様々な技法で表現された映画は、人々の心に深く入り込み、非常に影響力を持ちます。
なかでも興味深かったのは、虚像に対する苦悩。
これは観客にも責任があり、社会が成長したように、観客も成長しなければならないと感じました。
一昔前だとドラマの敵役はファンから嫌われたりしました。
さすがに今どき、悪役だから悪い人だと思う観客はいないでしょうが。
映画マジックが生んだ虚像を、演じる人に重ねてしまうこと自体は、今もなおあるのではないでしょうか?
あまりにもリアルな演技だと、あたかもその人自身のように感じてしまいますが、
正義のヒーローを演じた役者に、プライベートでも同じイメージを求めていないでしょうか?
人間なので間違うこともあるのに、ガッカリしすぎたり、必要以上に注目して大騒ぎしすぎていないでしょうか?
さすがに昔のゴシップやパパラッチほどタチの悪い暴かれ方は無いにせよ、逆にSNSなどで縮まった距離からの過剰な反応には、いくら夢を売る商売の人とはいえ精神がもたない。
観客も分別を持って作品とは切り分けて見るように、成長しなくてはいけない気がしました。
使い捨ての消費社会も描かれていて、今の感覚からすると本当に衝撃です。
今とは全く違う社会の価値観の中で生まれた作品たちは、その当時のテーマを当時の尺度で描いている。
昔の映画で描かれる価値観や倫理観を責めて作品を排除するのではなく、見る側の観客がきちんと作られた時代を加味することで学ぶべきテーマが見えてくると感じます。
今までに作られた映画へのリスペクトと、これから作られる映画へのリスペクト。
引き算の余韻に巨匠の余裕を感じました。
おまけ
ある学生から「映像を作る時に、自分の作品が誰かを傷つけるのが怖い。どうしたらいいでしょうか?」と質問され
「そんなことなら作るな。それが怖いなら作る資格がない」と答えたのは、大島渚賞の審査員である坂本龍一さんです。
主人公のサミー少年が、両親に連れられて初めて映画館で映画と言うもの...
主人公のサミー少年が、両親に連れられて初めて映画館で映画と言うものを鑑賞し、衝撃を受け、その後の人生に大きな影響を与える様は、自分自身にも少し当てはまり、とてもワクワクしました。誰しも、人生で大きな影響を受けたであろう作品との出会いがあり、彼の衝動や、この上手く表現しがたい高揚する気持ちは共感できるのでは・・・?
物語は、いかにしてサミー少年が映画製作に人生を捧げるようになるか、家族との物語を中心に描かれており、特に芸術的センス面で非常に影響を受けた母親との描写は印象的。反対に、映画製作を単なる【趣味】と決めつけ、現代社会に無くてはならない、当時は最新鋭のモノづくりに多大な影響をもたらしたであろう父親との関係も印象的。
1960年代以降のアメリカ社会の描写にも、とてもワクワクさせられた作品でした。
それにしても、彼の映画製作のセンスは、あの時代のかなり幼い時期に既に確立されていることは、非常に興味深かったです。本作鑑賞後、改めて彼の代表作を観ると、新たな発見があるかもしれないと感じます。
想像してたのと違ったが、、、
試写会にて初めて視聴しましたが、生い立ちエピソードは短めで初監督作品から現代に至るまでのエピソードをメインだと勝手に思っていました、、、。
そしたスティーブンスピルバーグ監督の壮絶な家族関係に正直びっくりという言葉しか出て来ませんでしたが母をきっかけに今至ると思うととても考え深い作品だなと思いました。
続編を期待したいですがなさそうです、、、。
ひたすら映画愛を語る青春時代を描く作品かと思いきや、シリアスな家族...
ノスタルジックで映画愛あふれる作品でした。どの登場人物の視点で観る...
ノスタルジックで映画愛あふれる作品でした。どの登場人物の視点で観るかによっても印象が変わってくると思います。それぞれ個性的な父母などキャスティングも良かったです。何といっても最後のあの大物役をあの監督にやらせるセンスにときめきました!
全390件中、321~340件目を表示