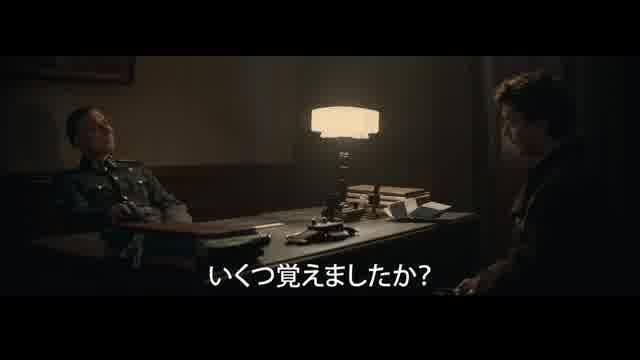「偽らなければ生きられなかった」ペルシャン・レッスン 戦場の教室 つとみさんの映画レビュー(感想・評価)
偽らなければ生きられなかった
デタラメなペルシャ語を教えるという、字面だけだとコメディのような物語だが、中身はものすごくシリアスなホロコースト系作品だ。デタラメペルシャ語を言うシーンでクスリとも笑えることはない。
そして、ユダヤ人が大変だったとか、可哀想だとか、そういった一般的なホロコーストものを超えて、サスペンスとして面白いことに驚く。
更にサスペンスとしての面白さも超えていくエンディングにまた驚いてしまうのだ。
コッホ大尉のペルシャ語がデタラメであることが発覚する空港のシーンで、拘束される大尉の姿に傷ましい気持ちになった。大尉が割とイイ人だったからだが、掘り下げていくと主人公との共通点が見えてくる。
大戦に突入する前のナチ党は、現代の人が想像するようなものではなかった。ドイツの経済を回復させたまともな党だった。
その裕福さに憧れてコッホ大尉は入党したのである。より良い幸せを掴むために。
そしてヒトラーが台頭し、党は増長、大戦に入り虐殺まで始めることになる。ただ幸せになりたかっただけのコッホ大尉は気が付けば泥沼にどっぷり浸かってしまっていた。もう離党など出来ない。そんなことをすれば死刑になってしまうから。つまり、党のやっていることに反発を覚えながらも保身のために現状を受け入れるしかなかったのだ。主人公ジルが保身のために自分がペルシャ人だと嘘を言ったように。
ある意味で、主人公ジルもコッホ大尉もナチ党に翻弄された被害者だったといえる。
だからラストで、連行されていく大尉の姿がいたたまれないのだ。
主人公とコッホ大尉だけではなく、登場人物の多くが自身の望みのために何かを偽っているところも面白い。嘘で利益を得ようとしている。
デタラメなペルシャ語というどデカい嘘に準ずるように、誰もが正直ではなかった。誰もが正直ではいられなかった。
一本筋の通った傑作級サスペンス。本当に面白い。