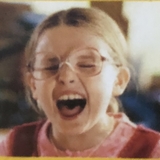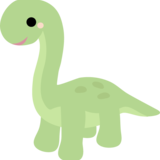聖地には蜘蛛が巣を張るのレビュー・感想・評価
全126件中、21~40件目を表示
裁き
一番驚いたのは、犯人もだが、
犯人の妻と息子の言動。
16.,7人殺した殺人犯であるのに、
妻は息子に
「お父さんは無実よ、何もしていないわ。町のゴミを掃除しただけよ。」と言う。
娼婦だとゴミという認識。
宗教の違いが影響するのだろうか。
娼婦なら殺害されてもいい、寧ろ、殺害してくれて感謝する人々がいるという国情。
娼婦という性を売る仕事の捉え方の違い?
娼婦も好き好んでの仕事ではなく。
さらには、
妻や息子が殺人犯である父親を毛嫌いすることなど毛頭なく誇りに思うところもチラホラ見え無実を訴える姿。
本人が、全ての殺人を認めているにもかかわらずである。
娼婦以外の殺人にならどう感じたのだろう。
多分殺人犯本人は、世間の思いとは裏腹に、ただただ娼婦を殺すことに快楽を覚えていたに過ぎないと、観て感じた。
この国の司法制度にも驚くばかりである。
アレは、油断させてジタバタさせない為か?
友人と検事が来て逃がす算段を打ち明ける。
これが罷り通るなら未来は無い。
ドキドキして処刑の場面を見守ったが、
処刑場面を見ることができる自分は非人間的にも感じてしまったが。
(我が国の数年前のオウムの時など一人を除いては、国が殺した、とジョックを感じたのに勝手なものだ。本作のは娼婦ではないが安心した)
無事、そう、この言葉が入る。
こんな人間、外に出たらエラい事になってしまう。
一応ちゃんと裁いてくれた。
ジャーナリストの勇気に感服。でも、二度としない方が良い、と思った。囮捜査は危険。
娼婦の扱い
2000年代初頭、イランの聖地マシュマドで、娼婦ばかりを狙った連続殺人事件が発生。蜘蛛殺しと呼ばれる犯人は「街を浄化する」すると声明を雑誌に送りつけ、住民は不安になる。妻子持ちのザイードは、家族に犯行を知られないようにするも、自らの行いに使命感を持っていた。女性ジャーナリストのラミヒが、警察をあてにせず事件を追う。
実際の事件をもとにした作品。娼婦ばかりを狙ったシリアルキラーは、いままで何人も実在して、そのおぞましい精神が注目されます。今作で目を引くのは、それよりも周囲の反応でした。街を浄化するするという犯人を英雄視し、息子は胸をはる。娼婦に対するあまりの扱いに、驚きました。イランの裁判や刑罰も興味深いです。
後味の悪さが残る
連続殺人事件の犯人を追う過程の中で、イランという国が抱える女性の差別問題について考えさせられた。同じ女性として、なかなか辛いものがある。宗教と国家が絡み合うことによって余計に複雑になり解決できない問題になってるんやろうな。女性の命がこうも軽いとは…
普通の家庭がありながら、浄化という名のもと自分の殺人を正当化しようとする犯人にもゾッとするが、一番最後の子どもの感想で絶望的な気持ちになる。まさに負の連鎖。誰か教えてあげる人がいないとあの子は犯罪者になるやろうな。
犯罪が無実化する寸前
メインの内容はよくありそうな殺人話しだったが、驚いたのがその殺人が許されそうだった事。家族は何もわかった上で無罪とか、息子は後を引き継ぐか迷ってるって。
頭がおかしいが、国や宗教の違いなのか、常識の違いにビックリ。国民皆んながそうではないが。
結局助けてやるって話は何だったのか?
死刑されて良かった。
実はおもしろい。
凄惨で恐ろしい映画
良かったのだけど、おっさん結局ただの変態なんじゃ、という描写が要ら...
みごと
人ごろしを英雄視する世界
主人公の女性記者こそ架空だがイランのマシュハドで16人の売春婦が殺害された実話にもとづいている。
映画の撮影中当局からの妨害に遭ったほか主演のザル・アミール・エブラヒミがカンヌで女優賞をとるとイラン文化省からフランス政府に「侮辱的で政治的動機に基づく行動」との抗議声明が発表されたという。のちにエブラヒミは何百という脅迫を受けたとCNNに語っている。
ザル・アミール・エブラヒミはもともと2000年代にもっとも人気を博したイランのテレビドラマのヒロインだったが、セックステープが出回って謹慎を余儀なくされたばかりでなく、誹謗中傷の標的になりイランからフランスに亡命したという来歴がある。──そうだ。
イスラムの男社会に蹂躙され放逐された彼女のキャリアは気骨ある女性記者を演じるのに適任で、冷たく射るような眼窩から屈強な信念を感じ取ることができる。
映画は一種のクライムサスペンスで殺害シーンなどリアルに描いているがその怖さよりも16人もの女性をしめコロした男を“聖地を浄化した英雄”と崇めるイスラム社会のほうがずっと怖い。
おりしもテロ組織ハマスの奇襲攻撃(2023/10/07)があり、ニュースは第5次中東戦争が勃発したと叫んでいるせいもあって、余計にこの映画の背景にあるイスラム世界にストレスをおぼえた。
(無知な素人の雑感に過ぎないが)宗教がらみの国家はまともじゃない。ヒジャブの問題にしろかれらは弱者を迫害するのがどう見ても好きな連中だ。
監督のアリアッバシは(ネットで拾い読みしたインタビューの中で)「彼らはセクシュアリティに取りつかれている」と言い、イランという国は当局が「女性を辱めることにある種の快感を得ている」と指摘していた。同感だった。
(真偽は不明だが)Tiktokにハマスらがイスラエル南部でおこなわれていた音楽祭を襲撃し裸にむいた民間人女性をトラックの荷台にのせて「アラーは偉大だ」と叫んでパレードする様子があがっていた。女性はたんにふせているのかシんでいるのかはわからない。親近者がかのじょの足にほどこされたタトゥーから識別・確認したそうだ。
宗教や思想下では善悪が形骸化するものだ──と考えてみても、わたしたちの日常とあまりにもかけ離れた残虐な世界線を受け容れることができない。なぜそんなことをするのか。なぜそんなことができるのか。
この映画が怖いのもわたしたちの世界との違い──あまりにもかけ離れていること──によっている。解りやすく言うと(解りやすくなるか不明だが)マシュハドの夜街頭に立たなければならなかった女性と大久保公園の立ちんぼの違い──のような。
だいたいわたしたちの世界線では勘違いした新聞記者が反体制映画を書いたとしても“当局”から叱られるなんてことはない。
名誉殺人
一族の女性が婚前交渉や不倫をしたり、あるいはレイプなどされるとそれを一族の名誉を汚したとして残虐な方法で殺してしまうという風習がイスラム教圏の国を中心として今でも行われているという。
男は女性に貞淑を求める傾向にある。そのような男の歪んだ願望が高じて自由恋愛などをする女性を否定し、宗教的教えを曲解して結び付けた結果、風習として長きにわたり地域社会で行われてきたのだろう。
本作の娼婦連続殺人もそんな名誉殺人と同じ延長線上にあったものと思われる。なぜなら犯人に対して多くの大衆は共感して賛辞を贈っていたからだ。性に奔放でふしだらな娼婦は殺してもいいんだというように。
人類史上女性は肉体的に男性に劣るという考えから女性に対する差別は古代からあった。それが特に西洋では宗教がはからずも後押しして女性差別が長きにわたり社会に根付いてしまった。
例えばイスラム教には家計は男が支えるものという教えがある。これは単に男女の役割分担を定めたものだが、この教えは家父長制と親和性が高く、女性差別を正当化する口実になってしまった。
女は男に従い、家に収まっていればいい。男の言う通りおとなしくしていろと。このような考えが根付いてしまったがために、女性の生き方や性格まで自分たちの都合のいいように押しつけてそれに反するなら殺してもいいという発想が生まれる契機になってしまったんだろう。
このように差別されてきた女性たちは男性のように自由に職には就けず、貧困の中、身を売るしかほかに方法がなくなる。つらい仕事ゆえドラッグなども手放せない。そんな状況下に女性を追い込んでおきながら、薬まみれの汚らわしい娼婦だと蔑む男たち。
連続殺人についても警察は野放し状態で本気で捜査する気もない。娼婦がいなくなれば町が浄化されて結構なことだと言わんばかりだ。
本来なら女性の地位を向上させて売春せずとも生きられる社会を作ることこそが浄化といえるだろうに。真に浄化すべきはこんな男社会だ。
宗教によって後押しされて長きにわたり社会に根付いてしまった女性差別。犯人は処刑されるもその息子が後を引き継ぐかのようなラストで終わるさまを観て差別の根深さを感じさせられた。
ちなみに夫婦選択的別姓に反対してる人たちは日本の古き伝統たる家父長制を守るべきだと主張してるけど、日本においては江戸時代まで家制度自体はあったが、家父長制のように父権が強いわけではなかったし、夫婦も別姓が当たり前だった。それを明治政府が日本を西洋化するために家父長制を取り入れて夫婦同姓を法制化しただけのことなんだけど。
一筋縄では行かない事件の背景を描く
2000年〜2001年にかけてイランで実際に起きた
「娼婦16人殺害事件」
監督のアリ・アッバシは、イランにいた2000年当時20代の若者で、
実際の事件を見聞きしている。
殺人犯サイードが「娼婦殺しは街の浄化である」
そう言い切るサイードは全く罪悪感を感じていない。
しかも多くの市民がそれを支持する様子を傍観していた。
スウェーデンの大学に進学してそれから20年が経つ。
アッバシ監督は前作の『ボーダー二つの世界』の成功で今作の資金調達に
道筋がつく。
イランでの撮影許可は下りず、ヨレダンで撮影を敢行する。
一見センセーショナルな「娼婦16人殺害事件」
その事件の取材に関心を持ち解決に導く努力をするのが、
女性ジャーナリストのラヒミ。
彼女は囮捜査まで敢行してサィードの検挙に導く。
彼女の徹底的な不信感。
警察を疑い、弁護人を疑い、検事も疑う。
実際に演じたザーラ・アミール・エブラヒミはSNSの
中傷によりイランを捨ててフランスに活動を移した女優である。
その硬い表情に世界への不信感がリアルに浮かぶ。
そして自分の殺人を「街の浄化である」と主張して
「正しいことをやった」と堂々と語る犯人サイード。
聖地アシュハドの街娼は「殺しても構わない有害な存在」
一般市民やサィードの妻、母親などの家族が英雄視される
サィードを認める。
この映画で何より恐ろしかったのは、サイードの息子のアリ。
まだ少年であるアリが幼い妹を実際に被害者に見立てて、
殺人を再現するシーン。
その嬉々とした表情に第二のサィードの狂気を引き継ぐ姿を
見てしまう!!
イランに限らず女性蔑視、女性嫌悪、女性差別は根強く残っている。
狂気に満ちた世界。
冒頭で暗闇に一本のハイウェイが俯瞰で写されて、
聖地マシュハドの全景の夜景が蜘蛛の巣のように開けて行く。
聖地は殉教者も娼婦も殺人者も呑み込んで、
闇に大きく蜘蛛の巣を張る。
イランの聖地で起きた娼婦連続殺人と世界の繋がり
実話に基づいた映画
映画が作られる元の話は、2000年から2001年のイラン第2の都市であり、シーア派の聖地でもあるマシュハドで起きた娼婦連続殺人事件である。16人の娼婦が犠牲となった。この事件を題材にした映画はこれが初めてではなく、「キラー・スパイダー」という映画が既にあった。この映画の製作者は今回映画を盗作だと主張しているらしいが、鑑賞する側としては、別の視点で事件を見ることが出来るので歓迎だ。
事件の背景に宗教の聖地の保守的な雰囲気
殺人の対象はすべて娼婦であり薬漬けにまでなっているものもいる。そんな彼女たちを殺して「浄化した」と新聞社に事を起こす度に通報するという行動に彼になかにある歪んだ正義感、偏狭な世界観が浮かび上がる。街を恐怖に陥れた事件だとしているが、犯人の行動パターンは知れ渡っており、犯人を英雄視する雰囲気があり、それが逮捕後に大きな運動となる。この映画は「イラン政府への批判でも、腐敗した中東社会に対する批判でもない。一部の人達、中でも女性に対する人間性の抹殺は、イランに限ったことではなく、世界中のあらゆる場所で起きている。(映画の公式HP日本版「『聖地には蜘蛛が巣を張る』が描くもの」より)と説明しているが、当のイラン政府がそう理解しないことが想像できる。実際、イランの文化・イスラーム指導省の映画機関は、カンヌ国際映画祭が本作に女優賞を授与したことを「政治的な意図を持った侮辱的な動き」と非難する声明を発表したとのことである。
本当の驚きは最後に
ストーリーは殺人犯は誰かというようなものではないし、犯人とそれを追うジャーナリストの駆け引きというようなサスペンスでも全くない。だから殺人事件の犯人が捕まって終わり、ではない。映画の展開は後半になるほど目まぐるしくなる。犯人の有罪が確定してもまだ終わらない。最後が女性ジャーナリストが取材を終えて現地から離れた後なのだ。
近年には稀な生々しい殺人の描写
殺人犯の残虐な殺人の様子が生々しく描写されている。なぜここまで残酷なシーンを見せる必要があるのか。オカルト映画的な表現もある。事件の残忍性を伝えるための描写とする評論もある。その生々しい描写が映画の最後に見事に繋がるので、最後まで見放せない。宗教の聖地だからこそ起きた事件なのか欧州の国は時に「表現の自由」を振りかざし、ムスリムとの摩擦を引き起こす。ムスリム女性の人権が十分に尊重されていないという問題は存在しないとはいえない。しかしながら筆者が想像するに、イラン・イラク戦争後のイランでこのような事件が起きる環境を作ったのは、イランだけに責任のある問題とは言えないのであるまいかと思うのである。約10年に及んだこの戦争で、国は疲弊したはずだし、多くの男性兵士が犠牲になったであろう。当然、その兵士には家族があり、家族にとっては大黒柱を失ったことだろう。ただでさえ米国の経済制裁により一般の市民の生活も楽ではないはずだ。そのような遺族の生活はどうなるのか。
遺族が救済されない理由とは
イスラムは一夫多妻制が認められているので、男性は未亡人を第2、第3の妻に迎えることができる。これは本来、ジハードで夫を亡くした女性の生計を助けるための制度であるらしい。では、イラン・イラク戦争で犠牲になった兵士の妻は救済されたのであろうか。筆者はそのような人は極めて少なかったと考える。なぜなら、この戦争に明確な勝者はないから、戦利品も賠償金もない。したがって、第2、第3の妻を迎えて生活していく経済力のある人も発生しない。さらにイラン革命から敵対する米国からの経済制裁を受けているため経済的にも困窮している。このため、第2、第3の妻を娶った男性はほとんどいなかったであろう。それまで多妻制のなかで暮らせていた女性が捨てられたケースもあったのではないか。こうしたなか要因も、聖地に困窮者が集まる要素ではなかったか。そもそもイランで困窮者が生まれる事情についても考察しなければこの事件の背景を理解したことにはならないと筆者は考える。
聖なる蜘蛛たち
蜘蛛は多くの人にとっては歓迎されないが、害虫なども食べてくれるの益虫でもあり、地球上の生態系のバランスを調整する働きを担っているといえる生物である。この事件で直接的に蜘蛛として表現されたのは犠牲者となった娼婦たちであった。イランで蜘蛛とはどのように理解されている生物なのかはわからなかったが、犯人の表現だとすると否定的な意味の可能性がある。冒頭に映し出されたマシュハドの夜景は蜘蛛(あるいは蜘蛛の巣)を形作っているようだった。昼間はシーア派の聖地という顔を持つが、夜には彼女たちのような蜘蛛を生み出す顔がある、そうした比喩がこめられていたのだろうか。犠牲者たちは腐敗しているから蜘蛛になったのではない。一人一人が尊厳ある人間で懸命に生きていたのだということをこの映画のタイトルから想う。
イランのシリアルキラーの話
売る側だけを悪し様にゆうなよ。買う側も罰しろよ。
春にみのがしてて、次の機会を待ってた。見られてよかった。
正義とは、社会とは?
まず、文化が違うという事はこれほどまでに通念や考え方が違う事なのかと驚いた。
17人を殺害しながら、本人だけでなく周りもそれを浄化だと言う構図は、外から見れば異常だが、狂気は1人でなければ狂気ではなくなるのだといわんばかりの描写にぞっとする。
サイードは徐々に殺害に快楽を感じているようにも見え、報道されないことに苛立ち自己顕示欲までもをさらけ出していく。
さらに逮捕後、ますます自信を帯びた顔になり、支持者の存在を得て自分の正当性に確信を得ていく様がおぞましく表現されていく。
笑った顔がだんだんと気味が悪くなっていく演技が凄まじい。
娼婦たちを、狂った信念で絞め殺したのがサイードとそれを支持する世論だとすると、サイードを絞め殺したものはなんだったのか。彼らの神とは、どちら側なのか。この社会の法とは?
社会全体が狂っていたとしたら、その犠牲者はどうなるんだろう。どこを正義とするのだろう。
いつでも、人は社会と隣り合わせだ。
そして、ラストシーンは戦慄だった。
等速直線運動
聖なる蜘蛛
連続娼婦殺人事件の犯人を捕まえるために主人公が囮になる、ようやく捕まった犯人は一部で英雄視され、社会全体(警察やお役所すら!)から養護され優遇され、子供もあとを継ぎそうで、思想の次世代への連鎖を匂わせる、だいたい想像通りの展開と結末。
娼婦が聖地を冒涜する街の汚物なら、買う方はどうなんだ、という真っ当な問いをしたところで意味を持たない社会、男尊女卑、ミソジニーが「正論」とされるところは世界中でかなりあると思う。少女を暴行した成人男性が無罪になり、被害者のほうが男と密通した等の罪に問われる理不尽極まりない話も珍しくない。
こういう問題は、「目新しさがない」くらいしつこく世界中に言い続けて共有したらいいのだ。
また、狂信的信者タイプの犯罪者は厄介だ。
やっていることに誇りを持ち使命感がある分、シリアルキラーにもなりやすいと思う。
この映画の犯人は狂信的信者でもあるが殺すことに快感を覚えるようになって、殺さないと眠れないほどになっており、周囲をうまく利用したような気もする。
この映画をイスラム社会は許容したのだろうか、と思っていたら、イラン文化・イスラム指導省が「この映画はサルマン・ラシュディ『悪魔の詩』のような道をたどる」と非難したとのこと。
この作品は「単なる映画」の範疇を超えてしまったようです。
関係者の皆さん、どうかご無事で。
黒頭巾ちゃん気をつけて
開幕早々に犯人は面を割っているので、想像していたよりミステリー要素は希薄だった。あとは追う者と追われる者の攻防ということになるが、女ジャーナリストが自らおとりになる展開は「ああ、やっぱりそうなるか」と気が削がれた。どう考えても無謀すぎるし、実際にはありそうにない。わずかのタイミングの差で主人公は確実に殺されている。
世界には法律よりも戒律が優先される国があり、何なら法律=戒律だったりもするのだろう。日本人には戒律というほどのきびしい宗教的な制約はなく、せいぜい二礼二拍手一礼とか。なので、ラスト彼の国でちゃんと判決どおり死刑が執行されたのは意外だったし、見直した。
娼婦殺しと言えば“切り裂きジャック”だが、あちらは未だに犯人も動機も不明のままらしい。ジャック氏にも宗教的動機があったのだろうか(島田荘司がユニークな説を提示していたが)。肌を露出しないヒジャブが義務付けられている国で街娼が立つというのも、混沌の極みだが。
最近妙に凝った邦題をつける例を散見するが、あざとすぎて鼻白む。この映画も「聖なる蜘蛛」か「スパイダー・キラー」でよくないか。
宗教の怖さでもイスラム特有の問題でもない
全126件中、21~40件目を表示