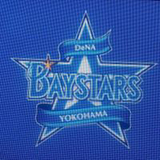あのことのレビュー・感想・評価
全130件中、61~80件目を表示
理不尽な世界の中で窮地に立たされた女性の凄惨な試行錯誤を至近距離で凝視するドラマ
1963年のアングレーム。大学で文学を専攻しているアンヌは教授もその才能に一目置くほど優秀な学生。進級のための大切な試験を前にしたある日体調の異変を感じた彼女は病院に行き妊娠していることを知らされ愕然とする。すぐさま中絶を希望するアンヌだったが当時妊娠中絶は違法であり、それを口にすることすら憚られる時代。親にも友人にも相談出来ないアンヌはただ一人で解決策を模索するが・・・。
アニー・エルノーの約60年前の実体験を綴った短編『事件』を映画化した作品ということですが、映像そのものには画面アスペクト比が4:3のスタンダードサイズであること以外ノスタルジーを喚起するような装飾は一切なし。引きのカットもほとんどなくアンヌに寄り添うカメラが彼女の試行錯誤を凝視しているので、アンヌの透き通るような佇まいに目を奪われながらもその試行錯誤の凄惨さに何度も目を背けそうになりました。劇中で引用されるルイ・アラゴンの詩に象徴されている通りアンヌが求めているのは自由であり、教授が読み上げるヴィクトル・ユーゴーの言葉を聞いた瞬間のアンヌの表情を見た瞬間に、本作が一人の女性が理不尽な世界を相手に戦い抜く勇敢な物語だと気付かされました。
このような非人道的な時代は1973年の米国における“ロー対ウェイド”判決、そしてフランスにおける1975年のヴェイユ法の施行によって終わったわけではなく、その後も延々と無数の悲劇が繰り返され、果ては米国連邦最高裁が“ロー対ウェイド“判決を覆す判断を示すという逆風の中で本作が上映されていることには途方もなく重い意味があると思います。
ほとんど笑顔を見せることのないままずっと映り続けているアンヌを演じるアナマリア・ヴァルトロメイの文字通り体当たりの熱演がとにかく凄まじいので、いつまでも脳裏に残像が残ります。
女性にも選択肢はある。
まだ中絶が法律で認められていなかったフランスで望まぬ妊娠をしてしまった女子大生の主人公があらゆる手を尽くして自分の人生を犠牲にしないために中絶しようと模索する話。
カメラはずっと主人公に寄り添い、画角も狭く、妊娠してからの時間経過がこまめに提示される。そんな中で、誰も頼りにできずに孤独に苦しむ主人公を見ていて「どうか無事に中絶できますように!」と祈らないではいられない。これなら中絶に反対する人でも多少は主人公を応援してしまうのではないか。
中絶が違法だったが故に何度も痛い思いをする主人公を見て、自分だったらこの苦痛に耐えてまで中絶するだろうかと思ったけど、痛みは一時のもの、今後の人生ずっと苦しむと考えたらそんな痛み痛くない。てかどうせ産むにしてもめっちゃ痛いし。同じ痛い思いするなら確実に私は人生を選びたい。
そして中絶が合法な現代でもこの時代と変わらないところは未だにあるし。アメリカほどキリスト教が浸透していない日本は空気的に中絶も1つの選択ですよみたいな面してるけど、実際自分妊娠しちゃったら誰にも何も言わずに中絶すると思う。そうして、この主人公みたいに何事も無かったかのように社会に戻る。妊娠において産むも中絶するも本人は孤独なのはずっと変わらない気がする。
本当につくづく思うけど男って夜遊び何のリスクも追わなくて羨ましいなー!一度の過ちで全部が犠牲になるなんてフェアじゃない!中絶したとしても「中絶」という苦しみは残るし!もっと女に敬意を払えー!!(笑)
トランプ元大統領はマジでない
男性からすると、まさしく女性性を擬似体験できる作品となっているのではないでしょうか?
メディアに良く出てくるお化粧をしておしゃれをし、恋愛を楽しむのが女性ではないです。だってこれは、男性でもできることでしょ?本作のアンヌの様に妊娠のリスクがありキャリアを断たれるリスクがあり主婦という病になるリスクがあるのが女性の本質です。
舞台は1960年代でしたが、人工中絶が合法化された現代に生きる日本人の私にも、他人事には思えませんでした。だから、本作を通して女性性の痛みを感じた全ての人達は、人工中絶禁止法が、女性の人権侵害、生命侵害をする全くばかげた法律だと理解できると思うのです。「生命の尊重」だと?だったら、戦争をする意義も説明してみろと言いたい。
戦争は、支配層が神の名の下に神を利用して民衆の命を握る行為ですが、人工中絶禁止法も戦争と本質が同じだと感じます。それは、絶対的に自分のものである女性の命、女性の身体の一部である胎児の命を支配層が日常的に握っているからです。
アメリカの中間選挙は予想外に民主党が得票したわけですが、これは人工中絶禁止法に反対する女性の票が入ったと言われています。
トランプ元大統領及び人工中絶禁止法に賛成する奴らは全員、アンヌと同じ目にあわせたい。また、中絶が出来なかったor失敗した大勢の女性達とも同じ目にあわせたい。本作は男性にも十分想像力を発揮できる作品だと思うのですが、同じ目にあうとか、どうですかね?
仮にこんな野蛮な法律が復活するならば、もうテクノロジーの力で、機械的に妊娠出産を性別問わずコントロールできる様になって欲しいですね。セックスというのが、過去の野蛮人が行ってきた行為になれば、人類はもの凄い進化といえますし、性欲を取り上げちゃえば、犯罪も大幅に減るのではないでしょうか。それくらい、女性は怒っています。
女性の性欲や向上心を隠さず(隠す必要がないから)表現しているところも、清々しくて良かったです。
衝撃の映画体験
2022.97本目
自分の体との、そして周りの人間との孤独な戦い。
その苦しい戦いの末に「ドボン」と便器に落ちた
赤黒いぐちゃぐちゃの塊。
大切な一つの生のはずなのに、「彼女を長く苦しめてきた悪魔だ」と思ってしまった。
スリラー映画やホラー映画より、痛くて、苦しくて、
焦燥感と閉塞感を感じた。
この映画には、性や生が美しく描かれない。むしろ、生々しく恐ろしいものとして描かれている。それも良かった。
鑑賞中の衝撃は、今年1番かもしれない…
自分と歳が近く、そして自分も生理が遅れていてソワソワし始めているから、感情移入も一層だったと思う。
鑑賞中も鑑賞後も、痛くて苦しくてボロボロ泣いてしまった…
すごいものを体験してしまった…!!
いらなきゃやるな! これも人類の永遠のテーマ
主人公に「案ずるより産むが安し」と教えたかった。賢さゆえに孤独になっていく女子大生
これは震え上がる男性続出だろうなあ。原作も監督も演者も、女性の賜物である。中絶のリアル描写は圧巻だ。かと言って、フェミニスト寄りのメッセージを感じるだけの啓発映画として見てはもったいないと思う。
欲望が羞恥心に勝った、って登場人物の一人が言ってたけど、二十歳前後の若者ってそんなものですね。そして、頭ではサルトルの実存主義を理解しようとしているのに、自分の身
に起こったことには脊髄反応のように一つの結論しか持てない悲しさ。発想を転換すれば、命を危険に晒すこともなかっただろうにね。60年代ってそんな時代だったのか。かたや「本音と建て前」の日本社会、(最近まで優生保護法なんかもあり)昔も今も比較的容易に中絶できてしまう。そして少子化。かたや現代フランスでは婚内子より未婚非婚カップルの子どもの数の方が多かったんでしたっけ。この辺はエビデンスなしに勝手に言えないけど、婚内子にこだわる日本社会の歪さの方にまで考えが及んでしまった。
刹那的に深く交わってもその後の妊娠をきっかけにどんどん孤独になっていく皮肉。相手の男性とも、両親とも、友人とも。自分だけの努力と才能で勝ち取ってきた高学歴者ゆえの孤独がヒリヒリ、相談下手。ヤンキー気質の人の方が柔軟に運命を受けれてコミュティの中で問題を解決する知恵を持っている?のはどこの国も同じなのかな。
365日働く階級の両親、特にお母さんとアンヌの関係性、セリフや所作によく表現されていたと思う。お母さんのピンタは、本当に痛かった。子どもって、いい方向にも悪しき方向にも、親の理解と想像を超えていくものだ。
ちょっと長くてつかれた。
監督が女性でよかった
意味深な映画
1960年代初頭と思しきフランスが舞台の映画でした。主人公は文学専攻の女子大生のアンヌ。成績優秀で担当教官からも将来を嘱望されるほど。ところが同年代の男子大生といい仲になり、生理が来ないので検査してみると、妊娠していることが発覚してアンヌの苦闘の物語は始まります。
これは観終わった後に調べたことですが、フランスでは19世紀初頭、まだナポレオンが皇帝だった1810年に制定された刑法により、中絶も避妊も違法とされており、1960年代に至ってもこの法律は生きていたようです。そのためアンヌは、普通の病院に行っても人工中絶手術を受けることが出来ず、自分で子宮に棒を突っ込んで堕胎を試みるものの失敗。最終的には同級生の男友達に紹介された非合法の中絶専門の女医(医師免許があるかすら不明だけど)に施術を依頼することになりました。
これまた鑑賞後に調べたことですが、当時人工中絶が非合法だったとは言え、その需要は少なからずあったようで、本作に登場するような非合法に中絶手術を請け負う女性が結構いたとか。ただ当たり前の話設備も技術も覚束無い闇医者が手術をする訳で、リスクも高かったようです。
そんな中絶禁止法がなくなり、フランスで人工中絶が合法化されたのは、この物語から10年以上経った1974年に成立した通称ヴェイユ法を待つことになるそうです。
要はこの物語、女性にとってのある意味暗黒時代の夜明け前を描いた作品でした。
興味深いのは、フランスで中絶が合法化されて半世紀ほど経過した訳ですが、同時期にロー対ウェイド判決により人工妊娠中絶が合法化されたアメリカにおいて、先ごろこうした流れに逆行する動きが出ているということ。事ある毎にアメリカの野卑で幼稚なところをバカにするフランスのこと、本作も婉曲的にアメリカの昨今の動きを皮肉っているのかしらと思わなくもないというのが感想でした。
肝心の映画の中身ですが、アンヌ役のアナマリア・ヴァルトロメイが難しい役柄に体当たりしていたのが印象的でした。親や友達に当たり散らしながらも、必死で中絶をしようとする哀れな姿を演じる様は、まさに迫真の演技でした。
あと、筋とは全く関係ありませんが、アンヌに闇医者を紹介した同級生役のケイシー・モッテ・クラインが、若い頃のプーチンに似ていて何となく笑ってしまいました。
そんな訳で、体当たりの演技で物語を面白くしてくれたアナマリア・ヴァルトロメイの活躍に★4の評価としたいと思います。
目を背けてはいけない作品
「レボリューショナリー・ロード」
「17歳の瞳にうつる世界」
のどちらも見たが、そのどちらとも違う作品。
一言で言えば「孤独」だ。
中絶が違法な時代、誰にも言えず、悩み苦しむ。
その苦しみを観客も追体験する。
目を背けてはいけない。
映画は「省略の芸術」なので、「見せなくても分かるよね」ということは見せない。
でも本作は違う。
その生々しい場面を見せる。
これは監督の明確なメッセージだ。
「目を背けるな」と。
なぜなら、これは「昔話」ではなく、「現代の問題」なのだから。
米国で「ローvsウェイド判決」が覆された今こそ見るべき作品。
これは海外の問題じゃない。
安価で安全な薬品による中絶方法が海外では一般的なのに、
日本ではリスクのある「掻把法」という方法が用いられる。
(本作と同じかな?)
ピル、アフターピル使用のハードルは高い。
これらは全て同じ延長線上にあり、他人事じゃなく、日本でも同じなのだ。
「妊娠と人生と引き換えにはしたくない」と闘った女性のありのまま。
中絶が違法であった60年代フランスで、人生を取り戻すべく中絶を受けるため最後まで戦い抜いた大学生の物語。ノーベル文学賞を獲ったエルノー氏の私小説に基づく。狭い画角、息遣いまで容赦なく描くリアリティに貧血や腹痛を感じ、動悸が起きたくらい。
この作品は男性にこそ観て欲しい。
セックスは2人で行うもの。
なのに、妊娠?中絶?女の問題でしょ?となるのはなぜだろう。
妊娠も出産も、中絶も、最後までふたりの問題ですよね。そこまで背負えないなら性行為はしない方がいい。
生涯生理もなく、妊娠もせず、出産もしない身体とは、どんな感覚だろうか。想像もつかない。
1週づつ、1日づつ、妊娠は進んでいく。
その恐ろしさ、焦りをここまで当事者以外の鑑賞者にまで伝えてくる作品、本当にすごい。
目を背けたくなる?とんでもない。気持ちのいいセックスの、すぐとなりにある現実です。
これは1975年まで中絶が合法化されなかったフランスでのお話ですが、現代においてもアメリカでは一部の州での中絶が禁止とされ、それが増えていくかもしれない状況。とんでもない話です。
その人の体はその人のもの。その人の子宮で起きていることを、他人の男性たちがとやかく決めて制御しようとするなんて、醜悪すぎて到底受け入れられません。
例外としてレイプによるものなら仕方ない?たとえいい加減な性行為による妊娠中絶であっても、最終的な決断権は女性本人にあるべきです。
そして一番男性に伝えたいのは、
「中絶の権利を女性に!」
これは中絶を良い手段と思っているのとはまったく違うということです。
進んで中絶したい女性などいません。心身ともに大きく傷つく処置です。
「望まないすべての妊娠を『ふたりで』避ける努力をした後で」最後の救いとして中絶は絶対に許されるべき手段だということです。
こちらの感想の中にも「女性も男遊びをしている」「自業自得」「消される命が」など散見しますが、それすべて、男性も背負っていますか?妊娠=軽率な女性への罰、かのような受け止め方が令和の今でも見られるのは残念ですし、道のりは遠いと感じさせられます。
この作品は、フェミニズム作品ですらありません。ひとつの事実を写しているだけです。
共感は難しい
中絶も避妊も肯定しない社会情勢で、直接の相手の男性への責任をも追及せず、犯罪行為の幇助になる医師や関係ない友人を巻き添えにし、条件が揃うのが遅れたとはいえ、胎児の命を奪って、苦痛は流産のときだけで、結末には笑顔というのはやはりいただけない。『ガール』でもやはり、周囲の助言を無視して自分の衝動で選択した行動を笑顔で迎えた結末に感じた思いにも似ている。女性が子を産んで育てながら社会進出が保障される環境であってほしいものである。
メッセージ性に優れ、サスペンスとして秀逸だが、主人公には同情できない
映画が始まって、スクリーンが「スタンダード」サイズであることに戸惑うが、やがて、その窮屈な画面から、主人公の置かれた八方塞がりな状況と、閉塞感や息苦しさがひしひしと感じられて、このフォーマットが高い効果を上げていることに気付く。
中絶を違法とする社会制度を声高に非難するような映画ではないが、女性が心身に被るダメージの大きさを生々しく描くことにより、その理不尽さと非人道性が肌で感じられるようになっている。
孤独や不安や焦りに苛まれながら、自らの未来を命をかけて掴み取ろうとする女性の、スリルとサスペンスの物語としても、非常に良くできている。
ただし、危険を承知していながらそのような事態を招いた主人公の行動は、軽はずみだと言わざるを得ないし、妊娠の発覚後も、避妊の必要はないと夜遊びを続けるその姿からは、やはり「自業自得」という言葉が思い浮かんでしまう。何よりも、胎児の命を奪うことに一切のためらいも罪悪感も感じていない主人公には、どうしても感情移入することができなかった。
ラストも、一応、ハッビーエンドになっているが、敢えて「学業の道も閉ざされ、何もかも失った」みたいなエンディングにした方が、主人公の置かれた過酷さや、当時の社会制度の非情さが、より際立ったのではないだろうか?
コレはキツい…
新聞売りの紹介で。
テーマは若さ(バカさ)の特権?
1960年のフランスの女子大学生が妊娠する話とのことで、渋谷のBunkamuraまで行きました。だいぶ外国人が増えてきました。スクランブル交差点の何がいいんだか?さっぱりわかりません。相手は消防士とのこと。これは八百屋お七みたいに逢いたさ余りに放火を繰り返すのか?と期待しておりました。
映画では字幕で何週間後とかご丁寧に出ますが、1960年の妊娠反応検査は今と違って簡単ではありません。妊娠かもと気がつくのも6週過ぎでしょう。医師が妊娠の徴候を疑うことができるのも8週過ぎでしょう。超音波検査なんてありません。妊娠証明書が送られてきたのは、今の日本で合法的な堕胎が認可されている12週をとうに過ぎてしまっていていたと思われます。1960年代の妊娠反応検査は今と違って、ウサギに妊婦の尿を注射して確かめるのが一般的で、ウサギが排卵したかどうか一定の時間をおいてから開腹して確かめるのです。ウサギはヒトとは違って、性交すると排卵するので、メスのウサギだけ飼って実験室で行うのです。ヒトでもウサギのように性交するとその刺激で排卵する原始的(失礼)な方も結構いますけど。
インチキ堕胎医のおばさんは最初は子宮の中にゾンデを入れるだけ。出血はしても堕ろすことは難しい。お金だけ取られた主人公が文句を言いにいくと、さらに強力な器械を入れますが、とっても危険。結局、ちゃんとした医療機関に送られて、完璧な堕胎術が施され、自然流産と診断されて、処罰の対象を逃れることができましたが、たくさんの人に迷惑をかけて、命を救ってもらえたからいいようなもの。主人公は複数の男性と付き合って、何回もしていたのに、初めてのたった一回で妊娠したと男性医師に嘘ついてましたから、なかなかしたたかで、強情な女でした。新川優愛さん似の純情派の女優さんでしたが、共感はしづらいですね。実際、寮のトイレでかなり太い臍帯がぶる下がっていて、友達にハサミで切ってと頼む場面があり、20週(5ヶ月)は軽く越えていて、非常に危険な状態でした。それでも鬼の形相で友達に指図する主人公の決意の強さは伝わりますが、地方出身の文学部のお嬢さんですから、医学部や法学部で弁護士希望とかとは違って、学業優先の目的は個人的なもので、共感はしづらく、命を粗末にしているだけと思う人も多いでしょうね。ベネチア国際映画祭での金獅子賞は強くなった女性たちと原作者がノーベル賞作家であることにかなり忖度しているような気がします。妊娠週数ばかり気になって、映画を楽しめなかったです。寮のシャワー室の女子大生達の裸体は悪くはなかったですが、時間ですよの銭湯の脱衣場シーンの方が刺激的だったような。妊娠して落ち込んでいる主人公に騎乗位でイク妙技を指南する3人娘のひとりの熱演はなかなかすごいものがありましたけど。若さの特権の映像表現という点では評価に価するってことでしょうか。自分の都合で実家に帰ってくる娘を迎える両親役の俳優さんの方が共感できてしまいました。
アマゾンやオークションなどで手頃な堕胎器具を自分で買って、やってみようなんて思って真似する人が出て来ないかすごく心配しております。
本当に大切なのはどのことよ?
全130件中、61~80件目を表示