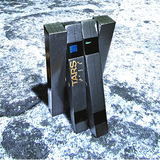パワー・オブ・ザ・ドッグのレビュー・感想・評価
全150件中、21~40件目を表示
フィル vs ローズとピーター
《母を守る》
映画の冒頭。
ピーターのモノローグではじまる。
「父が死んだとき、
「僕は母の幸せだけを願った」
「僕が母を守らねば、誰が守る?」
考えてみれば最初にこの映画のテーマが述べられているのだ。
ピーターがこの映画の隠れたキーパーソンで、
母親のローズが彼の一番大事な人である。
1925年。モンタナ
牧場を経営している兄弟がいる。
兄のフィル(ベネディクト・カンバーバッチ)と、
弟のジョージ(ジェシー・プレモンス)。
事務的な経営は弟のジョージ。
カウボーイを束ねて牛の放牧責任者が兄のジョージ。
2人は25年かけて牧場をここまで大きくした。
兄弟の絆は強く、同じベッドに寝てる程だったが、
ジョージがホテル兼ダイナーの店主ローズ
(キルスティン・ダンスト)と突然結婚する。
ローズのことを、連れ子のピーターの
《学費と財産目当てメス狐》と
フィルは罵る。
ジョージを奪われて悲しかっただろう。
ジョージは上昇志向が強く結婚披露に両親と知事夫妻を招く。
その席でローズにピアノの腕前を披露させるために
グランドピアノを買うジョージ。
しかしローズのピアノ練習する「ラディキー行進曲」を
妨害するフィル・・・子供じみた男だ。
フィルのバンジョーはローズのたどたどしいピアノより、
よっぽどリズムに乗った「ラディキー行進曲」を爪びく。
夫婦の寝室の隣がジョージの部屋。
フィルの嫌がらせと、ストレスから
ローズは酒に逃避してアルコール依存症になって行く。
一方で、
夏休みに牧場に帰ったピーター(コディ・スミット=マクフィー)
「お嬢ちゃん」
とカウボーイたちに揶揄われるほど線が細い。
痩せて背が高く色白、瞳が大きく目立つ美貌だが、
女の子のようだ。
しかし医学生のピーターは、ウサギを解剖したり不気味。
やがてフィルとピーターは急接近してゆく。
「あの山は何に見える?」
「吠える犬でしょ!はじめからそう見えた」
フィルは驚く。
もしかしたらピーターは俺の同類。
乗馬を教えるようになり徐々に距離は縮まって行く。
ジョージの師匠で「意中の人」ブランコ・ヘンリー。
ジョージにゲイの世界を教えた男でもある。
ブランコ・ヘンリーは16年も前に死んでいるのに、
ビリーの魔法(呪い?)に、かけられているジョージ。
(・・・あの日が懐かしい・・・)
(ジョージは過去に生きる男である)
ピーターの夏休みが終わる頃、事件が起こる。
ジョージが干していたら牛の毛皮を先住民が買いたいと言う。
それまでずっと、ジョージは毛皮を決して売らずに
燃やす主義だった。
先住民を見たローズは、追いかけて行き、
「牧場主の妻だから、貰ってほしい」
と毛皮をくれてやる。
怒るジョージ。
(ピーターに編んでいる縄の仕上げに毛皮が必要なのだと言う)
ピーターは「毛皮なら自分が持っている」とフィルに言う。
病死していた牛から剥いだ毛皮だ。
結果としてフィルは炭疽症らしき症状で突然亡くなる。
この経緯はかなり無理クリで、
ローズの行動(毛皮を先住民にただで渡す行為・・・
に、意図はあったのか?)
とか、
ピーターが病死した牛から毛皮を剥いだ時、
これでフィルに炭疽症に
感染させようと思っていたのか?
とか、
一連の流れがローズとピーターの連携プレイなら、
計画的と言われても仕方がないではないか?
(こんな事で人が死ぬなんて、3流ミステリーのようだ)
しかしフィルの葬式の席で、ジョージの母はローズに
有りったけの指輪を手渡す。
フィルの父親は、クリスマスの招待を嬉しそうに受ける。
そしてフィルのいない庭でジョージとローズは伸び伸びと
幸せそうに抱擁を交わす。
(フィルは、実は、小うるさい変人の余計者だっただろうか?)
伸び伸びした解放感が、牧場に広がるのだった。
(ベネディクト・カンバーバッチの存在と演技力、
(役にのめり込み、役に成り切る力量。
(他の役者では、これだけの没入感は示せないだろう)
本作品はアカデミー賞監督賞を受賞した。
ジェーン・カンピオン監督の「ピアノレッスン」1993年作品。
その完成度、独創性、官能性、映像美、詩情。
どれをとっても、比べ物にならないと思ったのは、
私だけだろうか?
ドラマ映画を好んでみている人 考察が好きな人向けの映画
事前情報を仕入れずにネットフリックスにて鑑賞。
映像一つ一つはなんとなく分かる→解説ブログ「なるほどそうだったのか !」となるので
繰り返し見ると理解できるんじゃないかな……
(この映画を二回も見る気にはなれないけれど……)
ベネディクト・カンバーバッチ
滑り込みで観たけど、作品書受賞しなかったなあ
アカデミー賞作品賞最有力候補と聞き、受賞して込んでしまう前にと滑り込みで観た。(作品書は受賞しなかったけれど)
主題を直接語ることはなく、雰囲気を感じ取ってくれという映画。気合を入れないと、「なんだ?この映画」となりかねないヤツ。
主人公は、イエール大で古典を専攻したインテリなのに、父の大牧場を継いだので、いわゆる肉体労働者であるカウボーイたちを率いており、風呂にも入らない、荒くれ者たちに近い生活をしている。態度もぶっきらぼう。マッチョでありたいという思い、あるいはこの立場はマッチョであるべきという信念か? 弟は兄のようにできる者ではないが、兄と一緒に牧場経営に励んでいる。マッチョでありたい兄にとって弟という存在は、頼りないが守ってやらなければいけない存在なのだろう。その弟が、宿屋の女主人、離婚歴があり子持ちの女性と結婚して、流れはかわっていく、という話。主人公は、弟が結婚したことも100%納得できないし、結婚相手の息子ピーターの柔らかな物腰も気に入らない(主人公にとっては「男らしくないヤツ」)。しかしふとしたきっかけから、主人公とピーターは仲良くなっていく。だがしかし・・・
まずはやはり多くの方が語っている、マッチョの話なのだろう。
主人公「男を強くするのは苦境と忍耐だ」
ピーター「ぼくの父は、強くするのは障害物だと言った。そしてそれを取り除けと」
主人公「お前には障害物がある。お前の母親だ。母親はぐでんぐでんだ」
このやりとりは、最後まで観ると思わすこの部分を思い出すかと思います。
そして俺がこの話を観てもうひとつイメージしたものは「依存」。主人公は、明らかに弟に依存している。だから同じベッドに寝るし、弟が結婚することがなんだか気に入らない。兄としてはずっとかまって守っていたつもりなのに、弟はずっとひとりだった。主人公は弟を支配していたかっただけだったのだろうか。
主人公が崇拝している、主人公が子供の頃、いろいろなことを教えてくれ、荒れた天候の中で裸で彼を温めてくれたたマッチョな、ブロンコ・ヘンリーという存在。
主人公「ブロンコ・ヘンリーは目を使うことも教えてくれた。あの山になにが見えるか、わかるか?」
ピーター「ほえてる犬。最初に来た時に見えた」
主人公「すぐに、見えただって?」
このやりとりがふたりの仲が変化するきっかけ。誰も自分と同じように見えてくれない中で、とうとう現れたブロンコと同じものを見られる少年。主人公の保護意欲は、すでに妻帯者となってしまった弟から一気に息子へと。つまり主人公が依存する対象が、弟から息子へ移る。
そしてまた、弟の妻もまた息子ピーターに「依存」している。息子はそんな母親に優しく対応する。
弟も、市長夫婦を牧場に招くことに成功するが、「兄貴がいないと(インテリ相手の)話がもたないから、家にいてくれよ」と懇願する点では兄に依存している面がある。
以下はネタバレなので、観た人だけ読んでください。
腐った動物の死骸に、しばらく漬けられていたかもしれない、炭疽菌漬けかもしれないロープ。
それは息子ピーターのベッドの下に眠り、今後もずっと、人の眼には触れないだろう。
ピーターは、父親が言う通り、自分で障害物を排除し、強くなり自分の道を切り拓いたわけだ。
真にマッチョ、「強い人」であるのは誰なのだろうか、という映画と俺には感じられた。
広大な砂の大地〜冷ややかな眼差し
ベネディクト・カンバーバッチ、キルスティン・ダンスト、ジェシー・プレモンス( 実生活でも夫婦だとは驚き!)、コディ・スミット = マクフィー、それぞれの個性が際立つ。
非情さと繊細さ、容赦ないラストに全てを持って行かれた。
自宅での鑑賞
荒々しさの中の最大の繊細さ
映画好きが映画館でじっくり観たい映画なんだけどね〜
アメリカ西部の広大な牧場で
颯爽と馬を駆るドクター・ストレンジ!
では無く、ベネディクト・カンバーバッチ。
最初に作品紹介を読んだ時にカンバーバッチのカウボーイ?
なんかピンと来なかったけど実際に映画を観てみると
彼以外に考えられないくらいカンバーバッチにピッタリの役!
西部劇の牧場主と言うとテンプレ的な荒っぽい男を連想しがちだけど
カンバーバッチ演じる牧場主は大学を出て楽器も嗜む知的な男。
それでいて荒っぽいカウボーイ達がちゃんと従う様な
強い一面をもっており、常に自信に溢れた男で誰に対しても上から目線。
牛を移動させる道中に立ち寄った小さな宿屋、
切り盛りする未亡人と、その息子の痩せっぽちの高校生を
露骨に馬鹿にした態度を取る。
気に入らないなら単に無視すれば良いだけなのに
わざわざ馬鹿にした言葉を皆の前で投げ付けるなんて.....
彼自身がある意味で己の男性性を誇示する事に
異常に拘っていることが伝わって来るシーン。
嫌味過ぎて、観ているこっちまで緊張して来る。
そんな男にも実は、誰にも言えない秘密があった!
さらに、心優しい男に見えた牧場主の弟も、また
違った意味での女性蔑視の塊であった。
そして、物語の中盤からあの痩せっぽちの息子が
物語を意外な方向に導いてゆく。
中々に複雑で今日的な見応えのある映画でした。
最後に笑うのは誰か?
見応え有りの作品でした。
で、月に8本ほど映画館で映画を観る中途半端な映画好きとしては
本当は映画好きが映画館でじっくり観たい様な
映像的にも内容的にも重層的な複雑な映画!
ネットの小さな画面で観るだけなんて勿体ないわ〜〜
昨年暮れに一部の映画館で期間限定で上映されていたけど
あの「ピアノ・レッスン」のジェーン・カンピオン監督の作品と
ちゃんと認識しておらず、うっかり見逃してしまいました。
「ピアノ・レッスン」は夫の有害な男性性により
心が壊れゆく妻と娘、そしてその再生を描いた映画だったと
記憶しているのだけど、今作は有害な男性性プラス
その男性性を持って生きなければならなかった男性も実は
結構苦しいと言う中々に奥深い作品になっている。
Netflix作品と言うことでアメリカのアカデミー賞では
監督賞しか取れなかった訳だけど
Netflixでなければこの様な内面的な奥深い映画に
お金を出してくれなかった。
映画館でじっくり観たい本当の映画好きに向けた作品に
お金を出せない映画界が、ネット配信の作品を目の敵にして
賞を与え無いと言うのも本末転倒で実に情けないわな。
期間限定でもこの様な良い作品を上映してくれた
Cinema KOBE のスタッフの皆さん!
本当にありがとうございました。
流麗だが不気味な音楽が非常に効果的な一作。
第94回アカデミー賞で監督賞を受賞した本作、出来映えを鑑みるとカンピオン監督の受賞は当然と思えるものの、作品の持つ力強さ、前評判の高さからすると、他の部門での受賞をことごとく逃しているのはとても意外でした。
米国西部が舞台となっているものの、撮影はカンピオン監督の故郷でもあるニュージーランドとオーストラリアで行われています。それもあってか人々を取り囲む風景の雄大さは非常に印象的ですが、とは言っても、西部劇として見ても全く違和感を感じませんでした。ロケーションの選択の巧みさでしょうか。あるいは実際に米国西部に住んでいる人からすると違いが分かるんでしょうか?
題名を旧約聖書から引用するなど、そこかしこに宗教的な要素を見て取ることができます。牧場主の兄弟による絆と諍いの物語は、カインとアベルの物語をなぞるように展開するのかと思いきや、ベネディクト・カンバーバッチ演じるフィルの複雑な人物造形は、観客の憶測を超えた側面を見せます。荒くれた男達を率いるために、過剰とも言えるほど「男らしさ」を強調する一方で、実は深い学識と教養、さらに美的感覚を備えた人物であることが明らかになっていきます。自分の生き方に信念を持ち、自信に満ちあふれているように見えるフィルの内面の葛藤を本作では、流麗な筆致やクラシック曲の口笛などで効果的に表現しています。
風景に目を奪われがちですが、本作では音楽が重要な役割を担っており、例えばローズ(キルスティン・ダンスト)とフィルが一種の共演を行う場面において異様な緊張感をかき立てます。本作の音楽担当は、レディオヘッドのジョニー・グリーンウッドとのこと。それもあってか、本作を観ながらどことなく同様に彼が音楽を手がけた『ファントム・スレッド』(2017)を連想しました。
ものすごく余談ながら、予告編のタイトルに誤植があり(『パワー・オブ・ザ・”ドック”』になっていた)、危うく間違えて周囲に吹聴するところでした…。公式の予告編映像は直して欲しい…。
映像と音楽は素晴らしいが…
1925年、西部モンタナ。マッチョな牧場主の主人公が、弟の結婚相手とその連れ子を毛嫌いするが、自らの秘密を連れ子に知られてから、徐々に連れ子と親密な関係になっていく。
荒涼とした山並みや牧場風景を写し撮った映像は素晴らしく、生楽器を使った音楽は、不穏で緊張感のある作品世界に大きく貢献している。
題材はホモセクシャルだが、主人公が粗暴で無礼な振る舞いをするのも、自らの性向を隠すためだということがわかってきて、中性的な連れ子に徐々に惹かれていくあたりは、物悲しく、憐れみさえ感じてしまう。
結末は衝撃的で、それまでの伏線が回収され、なるほどと思いつつ、描きたかったのはこっちなの?だからどうしたの?とも思ってしまった。後味がすっきりせず、自分にはあまり響かなかったのが正直なところ。
役者陣では、B・カンバーバッチはがんばっていたが、何と言っても、連れ子役が、表面的な線の細さと、内面的な芯の強さ、不気味さを醸し出していて、出色だった。
こじらせ男だね。
吸引力つよっ!
1920年代という人間の転換期
やっと宿題だった本作を観ることが出来た。まずは再上映してくれたこの“塚口サンサン劇場”に感謝ですね。
今やこの劇場は(娯楽系・アート系含む)私の劇場で観たい作品の8割位は上映してくれるので凄く助かり、個人的にはなくてはならない存在になっている。(実は本作も再映するかもと期待というか予測していたのですが…)
で本作の感想ですが、まずは予想以上に複雑・多層的であり、精緻な人間ドラマという印象ですね。
鑑賞後これがアカデミー作品賞ではなく「コーダ~」の受賞で正解だと思いました。
だってアカデミー賞って他の国際映画祭とは違い、大衆映画の為の賞であり続けていたし、こちらは大衆映画と呼ぶにはちょっと高尚過ぎるし、本作を理解するには相当映画を観極めた人であろうし、“大衆”とは本作レベルの作品を理解出来る対象の呼称ではありませんからね。
私も1回だけの鑑賞だと全容を理解するには難しい作品でしたが、今流行りのテーマである“トランスジェンダー”や“多様性”などを含めつつ新時代の転換期である時代の舞台設定が面白しく感じられました。
アメリカ映画の純粋な西部劇の大半は1860~65年の南北戦争辺りの設定が多いのですが、本作の様な1920年代の西部が舞台の映画って私の記憶では「ジャイアンツ」('56)「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」('07)などがあり、それらは共に前時代と新時代のはざまに起きる価値観の変化に対する葛藤が内在する人間ドラマとなっていて、本作もそうしたテーマが核となっていた様に思いました。
ただ、頭の悪い映画宣伝部のよくあるミスリードを招くような解説文が本作でも見受けられ、レビューの中にもその解説に影響されたような的外れというか「木を見て森を見ず」的感想が多かった様に思えます。
例えば映画comの解説の一文に「無慈悲な牧場主と彼を取り巻く人々との緊迫した関係を描いた人間ドラマ」とありますが、恐らく本作を観る前に一般の人がこの文を読んでしまうと、この“無慈悲”という言葉に完全に引きずられてしまうでしょうね。私は観終わってから読んだので、的外れな単語だと思いましたよ。そんな単純なキャラ設定ではなかったでしょう。
まず本作の主人公って、本当にフィル(ベネディクト・カンバーバッチ)なのか?、私は鑑賞中、主人公無しの群像劇だと思い観ていました。
で、単純にフィルが悪役だとも全然思えませんでした。主な登場人物は全て少し異様な一面が描写されていましたからね…
特にピーター(ひょっとするとこちらの方が主人公)は完全にサイコパスでしたし、フィルはサイコパスではないが、彼の中に自分と同じ性質を見出していたと思われ、母親はピーターからすると(愛情とは別の)守るべきアイコン的存在に過ぎなかった様にも感じられ、母親はアルコール依存症であり、この3人は明らかに社会的マイノリティーであって、ただジョージというのは、どの時代のどの社会にもいる一番の弱者でもあり、一番のマジョリティーでもあり、マス(鈍感・自分勝手)の象徴的存在に思えました。
なので、フィルを主人公としたサスペンス映画としてだけ追って見ると非常に薄っぺらいドラマになる様な気がしますが、この作品の奥深さは、ある時代の社会の転換期を一つの家族の出来事として集約して描かれているという観方や解釈も出来る物語構成でした。
これ以上の事はまだ私も整理が出来ていせんが…、もう一度見直したい作品です。
追記,
しかし、画面にキルステン・ダンストが登場し(かなり年取ったなと思って見ていると)息子に「ピーター」って呼ぶのを聞いて、思わず笑ってしまった。
異色の西部劇 やっぱり西部を描いている
モンタナ州は今でも「偉大なる西部」と呼ばれているそうで
きっと壮大な自然が広がる所なんだろう
1920年代が舞台というから時代的には『ギャツビー』の時代と重なる
東部と西部ではこんなに違ったとは言え、既にモンタナの町の中では
女性が自動車を運転していたり、ドレスの裾も短くなってきている
そんな、いわゆる一世代前の西部劇とは違う世界に住むフィル一家の物語
カンバーバッチ演じるフィルと弟の連れ子のピーターとの
距離の縮め方が見ていてハラハラさせられる
特に2人が煙草を吸い合うシーン、ピーターの誘うような目線に釘付けになった
フィルの秘密の場所でのシーンも美しいばかり
次第に深いところで交差するかに思わせた後でのあのラストは
怖いくらいの驚きだった
フィルは東部の大学に在籍していたという設定なのだが、
時代に背を向けているのに、実は西部の男達の世界には
本当には溶け込めていない、どちらにも真実の居場所がみつからない、
そんな人間に見えた
今時の西部劇はこんなに複雑な内容を含んでいると思える面白い作品だった
カンバーバッチの繊細な演技が光る!
ほぼ中身のないレビュー、とまでも言えない自分用メモです。
第94回アカデミー賞 11部門で12ノミネート(助演男優賞に2人ノミネートされているから数が合わない)の最多ノミネート作品。ずっと最有力視されていましたが、最後に「コーダ」に逆転されちゃいましたね。唯一、ジェーン・カンピオンが監督賞を受賞。女性監督の受賞は3人目です。
もう登場シーンからカンバーバッチ演じる主人公のフィルが嫌なヤツ過ぎて嫌悪感マックスに。
それでも1920年代のカウボーイってこんな価値観だったのね、って見ていたら途中から(そうだったのか!)という展開に。
ラストは(えーーー、そういうこと!?!?)って結末なんですけど、全てはっきりと描写はしていないので、よくわからないという声が多いのもごもっとも。
この映画は特に人によって合う合わないあるでしょうね。
結末を知ってからもう一度みればまた違った見方になるのでしょう。
鑑賞後ずっと星3.5か4.0か悩んでおりましたが、この後に鑑賞した作品は4.0相当が続きましたので、相対的に3.5になりました。全然悪くはないのですが、少し肌に合わなかったので。
厳密に言うと3.75位です。
おそらく数年前のアカデミーなら「コーダ」よりこちらが作品賞を獲得していたのでは?
芸術性だけで選ぶなら今作でしょうね。
(個人的な好みはダントツで「コーダ」でした)
手袋が当たり前の世界に・・・
最近、マスクのみならず使い捨て手袋をしている人が増えてたりしませんか。やっぱり感染対策として必需品。怪我してても平気だ!というマッチョな人ほど感染しやすいもの。などと考えながら、犬があまり登場しなかったり、牛や馬やウサギがメインの動物となっていた映画だったことに気づきました。
異色の西部劇だという触れ込みもありましたが、西部劇は異色の作品ほど面白いものです。最も驚かされたのは、時代が1925年とは言え、主要な男たちはみんな大学に行ってたこと。酒瓶もいっぱい出てきて、そこでバーボンと書かれたラベルを見て真っ先に思い出したのがバカボンのパパ!バカボンのパパだってバカ田大学を卒業しているのだ(都の西北ワセダの隣)。これでいいのだ!
ブロンコ・ヘンリーという名前。ついついブロンコビリーと記憶してしまいがちですが、それは多分ビリー・ザ・キッドとか混同してるからでしょう。マッチョな男でゲイ。そんな伝説のカウボーイに手ほどきを受け尊敬しているフィル(カンパーバッチ)は男性優位社会に育ち、女性嫌いが徹底している。ブロンコ愛用の鞍を今でも丁寧に扱っているシーンもありますが、あの鞍の先っちょもどこかゲイを思わせる形。そんなフィルは弟ジョージが嫁として連れてきたローズを徹底的に貶しているのです。ローズが練習しているラデツキー行進曲をもバンジョーでメロディを被せるシーンはとにかく凄い。俺の方が上手いぜ!へっへっへ~的な。しかも1階と2階という位置からしても上下関係を暗示している演出の巧さ。
女なんて要らん的なフィルはやがてローズの連れ子ピーターに秘密を垣間見られた辺りから、女々しいギョロ目と蔑んだにもかかわらず、彼を立派な跡継ぎにするかのようにカウボーイの仕事を教え込むようになる。意外な展開。アル中になった母ローズをこき下ろされ、出会った時に丁寧に作った造花を燃やされた恨みも再燃し・・・というか、どこからか復讐を企むようになっていたピーター。投げ縄用のロープをプレゼントしてくれるというフィルに仕組んだ罠がとにかく強烈だった。紙巻きタバコのシーンからは想像できない・・・
まぁ、ラストに愕然とさせられるものの、全体的には抑揚も小さく、感情を揺さぶられることもなかった。山の影になった犬の形は面白いし、主要人物の章ごとの心理変化も絶妙。終盤にはピーター目線ともなるし、4者それぞれの感情移入さえも否定してくるような圧倒される映像には恐れ入った。ただ、やっぱり後味がよくないし、この時代向きではなかったかな・・・アカデミー作品賞を獲ってしまったらビックリするかのような。
スリリングな愛憎劇に目が離せない
フィルのマチズモは一見すると昭和オヤジの典型のような古臭さを感じるが、しかしよくよく考えてみれば強権によって他者を支配するという行為自体は現代でも身近に目にするものである。例えば、昨今のMeToo問題やパワハラ問題然り。世界に目を向ければ、一部の超大国による搾取や圧力が横行している。そう考えると、本作は普遍的なテーマを描いているという見方もできる。
本作で面白いと思ったことは2点ある。
まず、1点目はフィルの造形である。
フィルのバックボーンには幼い頃に師事したブロンコ・ヘンリーという男が存在している。このブロンコは劇中には登場してこないが、今でも彼愛用の鞍を大切に保管していたり、彼の思い出を度々反芻することから、相当フィルは彼に信奉していることが分かる。きっと現在のフィルのようにさぞかし厳格な西部の男だったのだろう。
ところが、映画の後半に入ってから、ブロンコには”ある秘密”があったことが分かってくる。それは男らしさとは程遠い、全く意外な秘密である。フィル自身もそのことは理解していて、そこも含めて彼を信奉していたということが分かる。こうなってくると、途端にそれまでのマチズモが滑稽で憐れに見えてくるようになる。フィルの強さの裏側には、他人には言えない弱さがあったのだ。
この表裏のギャップが自分にとっては意外であったし、フィルという人物の深層を探る上ではとても興味深く観ることが出来た。
2点目は、ローズの連れ子ピーターのミステリアスさ、そして彼をキーマンに仕立てた脚本の巧みさである。
本作は全5章から構成されており、フィルとジョージ、ジョージとローズ、フィルとローズ、フィルとピーターの関係に注視しながら端正に紡がれている。個々のキャラの立ち回りは終始揺るぎなく一貫しており、その甲斐あって、彼らの愛憎劇には説得力が感じられた。
そして、前段でしっかりとフィルの独善的なキャラクターを積み上げた先で、いよいよフィルの適役(?)とも言うべきピーターの登場と相成る。マチズモの権化フィルと花を愛する心優しい青年ピーター。二人はまったく正反対なキャラクターであり、その対峙は非常にスリリングに観れた。この”したたか”な脚本には唸らされてしまう。
ピーターの造形も大変ミステリアスで面白い。
初めこそ純真無垢な、か弱き青年として登場してくるのだが、実はフィルと同じように彼にも表と裏の顔があるということが徐々に分かってくる。
最初にその片鱗を見せるのは中盤のウサギにまつわるシーンだ。ここではピーターに潜む魔性がショッキングに開示されている。その後も彼の言動などから彼の中に眠る”怪物性”は次第に頭角を現す。そして、クライマックスとなる第5章で、いよいよその本性は露わになる。その瞬間、自分は思わず息を呑んでしまった。
ジェーン・カンピオン監督の演出も今回はギリギリまで攻めていると感じた。特に、フィルの隠された”秘密”に迫る描写はかなり際どい所まで描ていて驚かされた。カンピオンというとここ最近の作品は未見で今一つパッとしない印象を持っていたのだが、それは全くの見当違いだったと反省するしかない。「ピアノ・レッスン」の頃を彷彿とさせる不穏さと緊張感に溢れたタッチに最後まで目を離すことができなかった。非常に熱度が高い。
キャストではフィルを演じたベネディクト・カンバーバッチの好演が印象に残った。最初は彼が西部の男を演じるということに今一つピンとこなかったのだが、実際に観てみると上手くハマっていて驚かされた。厳格さの裏側に見せる一抹の孤独と哀愁。そこに人間臭さが垣間見えて、どこか不憫さを覚えた。
また、ピーターを演じたコディ・スミット=マクフィーは、ビジュアルからして強烈な印象を残し圧倒的な存在感を見せつけている。これまでも彼の出演作は何本か観ているはずなのだが、正直全く記憶に残っておらず、今作でようやくその存在を知った次第である。まさか「X-MEN」シリーズのナイトクローラーだったとは…特殊メイクをしているので分るはずもない。
格の違い?🤔
全150件中、21~40件目を表示