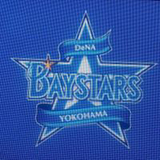ある男のレビュー・感想・評価
全409件中、321~340件目を表示
平野啓一郎の社会性が出た作品
原作者の根本思想として、自分の実態を消去したいほどに差別的で抑圧的な社会を告発したいということがある。そこをベースに考えれば仕掛けの意図がよく分かりる。
妻夫木聡、窪田正孝の演技はなかなかのものであった。妻夫木の被抑圧的な気分の表現は素晴らしいし、窪田のボクシングシーンは違和感を抱かせない動きでセンスを感じた。
しかし、それ以上に感嘆したのは柄本明の演技だ。歳を重ねるごとにすごみを増している。ベテランの男優では、石橋蓮司と双璧ではなかろうか。一方で主役級では目立った俳優がいなくなった気がする。例えば緒形拳は善人と悪人を対照的に演じ分けることができたが、そういう俳優は今は思い浮かばない。これは映画産業の衰退と軌を一にしているのだろうか。監督に巨匠と呼ばれる人がいなくなったのも同じようなことだろう。
これはミステリー?
ラスト暗いなぁ...
窪田さんの谷口の判りやすい闇ではなくって、
妻夫木さんの城戸の笑顔の嘘っぽさというか、
どこか影のある感じが上手かったなー。
ラストのバーのシーンも感情のなく、ただただ語ってるだけみたいな、
だから、こっち側で判断を任せられたような、にしても、まったく前向きさを感じなかったな。
安藤サクラ親子のシーンと真逆だよね、正直。
城戸だけが、完結していない感じで、これから、この男がどうなっていくのかが、めっちゃ気になってしまった。
といっても、何にせよ、柄本明さんの小見浦憲男が、
いちばん心に残って怖くて痛かったなー。
帰化した在日3世の城戸に対する
他人の痛いところをえぐるような煽るような言葉と演技が...。
他のみなさんの演技もスゴイし、ストーリーも面白かったんですが、
ただ、残ったのがそのシーンで、この作品のメッセージが、
柄本明さんの言ってること全てに思えてしまいました...。
だから、わたしの中では他がボヤけてしまって、薄まってしまった。
あとは、
違う自分になってでも自死することなく生きるなら、
戸籍売買が犯罪だとしても.、それはそれで良いと思ってしまいました。
うん、原作を読んでみよう。
与えられた背景と自身が生んだ経歴と
宮崎で林業に従事する谷口大祐が亡くなって1年後、法事にやって来た大祐の兄から弟ではない別人と告げられたことで、弁護士が身元を調査する話。
谷口大祐は誰なんだ?過去に何が?が主な話しかと思ったら、確かにその部分もあるけれど嫁に呼ばれてやって来た横浜の弁護士がメイン!?
結構なご都合主義でXの父親の素性と遭遇、判明しちゃったのは頂けなかったけれど、そこからみえてくるXの過去はなかなかキツい。
ただ、リアルな話しだと正式な手続きでも氏名は変えられるはずだけど。
そして小見浦に見透かされた弁護士は、ここで知り得たそんな世界に憧れて、初めての店での息抜きですか…これは憐れで哀しさを感じた。
そして、プライベートでは仕事を活かしたのか泣き寝入りなのか、その先が気になった。
ラストシーンまで引き込まれます
ある人生
平野啓一郎原作×石川慶監督「ある男」を観る。「愛したはずの夫は全くの別人でした」というコピーに「よくあるストーリーだよな、でも平野啓一郎さん原作だし」とあまり予備知識無しで観たら、予想を覆えす作品で、妻夫木聡が在日3世の人権派弁護士役でその妻を真木よう子が演じ、王道ミステリーの形式を取りながら、人を出自で判断する行為がいかに当事者の人生を狂わせるかを描き、その愚行を糾弾する傑作。妻夫木と窪田の演技と2人の人生がシンクロしていく構成は圧巻だった。
劇中のニュースでリアルなヘイトデモとカウンターのシットインが登場し、露骨なヘイトスピーチもあります、今もあるヘイトを描くために必要なシーンなんだけど、結構しんどいのでそこは気をつけてください。
#ある男 #妻夫木聡 #窪田正孝 #安藤サクラ #石川慶
自分の中の偏見に気付かせてくれる作品
ラストで「そっちだったんかぁ~い」って叫びたくなる邦画! 本年度ベスト!!
私はどうやら本作の主人公を終始勘違いして観ていた様です(笑)
でもこれが本作の満足度が上がった感じ。
巧妙に作られた脚本が良かった!
個人的に脚本賞を差し上げたい!
ラストの騙された感からのエンドロール。
最初に出てくるキャストの方の名前。作者の、してやった感が伝わって来る。
安藤サクラさん演じるバツイチの谷口里枝。
里枝の住む街にやって来た窪田正孝さん演じる谷口大祐。
二人が急接近して結婚するものの、大祐が仕事中の事故で他界。
疎遠だった大祐の兄が遺影を見て大祐では無い事が発覚。
妻夫木聡さん演じる弁護士の城戸が大祐が何者なのかを究明して行くストーリー。
大祐と呼ばれる男の過去が少しずつ解き明かされるストーリーに引き込まれる。
窪田正孝さん演じる男の過去が重い。
でもお目当てだった河合優実さんとのシーンは羨まし過ぎた(笑)
彼女はトータル2分位しか登場しないと言う贅沢な使い方だけど河合優実さんファンなら必見の作品かも(笑)
窪田正孝さんをはじめ、安藤サクラさん等、ベテラン俳優さんの安定した演技が良かった。
真木よう子さんや清野菜名さんは美しかった。
河合優実さんは別格(笑)
終始シリアスな展開に加え、笑わせてくれるシーンもあり大満足の作品でした( ´∀`)
誰しも
誰しも有るのかも知れない。
人に知られたく無い、いや自分の経歴自分の記憶からすら無かった事にしてしまいたい過去や事実。
そんな個人の「秘め事」をミステリとして解釈し暴いてしまう映画です。
知りたいと思う、知る権利が有る。
まあそりゃ解る、俺も映画館に足を運んでしまったのだ、人の秘密となれば暴いてみたい知りたいのです。
本作では主演、妻夫木聡や安藤サクラが「知りたい者」として描かれ、最終的にその秘密を知る事とゴールを迎えます。
まあそれなりのハッピーエンドだ、目的は達成されエンドロールですよ。
が、この映画の面白くも怖いところは
じゃあ、あなたが秘密を暴かれる側になったらどうなの?
じゃあ、求めてもいない秘密を知らされても受け止められるの?
って、意地悪に提示してくるんすよ。
人の秘め事を探し暴くのも大変だけど、それを知り受け止めるのにも命張って下さい。
たぶんそうしないと釣り合わないんですよ、知るって行為は。
残尿感
必ずしも安易なハッピーエンドは望んでいない。
むしろ心に何らかの痛みがあった方が心地良い。
だが、今回のそれはいまいちスッキリしない。
予告編からはサスペンス的な展開を期待していたが、ほぼその要素はない。
柄本明の怪演は見事だったが、それはあまり活かされていないように感じた。
根底に流れるヒューマニズムがこの映画のメインテーマで、それは子供の言動を通じて心に響いた。
一方で死刑囚の子供に対する差別と同様もしくはそれ以上に
在日差別をクローズアップすることに違和感を禁じ得ない。
これは子供の頃に学校の映画観賞で「橋のない川」を観せられて何のこっちゃと思ったのに似ている。
だから、この映画の本質、妻夫木の存在意義が理解できていないのかもしれない。
在日の方々なら深く感情移入できるのだろうか。
全体としてはつまらなくはなかった。
どうなるのか興味津々で過ごすことができた。
だからこそ中途半端な感じのラストに理解しきれていない感じが残った。
これから他の方のレビューを拝見して考えたい。
そういうことね…
何故か落ち込んだ
ある男たち、ある女たち
笑顔に隠された心のざらつき
全409件中、321~340件目を表示