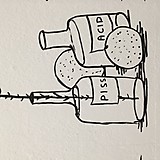ある男のレビュー・感想・評価
全556件中、281~300件目を表示
面白いけど、よくわからない
ちゃんと解決してるんだけど…。
言いたいことは何となく伝わったんだけど、それだと最後のバーのシーンがいらない感じがする。
謎解きも最初と最後がわかった後に間がわかるのが何となく謎解き要素が薄い。
全体的にスッキリしない。
タイトルなし(ネタバレ)
とても面白いミステリー映画でした。
息子を亡くして日々意気消沈して過ごしていた安藤サクラさん演じる里枝は故郷の文具店で働いていたが、そこにある男が画材道具を買いに通うようになり、二人は徐々に仲良くなっていきやがて結婚するが。その男は群馬県の伊香保温泉の次男坊という経歴と妻の里枝には話していたが、男が仕事中に不運な事故で亡くなってしまったことをきっかけに、その男が実は違う経歴だったことがわかり、その調査をしていくことになり。
とても良くできたストーリーで、最後まではらはらと楽しむことができました。
映画の終盤の里枝の「全部分かってから言うのもなんですが、本当はどんななんだって、どうでもよかったんだなとわかりました。だって、私が彼と過ごした二年半の日々は事実だったんだから」と言うセリフはとてもよかったなと思いました。
妻夫木聡さん演じる弁護士の城戸も自身の出自からこの事件に自身を重ねたり、また男自身の壮絶な人生が描かれていたり、人生についてしっかりと向き合いさせてくれる内容でした。よかったです。
ミステリーと差別と家族愛
短時間でとても丁寧にまとめられていました。
安藤サクラ演じる家族パート
小籔が出てくるミステリーパート
妻夫木の家族と差別パート
この要素をまとめるのは大変だったろうなと思います。
安藤サクラが再び登場したとき、「あ、そう言えば出てたんだ」と思ったくらい、それぞれのパートが濃厚でしたね。
冒頭の安藤サクラの涙のシーン、そして柄本の演技は圧巻でした。本当に「食う」という表現が合うと思います。めちゃくちゃ印象に残りました。窪田さん、でんでん、皆さん演技素晴らしかったです。妻夫木さんは下手ではないけど凄い上手くもないので、小籔出てなかったらヤバかったですね。
妻夫木演じる主人公が、事件を通して自分自身の中にある在日差別への感情や、家族との距離感に気付いていって、最後には自らも過去を全て捨ててしまうという決断に至るというのが、見ていて本当に自然と理解出来ました。苦しかったんだろうなあ、と。
いくつかちょっと無理があるところもありました。特に親子で同じような絵を描くというのは、ありえないかなと。死刑囚の心理状態から来る表現と、その親を憎む子供の絵が一致するのは変ですね。
ミステリーとしての完成度は低めだと思うので、いっそのこともっと簡単に判明させても良かった気がしました。欲張り過ぎかなと。
伊香保、宮崎、東京と舞台を移しながら、象徴的なバー、刑務所、桜と、見ていて飽きさせなかったです。ところで刑務所はブローカーの収監にしては厳重でしたね。柄本なので超凶悪犯に見えてしまうので不思議です。
音楽も良かったですね。映画らしい映画でした。石川監督の地力を感じました。
今後も注目したいと思います。
誰でも 時には ふと"違う人物"に成りきってみたいものです。
謎めいた映画題名とそれに伴う 予告編 は 人を引き付ける魅力があって、
僕は映画館に自然と引き寄せられるように、この映画を鑑賞しました。
ミステリー・サスペンス調の映画に成っているが、実は在日弁護士から描く"在日問題"を考えさせる映画にも なっていた。
"親ガチャ"から得られる自分のアイデンティティを良しとせず、
隣の芝生ならば、青く見えるのだろうか?
男たちは 何も背負っていない処から、人生を再出発したいと考えた。
そんな過去を抱えた2人の男と違い、
肩書ではなく、"今"を大切にしている ある男 の妻子は「真髄のみを大切にした」違いは考え深いものであり、本作の答えであり、誠のテーマとなっていた。
どんな人生でも、それなりの厳しさがあり、「けして蒼くはない」って事
だから、誰かが捨てたアイデンティティでも、他から観れば、魅力的だと言う事。
自分の人生 自分なりに楽しみましょう。
この映画を観た後に、映画「万引き家族」と見比べると面白いかもしれない。
「流浪の月」でも良いかも。
自分とは
後を引く,考えさせられる映画
解りやすそうで難しく,後を引く映画でした.
登場人物全ての設定と演技が非常に良かった.小藪さん演じる同僚弁護士は,映画全体が重苦しくなるのを防ぐ重要な役なのかと思いました.
城戸弁護士は,刑務所で接見した柄本明さん演じる詐欺師に,「あんた韓国人やろ.顔をみたら分かるわ」(セリフを正確に覚えていないので,こんな感じのこと)と,いきなり言われてしまう.大祐探しとは無関係のことなのだが,詐欺師はそれに執拗にこだわった.これまで,妻の家族にも在日3世であることを話題にされたりしていたが,やはりこの詐欺師の言葉が,城戸弁護士の心の歯車をカチャッと狂わせるきっかけになったのかなと思いました.
ここでの柄本明さんの演技はすごいと思います.
最後のスナックでの会話シーンの解釈が難しい.
自分が植えた木は,生きているうちには収穫できない.子供の世代に託していく.
これが意味するのは,他の誰かに入れ替ることの功罪は,次の世代で判断されるのか.
大祐が,自分が切った木によって命を落とすことの理由に絡むのかなと思います.
人は変わることができるという言葉が,なんとも軽く聞こえるように思いました.
他にもたくさんの名場面がありました.良い映画だと思います.
ラベルと中身。何が真で、何が偽なのか。 張り替えると偽なのか。そもそも真とは何か。
映画はたんたんと進み、終わる。
ミステリーとして観ても、人間ドラマとして観ても、胸にとどめておきたいような珠玉のシーンはあるものの、大きなカタルシスに向かってドラマが進むわけでもなく、ラストの意表をつくようなシーンはあるものの、どんでん返しというほどではない。
役者の演技で及第点ではあるものの、すべてが薄まった、帯に短し襷に長し、今一つのうまみが足りないもどかしさに、映画館を後にした。
なのに、なんだろう。後からじわじわ来る。
里枝と、自称大祐、里枝の母も含めた5人家族が、頭の中でかってに動き出す。
悠人が父の面影を追う姿。
城戸夫妻のそれから。
城戸自身の生きざま。
谷口のサイドストーリー。
小見浦のサイドストーリー。
そして、曽根崎のサイドストリー。
原作未読。
かなりはしょって映画化したのだろう。エッセンスだけを集めたように。
ラベル。
合法・違法な手段でラベルを変えることで、変わるもの・変わらないもの。
なりすました自称大祐。
帰化という形で、国籍というラベルを付け替えた城戸。
親の離婚・再婚によって、姓が変わる悠人。
自身の結婚・離婚によって、姓が変わる里枝。
ラベルこそ変えないのに、ラストに鵺の様相を見せる城戸の妻。…あなたは何者なんだ。
そして、その妻の真実を知って、城戸はカオナシになる。
城戸が被った仮面…。心の安らぎを求めたのか。
自分とは?
小見浦も言っていたが、その人がその人である証って何なのだろう。
他人が認める自分だけではなく、自分が認識する自分。
人生にいくつもある「たら、れば」
こうありたい自分と、こうである自分。
母であり、妻であり、子であり、女である里枝と城戸の妻は、それぞれにそれぞれの顔を見せる。
父であり、夫であり、子であり、男である城戸と自称大祐も、それぞれにそれぞれの顔を見せる。
そこにも、「父である」とか「弁護士である」とかのラベルが存在する。
戸籍を変えることで(帰化という手段で国籍を変えることで)、自称大祐や城戸が手に入れたかったものは何なのだろう。そして、手に入れられたのか。
自称大祐に関しては、手に入れられたのだと思いたい。
ラベル(名前)を付けることで、不特定多数の対象が、誰でもない特別なものになる(A manから The man)。そのラベルを付け替えたら…。
でも「ぼくのお父さん」というラベルの付け方もあるんだな。戸籍上・血縁関係がどうであろうと。
ステップ・ファミリーや事実婚の関係性。何を本物とし、偽物とするのか。心のつながり。制度のつながり。
「分人主義」
原作者の平野氏の講演を聞いたときはわかったような、「面白い発想」と思ったものだ。
だが、この映画を観てよくわからなくなった。
結局、自称大祐が手に入れたものは、それまでの人生で培った人間性によるものではなかったのか。彼の悩み・苦しみ・絶望が、人への優しさ・慈しみに昇華されたからこそ、手に入れられたもの。「ラベル」こそ変えて、リセットできたから、その優しさ・慈しみを素直に表現できたのではあるのだが。そして、それは悠人に受け継がれていく。
反対に、瓦解していく城戸。息子が名付けた金魚の名前で困惑。息子と同じものが見られない城戸。象徴的なシーン。
時間がたつにつれ、様々なことが頭に・心に浮かんでくる。
余韻がいつまでも響く。
★ ★ ★
しかし、原誠のトラウマは半端ない。
死刑囚の息子という境遇。
友達のうちに遊びに行ったら、まさかの場面に遭遇。その現場を見ただけでも、トラウマ必須なのに。その犯人が父だなんて。その父から手渡しされたもの。
なぜ、彼は顔を変えなかったのだろう。
余計な装飾を加えない俳優陣が素晴らしい
天才同士の融合
タイトルなし(ネタバレ)
九州で暮らすシングルマザーの谷口里枝(安藤サクラ)。
夫と暮らした横浜から離婚後、実家に戻り、役所勤めしながら実家の文具店を手伝っていた。
ある日、文具店にスケッチブックを買いに来た青年(窪田正孝)がいた。
どことなく暗い感じで、どこか他所からこの町に来たらしく、いまは山仕事の見習いのようなことをしている。
暗い感じだったが、無口で誠実なところがあり、しばらくして彼は里枝に自分が描いた絵を見せ、谷口大祐と名乗った。
絵には、神社で遊ぶ里枝の一人息子が他の子どもたちと一緒に描かれており、それがきっかけで二人は交際するようになり、やがて結婚、ふたりの間にもうひとり娘を授かることになる。
が、不幸にして、彼は伐採作業の際に事故を起こして、倒木の下敷きとなって死亡してしまう。
一年後、一周忌の後、彼が生家と言っていた北関東の温泉宿に連絡をし、彼の兄という人物・谷口恭一(眞島秀和)が訪ねてくるが、仏壇の写真をみた恭一は「写真の人物は弟とは似ても似つかない・・・」という
といったところから始まる物語で、その後、里枝が離婚の際に世話になった弁護士・城戸章良(妻夫木聡)に連絡し、大祐と名乗っていた男性の素性を調査することになる。
ミステリの物語としては、宮部みゆき『火車』などで描かれた戸籍交換の物語で目新しさはありません。
そう、目新しさはないんです。
谷口大祐と名乗っていた人物の素性が殺人犯の息子というのもテレビの2時間ドラマで幾度となく登場した設定で、新しくはありません。
だからといって、この映画がつまらないかというとそうではなく、常に観ている側を不安に陥れてくるあたりが興味深く、その原因がどこにあるのかを考えながら観ました。
観ている側を不安にする要素は、ずばり「アイデンティに対する不安」「自己存在に対する不安」です。
自己存在に対する不安といっても、いわゆる自己肯定感の乏しさ、自己に対する承認欲求への不満とかというものではありません。
アイデンティを、理系的に分析したというか、そういうところです。
少々七面倒くさい話になりますが、大学時代にスイスの学者ソシュールの記号論を学びました。
言語や記号はふたつに分解でき、
ひとつは、言語は音声、記号ならばその形象(シニフィアンといいます)
もうひとつが、その音声・形象が指すイメージ・概念、ないしその意味内容・本質(シニフィエといいます)
です。
記号論を推し進めると、いわゆる音声・マークなど記号のほかの物事を、シニフィアンとシニフィエに分解することができる、というものです。
(かなり昔に習ったことなので、現在は変化しているかもしれませんが)
さて、自己のアイデンティというものも、シニフィアンとシニフィエに分解が可能で、
名前はシニフィアンで、自己の本質的存在はシニフィエと言えます。
窪田正孝が演じた男の最終的なシニフィアンは谷口大祐で、
谷口大祐には「老舗温泉宿の次男坊」というプロパティ(属性、付属的性質)があります。
しかしそれは男のシニフィエではありません。
シニフィエは、殺人犯の息子というプロパティに苦悩して生きてきた「暗いけれど誠実な男性」です。
しかし、多くのひとびとは殺人犯の息子というプロパティを、男の本質だと見誤ってしまう・・・
そして、谷口大祐の過去を調査するうちに、自身のアイデンティに不安を感じる男が、弁護士の城戸章良。
彼のプロパティは、人権派弁護士のほかに、在日韓国人三世というものがあります。
(柄本明演じる戸籍ブローカーの言では「男前の」というのもありますが)
その城戸は、調査の過程で自身のアイデンティのシニフィエを見失っていきます。
(「暗くはないが明るくもない、が誠実な男」といったところでしょうか)
ここが怖いところです。
表層と属性に惑わされて、自己の本質を見失う・・・
何々社の誰それさん、どこどこのパートさん、誰それのおとうさん・おかあさん、
何々で活躍したひと、何々でしくじったひと・・・
それらは本質じゃない。
じゃないけれど、それらが持つ意味は社会的に大きい。
そして、自己の本質を見失う不安が常にある。
そういう意味で、観る側を不安にさせる映画でした。
<追記>
この映画を観ている間のわたしは「映画を観ているひと」であり、それ以外の何者でもありませんでした。
内容的には面白さを感じたものの・・・
世間の闇の部分
「映画」版『ある男』が、視覚を通して思考させる、傑作!
ミステリー小説『ある男』の、映画版!
(映画化ではなく、映画版)
石川監督は、「人が生きていく中で、かかわる人たちとの関係性をつなぐ個々人の真実」とは、何なのか?
「事実を全て知ることが(は)、生きる上で、最善、最重要なのか?」
映画(映像で)を通じて、私たちに分かりやすく、突きつけてくる。
素晴らしい俳優陣が、作り出したこの作品では
主役の妻夫木さん、安藤さん、窪田さん、
さえも、作品の一つのピースでしかない
(それほどに、よくできた作品)
オープニングの一枚の絵
の意図する答えが
ラストカットに明かされる!
深い深い映画です。
*生い立ち、親族、国籍、宗教、仕事、収入、身体、体型、外観 etc.
きっと、私たちは、どこかで、何かを差別している、させている・・・。
ラストは不倫ですか?
象徴的な絵
考えさせられる
レビューを書こうとしてここの、すでに書いてあるレビューをみて考えてしまった。
そうだよなあ。戸籍って何なんだろう。
俺の上に乗っかっている、あの紙1枚。あれが俺のすべてを証明している。
で、いいのか?
俺は本当に俺なのか? 俺は俺を代えられるのか?
脚本と役者がしっかりしているから落ち着いてみることが出来た映画でした。
・妻夫木聡と窪田正孝。役者だなあと思います。いつも違和感なく作品のなかに引き込んでくれる。
・柄本明・・・少しの場面だけでも作品全体を締めてくれる。存在感がゆるぎない。
・田舎の文房具屋さん・・・他のコメにもあったけど、独特ですよね。
誰もがあそこで買い物をした経験がある。鉛筆やスケッチブックを買った経験がある。なつかしい。
今の子はショッピングモールでしか鉛筆を買った経験がないのか。なんかかわいそうだなあと思いました。
本人が知られたくなかったんやから死んでから調べんとってくれる?
戸籍を買って別人になって横浜から宮崎に移り住んでかなり幸せな生活を送り始めるのだけれど数年しか続かず突発的な事故で死んでしまってそれでおしまいで良かったのだがそれではドラマにならず・・・一体ほんとは誰やったんやと、誰が何故に別人になりすましたんですかと、故人が絶対知られたくなかったであろうことを根掘り葉掘りおせっかいなことに調べつくしてどうしたいのどうしてくれんの?脛に傷持つ身というのがある高倉健さんが倍賞千恵子と出会うのもそれだ。前科持ちでも刑期を終えて出てきているのだから隠す必要は無いはずなのだが世間の目というやつ。「世間てなんやねん。その世間一般というやつをここへ連れて来い!」という名台詞もあったことだがましてや出自の秘密というやつ。どこで生まれようがどんな両親から生まれようがそれが何か?私に選択の余地はナッシングでそれによって差別するような輩は銀河系の果てまで飛んできゃいいのに。安藤サクラという役者がうますぎて石川慶監督がワンショットでゆっくりズームインというあまりにも前時代的なカメラワークで見せたくなる所以。
ミステリーより人権とかの印象
締めが自分の好みじゃなかった分▲。
原君の思い的なのもう少し大切にして欲しかった。
丁寧に描写してるんだろうけど冗長にも感じた。
戸籍レンダリングは面白かったし、柄本父はやっぱ迫力ある。
全556件中、281~300件目を表示