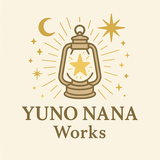シン・仮面ライダーのレビュー・感想・評価
全912件中、1~20件目を表示
父よ、母よ、妹よ
ダブルタイフーン、命のベルト。とはいえ、私が見た仮面ライダーは、精々アマゾンライダーをチラ見したぐらいでしょうか。なので、仮面ライダーはどうあるべきなのかは私が語れることでは無いかもしれません。
でも、実際に素手で殴りつけ、直に脚で蹴り倒し、それが敵を殺傷するほどのものであるならば、どのようなことになるものか。それは映像の話ばかりで無く、ライダーの心を蝕むところから始まる。それが仮面ライダーを突き詰めるべき「シン」シリーズの作品なのかな、と感じました。
様々な場面で当時の特撮らしいサウンドがサービス精神っぽく用いられていますが、なにより、主演のぎこちない口調がなんだか好きです。これこそが正しく当時の特撮っぽくて良いですね。
そして当時の主題歌の流れるスタッフロール、いったい幾つ庵野監督の名前が登場するのかと、数えるのもご一興ですね。頑張ってるなあ、庵野さん。そして最後の「終」ロゴでビシッと締めます。有り難うございました。
優しさを持つヒーロー
池袋の4DXで鑑賞。
私は仮面ライダーをよく知らないで観ましたが、元祖なアクション映画として楽しむことができました。
派手なCGをあまり使わず、肉体で戦うシーンが多かったため、ここから俳優達の本気が伝わってきました。また、音楽も攻めたものではなく、渋い落ち着いた曲調になっており、昔ながらの特撮のイメージが表れていて新鮮でした。
また、アクションだけでなく、暴力と優しさについても考えされられました。主人公の本郷猛が暴力よりも優しさを大事にして戦う姿から、生き残るためには暴力で倒す選択があるにも関わらず、相手を傷つけたくない気持ちを優先した彼に共感できました。また、ヒロインのルリ子もクールな表情で行動している所がかっこよかったです。
ただ、全体的に血が噴き出す場面が多く、虫が大量に出てくる場面もあるため、このようなグロテスクなシーンが苦手な方は注意した方がいいかもしれません。
今回は4DXで観たので、通常で観るよりもアクション映画への没入感がありました。バイクで疾走するシーンでは心地よい風が劇場内に流れ、悪と戦うアクションシーンでは座席が激しく揺れて仮面ライダーと一緒に戦っているような感覚になりました。他にも、変身するときに背後から熱風がきたり、香り効果も意外な場面で使われていて驚きました。
仮面ライダーの基本を大事にしつつ、若い世代でも楽しめる要素を盛り込んだ特撮アクションになっていました。
それと余談ですが、上映終了後に周りから拍手が起きました。私はびっくりしましたが、ここから仮面ライダーが多くの人に愛されていることを実感しました。
Movie of ANNO, by ANNO, for ANNO
「シン・仮面ライダー」観てきました!!
ひと言で言えば、
「庵野監督の 庵野監督による 庵野監督のための映画」です。
1971年4月からはじまった仮面ライダーシリーズ。1960年生まれの庵野少年は当時11歳。まさにリアルで仮面ライダーに夢中になっていた世代です。
本作はそんな初代仮面ライダーへのオマージュが存分に取り入れられた映画となっています。昭和の特撮感を残しつつ現代CG技術も駆使したそのバランス感が絶妙。音響もちょうどいい塩梅。エンドロールの主題歌3連発からの「終劇」の文字に胸熱必死です!アラフィフ以上はこれだけでも十分に満足して帰れるハズ。
「エヴァ」や「シン・ウルトラマン」で庵野作品を好きになった初代を知らない若い世代には、少し肩透かしをくらう仕上がりになっているかもしれません。
賛否が分かれる作品となりそう。
ただ本作品、
非常に豪華な出演者がちょい役で紛れ込んでいます。それを探すだけでも十分楽しめます。
・見つけられた人
長澤まさみさん
・見つけられなかった人
菅田将暉さん、松坂桃李さん、安田顕さん。
どこにいた?
たぶんあの中の人…
では、
この映画を観るべき人、観なくてもよい人をまとめます。
【観るべき人】
初代仮面ライダーを知っている人
戦隊モノ、変身モノが大好きな人
庵野秀明作品は欠かさず観ている人
【観なくてもよい人】
上記以外の人
庵野秀明監督「シン・シリーズ」最新作!!
初代仮面ライダーを知ってる貴方は映画館へ
仮面ライダーへのオマージュと愛にふれる時間
さぁ、高らかに歌おう♪
{ 仮面ライダー♪〜×2 ライダー♪〜×2 }×2
※まだ観ようか迷っている方の少しでも参考になれば幸いです♪
中間領域の映像に、いかに説得力を持たせるか
巨大化ではないヒーローを、庵野秀明監督のビジョン、実写とアニメーションの中間領域の「トクサツ」空間でどう描くか、これは大きな挑戦だったと思う。仮面ライダーも元々特撮番組ではあるが、ミニチュアものとは映像のあり方が異なる。『シン・ウルトラマン』は巨大化するので、ユニークな遠近感やミニチュアや合成を駆使して特異な空間の創出にある程度成功していた。
実写映画ではあるけれど、庵野秀明監督の作品は現実の再現を目指さない。トクサツ的リアリティラインの再現を目指そうとする。それゆえに3DCGもキッチュ感をわざわざ強調する(シンプルにリアルの再現よりもセンスが要求されるに違いない)。この美学が等身大ヒーローの場合に上手く調整できるかどうかが難しいポイントだったのでないかと思う。結論的には『シン・ウルトラマン』や『シン・ゴジラ』の時ほど上手くいっていないと思う。
それでも、庵野秀明監督の絵のセンスがいいので、全編飽きずに見れてしまうのはさすが。キャスティングの嗅覚も冴えている。浜辺美波じゃないとあのヒロインは成立しなかったかもしれない。女性キャラクターのリアリティのなさは生身の役者に演じさせると気になる時があるが、浜辺美波はそのリアリティのなさをこなしてみせた。
冷めて内省的な変身ヒーローに、半世紀の隔たりを思う
小学生の頃はテレビ放送の「仮面ライダー」人気が結構大きくて、変身ポーズやライダーキックを皆で真似したり、サイクロン号の人気に便乗?して売り出された電子フラッシャー(電池で光る方向指示器)付きの自転車を比較的裕福な家の子が買ってもらって羨ましがられたりしたことを覚えている。本作の本郷猛はなぜ変身ポーズをとらないのかと鑑賞中は疑問だったが、あとでWikipediaの「仮面ライダー」の項を見たら一文字隼人が登場してから変身ポーズが導入されたと書いてあった。そのあたりもオリジナルのシリーズに忠実だったかと感心した。
脚本・監督を庵野秀明が務めたことも大きいのかもしれないが、池松壮亮が演じる本郷猛は、オリジナルの藤岡弘が演じたキャラクターよりも冷めていて内省的な印象で、高度経済成長期の昭和と震災やコロナ禍を経た令和5年の今、半世紀分の隔たりが反映されてもいるのだろう。柄本佑が演じる一文字隼人の軽妙なノリ、SNS風に「いいね」とサムアップさせるあたりも憎いアップデートだ。
本作、スクリーンでの試写はパスしてしまい配信での視聴となったが、テレビ画面サイズで観るのも悪くないスケール感かなと思う。子供の頃にテレビで元のシリーズを観ていたことが刷り込まれているのかもしれないが。
客層からは漏れていると思うが、惚れ惚れはする。
困っている。庵野秀明というひとが作る以上、度を越したマニアックな要素が入ってくるだろうし、世代的にはちょい後追いなので、その意図をすべて汲めるとは思っていなかったものの、思っていた以上の難物がきた。ライダーの造形、美しいトランポリンアクションなど昭和特撮に馴染んだ身にはたまらない要素が詰め込まれている一方で、ハニメーションを彷彿とさせるアニメ風アクションが混ざってきたりして、作品のバランスが掴めずに翻弄されるのだが、確かにどれもこれも濃厚に庵野秀明であって、強烈な作家性がモロ出しになっている作品だとは思う。
じゃあ面白いかというと、面白くはない。もう庵野的なものの先を見せてほしいというこちらの勝手な気持ちもあれば、予算のせいなのかそもそもオリジナルへのリスペクトからきた意図的なものなのか、にじみ出るチープさに心から乗っかれないもどかしさもある。この映画や物語が、どうしても切羽詰まったなにかに刃を突きつけているようには感じられず、形式や作法がいちいち空虚に思えてしまったからかもしれない(空虚さは庵野作品にはつきものとは思うが)。
さりとて思い出すのはライダーのカッコいいジャンプだったり宙返りだったり、やたらとカッコいい瞬間ばかりが脳裏に焼き付いている。それは動き、構図、画調といったさまざまな要素が組み合わさっているからで、それはそれでいい映画じゃないかと思えてくる。でも見直したらやはり、面白くはない、と思うんだろうし、それでも魅了される瞬間がときおり表れては、つい惚れ惚れとしてしまうんだろう。
大人向け仮面ライダー。過去の仮面ライダーの整合性を最新に再構築したという点からは評価に値する作品。
本作は冒頭の映像などからPG12と指定されている「大人向け仮面ライダー」となっています。
子供向けな作品であった1971年放送開始の特撮テレビドラマ「仮面ライダー」は、予算や技術の面などからも、いわゆる「子供向けテレビクオリティー」にならざるを得ない面がありました。
それを今回、「シンシリーズ」としてリブート版を作る意義として、キチンと整合性を再構築し、あらゆる事象を論理的に作り上げたという点において本作の意義は十分にありますし、大人の鑑賞に耐えうる作品にしたのは評価に値します。
「仮面ライダークオリティー」を高めたという視点から評価は最高峰として認定できます。
ただ、一般の映画として楽しめるかというと、これはかつての「仮面ライダー」シリーズにどこまで愛着を持っているのかによって変わると思われます。
庵野秀明監督らしく、これまでの「エヴァンゲリオン」などを感じられる背景のシーン等、「らしさ」全開でしたが、これは視点を変えると、今後の展開への「伏線」なのかもしれません。
強いて言えば、戦闘シーンは「実写版」での限界も感じられました。アニメーション映画であれば凄いシーンの連続になったのでしょうが、実写であるが故に動きが必ずしもスムーズではなく魅力が減る部分でもあります。
あくまで、かつての「仮面ライダー」の世界観を踏襲し、それを最大限リアルに仕上げた作品として見るのが正解なのでしょう。
池松壮亮の奮闘ぶりに感嘆 女優陣の振り切った姿も見逃せない
庵野秀明監督作ゆえ、一筋縄ではいかないのは誰もが承知のうえであろう。
シン・仮面ライダーはシン・ゴジラ、シン・ウルトラマンと異なり等身大のキャラクターのため、それゆえの難しさはあったはず。
それにしても、池松壮亮の奮闘ぶりには感嘆せずにはいられなかった。
1フェーズどころか、2フェーズ上がったのではないか…と感じるほどに、痛みの分かる主人公を見事に体現してみせた。
また、女優陣(浜辺美波、西野七瀬ほか)の振り切った姿には、声が漏れそうになる。
私はIMAXで鑑賞したが、個人的にはビッグフォーマットでなくても十分に楽しめたかもしれないということは記述しておく。
表層だけの変身(へん~~~しん)
難解な言葉を並べることで深みを出したつもりなのだろうか。
セリフの数々に、まずうんざりさせられる。
だが問題は言葉遣いだけではない。
ストーリー構成は単調で、脚本は冗長、そして何よりキャスティングが作品と噛み合っていない。
誤解してほしくないが、役者が悪いのではない。
問題なのは、その俳優を、その役に当てた判断そのものだ。
本郷猛、一文字隼人、立花藤兵衛、滝和也、そして緑川ルリ子――
いずれもキャラクターとして「滑っている」。
立花はおやっさんであってほしいし、滝は、そこにいるだけで懐かしさがこみ上げてくる存在であるべきだ。
だが本作では、感情がまるで立ち上がらない。
特に立花と滝に関しては、『シン・ウルトラマン』の感覚がそのまま持ち込まれているように見え、違和感というより怒りを覚える。
ここまでくると、この作品は、
仮面ライダー第一世代への目配りを欠いたまま、その記憶だけを借用しているように思えてくる。
それは敬意とは言い難く、むしろ冒涜に近い。
そんなに我々の世代が羨ましいのか。
それとも、憎いのか。
「エヴァ」の監督はいったい、何をしたかったのだろう。
正直なところ、完全に迷走しているようにしか見えない。
年齢的に考えれば、仮面ライダーは彼にとって小学校高学年の作品で、
その歳、自分は、Xやアマゾンのライダーをすでに卒業していた世代でもある。
そう考えると、この「シン・仮面ライダー」は、
監督自身の体験が最も薄い場所から作られてしまった作品なのではないか、という疑念が残る。
登場人物の表層だけを取り出して並べても、それは大人が解釈した仮面ライダーにすぎない。
必要なのは分析でも再構築でもない。
仮面ライダーを本気で求めていた、あの頃の「子供の心」だ。
意味もなくライダージャンプやライダーキックをしたくなる、あの衝動である。
どうも本作は、男女のショッカー隊員がベレー帽をかぶっていた、
陰影が強い初期ライダーの世界観にこだわりすぎたように思える。
だがそれは「シン」ではない。
それをやるなら、「コア」と呼ぶべきだろう。
それにしても――
ロボット刑事Kはどこへ行った?
ついでながら、
せっかくここまできたら、あの時代の少年少女がワクワクした「キューティーハニー」を「シン・キューティーハニー」で作ってほしい!と思っていたら、作ってるやん! (笑)
見てみようっと。(なんやねん)
シン・仮面ライダー
仮面ライダーも敵のオーグも良い。が…
こういうのが仮面ライダー
最近の子供向けという言い訳で女性オタク向けに成り下がったアホのような仮面ライダーを一蹴する作品。
仮面ライダーは別にイケメンを眺める為の装置じゃねぇ。
人間を超える『暴力』を持った辛さ、孤独。
それでも人間で居ようしてその力の責任を果たそうとする者。
それが俺が子供の頃に憧れた仮面ライダー。
この作品には最近の仮面ライダーが完全に忘れてしまっている暴力(敵も仮面ライダー自身も振るう力)の恐ろしさとそれと戦おうとする美しい心が全て描かれている。
そしてだからこそ丁寧な描写で話の中から『必然性』を持って突入する戦闘シーンの説得力は段違いだしその映像自体も『暴力性』を強調した冒頭、人を超えた力を強調する中盤以降、最後は生身の人間として必死に生きようとする泥臭い肉弾戦と三つの描写が絡み合い全てが『戦闘で仮面ライダーを表現すると言う事はこういう事だ』と伝えている。
本気のライダーファンが作った本気のライダーであると思うしこれが合わない人はそもそも仮面ライダーという『本来は異端な』ヒーローのメッセージを受け取れない人だと思う。
ヒーローである前に人間であり人間が藻掻くからヒーローたり得る。
という普遍の法則を丁寧に示してくれる作品。
心の中に正しく正義を愛する心があるなら必ず響く作品。
主人公は誰?(笑)
面白いことは面白かったが、仮面ライダーよりも浜辺美波のほうが主役だったような(笑)。最初はまた専門用語みたいな難しい言葉連発でこっちがついてけないまま話が進み、そこがちょっとあれだったが、元祖『仮面ライダー』初期や石ノ森章太郎の原作マンガ版みたいなダークな作風は良かった。怪人が泡になって消えちゃうのもオリジナル版初期の演出だし。
あとロボット刑事みたいなやつが出てきたと思ったらKって名前で、やっぱロボット刑事Kじゃん!て思った。そう考えると、その前のJもキカイダーっぽいデザインだったが、そういやキカイダーの名前はジローでイニシャルはJだなと思ったり。立花藤兵衛は出てこないのかと思ったら、竹野内豊が立花で斎藤工が滝。てっきり『シン・ウルトラマン』からのゲスト出演かと思ってた。長澤まさみもサソリオーグだったんだな。観てる時は誰だかわかんなくて、エンドロール見たら名前が出てきた。他にもエンドロールに名前があったけど、どこに出てたかわかんなかった人たちは、本郷奏多がカマキリカメレオンオーグ、仲村トオルが本郷猛の父、安田顕が父を殺す犯人、松坂桃李がKの声、大森南朋がクモオーグの声らしい。
ただハチオーグが出てきたあたりからライダーよりも浜辺美波が主役みたくなってしまった。とはいえハチオーグ(&サソリオーグ)を飛ばすといきなりラスボスとの戦いになっちゃうしなあ。怪人の数も多すぎて若干話が長く感じたが、かといって怪人を減らすと話が唐突になっちゃうし難しいところだ。あと森山未來のチョウオーグがいかにも森山未來でしかないってのもどうも。ロボットKも思わせ振りに出てきながら、特に意味がなかったような。とはいえ全体的には『シン・ウルトラマン』ほどの出来ではないものの『シン・ゴジラ』よりはずっと面白かった。
中盤までのテンポの良さは秀逸だった。30分番組4本分ぐらいの戦闘を前半で描ききった手際の良さは素晴らしい。
シン緑川ルリ子
横に居る仮面ライダーは単なる暴力装置的位置づけ。
懐古趣味的なBGM&SEを使いながら映像とコスチューム、周囲の美術、セットは最新。
わざわざ、チープな感じを出しTV特撮感を押し出したり、色々な違和感を感じつつ視聴した結果、庵野監督の仮面ライダー観はこうだと言いたいのは伝わった。
原作マンガの暗いとことかオーバーな位に盛り込んでいるが、もうちょいすっきりしてほしい。
本郷猛がわざと棒読みなセリフを言い、感情もはっきり出さない様は不満。
〇〇オーグなんて言わせないで〇〇男、〇〇女で良くないか?
サソリが意外にあっさり倒されたのは拍子抜けしたし、長澤まさみ勿体ないって思ってしまった。
ハチのツインテールは好きな人多そうだけど、新選組の突きや牙突めいたポーズ取る位ならサーベルが良かったと思う。
Kを見た時はロボット刑事Kを、蝶オーグはベルトでV3、面でシャドウムーン、イチロー兄さんと言う名前で01、攻撃でイナズマンを想像した。
ストーリーとしては変に捻るよりは良かった。
キャラクターに何度も同じセリフを言わせる気持ち悪さはあったけど、あれだけ、しつこいとネタのつもりなんだろうな。「私は常に用意周到なの」とか「あらら」とか「すっきりしない」とか。
全体にTV特撮だった仮面ライダーのエッセンスを取り入れつつ、石ノ森原作に近い感情の揺れで人を殺す事に躊躇させたり、他の石ノ森作品キャラクターを入れてみたり、怪人もニコイチ作ってみたり、やりたいようにやってる。
ラストに本郷譲りの仮面の色や身体のラインが二本線に変わってコブラオーグを倒すなどの部分が出てくると一気にTV特撮部分の帳尻を合わせてきて、そう来たか…と。
アンチショッカー同盟の2人が名前を明かすだけで、おやっさん〜、滝〜ってなった。
文句言いながらも見てしまう。
昭和仮面ライダー好きな人ならとりあえず観てから文句言えって作品でした。
見ても文句は言うけどね。
思ってたのと違う…。
実はずっと以前に、本作のレビューはしていたのですが、こちらのサイトが合併云々した際に、古いレビューを消されてしまった様なので、改めて記しておくこととしました。重複している部分があったらごめんなさい。
「シン・ウルトラマン」を観ていたお陰で、庵野作品と言えど《過度な期待はしない》で、劇場へ行きましたが、それでも1stライダーの物語ですから、どんな仕掛けを作ってくるのか興味津々だったのは確かです。
ところが正直に言って《エヴァ》の影響が本作にも出ており、生い立ちやら親との関係やらでゴチャゴチャと捻じくれた登場人物が多く、その点ではガッカリしました。
それは確かに《明朗快活な仮面ライダー》を改めて作ったところで、既存の(今やってる)お子様向けのライダーと変らなく成っちゃうのは分かりますが、どうしてこう皆が皆、内に籠った暗い生い立ちの人ばかりに成るのか、「またか…」とウンザリしました。
浜辺美波ちゃんだって、もう少し明るい役に設定したって問題無いでしょう。怪人同士も、知り合いだったり、敵対関係だったり、ライダーと戦う前に政府組織にヤラれちゃう長澤まさみさんの蜂女が居たりと、正直物語の構図が〈仮面ライダーの物語として〉理解できませんでした。
それから森山未來君演じる悪の組織と、池松くんのライダー(と柄本くんの2号)、そしてそれらの先端技術を狙う政府組織の三つ巴の展開も、少し前に何処かで観たような“既視感”が有りました。
但し、メカや装備等の技術面では全く問題無く、素晴らしいギミックに満ちたアイテムが出て来て、この点では流石お見事だと思います。CG合成等も派手に使わず、わざわざ人力で作り出すアクションにはやはり迫力が俄然違いました。
ところが、東映と共同で作る映画なのに「仮面ライダー」伝統の大野剣友会による《戦闘員の取扱い》がとても雑だったのには正直驚きました。
そしてその前後に、本作の製作の裏側をNHKのドキュメンタリーでやっていましたので、見たところ、監督は「大野剣友会さんには充分に頑張ってもらう」と事前に言いながら、撮影が始まると例によってドンドン異なるアイデアが浮かんで来て、やる事が変わってしまい、その辺から東映側の困惑が、画面からでも、ものすごく伝わってきました。
又、ライダー役同士での演技の擦り合せと云うか事前の関係性に関する話し合いについても、森山君が折角「やっておきましょうか?」と提案しているのに『別に、やりたきゃやれば?』みたいな返答をしていた点にも違和感を憶えました。
最終的な決着についても「どうしてそんなに煮え切らない答えにしちゃうかなぁ…」と、ため息が出る思いで終了。
戦闘シーンの迫力や、ワイヤーアクション、スマホで撮る等の『シン・ウルトラマン』でも活用された技術を使って、盛り上がった部分も少なからず有っただけに、勿体無いなぁ…と云うのが総括になります。
池松君だって、そんなに杓子定規に死なせる必要が有ったのかなぁ…。
監督が、若い頃自主製作で作っていた頃の「ライダー愛」は何処へ行ってしまったのか、甚だ疑問に感じました。
庵野監督、もう〈エヴァ的な展開に固執する〉のは止めていただけませんか?
エヴァは御自身でもう決着を付けたのですから、チョロチョロと他の作品に援用等せずに、スパっと断ち切って、新しい物語を作ってください。
そして出来ることなら『シン・宇宙戦艦ヤマト』じゃなくて『続 シン・ゴジラ』の方が余程観てみたいと、個人的には思っています。
激情のなさ
全912件中、1~20件目を表示