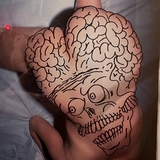14歳の栞のレビュー・感想・評価
全75件中、1~20件目を表示
生きづらさは中学がピークだから安心して!と教えてあげたい
「話題作」「配信されない作品」そして「季節が春」ということで足を運んだ。
しかし、、、、単調。。眠い。感動的な出来事なんて何も起こらない。でもそれは作り物でないリアルであるという証でもある。
おかげで、中学の時の生きづらい感じを思い出すことはできた。
「明るさ」「コミュニケーションとれること」に重きを置かないといけないとか、しんどいよね。わかるわー。
人との関わりや周囲の視線のなかで、自分を殺したり、キャラを演じたり、同調したり、陽キャとして必死に作り笑いしたり、または逆に、斜めに見たり、線を引いて内心小バカにしたり、心を完全に閉ざしたり。。。クリープハイプの歌詞にあるように“空気を読むことに忙しい”。集団に受け入れられながら自分を出すその距離間が中学時代は未熟であり、そのために自己肯定感が低下して、生きづらさにつながる。
ただね。その生きづらさは高校→大学→社会人と、どんどん薄れていくよ。生きやすくなっていく。周りも自分も成長するから。しんどいのは中学がピークだよ、と教えてあげたい。この点において「チケット間違ったか?」と思った冒頭の馬のシーンも「子供から大人に社会的に成長する過程の暗示」として活きてくる。(なくても全く問題なかったとは思うけれど笑)
バスケ部やサッカー部に属するようなクラスの中心系より、不器用な子たちの方に魅かれる。最後の場面「S君、来なくていいから!」と思ってた。こんな集合写真や映画撮影のようなご都合主義に負けんなと。ホッとした。
当時、私の一言が誰かの心を抉ったりしていなかっただろうか。
また逆に、私との関わりが支えになった人がいたりしただろうか。
あの頃のクラスのみんなが何を思い、何を考えていたのか知りたくなった。
※この映画、中学生版の『桐島、部活やめるってよ』の側面もあるね。
※「実在の人物なのでSNSに誹謗中傷をあげないで」と注意喚起があったが、生徒ではなく映画そのものに関する批評はありですよね?でないと公正でない。ひょっとしたら高い評価はこの注意喚起からきている面もあるのかも。生徒たちは演じずにそのまま映ってくれて二重丸だが、映画としてはちょっと「う~ん」だったもの。(期待値が凄く高かったこともあるが)
※映画のエンディングとクリープハイプの歌はどうしてこうも合うんだろ。『ちょっと思い出しただけ』とか。
これが14歳のリアル
14歳、中学2年生の学級の空気感て確かにこういうものだった。ドキュメンタリーとはいえ、本当の空気感を映すことはすごく難しい。なぜなら、人はカメラを向けられるとある程度、自分をよく見せようと「演じる」意識が生まれるからだ。羽仁進は、『教室の子供たち』というドキュメンタリーで、カメラに慣れない子どもたちをカメラに慣れさせるため、フィルムを回さず、教室にカメラを置き、カメラが珍しくなくなってから撮影をはじめたそうだ。この作品の子どもたちもまるでカメラを意識していないかのようだ(インタビューパートは別だが)。
14歳という年齢は、フィクションでもよく取り上げられる年齢だが、この作品を見るとあらゆるフィクションで描かれる14歳が陳腐に見えてしまうかもしれない。それぐらい本物が映っている。普通の中学生の普通の感覚が画面中に充満しており、これが本物かと圧倒されてしまった。これを見ると、青春映画や青春アニメの見方が一変すると思う。
14歳の栞
等身大の自分
社会だなぁ
時代は変わっても学校生活ってあまり変わってないもんだ
竹林監督作品は『MONDAYS』が初で、次に『大きな家』でこれが最後と順番バラバラ。
初公開時は上映最終日の二択でやむなく落選したけど、今回やっと観れた。
リアルな日常を撮ったドキュメンタリーだから、芸能プロダクションに所属する完成された美少年美少女が出てくるわけでも、劇的な奇跡のような出来事があるわけでもない。
14歳というと思春期で、男子と女子の体格差もちょっとずつ逆転していく絶妙なお年頃。
男子は世界共通でくだらない事ばかりやってるし、女子もスカートの丈が膝下で短くしてる子もいない、ごくごくフツーの子たち。
なんだか自分が中学生だった遠い昔を思い出し、それぞれの生徒に似ている部分があったり、こんな奴いたなぁとか懐かしい気持ちになった。
意外にも10代らしき若い子たちが多く観に来ていた。
昨年、この映画の事を知って、公開から5年目で鑑賞できた。 初めて観...
配信もDVDもない映画
ようやく鑑賞出来ました。
配信もDVDもない、こんな映画があっても映画良いでは無いですか。
毎年春になると今年こそと思いつつ、鑑賞できる映画館も少ないので、今年も無理そうでしたが、平日の仕事の合間に鑑賞しました。
映画館ありがとう。
「大きな家」もとても良かったけどこちらもいいドキュメンタリー映画でした。どちらかと言うと、こちらは本当に普通の中学生。自分もこうだったな、、と、さわやかに切ない。
何十年経っても、中学生は変わらないのか。ちょっと安心。
SNSで個人攻撃するひといるのかね?
てっきり、イジメや何か叩かれるような描写があるのかも思ったけど、みんないい子だな。
先生や親目線で見ると泣ける。
自分が14歳の時は、朝礼や集会に出るのが嫌で放送委員長に立候補してたな、、、
偶然か、コロナ禍前の普通の中学生の生活ですが、この普通さも今では尊い。
子供たちは去年か今年?20歳になったかな?思い描いていた大人に近づいていれば嬉しいし、全く違うことのなっていても頑張って欲しい。
たしかに 心のタイムマシーンに乗った。 私の学生時代は、今より自立...
どこにでもいるリアルな中二を撮影できたのにビックリ!
私は、どんな14歳だった?
この映画をみて、14歳の自分を思い返す。
ある1人の女の子が、「子どもからやりなおしたい」って言っているのをみて、心の中で、“まだ14歳なのに"と思ったけど、14歳の時の自分も、そういえば同じ事を考えていた。
この映画をみたら、なぜか大嫌いだった中学生の時の自分が、愛おしく思えてくる。14歳という時期を、14歳らしく過ごせて良かったと思える。
カメラの前にいる35人の生徒たちは、いつも自然体に見えて、なんだか映画館の中で中学時代にタイムスリップしたような感覚だった。みんなが、みんなのあの頃の同級生だったし、自分だった。
この映画は、映画館でしかみることができない。映画館で、あの35人に出会えて本当に良かった。嬉しかった。またこの作品をみたい。この映画のチケットは、私の大切な「栞」として取っておきます。
映画館でしか見られない今後も配信サービスされない映画
ドキュメンタリー楽しめました。
中学生に限らず日常は淡々の流れて行きスーパーヒーローなどいませんしビックリする様な大どんでん返しな話しはありません。でも中2の頃って特にそうだなと思いました。些細な事件までは行かなくとも盛り上がったり問題提起はあっても何となく曖昧に時間が過ぎて行きます。
何十年も前ですが自分も中2の頃はそうでした。
出てくる生徒はカメラがあるのが日常になってしまったのか構える事無く振る舞ってるのも良かったです。
自然な言動はどんな役者でも敵わないなとも思いました。
誰もが通る道The Path Everyone Walks
気がつくのが遅れて何度か見逃し、
今回、気がついたタイミングで、
時間もいけそうだったので、
ようやく観ることができた。
自身のあの頃はあまり思い出したくない。
今振り返ると、
同級生の中には、
それぞれ光る才能を持っていたなと。
踊りの上手い子(チアリーディングだったか)
絵の上手い子(息をするように見事な絵を描いていた)
頭の良い子(自分みたいな付け焼き刃ではない)
を思い出す。
それに比べると、
自分には夢中になる何かは無かったのも
覚えている。
と同時に、多少なりとも自分自身の
その後が変わり始めた時期でもあった。
出演している学生たちは
生命力に溢れていて、
同時に簡単に変形してしまう危うさも感じた。
映画に出ていたその後に幸あれ
と思わずにはいられなかった。
色々考えさせられる意味でも
とても良い映画でした。
「小学校 それは小さな社会」と併せて観てほしいです。
I missed it several times before realizing it,
but this time, I noticed it at the right moment,
and since I had time, I was finally able to watch it.
I don’t really want to remember those days of my own past.
Looking back now,
I realize that many of my classmates had unique talents.
I remember:
• A student who was great at dancing (perhaps cheerleading?)
• A student who could draw breathtaking pictures as naturally as breathing
• A student who was truly intelligent (not someone who just crammed knowledge like me)
Compared to them,
I remember that I didn’t have anything I was truly passionate about.
At the same time,
I also recall that it was a period when, in some way,
my life started to change.
The students in the film were bursting with vitality,
yet at the same time,
I could sense their fragility—how easily they could be shaped and reshaped.
I couldn’t help but hope that they would find happiness in the future.
It was a film that made me reflect on many things,
and for that reason, I found it truly wonderful.
I highly recommend watching it alongside
“Elementary School: A Small Society.”
14歳のリアリティショー?
厨二ではなくマジ中2のリアルってことで高評価を得ていた本作、再上映を機に鑑賞。1クラスの生徒に50日密着し全員を描くというアイデアは興味深いし、取材・撮影の苦労も相当とは思われるが、正直、企画倒れという印象。120分で35人を紹介するには1人あたり3分ほどしかないわけで、おもしろい・気になる発言もあるにはあれど、それで35人全員やれば「14歳の何か」が浮かび上がるってわけでもないと思う。どうせなら1年間全員に密着して12時間ぐらいの作品にしたらよかったのではないだろうか(誰も観ないけど)。
そもそも産まれたてのウマの画に「成長してやがて大人の一員になる」的なベタなナレーションを被せクドい劇伴を流して、いかにも14歳なクサい方向づけをしちゃってるのはどうなのか。あと、生徒全員に了承を得てやってるのだろうけど、担任がパワハラ教師っぽいし、同調圧力で協力せざるを得なかった子とかいないのかな?
ヤマギシくんのおじいちゃんが20回も職業変えてるのがすごいと思ったのと、映画観に行ったことがあるイオンモール春日部が写っていたことには共感(そこかよ)。まあ、本作観て中学時代に思いを馳せるにはジジイの自分には遠い昔すぎて感受性もクソもない。最初から観客として不適格だったかも…。
絶対に時代はよくなっていると思う
私は、ファースト金八先生の時が、リアル中学生だった。当時金八先生がもてはやされたのは、キチ〇〇と呼ばれてもしかたがない教師が多すぎたからで、男女問わず殴る蹴るはあたりまえで、女子中高生を殴ることに性的喜びを感じていた男性教師も少なからずいたのではないかと思ってしまうほど、ひどかった。(もちろん尊敬できる先生もいらっしゃた。)
時代の反省にたった、関係者の努力のたまものだと思うが、あの時代にくらべて、現代は格段に良くなっていると思う。日本の教育は悪い方向に進んでいるような報道ばかりで、油断するとマスコミに騙されてしまうが、確実に時代は良い方向に進んでいると思う。もちろん問題は山積みであるかもしれないが、それでも、偏見や暴力で、問題を覆い隠し放置していた時代にくらべれば、格段の進歩であるといえる。
バブル崩壊からのデフレ、不景気、失われた30年は日本にとってむしろ、良かったのではないかと思う。時代の回転軸になって、時代が、社会が、大人が、教師が、謙虚になることができたのではないか。自分をきちんと見直すことができたのではないかと思う。けっして悪いことばかりではないのである。
今の時代の若者は、特にスポーツの世界では顕著であるが、私の時代とは比べ物にならないぐらに世界で活躍する人材が陸続とでている。すべて、マスコミからは散々けなされている、教育のお蔭であろうと、私は考える。
この14歳の栞は、私より10年20年若い世代には、懐かしくも切ない自分自身と重ねることができるのかもしれないが、(監督さんは何歳なんだろう、きっとお若いだろう)私にとっては後悔と血みどろな心しかないというのが感想である。もし、このゆとり、さとり世代に生まれていればどのような大人になっただろうと、悔やむ私がいるのである。心が痛い。ふぞろいの林檎たちで、バブル末期に社会人になったもののなれの果てなのである。
感動的にしないのが良かったです。
"ありのまま"で息が詰まる
カメラが入っているため本当のありのままでは無いことは分かる、が。あまりにも
とはいっても私が14歳から倍ほど生きてしまっており、時代感も変化しているのは当然。だがそこで生きる中学生の苦悩、同級生やクラス全体を俯瞰で見ているという自覚と驕り、でも本質も見透かしているような場面もある
特に不登校(正確には登校はしているが教室に入ることができていない)の生徒と、その不登校の一因となってしまったのかもしれないと自覚している生徒とのやりとりには真っ直ぐな心と人の心の解らない部分が見え隠れしておりホロリときてしまった。
モラトリアムと言ってしまうことは簡単だが、そのまっすぐゆえの複雑さと自己陶酔と他人の評価に溺れる様子がドキュメンタリーとしてだけでなく、物語として完成しているのはそれが"人生"をそのまま切り取ったからなのか。
あとエンディングは反則だ。王道のタイトルバックで流れるテーマ曲、陳腐で使いたくないが『エモすぎ』て刺さった。
「14才の生活思い出す」
全75件中、1~20件目を表示