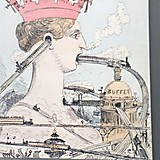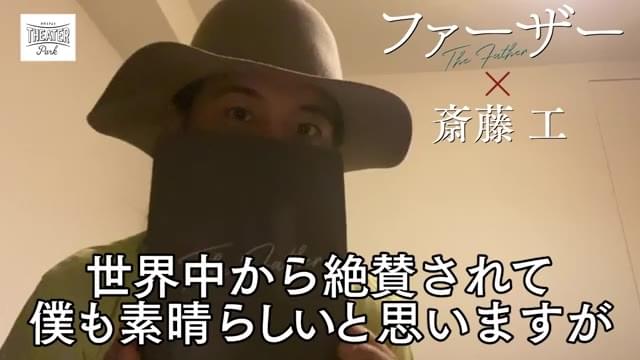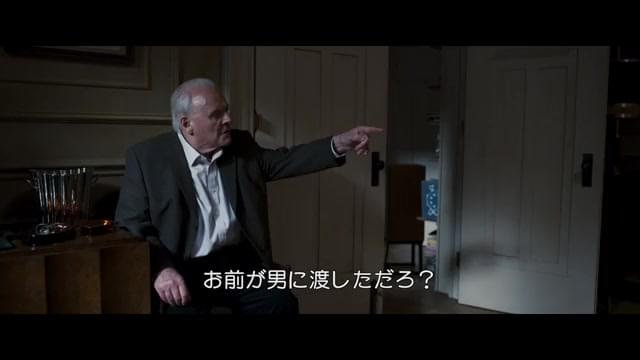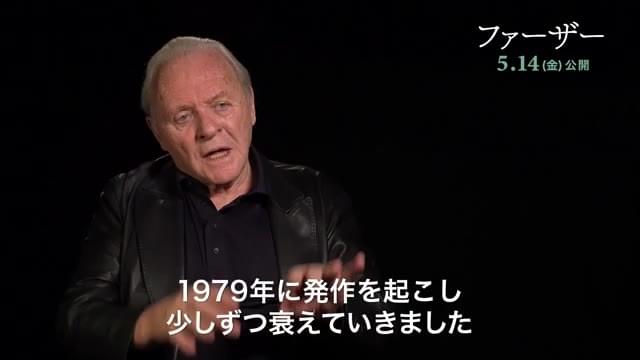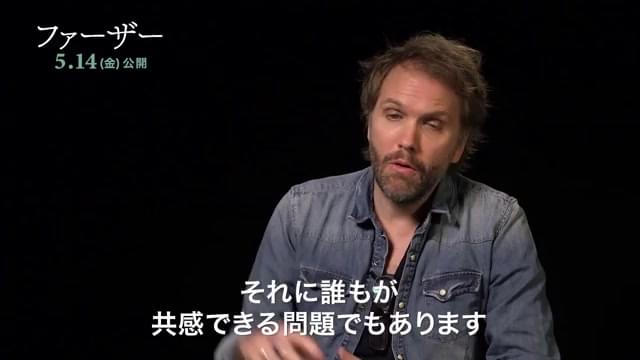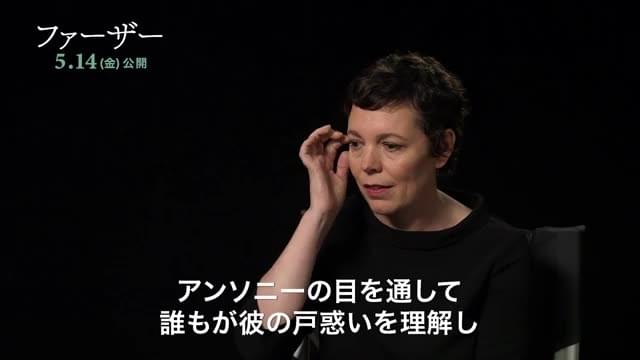ファーザーのレビュー・感想・評価
全346件中、61~80件目を表示
観ている人間が認知症になった時の苦しさを疑似体験でき、ミステリー映画様で真偽の推理も楽しめる
フロリアン・ゼレール 監督による2020年製作のイギリス・フランス合作映画。原題:The Father、配給:ショウゲート。
楽しくなる映画ではないが、認知症のアンソニー(アンソニー・ホプキンス)視点で物語られ、観ている人間が認知症になった時の苦しさを疑似体験できる凄い映画であった。ぜレール監督による原作戯曲が元らしいが、とてもよく練られた脚本(ゼレール監督及びクリストファー・ハンプトン)と思えた。認知症が進むと、今居る場所が分からなくなり、誰が誰かが混乱してしまい、時間の観念や大きな出来事の記憶さえ消失してしまうのか!誰もが成り得て、本人に悪気は無いだけに、悲しく、そして苦しい。
加えて、サスペンス調映画でもあり、事実が何かという推理を楽しめる映画(自分の場合はそれは視聴2回目で初めて可能であったが)でもあった。
長女はオリビア・コールマン(アン)で、そのかつての夫はジェームズ。今の恋人がルーファス・シーウェル(ポール)。長女より可愛がっていた次女(ルーシー)は、事故で次期不明ながら既に亡くなっている。ここまでは、明確な事実。
アンソニーはアンの家で一時的ということで暮らしていたが、長期になりそのストレスからかポールは随分と苛ついていた。その後ヘルパー・イモージェン・プーツ(ローラ)が面倒を見てくれていて、アンソニーは次女に似ている彼女を気に入っていた。但しローラーに関しては、真偽がかなり自分には不明。
しかし、アンに新しいパートナーができパリで同居のため、アンソニーは老人ホームで暮らすことになった。マーク・ゲイティス(ビル)とオリビア・ウィリアムズ(キャサリン)はその老人ホームの介護職員。これも事実。ただ、マーク・ゲイティスによるアンソニーの殴打は事実か妄想なのかも自分には不明。アンソニーの妄想の可能性の方が高いとは思うのだが。
長女アンの長年の介護の徒労感も見事に表現されていて感心させられた。献身的に介護しているのに、妹への愛情は表明されるが自分への愛情表現は殆ど無し。さんざん苦労して探してきたヘルパーも何人も追い出してしまう。挙句の果てに、娘の自分さえ誰か分からない反応を示す。首を絞めたくなる気持ちも共感できるところ。そうした、介護に苦しんできてる家族の割り切りと新たな人生への再挑戦を示した映画でもあった。
監督フロリアン・ゼレール、製作デビッド・パーフィット 、ジャン=ルイ・リビ 、クリストフ・スパドーヌ 、サイモン・フレンド、製作総指揮エロイーズ・スパドーネ 、アレッサンドロ・マウチェリ、 ローレン・ダーク オリー・マッデン 、ダニエル・バトセック 、ティム・ハスラム 、ヒューゴ・グランバー ポール・グラインディ。
原作フロリアン・ゼレール戯曲『Le Père 父』、脚本クリストファー・ハンプトン(1988年『危険な関係』ではアカデミー脚色賞) 、フロリアン・ゼレール、撮影ベン・スミサード、美術ピーター・フランシス、衣装アナ・メアリー・スコット・ロビンズ、編集ヨルゴス・ランプリノス、音楽ルドビコ・エイナウディ。
出演 アンソニー・ホプキンス:アンソニー、オリビア・コールマン:アン、マーク・ゲイティス男、イモージェン・プーツ:ローラ、ルーファス・シーウェル:ポール、オリビア・ウィリアムズ:女、アイーシャー・ダルカール:サライ医師。
認知症目線の作品
過不足なく認知症そのもの。
何もかもがすべて、認知症の方そのもの。
特有の目の感じまで、そのもの。
アンソニーホプキンスは誰かを参考にしてアンソニー役を演じたのかもしれないが、本当に認知症なのではと疑ってしまうほど。
健常者から見ると十分攻撃的な時もあるが、これはレビー小体型ではなく、アルツハイマー型。
作品内は認知症の認知世界で描かれているため、時系列が思い出す順で、バラバラ。
娘のアンを思うと、認知症になった父親に悪気は一切ないだけに、吐き出す場もなく、本当に気の毒で。
時系列順に並べてみると、おそらく下記の流れだろう。
幼い頃から姉妹のうち姉のアンよりも妹のルーシーの方をアンソニーは可愛がっていた事がよくわかる。
ルーシーは容姿も可愛らしく、画家になり、アンは馬鹿扱いされていたが、ルーシーは事故で亡くなった。
その後痴呆になったアンソニーはしばらく独り暮らしをし、アンは仕事をしながらほぼ毎日通って面倒を見ていたが、大変なのでヘルパーさんにも来てもらう事に。
ところがアンソニーは癖がある性格で、言葉を選ばないところがあり、どのヘルパーさんも長続きしない。
良いヘルパーさんとも揉めてしまったため、アンは夫とイタリア旅行に行くはずが旅程をキャンセルし、次のヘルパーさんが見つかるまで、アンソニーは長年住んだフラットからアン夫婦の自宅へ。
そのまま同居となる。
アンソニーがいる暮らしが長く続き、アンの夫は我慢の限界を迎え、アンは離婚。
その後しばらく、アンの自宅でアンソニーは暮らしていたが、アンにはフランス人のパートナーができて、いよいよアンソニーは施設に入る事になる。
施設に入る頃には認知症もかなり進行していて、職員や医師のことも毎日忘れてしまうし、かなり幼児退行が進んでいる。周りが誰か自分が誰か、どこにいるかもわからない、怖いからママに迎えに来て欲しいと泣きつく。
この間、15年くらいだろうか。
元エンジニアだったアンソニーは快活でよく話す、冗談好きで陽気な性格だったが、認知症になると、言っていいことと悪いことの線引きができなくなってくる。
そのダダ漏れする心の声に、アンがどれだけ傷付くか。
はじめのうちは理性がまさり、忘れてしまっても尋ねては失礼だと躊躇し、遠回しに聞いたり、わからなくても悟られないように話すが、言葉も態度も場面に合わせた適切な選択ができなくなり、分別がつかなくなっていく。特有の、物の場所を把握しきれなくなり、あると思った場所にない=盗られたと言い出す症状も。
思い出すのは、人生で強く気にかけている事ばかり。
つまりは次女のルーシーや、ルーシーが描いた絵、いつでも旅に出られるように肌身離さず着けていたい腕時計など。毎日十何年も見てくれているアンは出てこないのが酷。
しゃんとしていた時を知っているからこそ、進行が悲しいが、元々そうではないと知っているからこそ、嫌いにはならない。
ただ、他人は認知症慣れしていなければそれがわからないから、なんで酷い人なんだと、アンの夫のように腹を立ててしまう。
昔からルーシーばかり可愛がられていて複雑な気持ちも抱えつつ、アンはアンソニーの認知症進行を大きく受け止め、長年生活を合わせ、周りに理解者がいなくても心の整理をし、とても優しく、できた人。
そのアンが、初老に差し掛かるくらいの年齢にも関わらず、髪型が短いことを父親に褒められただけで、ものすごく嬉しそう。
笑顔が、いかにこれまで褒められてきておらず、幼少から妹ルーシーとの扱いの違いを我慢してきて、なのに介護を一手に引き受け、夫や人生を犠牲にし、それでも認知症の父親を受け止めて向き合っているか、全てを物語る描写。とても印象に残った。
作中、アンソニーが相手が誰かよくわからない時に出てくる、シャーロックホームズでホームズの兄マイクロフトを演じるマークゲイティスが余計に、アンソニーが認知症として認知する世界の、不可解で何が何だかわからない怖さ不気味さを助長する。
身近で認知症の過程を見たことがあれば、誇張も何もなく、そのものなことがわかるはず。
自分もいつかなるかもしれない認知症の世界の視点で、実際に認知症の人に携わった時に、心情や進行度を理解し、寄り添える人間でありたい。
身近な人が密かに始まっている時にも、気付けるようでありたいとも思う。
老人の孤独感
ミステリー映画
残酷なまでに疑似体験させられる
混乱し迷路を彷徨う当事者の辛さ、苛立ち
面倒をみる家族やその近い関係の人たちの辛さ、苛立ち
介護の経験はないが祖父母や
これまで会話をした年配の方々
アンソニーの仕草や様子の全てが
よく知っていた光景だった
あの時のあの人たちの混乱した様子や
寂しそうな目や孤独を知って涙が止まらなかった
今どこにいて何をしているのか
腕時計を見て時を把握する
それだけで孤独な自分は少しは落ち着くと思う
娘と笑い合ったり、感謝の言葉を述べたり
アンの涙を拭ったりする父としての優しさ
日々忘れることが多くなり混乱している一方で
まだいるアンソニーの中の父としての在り方にも涙
最後は胸が辛くなる子供返り
キャサリンが優しい介護士でよかった
高齢化が進んでいる今の日本
自分も同じくらい歳を取ってから理解するのでは遅い
現代の人に観て欲しい一本
これを観るだけでどれほど歩み寄れるか
歳をとるまで理解し得なかった感情を何十年も早く
疑似体験させてくれたアンソニー・ホプキンスの
名演技に感謝し、拍手を贈りたい
認知症の老人側からみた世界という解釈
映画をサブスクで見る事が習慣になっている中で、もう一つ習慣になっているのは、ここで皆さんの評価のみ垣間見てからにする というもの。
人生が、私も漏れなく終盤に差し掛かって来たと(夫を亡くしてから特に)感じる日々の中、あまり見たくないものは見ないと切り捨てられる。ようになった。
そのレビュータイトルの多くに
「何がなんだかわけがわからない」とあって、
そんなに難解なやつなの?と思いつつ見始めて、ああそうか、彼の この映画全体の主題である老いの
その セリフ なのだと 気づく。
なるほど。
私の父は 前頭葉あたりの強打(多分そうだろうと医者は言った)
による血痕が脳の中で固まったことによって血腫になり手術した。
一旦 失語症を患うも一気に回復しその後 商売(書店経営)の悪化も伴い 脳の一部からどんどん硬化が始まる認知症を発症した。
父の場合 こんなに穏やか(に見える)な状況ではなく
本人にしてみれば まさにもう 筆舌尽くし難き状況を経て最終的には、老人施設に入居して その後数年で亡くなった。
父の場合を考えてみるに
この映画に描かれている内容をまさにこれよと 思う感じはなくて、老いとは 認知症とは それぞれのものだろうなあと実感するに至った。
それとは別に この 作品としての構成力や説得力
そして演技による吸引力が 凄まじい。
イギリス。
私の娘夫婦がコロナ騒動直前の2020年2月(もう始まっていたが)に 偶然 帰国するまで住んでいたので
何度か渡英した。
孫が生まれてからは一年に四度行った年もあった。
イギリスのフラットは なので 空気感に馴染みがあるし
日本人として アメリカ英語に比べ 非常に聞き取りやすいイギリス英語は 字幕は補助的な程度でも理解出来て
その分の感情移入が可能である点はありがたい。
バスルームに金属のタオル掛けがあって
かけておくと乾くんだよね とか。
廊下の感じや部屋のドアなど
まあ この映画のは かなり広めのお家ではあるが。
イギリスのお家事情は 日本より大変で、新しく建てることが禁じられているため 若い夫婦が自分の家を持つことが非常に困難らしい。
国営の、あっさりしたビルは 難民などの低所得者のためのもので、こういう所の治安は良くないと言っていたが
イギリスという国は 自国民とそうでない永住者との待遇の違いがかなりあって 日本ってその点 外国籍の永住者に厚いなあとしみじみ思ったりもした。
そういう事も思い出しながら
イギリスという国でイギリス人男性が老いるサンプルの1つを見せてもらった。 んだなあ と思った。
「え、どういうこと」が正解の作品
まるで認知症の疑似体験
よくある父親介護問題を描いた軽いモノだと思い、
軽い気持ちで何気なく観たのですが・・・
間違いでした!観てビックリしました!甘く見てた!
最初のうちは、普通に話が進んでいくのだが、
途中から「あれ!?何か変だな?」と、なっていく。
そいて観ていくうちに混乱していき・・・
まるで自分が認知症の疑似体験しているかのような錯覚に陥る。
1回観ただけでは絶対に完全には理解出来ない!
何度か観たくなる作品。
話の構成、脚本、演出、演技、どれをとっても素晴らしい!
とにかく観てほしい!
今まで観た事のないタイプの映画でした!
しかしアンソニー・ホプキンスは、本当に上手い役者ですよね。
年老いても尚、この素晴らしい演技!
サーの称号を授与したのも納得です。
自分が認知症と気づいてない事が怖い
なかなか難しい映画でした
認知症視点という予備知識があっても、どれが今の話しか映画が進まないとわからない。幻覚と時系列が前後していると思うけど、最後のシーンで前半のシーンであの人達がそのセリフを言っていたのかとわかって、流れが掴めました。
映画の序盤はこっちも困惑します。
見終わったらそういうことかとわかります。あるシーンで返事しなかったこととか他にもいろいろ。
認知症の困惑した感じなどよく演じていたなぁと思います。
さすが、ハンニバル・レクター!
高齢化社会、他人事ではない
認知症「側」の観点から描かれる世界。人物や時間軸や場所や出来事が入り乱れて、トリックのような現実の「老い」。
偉そうな姿から愚かで赤子のような姿まで晒すアンソニー・ホプキンスは流石。
高齢の親が居る身としては他人事ではないなぁ。
さすが名優
認知症の世界
自分がわからなくなる!
自分を失う恐さを体感しました。
仕事の関係で介護施設でお世話になったことがあり、認知症の方と接する機会がありました。
どうしていいかわからないのょと急に混乱をしたり、数分前に食べ終わったごはんを、今日のごはんはまだ?早く食べたぃと言ってくる。
夕方になれば、帰宅願望がある。
突然、陽気に歌い出す。
その薬で殺そうとしてるのね?の言葉。
現場では介護の他に、もっと深い心のケアも必要だ。
その場所でその時間で、生きているのは事実。
記憶、とはなんだろう。
実際その方たちに触れていても、いまだに根本的ななにかがわからない。
寄り添おう。
笑顔でいられるように。
快適に過ごせるように。
劇中の男性は、本当に主人公の前にいた人物だったのかな、娘のアンと接点はあったかな?と考え直してしまいました。
実は主人公の妄想やせん妄や幻覚から来るものだったら、、と考えずにはいられませんでした。
ちょっと重い。。
全346件中、61~80件目を表示