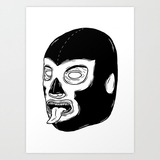サウンド・オブ・メタル 聞こえるということのレビュー・感想・評価
全115件中、1~20件目を表示
それでも、人生は続く(取り戻す、を手放すとき)
(話は飛躍するが、)子育てをしていると、「変わらない」物事はなく、後戻りはもちろん、「取り戻す」ことは到底できないなとつくづく思う。これまではこうじゃなかった、こんなはずじゃなかった、と思っても、子は刻一刻と育って変化していき、親の感傷をよそに、時間はどんどん前に進んでいく。
聴覚を失い、轟音に彩られた生活を突然絶たれたドラマーの主人公、ルーベン。激しいいらだちをバンド仲間の恋人・ルーにぶつけてしまうが、彼女の必死の勧めに従い、しぶしぶ自助グループでの共同生活に転じる。徐々に穏やかな生活に馴染んでいったかに見えたものの、恋人との音楽の日々を諦めきれない、取り戻したい彼は、思い切った行動に出る。
寄り添い、支え合う生活は理想のはずなのに、はまりきれないのはなぜなのか。心穏やかな生活には、目立った変化は降って湧いてこないない。目指すことややりがいは、自分で見出さなければならないのだ。子どもたちに音楽を教える姿が帰着かと思えたが、ルーベンの視線は、遥か遠く、輪の外に注がれ続けたままだった。
ツアーバスを売り払い、コミュニティでの繋がりを捨ててインプラント手術を受け、ノイズに耐えながら恋人の家を訪ねるルーベン。まるで、声と引き換えに足を得た人魚姫のように痛々しい。そんな彼を迎え入れる、ルーの父を演じたマチュー・マリアックが、近すぎず遠すぎず、絶妙の立ち位置だった。ルーベンを演じたリズ・アーメッドと同じく、眼力が強い俳優さん。鬼気迫る・狂気が滲む役柄が多く、主人公とぶつかり合うのかと思いきや、今回は徹底して「色々あったけれど、何とかここに行き着いた」娘の父を演じていて、ますます好きになった。(余談だが、ルーベンに茹で卵を振る舞うところが、観ているときは少しピンとこなかった。後でざっと調べてみた限りでは、半熟茹で卵を、カリカリにトーストしたバゲットにつけて食べるのは、フランスではごく日常の食事(夕食)らしい。娘の恋人を、家族のように気負いなくもてなした、ということだろう。卵の殻をナイフで割り、パンをざくざく噛む音もごちそうのうち、というところも印象的だった。)また、父と娘の歌が、哀愁とも不協和音ともつかないメロディと歌詞だったのも良かった。ルーの家でのルーベンの音世界は、何と悲しく、騒がしいものだったのか。
心待ちにしてきたはずの再会は、心の穴を埋めてくれない。ルーベンが、新たに踏み出した世界とは… 。時間を引き戻し、失ったものを取り戻すことを「手放した」重み。新たな世界の美しさと厳しさ。今も、余韻が耳に残る。
(付記というか、ちょっとした不満。
本作は、聴覚を失うルーベンの音世界を追体験させるべく、音作りに細やかな工夫がなされている。けれども、カッコ書きの字幕で音の説明が付されるのは、むしろ余計で、目にうるさい気がした。これは日本版のみなのだろうか?「静かな騒音」なんて、完全に矛盾している。せめて、「くぐもった騒音」あたりではないか。字幕を無視するのは難しいので、出来れば、カッコ書き字幕抜きで観直してみたい。)
喪失と絶望の先に見えるもの
聴力を失ったメタルバンドのドラマーがたどる運命を描くこの作品は、様々な音に彩られている。
冒頭のライブシーンの激しい音の洪水の後は、コーヒーのドリップされる音や開け放たれたドアがかすかにきしむ音、遠く響く鳥の鳴き声、人混みの柔らかなざわめき。遠景のような音がそこかしこに散りばめられる。
そしてこれらの聞き慣れた音と対照的で印象深いのは、主人公のルーベンが聴力を失った後に聞く「音」だ。わずかに残った聴力が拾う、曇って細部の潰れた音。張り付いて離れない不協和音のような耳鳴り。人工内耳の金属をこするような音。
本来昨年8月に全米公開の予定だったこの映画を、映画館で観られないことを当初残念に思ったが、ヘッドフォンをつないで鑑賞したことでその考えは変わった。これらの音達を耳元で聞くことで、ルーベンが襲われた変化をよりリアルに追体験し、彼の絶望を間近に見たような気持ちになった。
過剰な言葉はない。音と、リズ・アーメッドの細やかな表情が、主人公の感情の流れを雄弁に語る。
パートナーのルーは、当事者のみの参加が条件の自助施設にルーベンを行かせるため、荒れて追いすがる彼を振り切って彼の元を離れた。二人の出会いと同時期にルーベンがドラッグをやめたこと以外、彼らが共に過ごした過去の説明はない。だが別れる間際のやり取りに、繊細な二人が出会ってから4年間、どのように身を寄せ合って生きてきたかが滲む。
「あなたは自分を傷つけ、私も傷つけてる。私も自分を傷つける。施設に行くと言ってほしい。じゃないと全部ムダになる」
これほど大きな困難を、無謀に受けて立つと二人とも壊れてしまう。そうならないために寂しさを堪えて突き放すルーと、目の前の孤独に怯え助けを求めるルーベンの姿がひたすら切ない。
自助グループに参加したルーベンが施設に馴染むまでの描写は比較的淡々と進む。元いた社会と接触を絶たれる厳しさはあるものの、彼を受け入れる聾者の世界はどこか牧歌的だ。マーダー監督は、寛大な精神を保つ聾文化を表現するこの物語の構想に13年をかけたという。施設の指導者ジョーには、聾者の両親の元で育ったポール・レイシーをキャスティングしている。
聾者であることは不幸なことではなく、身体特性に応じた文化に生きるということに過ぎない。そんな印象を受けた。
ただ、自助グループは聾者として生きていくことを前提に、精神面でのサポートをするものだ。そこでの生活にひとまず馴染みつつも、ルーベンはあくまで手術での聴力回復に望みを繋いでいた。大切な音響機器やトレーラーを売り払って手術費用を工面する彼だが、物語の肝となるさらに厳しい試練が彼を待っていた。
希望を失った時、生きてゆく力をどう紡ぐのか。
ルーベンは、生活だけでなく自己表現に直結していた音を奪われた。そこには誰の悪意も過失も介在せず、恨みをぶつけるよすがさえない。
失われたかけがえのないものが二度と戻らないという事実を、受け入れることは苦しい。諦めれば楽になるなどと、とても軽々しく言えない。
それでも覚悟を決めて一歩を踏み出せば、その先は決して絶望のみではないと信じたい。
そして、監督がインタビューで語ったこの映画のテーマ「目覚め」が、ラストシーンに凝縮されている。ルーベンの苦悩と彷徨の物語をたどってきた私たちも、最後に音のない世界を彼と共有し、どんな言葉より胸に迫る安らかな静寂によって目覚めを体感するのだ。
「ろう」という生き方
メタルバンドの話で、ものすごく騒がしい作品なのかと思っていたら、むしろ聴覚を失ってゆくミュージシャンの物語だった。まあ、メタルバンドのドラマーが主人公なので、最初の印象が間違っているわけではないのだが。
タイトルの「サウンド・オブ・メタル」はダブルミーニングだった。メタルバンドの主人公が音を失っていくという点でメタルの音の物語でもあるが、もう一つは、聴力を取り戻すためのインプラント手術後の音を指している。インプラント手術は簡単に言うと金属を耳に埋め込むようなもので、疑似的に聴力を回復させるためのもの。この音が大変に不快な金属音なのだ。映画は主人公が手術を受けた後の音を観客にも体感させる。世界の音の何もかもが金属の反響音として聞こえてくる。本作は、そんな描写も含めて、「ろう」とは治すべき病気や障害ではなく一つの生き方の実践であると描いている。ろう者のコミュニティが牧歌的な心地よいコミュニティとして描かれているのもその表れだ。音が非常に重要な作品なので、本当は映画館で観たい作品である。
Deafness, Strangely, A Theme Seldom Explored in Cinema
It's hard to approach deafness or blindness in the way paralysis was explored in The Diving Bell and Butterfly. How can a film sell if there is no sight or sound to it? Sound of Metal goes in an out of the lead character's head, and to a new realm when cyborg technology takes hold. The film is touching, seeing an authentically portrayed crust punk schooled on community. Also a sad film. Must see!
苦悩の先に答えなんてなくていい。
突然重度の軟調になったメタルバンド(正確にはデュオ)のドラマーが、否が応でも生き方を変えることを迫られる。その道程はもちろんたやすいものではない。主人公に麻薬中毒の既往歴があり、恋人(バンドのギターボーカルでもある)には自傷癖があり、ふたりが小宇宙のような安全地帯を築いて、支えあって生きていることも、生き方を容易に変えさせてくれない要因になっている。
ただ、この映画は主人公たちの七転八倒をスリルたっぷりに描くわけではなく、起きてしまったことと向き合うまでの時間を、丁寧に、繊細に見つめようとする。オリヴィア・クック演じる恋人は、中盤は出番がないのだが、彼女にもまた、自分と向き合うための試練の時があったことを、われわれ観客は窺い知ることができる。
結末めいたものはある。しかし、彼らが何か求めていたものを得られたのかどうかは明示されない。確かにふたりの人生は大きく変わったが、答えが示されるわけでもない。いや、実際のところ、答えなんて見つからないものであるという真理を信じているからこそ、あの瞬間で潔く映画を終えられたのだと思う。彼にとってはとても大きな瞬間だが、その後も人生は続いていくのである。
すべてを肯定して静寂に身を置くことで得られる平穏
ある日突然、耳がほとんど聞こえなくなる。それも、恋人と一緒にトレーラーハウスに住まい、行く先々のライブハウスでドラマを叩き続けるドラマーがである。当然、彼の絶望感は半端ない。唯一の治療は脳に音を音として感知するチップを埋め込むことなのだが、如何せん治療代が高額だ。そんな八方塞がりのドラマーが、友達の紹介で入所するろう者の支援コミュニティで、仲間たちと手話を介して対話し始める。だが果たして、そこは主人公にとって終の住処たり得るのかどうか?ことはそう簡単ではないことを本人も観客も知っている。しかし、明確な手がかりがある。焦り、もがき苦しむドラマーに対して、コミュニティの創設者がこう語りかけるのだ。「耳が聞こえないことはハンデではない。治すものではないのだ」と。そして、「静寂こそ平穏が得られる場所なのだ」と。音のある世界からない世界へ、豊かさから貧しさへ、勝者から敗者へ。人生は様々な試練(騒音)と無縁ではいられないけれど、もしもそれを肯定できたなら、人は救済されるに違いない。激しいドラムプレーで始まる物語が、無音の世界へとシフトしていく意外性のある構成、主人公の聴力と第三者(観客も)の聴力を区別した録音演出、主演のリズ・アーメッドの痛々しいほどの肉体表現と追い詰められた演技。見所はふんだんにあるが、白眉はコミュニティの創設者を演じるポール・レイシーの、まるで神のような佇まいだ。レイシー自身も役柄と同じくベトナム帰還兵で、ろう者の両親を持つ身であることを考えると、さらにその演技は説得力を持つ。アーメッドとレイシーは共に来年のオスカー候補入りが確実視されている。
タイトルからの印象とは違った
ドラマーに興味を持って観たけれど
そういう話ではなかった
聞こえなくなるということ
聞こえないということ
聞こえるようにするということ
色々知れたし考えるきっかけになった
ラストは良かった
いつ視聴したか忘れたけど 11月だとは思う
聞こえるいうこと
見る前は副題ダサいなと思っていたが、「聞こえるということ」の答え?がラストにわかる。
主人公は突発性難聴で耳が聞こえなくなるが、音楽系の仕事をしている人ほどこの病気になり仕事が出来なくなるという悲しい病気。
主人公が治療のため入っていた施設は厳しい規律があり、外部との連絡遮断のためスマホ等没収されたり、主人公が手術をして治した後はすぐ出て行かされたりした。
施設主、の耳が聞こえないということは病気ではなく個性だから治すものでは無いという考えも理解できる。
最後は頭に埋め込んだ機械のおかげで耳は聞こえるようになったが、周波数の関係か全てが機械音に聞こえてしまう。手術したのを後悔してるかどうかはわからないが、静寂の世界も悪くないのかもと思わされる映画だった。
終わりの心得①
メタリカみたいなメタルバンドのドラマーにスポットを当てた音楽映画を想像し、なんとなく今まで見なかった作品。ようやく見たら、全然違ってました。私の『終活の心得』として記憶に残さねばいけない。
恋人の女性ギターボーカルと二人でメタルバンドをやっているドラマーの主人公が、突発性難聴で音が声が聞こえなくなってしまいます。長年バンドで生活してるんだから、さあどうすんな?というお話。
私は今年50歳になる。人生100年時代ともなれば、折り返しになります。いやそもそも、100年どころか明日、目が覚めない可能性もある。なんも保証ありません。誰しも歳を重ねることにより、目が耳が身体が悪くなる。必ず衰えますわ。おまけに私は色の見分けも弱い。学生の頃、美術の先生に『絵は上手く描けてるが、なぜここをこの色で塗ったん?』と言われ、やっぱみんなと違う見え方してんやなと自覚。なんか暗い感情が湧いたが、今は上手く描けてたんならええやんけと思う。
老眼という新たなる敵が加速装置を搭載してやってきたが、眼鏡があれば本も読めるし、車やバイクの運転もしていいライセンスがあるので、今は特に困ってはいませんが、いずれは受け入れなきゃならんでしょう。
ラストシーン
もはや生活レベルや環境の違いを感じ、恋人の家を黙って去った主人公は、街のベンチに座る。サウンド・オブ・メタルというタイトルは、こういう事かと。高い金を払い手術したものの、元の状態になんか戻るわけがなく、不快な金属音ばかりが延々と彼には鳴り響くわけです。医学的な細かい事はわからないが、どうもそういうもんらしい。
後半の流れから、ネガティブな私は彼が自ら命を絶ってしまうだろうと思って見ておりましたが、補聴器を外し、無音の世界で佇む彼の表情で終わるラストは、彼がこの病気を、聞こえない世界を受け入れたんだなと思いたい。
聞こえないということ
評価基準にかなり苦しんだが・・・・・
このエンディングはとても美しいと思った‼️即ち最後の最後に静寂の美しさに気が付いた主演のリズ・アーメッド・・・。それは孤独を受け入れると云う事を悟ったと云って良いのだろうと思う。音を扱った作品の中でこれほどまでの美しさを持ったエンディングは久しぶりである。
音の質・・・聞こえれば、それで良いというものでは無いのが分かりました。
ルーベンの場合(ミュージシャンが音を失ったら?)
身につまされるストーリーでした。
目(見える)と耳(聞こえる)のどちらかを失うとしたら、
目と耳のどちらを選ぶだろう?
そんな問いかけをしたことがありませんか?
私は、やはり「目」を選ぶと思います。
ミュージシャンでドラマーのルーベンは、ボーカルでギターを弾く
ルーと2人、レーラーハウスで全米を移動しながら、ツアーをするのが
ここ数年の日常だった。
ルーとルーベンは恋人関係にあり、マネージャーであり
公私を共にするパートナーだった。
ある日突然ルーベンは難聴を発症する。
それは瞬く間にルーベンの聴力を奪った。
病院で聴力検査を受けて診断を聞く。
取り急ぎ2人は、教えて貰った
「聞こえない人たちのコミュニティ・・・支援センター」を
訪ねる。
突然の事に苛立つルーベンをリーダーのジョーは暖かく迎える。
失聴を受け入れて「手話」を学び、役割分担をして協力し合って
共に生活をする。
静かで豊かな思い遣りの生活があった。
映画を見た限りでは健常者で指示したり命令を下す人は居なかったように
見受けました。
ボスはジョーだけ。
失聴を受け入れた様子のルーベンだったが、
彼ははまだ諦めていなかった。
トレーラハウスを売り払い身の回りの金目のものを売り払い、
難聴を治す最後の手段、
《人工内耳インプラント手術》を受けたのだ。
耳の奥に人工の内耳チップを埋め込む手術を受けて、
4週間後に《音入れ》という操作を行う。
補聴器のようなサウンドプロフェッサーを装着して、
「スイッチオン(音入れ)」をするのだ。
確かに聞こえる。
しかしキンキンして不快感がある。
実際には入念で根気強いリハビリテーションが必要とのこと。
個人的には「難聴のインプラント手術」
これは初耳でした。
この映画は、
無音、
ノイズ、
(メタル・・金属を埋め込んだ音は、耐え難く不快だし、
(ノイズはパーティーなどの多数の人がつとろう場面や、
(交通量の多い雑踏などがうるさく感じる、ようです。
手術を受けたルーベンはルーの実家の父親(マチュー・アマルリック)を
訪ねる。
ルーは留守だったが、夕方、2人はひさしぶりに再会を果たす。
すっかり印象の変わった2人。
黒髪でボブヘアのルーシーは、すっかりしっとりした大人の女性に
なっている。
ルーベンも髪を殆ど坊主頭にして、雰囲気が変わっている。
身を引くように、翌朝、ルーの家から出て行くルーベン。
あてはあるのだろうか?
ベンチに座ると教会の鐘が鳴っているようだ。
それはグワーン、プワーンと反響して耐え難く五月蝿い。
思わずルーベンはサウンドプロフェッサーを、外してしまう。
ホッとして安堵して寛いだ表情を取り戻すルーベン。
そこで映画は終わる。
彼が今後どのように決断して生きていくのかは、分からない。
ただ支援者センター長のジョーの言った言葉。
「聞こえないことはは障害では無い。」
「静けさを受け入れた先に平穏な生活がある」
この言葉が耳に残っている。
とは言っても若者が仙人のような境地になのは簡単ではない。
人はパンのみで生きるもにあらず・・・だし。
やはり悩ましいです。
私の感想を書くとこの映画の良さが逆に下がってしまいそうでコメントし...
筆舌に尽くし難い
自尊心をブッ壊す凄まじい葛藤と静寂に心打
第93回アカデミ-賞のノミネ-ト枠で上がっていたので
作品名は知っていた程度。
或るときラジオ番組で この作品の紹介をやっていて
興味が湧いたので 先日やっと
鑑賞に至ったので、ここに記したいと思う。
感想から言うと、久しぶりに心を強く打たれた。
この手のセカンドライフへ誘う思いをさせる作品は
何十年ぶりかだと思う。素晴らしい作品だった。
mc:
ルーベン・ストーン役(主役、難聴者):リズ・アーメッドさん
ルー役(主役の彼女):オリヴィア・クックさん
ジョー役(自助グループ所長):ポール・レイシーさん
身体障害者の作品や役で、盲人演出と言えば
白杖や、盲導犬や、役者の演技でそれらしく見せているため
映画演出しやすかった。話せるし、聞こえるし。
映画にとってこの役柄の相性は良い。
一方、聴覚障害者の演出は実は難しいのだ。
見た目が 健常者と一見変わらぬため
演出が非常にしずらい。伝わるようにするには
サウンドエフェクトを酷使するしかないのである。
勿論役者の演技もそれなりで無いと伝わらない。
映画を甘く見ていた私は、最初寝っ転がって見ていた。
主人公ル-ベンの やんちゃな香りがする風格の男が
ドラムをバンバン叩いている・・・そこから始まった。
そう、彼はバンドのドラマ-なのだ。
最初は全く普通に改造バス生活で暮らしていたが、
或るとき ん? ん? 音の聞こえ方が お・か・し・い。
極度にコモッた様に聞こえてきて、焦る 本人。
実は 私も中耳炎になった事が有るので
この心境は凄くわかる。
やがて、医者に診てもらうと 80%の聴覚を失っている事実を
知る。このシーンを目の当たりにして ハッとした。
すかさず姿勢を正して 映画を真剣に見入る様になった。
彼は、急遽 聴覚障害者ばかりで生活する自助グル-プに入れられる。
ココでの生活が彼を唯一救うと思っていたからだ。
しかし、そんな簡単な問題では無かった。
健常で育った期間が長い彼にとって
ココでの生活、これからの運命は到底受け入れられない・・・
彼の孤独な毎日が続く。
何とか現状を打開して、元の彼女との生活に 元の仕事に
戻ろうとするが、まずはココの生活に慣れて
コミュニケ-ションを図らないとダメだった。
ろうあ者のコミニケ-ションが 物凄く静かに会話されて
盛り上がっているのが 不思議な世界観だった。
この感覚に慣れるかが、ルーベンの生きる道であった。
今までヤンチャなミュ-ジシャン ドラマ-が
ココでの生活に溶け込めるとは思えない。
しかし、少しづつ 子供たちと親しくなり
会話がみんなと出来る様になった姿に
観ているこちらも安堵していく。
そう、いつの間にか 私は彼を心から応援していたのだ。
これがこの映画の力点だと思いますね。
ジョ―に 部屋に籠って ノートに文章を書け!
言われて しぶしぶ書いていくルーベン。
この教えの意味する所が 最後に繋がる。
約束事でグル-プ施設の外界とは遮断されているのだが、
隠れる様にして PCをこっそりいじりネットで
彼女の現状を知る。
歌手として活動を続けるも、彼が居ない彼女のバンド活動は
へこんでいた。
彼女の新曲プレビュ-動画を再生するも
彼には全く聞こえない。 涙するよねココね。
この現状を打開すべく、彼は折角 施設に慣れてきたが、
全私物をお金に換えて 聴覚を取り戻すべく
手術に挑み 人生の賭けに出る。
やっとの思いで、本当にやっとの思いで
補聴器を両耳の神経に当てて 音を大きく聞き取れる
様には成ったが・・・何かが変だった。
そう、音質、質感の相違である。
健常者時の頃と同じように聞こえると、
戻れると思っていたが
それは 大きな間違いだった。
この 愕然とする 深い喪失感は
本当に同情した。
もう、ミュ-ジシャンに戻れないのか?
それはジョ-の言った通りのことだった。
インプラント(手術・補聴器)を試しても
ダメだったと 彼が言っていたのを思い出す。
しかし日常は話せるようになったのは良かった。
相変わらず 音質はメタルっぽいから嫌だけど。
久しぶりに彼女 ル-に会いに行って
もう一度 俺とバンドツア-をと 言い出すが、
二人に その未来は待ってはいなかった。
それを悟るルーベン。
二人で涙しながら抱き合う姿は
とてもジーンと来たよ!
本当に良いシーンでした。
そして 翌朝 早くに、彼女の元を去るルーベン。
行く宛は 多分施設へ戻るのだろうか。
そう思った。
金属音質な補聴器を 両耳からそっと外す・・・
そこに広がる 静寂な世界。
心地よい風が吹き、木漏れ日が彼の顔を照らしている。
そう、彼に セカンドライフが訪れた瞬間だった。
そこから 彼は 少しずつ次の人生を
歩んでいく事だろう、きっとそう成る。
私の心は 彼を応援し続けていた。
いつか、心のドラムを思いきり叩く
彼がいる事を 願いたい。
全115件中、1~20件目を表示