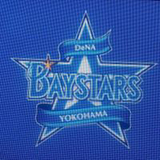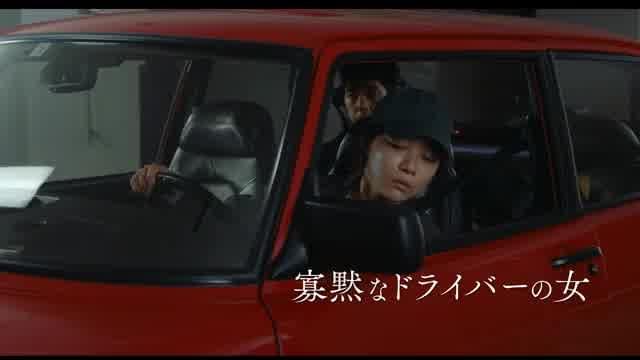ドライブ・マイ・カーのレビュー・感想・評価
全796件中、381~400件目を表示
車内での沈黙の姿リアルでした。 車内で二人きりの時って、 楽しく会...
車内での沈黙の姿リアルでした。
車内で二人きりの時って、
楽しく会話している時もあれば、
沈黙しているときもあるし、
仲のいい人と、会話が無くても苦にならない人もいるし。
ドライバーの女性は、
空気のような存在でありながら、
最低限の生身の会話をしてくれるのがありがたいです。
映画としては、
生身の人間の姿をうまく描写しつつも、
全体的に、(リアル演劇演出以外の)演劇のような演出は自分には合わなかった。
たぶんストーリーが自分に合わなかったからだと思う。
村上春樹ってだけで海外でも受けるんですね 僕はまっぴらごめんだけど
なんの知識もなかったんで何が起こったのかわからないうちに話が進み、終わってみれば3時間
後で知ったんですが、”ハッピーアワー”の監督じゃないですか
あの5時間越えのインディーズ映画を元町映画館でイッキ観した苦痛を思い出したよ
あの映画よりましだったけど、カットする事を知らないのかな
いや、疲れました
テーマは1つなのに、まあ延々とよくやる
これはエンディングで知った
村上春樹の短編なのか
どうりで内容が薄い
短編を3時間ひっぱったのか
ノーベル賞でいつも話題になる村上春樹
実は一つも読んでない
”ノルウェーの森”を映画で見たくらい
自分には合わなかったなあ
まあ、春樹オタクには楽しかったんだろうなあ
カンヌで評判が良かったのは村上春樹のおかげでしょう
最初から文学臭いセリフ回しがくさいくさい
知らないものには西島秀俊がベッドシーンでそんなセリフを吐くもんだから心配になってたら、いつのまにかいつもの西島君になっとるやん
どうなってんの
演劇の多言語はなんなん?
いきなりで理解するのに時間がかかったしね
なるほどなるほど、手話まで言語として取り入れるのかぁ・・・まではわかる
で、なんの意味があんのかな?
原作読んでる文学オタクがしたり顔で高評価しそうです
村上春樹の文学って、この映画だけしかわかりませんが、生きることとか愛とか個人的な事が多いんでしょうかね
えらい真剣に生きてる特別な人に焦点をあててもね、人それぞれだから
真剣すぎるとしんどいだけだと思うんだけどね
人間なんて、そんな特別な物ですか
生まれて生きて死ぬだけの泡みたいな物ですよ
知らないことは知らないままでいいし、勘違いも思い込めば強い
時間とともに記憶も薄れる
そのうち順番が来ればなにもかも放り出して自分が死にますよ
自分が納得いくまで突き詰めたり、整理しないと気が済まないのが文学なら
僕はまっぴら御免です
とりあえず
文学の評価はわかりませんが、映画としてどうなん?
て考えると・・・
あかんやろ、こんなん
原作は読んでいなかったけど、村上春樹の世界にもう一つフィルターが加わった感じ
多分映画館で観ないと、眠くなってつまらなく感じちゃう映画かなと思って見に行ってよかった。
この映画のメッセージは、どの国の誰にでも当てはまることで、それが海外からの共感を得ているんだと思う。
見終わったあと、1日中、考えてしまった。
大事な人を失った喪失感。でもその人の知らなかった部分を見てしまう。
自分は本当に愛されていたのか、その人にとって自分はなんだったのか、聞いてみたくてももう聞けない。
その喪失感にずっと追われている。
どんなに近くにいたとしても 全てを知ることなんて出来ないし、知らないままでいることの方が幸せだったりする。
答えは、自分の中にあるのかもしれないけど、ずっとそれを覗けないまま、ずっとずっと心に蓋をして暮らしていく。
予想できない展開が何度も続き、チェーホフの劇中劇と彼女が作り出したストーリーが入り混じって、
そこにロードムービーが加わり、今までにない感覚だったところが新鮮だった。
このずっと後を引く感覚は、村上春樹の世界観。原作を読んでみようと思う。
ドライブの幕が開く
去年は『ノマドランド』の中国人女性監督クロエ・ジャオが、一昨年は韓国映画の『パラサイト 半地下の家族』が米アカデミー賞で頂点に輝き、同じアジア人として誇らしいと同時に、メチャクチャ悔しく、情けなかった。
何故、日本はこの場に立てない…?
かつては“クロサワ”や“ミゾグチ”や“オヅ”の国として、アジアの国々では何処よりも評価され、尊敬されていた日本。
それがどうだ、今は!?
狭い国内だけでしかウケないようなコミックの実写化、TVドラマの劇場版、アニメの氾濫…。実力不足のアイドルが話題性だけで主演を張る。
ファンだけ喜ぶ中身スカスカ、萎えるようなものばかり…。
無論、世界で評価される秀作は毎年生まれている。が、さらにその先一歩、踏み出せない。
国内年間興収で毎年、“洋低高邦”なんて言われてるけど、実際は上記のようなものが宣伝やファン人気に支えられて上位を占め、浮かれているだけ。
そうこうしている間に、瞬く間に韓国や中国に追い抜かれた。
その先頭に立つのは、日本ではなかったのか…!?
これでいいのか、日本映画!
米アカデミー賞の場に立って戦えるような、作品や人材は居ないのか…?
何年後の先になる事やら…。
同じような事を『ノマドランド』や『半世界』のレビューでも書いた気がする。(何故『半世界』かと言うと、『パラサイト』がオスカーに輝いた時ちょうど見てて、感想合わせて一言触れさせて頂きました)
↑何をコイツ、偉そうに…と不快に感じる方も居るかもしれませんが、私はこれでもそれなりに見て言っている。ちゃんと見れば、どんなに絶賛しようと酷評しようとこっちのもん。見ないで貶す輩は言語道断!
…2週間ほど前、“その時”が!
先日発表された第94回アカデミー賞ノミネートで、日本映画史上初、米アカデミー作品賞ノミネートに!
遂に、やった!
国際長編映画賞の受賞はほぼ確実視。正直、作品賞・監督賞・脚色賞の受賞は難しいかもしれないが、これだけでも充分充分!
素晴らしい!
一昨年韓国、昨年中国…遅れを取り、遠い将来の事になるかと思いきや、間髪入れず日本がやってくれた!
さて、記念すべき作品となったのが、本作。
村上春樹の短編小説を映画化した濱口竜介監督作。
『ドライブ・マイ・カー』。
本公開から半年、このタイミングでやっと鑑賞。
率直な感想は、よく米アカデミー作品賞にノミネートされたなぁ、と。
かなり難解で、哲学的でもある。ほとんど台詞劇。
詩的で、演出・ストーリー・演技(=感情)も見て分かるのではなく、掬い取るように感じる。日本映画特有のベタ臭さも感じない。
欧米より寧ろ、ヨーロッパ向き。実際まず最初にカンヌで絶賛され、作風もヨーロッパ映画のよう。
日本でも好み分かれそうで、ましてやハリウッドでは敬遠されがち。
それが評価されたとは、改めて本当に凄い。
勿論それは、作品そのものの質、演出、演技、メッセージやテーマなど、“総合芸術”の素晴らしさ他ならない。
元々は短編小説だが、膨らませて3時間という長尺に。
長くは感じなかった…と言えば嘘になる。やはり3時間。長さは感じた。
しかし、全く退屈でただ長いだけの3時間には感じなかった。
それとは逆に、実に没頭出来た3時間であった。
開幕から登場人物たちの心の機微、彷徨、関係性にじっくり魅せられる。
喪失、再生…万国共通のテーマ。
だからと言って、ただそれだけを描けばいいってもんじゃない。
濱口竜介監督の、繊細で、じっくりと、堂々たる演出。大江崇允と共同脚本の、ストーリーや内面を代弁するような劇中劇を取り入れた巧みさ。
“演出”や“脚本”が認められた事が、さらにさらに嬉しい。
それにしても、まさか濱口竜介がこんなにも一気に飛躍するとは…。
てっきり是枝裕和がもう一度米アカデミーの場に挑むと思っていた。2018年のカンヌ国際映画祭でも是枝監督に注目も話題も賞も持っていかれたし。
その2018年の『寝ても覚めても』も自分は良かった。何だか日本では、主演二人のスキャンダルのせいですっかりヘンなレッテルを貼られてしまったようだが…。
その時感じた“確かさ”は本物だった。
世界を唸らせ、羽ばたき、勝負出来る新たな才能。今こそ、濱口竜介が魅せる時!
ノミネート発表以降、ワイドショーなどで散々話は知られているので、あらすじ記載は割愛。
ストーリー展開や登場人物たちの感情など個人的に感じた事を、順々に。
まず、主演の西島秀俊。人気の反面、よく“棒演技”とか言われてるようだけど、本作での演技は良かったんじゃないかな。
逆に、喜怒哀楽色の付いた熱演は本作の作風や主人公のキャラ像に合わないし。
ボソボソと喋り、感情を削ぎ落とし、抑えた自然体の雰囲気は、寧ろリアルに感じた。
西島演じる主人公、家福(かふく)。妻を亡くした舞台俳優で演出家。
妻とはとっくに死に別れたか冒頭数分描かれていると思っていたら、冒頭約30分強、妻との関係や死別までが描かれていた。
妻・音も女優から脚本家に転身。
共に作家同士として、作品を生み出す刺激になっている。時には、ベッドで求め合いながら…。
劇中で触れられていたが、夫婦それぞれの作品は全く別だが、目指してるものは同じ。何だかこれが、夫婦そのものを言い表しているような気がした。
夫婦として仕事上のパートナーとして、愛し合い、絆深く見える。一見は。
が、何処か“すれ違い”も感じる。
夫婦には幼くして死んだ娘がいた。
ある時家福は、妻が自宅のベッドで他の男との最中を目撃してしまう…。
しかし何故か、家福は妻を咎めない。愛故か…?
と言うより、夫婦は愛し合いながらも孤独や寂しさを抱えているように感じた。
傷に触れてはならないような、近くて遠いような…。
話しておきたい事がある。妻はそう告げた後、傍らから永遠に居なくなる…。
何を伝えたかったのか…?
いや寧ろ、自分は妻に伝えたい事はなかったのか…?
何処か“別世界”に居るような存在を感じる。霧島れいかが冒頭30分ほどだが、深い印象残す。
家福には変わった習慣が。
運転する車の中で、妻の声を録音したテープと自分で、舞台の脚本(ホン)読み。
うんざりするまで台詞を完璧に覚える為と家福は言うが、別の意味もあるだろう。
この愛車の中、テープを流している時だけ、亡くなった妻と一緒になれる。
自分だけの世界、一時…。誰にも脅かされたくない。
だからなのだろう。当初、ドライバーを雇う事に反対したのは。
家福の専属ドライバーとして雇われたみさき。
寡黙でぶっきらぼう。
が、運転の腕は確か。家福もその腕を認める。
みさきを雇いながらも、妻のテープを流す家福。
みさきの運転が静かで、妻との脚本読みに没頭出来、時々みさきの存在すら忘れるほど。
自分と妻だけのものであった空間(=車内)。
そこに邪魔する事なく、自然と居る事を許されたみさき。
見て分かる通り、他人に心を開かない家福。無口なみさき。
この空間の中で、少しずつ口を開いていく。
妻が不倫していた事、妻の自分への思い、自分の妻への思い…。家福が他人にこんな心境を吐露するのは初めて。
単に運転能力だけじゃないだろう。みさきも何処か、家福と通じる孤独さを感じる。
みさきの暗く、思い過去…。
本作のキャストの中ではピカイチの存在感。三浦透子がぶっきらぼうでありつつ複雑な内面名演。佇まいや煙草を吸う姿すらカッコいい。
演劇キャストに、人気俳優の高槻。
終盤、進行していた劇に思わぬトラブルを掛けてしまう、見た目はイケメン正統派だが、実際は困ったトラブルメイカー。
しかし家福は、高槻に厳しい演出をする一方、彼を何故か見離せない眼差しも感じた。
亡き妻のお気に入りだった高槻。高槻自身も、妻の脚本が好きだった。
自分と妻を知り、唯一自分と妻を今も繋げてくれているような存在。
であると同時に、衝撃の告白。
岡田将生が好助演。オーディション・シーンの迫真の演技、車内で暴露する家福との対話は圧巻。
以上が中軸のキャストだが、周りのキャストも忘れ難い。中でも、演劇スタッフ兼通訳のユンスさんと、ただ一人口の利けないキャストのユナ。
実は、夫婦であった二人。自宅に招かれ、会食する。
ユンスさんは韓国語、日本語、英語が堪能の上、手話も。そのきっかけは、妻ユナ。
彼女の事をもっと知りたい一心で。
一度は舞台を降りたユナだが、復帰。ユンスさんは自分の仕事傍ら妻の通訳や手話など、全面バックアップ。
何と、素敵な夫婦だろう。
愛情が満ち溢れ、見るこちらにも温かく伝わってくる。
ジン・デヨン演じるユンスさんの穏やかさ、パク・ユリム熱演の手話とキュートな魅力。
二人の姿に、家福も自然と笑みがこぼれる。
不思議なものだ。手話での会話なのに、こんなにも心が通じ合い、お互い思いあってるなんて…。
自分たち夫婦は…。
しかしそれが、妻との関係や他人との関係を見直し、縮めるきっかけとなる。
会食にみさきも招待。ここで初めて、みさきの運転能力を評価する。
家福が閉じていた心を開いた瞬間。
劇中劇が風変わり。
演劇キャストには、オーディションで選ばれた日本人、韓国人、台湾人、フィリピン人…。
劇中の台詞は、各々のキャストが母国語で。言葉ではなく、感情や動作で演技する。
稽古や舞台上でも、日本語・英語・韓国語・北京語・ドイツ語のみならず、手話も入り交じる。
独特の演出。
これが本作が、世界で評価された要因の一つかと。
言語、人種の多様性。障害の壁も超えて、皆で一つの作品を作る。
演劇の舞台裏の見方もあり。
本当にこの舞台が見たくなった。
私にはちと敷居が高かった点も。
劇中用いられる舞台の演目、チェーホフの戯曲『ワーニャ伯父さん』の内容を全く知らない。
知っていれば、二重三重に作品の深みが分かったのだろうが…。
しかしそれでも、本作のストーリーや登場人物…特に家福の心情とリンクしているのは感じた。
物語上は感情を内に込め、劇中劇では感情爆発の熱演。鬱憤、心の声を叫んでいるようだった。
この劇中劇を通じて、悲しみ、怒り、苦しみ、赦し、包容、癒し…あらゆる感情が伝わってきた。
と同時に、生きていく事への力強く、優しいメッセージ。
クライマックスの舞台直前、思わぬトラブルで舞台を存続か中止か迫られる。
決断出来るような場所へ。家福とみさきはドライブ(旅)をする。
雪深い北海道のみさきの生地へ。
ここで各々の過去や感情と対峙。
みさきは悲しい過去。
家福は、目を背けていた妻への思い、真実…。
それは、辛くもある。悲しくもある。苦しくもある。
しかしそれらと対峙し、見つめ直し、乗り越えた先に、きっと新たな思いがある…。
家福は言った。みさきの運転は心地よい、と。
私もそう。
やっと本作を見れて、この3時間のドライブに、同じ思い。
余白。ミニマルミュージック。北野武。
静かに淡々と進む物語。
家福お気に入りの車の中で、音の手により「ワーニャ伯父さん」が朗読され、家福がその空きスペースに自分の演技を入れる。何か起こって、車中に戻り、また何か起こって、車中に戻る。この反復が演出の骨組みと感じた。
また、「音(≠家福)」という観点では、セリフと車の音、セリフと波の音、セリフと風の音、と、常に2パーツでの展開に統一され、これが物語に現代音楽のような余白を生んでいる。ここでいきなり「バーン!」と銃声が聞こえたら北野映画だな…笑 と思っていたら、監督ご本人も北野武は通っているらしい。納得。
この描写の反復感がジャブの積み重ねになって、最後に、雪で一杯になったみさきの故郷を訪れた時の、静かな無音の迫力に繋がっていると認識。非常に構築的で、ノンバーバルな部分に粋がある作品。海外の高評価は納得。
主題に関しては、喪失という非常に村上春樹的なテーマ笑。しかし、この映画の粋が極めて映画的=他ジャンルでは語りづらい部分にあるのと同様、ご存知のように、村上作品の粋は極めて文学的=叙述の手触りや感触にある(と自分は思っている)。「移植」として見ても、難易度の高いニュアンスの再現を見事に行なっている高難度作。
3.5点の理由。ここまで言っておいてなんですが、映している世界の骨子は理解すれど、素直な感覚として、初回でそこまで世界に没入できてません笑。たぶん2回3回見たら5になるかな〜という思いがある一方で、う〜ん長いから見ないかもな〜という、極めてくたびれた理由で、点数下げてます。次見たら再評価しますね。
「ワーニャ伯父さん」予習が吉
原作未読ですが、村上春樹っぽさを十二分に感じる作品でした。
3時間という長さなので見る前は少し腰が重かったのですが、見てみたらそこまで長くは感じませんでした。淡々とした演出と嘘くさい台詞回しだからからこそ一層台詞が際立って聞き入ってしまうかたちに。
演劇に疎く、チェーホフの戯曲「ワーニャ伯父さん」もよく知らなかったので、知っていたらもっと理解できて楽しめたのだろうと思います。ワーニャ伯父さんが家福、ソーニャがみさきになぞられてること、なかなか気付けなかったです。
基本的には好きな映画ですが…、
評価が真っ二つに分かれていて、アカデミー賞につられて観た「パラサイト」が全く受付けられなかった私は躊躇していましたが、観てみました。
結論から言うと私はすごく好きです。
ただ、最期のシーンは「えっ?」となり混乱しました。あれ、必要だったかなぁ
ない方が私的にはよかったかな?
あとは皆さんで想像してください、ってことなんだと思いますが、それならば、伏線を置きっぱなしにしていく必要があったのかな(韓国にいることとか車がサーフのままとか犬がいたこととか)あれがあると想像が限定されてしまうような?
ここは好き嫌いが分かれると思います。
上質な小説
映画は虚構、リアルを求める必要はない、だけど…
なんの事はないNTRの話なんですね…。期待して観たのですがガッカリでした。子供の事が語られるシーンでもはや方向性は決定。これがきっかけとなり夫婦に見えない溝が生じて嫁の「男漁り」が始まる。結局は主人公には、嫁の「男漁り」の理由がわからないまま嫁は死んでいく。主人公の懺悔と再生がテーマというのだろうが方向性がわかった段階で観るのが苦痛になってきました。
そうそう、物語の設定についてもいい加減なところがあって…女性ドライバーの設定。中学生が公道で運転できるほど北海道は「秘境」ではない。北海道を馬鹿にするな😤確かに北海道は車が必要だよ、札幌の中心部以外は車が必要。だからといって中学生が運転した車で毎日送り向かえなんて😩
札幌駅のJRの始発時間が朝の6時以降という事もわかっていない。札幌駅から何時の「列車」(北海道の人は電車と言わない)に乗って7時に向かいに行く駅に着くのだろう…
映画は虚構でリアルは必要ないのだろうけど、野暮な話の展開といい加減な設定で映画を観ている途中に現実に戻ってしまった。
見ごたえはあるが、ギクシャクした場面あり物足りない処もありで秀作とは呼べない。人間関係や自省に関する含蓄ある話ではあるが、一人の男のグズグズした自分探しに180分付き合わされたという印象もあり。
①重要なモチーフである「ワーニャ伯父さん」を劇中劇にしたり(台詞が刷り込まれるように頻繁に出てくる)、劇中劇も手話も交えた多言語での芝居にしたところは確かに上手い構成だと思うのでカンヌで脚本賞を取れたのだとは思う。②180分持たせる演出は確かにしっかりしているが監督賞にノミネートされる程ではないと思う。③終始無表情で運転する三浦透子が宜しい。西島秀俊や舞台俳優・関係者たちのために運転しているうちに少しずつ自分の過去を語り始め悲惨な少女時代を過ごしたことや心に癒せようのない傷を負っていることがわかってくる自然な流れが良い。頬の傷を直し明るい顔で韓国の道を西島秀俊(から貰ったのだろう)の車で走っていくラストは爽やか。③あと、出演者の中ではジャニス役のソニア・ユアンが魅力的。まあ自分の好みですけど。北京語の発音がとてもキレイ。演劇蔡の担当者役の安部聡子は台詞のあまりの棒読みに素人さんかと思ってました。④岡田将生演じる高槻というのも感情移入しにくい役だ。家福夫婦の夫婦関係の実態に光を当てる重要な役どころかも知れないが、自分で応募しておきながら本番近くになって舞台に穴を開ける事を引き起こすなんて舞台人の風上にも置けない。その暴力性を示す兆候が描かれていたり、「分別を持て」とか「社会人としては失格だが」とかの台詞はあるが、それでも唐突感と不自然さとは拭えない。そういう人間であると見抜きながら選んだとすれば、家福の舞台演出家としての分別も疑わざるを得ない。⑥クライマックス。みさきの生まれ故郷に帰るシーン。廃村に続く未舗装の道路を走るとき結構ガタンガタンととてもスムースとは言えぬ母親が乗っていたら座席を蹴られそうな運転だったのが気になった。こういう細部が却って気になるのだ。⑦みさきの倒壊した家の前で二人が対峙し家福が初めて泣きながら自分の弱さを吐露するシーン。映像が硬直してまるで舞台の立ち稽古を観ているような絵。西島秀俊は熱演だが子供のように亡き妻への思慕を吐露したあと余韻もなくみさきを抱きしめて「大丈夫だよ」という流れが拙速過ぎて感心出来なかった。
淡々と、でもあっという間に終わってしまった
休日出勤が速攻終了したので劇場直行。3時間という長さに怖気づいたが...
休日出勤が速攻終了したので劇場直行。3時間という長さに怖気づいたが、さすがは話題作、その長さを全く感じさせなかった。
なんやねん、このやば綺麗な妻からスタート。岡田将生が肝となり、徐々に明らかになる主人公とドライバーの真実。
私のツッコミポイント
・どこか落ち着いて考えられる場所へ…広島から◯◯◯へ。それはないやろ(笑)
・劇中劇が私には無理。あんな多国語(まさかの手話まで)でセリフ言われてもわかるかい!
・セックスすると閃くらしい
ラストシーンが象徴してるが、「なぜか分かるか?さあ考えよ」的部分あり。◯◯賞を受賞する作品、そんなの多いですよね。
シアター4 E-7 神戸国際松竹で見る最後の作品となりました。相応しい良き作品でした。
小説のような
本を読んでいるようなその感覚に出会った作品だった。
主人公は、舞台俳優をしながら脚本家として活動していた。その彼には、妻がいた。とても仲の良い夫婦で誰もが羨むような夫婦だった。だけど、そこには、隠された悍ましい感情があった。
この作品は、とても長い作品だったと思ったけど、時間の長さを忘れるくらい深いものだった。
生きる事、死んでしまう事。
劇中ででくるセリフで印象深いものがあった。
「本当の自分に深く、真っ直ぐに向き合う事」少し売る覚えなので、正しく無いと思う。
自分ってとても空虚なものに感じてしまう事がある。
それは、自分というものに向き合う努力をしてこなかったらかな。
知らない事が一番の恐怖。
たしかにと感じた。
観終わった後には、少しだけスッキリした感じがあっていい作品でした
全796件中、381~400件目を表示