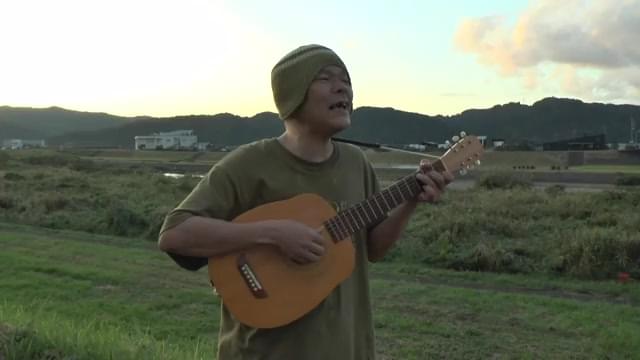川っぺりムコリッタのレビュー・感想・評価
全211件中、121~140件目を表示
食べる、働く、育てる、怒る、泣く、笑う、生きて行く
かもめ食堂の監督作だから、どんな美味しそうな料理が出るのかと思ったら、まさかの白米!
もう、おにぎりですらない
でも、この白米を訳あり松山ケンイチと、空気読めないムロツヨシという最強の二人コンビが食べると美味しそうなんだ☺️
何かしら抱えた人々が、近すぎない距離を保ちながら寄り添い生きる日々の暮らし
なにも解決しなくても、ただ毎日を懸命に生きる尊さが、川を渡る風や流れる雲、木に降りかかる雨や炊き立てのご飯の白さから伝わってくる
生と死と、いわゆるルートから外れた人々を描いているから、かもめ食堂のイメージで見に行くと、あれ?となりそう
ただ、監督の持ち味のユルいほんわかした空気感と、美味しい料理は健在
脇役まで豪華な役者陣がみんな魅力的で、2時間あっという間でした
個人的に、亡き夫を愛し続ける満島ひかりが印象的だった
健気な未亡人という綺麗事じゃなく、生身の女として美しかった
ラストシーンを彩るエンディング曲もよき😊
ご飯は誰かと一緒に食べた方が美味しいよ、というセリフが、鑑賞後の心に余韻として広がる映画でした
生きているって、当たり前じゃない
予告からして、すごく心が温まるホッコリ系の映画だと思っていた。松山ケンイチ、ムロツヨシ、満島ひかり、吉岡秀隆というメンツからもそう想像できた。だけど、想像とはかなり違くて、「生死」という重いテーマを扱った、深みのある人間ドラマでした。とても良かった。
登場人物全員、生と死の狭間で生きている。
4歳の時に母親と離婚して以来、1度もあってない父親が死んだ山田(松山ケンイチ)。
庭で野菜を育て、自給自足の生活を送る島田(ムロツヨシ)。
何年も前に死んだ旦那を未だに愛する南(満島ひかり)。
子どもと一緒に墓石の訪問販売を行う溝口(吉岡秀隆)。
死を間近に感じながらも生きている彼らは、生きることに一生懸命で、命をとても大切にする。4人の演技力は流石なもので、中でも松山×ムロは息の根ピッタリ。「マイ・ダディ」「神は見返りを求める」と、少し重い映画に近年出演し続けているムロツヨシだが、福田雄一作品では気付けなかった、演技のうまさに驚かされるばかり。柄本佑も同じく、役幅の広さに驚かされ続けています。
重いテーマながらも、終始居心地が良くて、しっかりと胸に染みながらも沢山笑える。日常の些細な幸せを描く映画で、この映画を見たらご飯がいつも以上に美味しく感じること間違いなし。陽気なシーンと考えさせられるシーンが交互になっている構成なため、飽きることもないし、交互だからこそより一層深みが増しているよく出来た映画です。
雰囲気がとてもいいのは、役者全員が優しい雰囲気を作り出しているというのもあるのだけど、「パスカルズ」の音楽があるからこそだと思う。「さかなのこ」でも音楽担当をしていたパスカルズだが、映画をとても暖かく包み込んでくれる素晴らしい音楽集団。ラストシーンなんて、心が一気に浄化される落ち着く曲でした。
それぞれ何かを抱え、少し歯車がズレている。
だけど、みんなが一緒ならその歯車もキレイにハマる。ギリギリの生活ながらも、支え合いながら生きている。「自分が死んだ時に1人でも悲しいと思ってくれる人がいたらそれでいい。」生きるって難しいけど、生きていないと幸せは感じられない。ハイツムコリッタの住民たちには癒されながらも、すごく胸に刺さるセリフがいっぱいで、とても味わい深い映画です。
前半の歯切れの悪さ、そして社長の説教臭いセリフに嫌悪感を持ってしまったり、断片的なところがいいところなのかもしれないけど、ちょっと物足りなさを感じてしまった。だけど、誰でも確実に刺さるものがあるだろうテーマを扱った、ちょっぴり重くてちょっぴり泣ける、コメディタッチの質の高い人間ドラマでした。ぜひ、映画館でこの雰囲気を堪能してください。
でんでんむしのかなしみ
予告から、孤独な若者とおかしな隣人たちとのふれあいを描いたコメディ、くらいに思っていたら、意外にも奥が深かった。
誰しもが哀しみを背負って生きている。
他者とのつながり、自らの過去とのつながり、死者とのつながり、いのちのつながり。いろんなつながりを感じる(考えさせられるよりも感じる)作品だった。
松山ケンイチ、ムロツヨシ、満島ひかり、吉岡秀隆、柄本祐、緒方直人、みんなそれぞれがこの人じゃなければ考えられないという役を上手く演じていた。
他者との関わりを避けて暮らしている山田君。迷惑ながらも人とふれあうことでだんだんと表情がいきいきとしてくる。松山ケンイチがただご飯を食べているだけなのに飽きることなくいつまでも見ていられる。
満島ひかりの亡き夫の遺骨とのラブ・シーンは哀しくせつなくも美しい。満島ひかりだから生々しくならず美しく哀しい。
風呂を貸してくれと勝手に上がり込んでくる隣人。ムロツヨシでなかったら、すごい嫌な奴になってたろう。ムロツヨシだからなんか憎めない。
薬師丸ひろ子、どこに出てたんだろうと思ったら、声だけだった。確かにいい声だった。あの声で優しく語られたら死ぬのを思いとどまるだろう。
吉岡秀隆演じる墓石のセールスマンも、あの声で空に浮かぶ金魚の霊の話を聞いたんだな。だから生きているんだ。(どですかでんの三谷昇のまんまのシーンも良かった)
蝉の声、キュウリを齧る音、炊き立ての白米、生きていれば何にだってしあわせを感じることができる。
ラストの葬送行進は現実離れしていたけど、この映画にはぴったりの美しい(画も音楽も)シーンでした。
花火でドーーーンッ!!
ささやかな日常の尊さを、奇跡的なまでの煌めきで捉えた超絶大傑作
タイトルにあるムコリッタは、どうやら時間の単位を表す仏教用語らしい。
ムコリッタは1日の三十分の一、つまり48分で1ムコリッタになるとのこと。
こうした説明が映画の冒頭ではさまれる。
そこから松山ケンイチ演じる訳ありっぽい男が富山県の田舎町に越して来るところから物語は始まる。
イカの塩辛を作る工場で働き始め、そして川っぺりにあるムコリッタというアパートで暮らし始めるというシンプルなストーリーだ。
この映画はストーリー自体がシンプルだからこそ、日常の生活を捉える細かい描写がとにかく素晴らし過ぎました。
まずは、素晴らしかったのはご飯のシーン。
炊きたての炊飯器のアップとか、イカの塩辛とか、採りたてのトマトとかきゅうりとか、みんなで食べるすき焼きとか、出てくる料理全てがどんな高級料亭の料理よりも美味しそうに見えました。
やっぱり、ご飯は何を食べるかじゃなくて、誰と食べるかってことが重要だということを改めて教えてもらったような気がしました。
他に素晴らしかったのはお風呂のシーン。
昔ながらの大人1人がギリギリの入れるくらいのせまい風呂場なんですが、松山ケンイチとムロツヨシの表情も相まってめちゃめちゃ至福の時間なんだろうなっていうのがとても伝わってくる良いシーンでした。
あと印象に残ったシーンは、満島ひかりがアイスを食べながら妊婦のお腹を蹴りたくなるって話すシーンとか、満島ひかりが夫の遺骨を口に含めりして亡き夫に想いを馳せるシーンとか、台風の日に松山ケンイチとムロツヨシが九九の7の段を逆から言うシーンとか、お風呂上がりに牛乳を飲む習慣が実は父親からの影響だったと気付くシーンとか、決してドラマティックな訳ではないけれど深く心に染み入るようなシーンたちが本当に素晴らしかったです。
全体的に横長のスクリーンサイズを活かした平行線が幾重にも折り重なった横長な画作りが素晴らし過ぎました。
お彼岸系
とても穏やかな気持ちで最後までまったりと観ていられました。
お彼岸のこの時期に観るにはとてもいいんじゃないでしょうか。
前科持ちの再スタートと自己嫌悪
必要最低限の生活
炊き立てのご飯
毎日単調な作業の繰り返し
親との死別
遺骨の行方
お墓の値段
お坊さんの相場
孤独死予備軍
お節介な隣人
子供の世界
重過ぎず軽過ぎず深いようでしっくりじんわり笑ってしまう。
印象に残った隣の島田のセリフ
「もし僕がいなくなったら寂しいと想ってくれる人が
一人でも居てくれたらそれだけでいい」
なんでもないことの有り難さを気づかせてくれる。
今の自分がいるのは両親のおかげ。お墓参りに行かなくちゃ…
あとからじんわり…
そういえば満島ひかりは「川の底からこんにちは」で父親の遺骨を人に向けて投げつけてたなぁ。
最後のふわふわと飛んでいく魂はイカの塩辛星人?「NOPE」と重なって笑えた。
エンドロールに「江口のりこ」やっぱりそうだったんだっ!て驚いたり。
同じく「薬師丸ひろ子」えっ?出てたっけ?…あっあの人か!って驚いたり。
同じく製作に「竹内力」なぜだか安心したり。
すき焼き食べて白目むいて震えてる松山ケンイチを思い出してまた笑ってしまった。
観てて腹減るわっw
今回はがっつりしっかり「死生観」のお話。
単調でも丁寧に生活し、食事をする。そして(親の)死に向き合いつつも、また新しい繋がりを噛みしめながら生きていく。そして気づけば、いろんな背景、想い、生き方の人間がいて、戸惑いながらも理解し、受け入れる。そんな関係性にしみじみと感じ入る作品です。
私自身も50を過ぎ、親兄弟を含めた近しい人との死別を経験し受け止めてきました。そして思うことは、死別することは悲しく、寂しいものではありますが、その経験を踏まえ、且つ自分もそれなりの年齢になってきたこともあり、映画などで表現される様々な死生観についていつしか、「味わい深さ」を感じる自分に気が付くものです。
この作品も、観ていていろんな感慨がありました。とは言え、正直実際に観るまでは、派手な作品ではないだろうし、わざわざ劇場で鑑賞するまでもないかとの考えもあったのですが、実際は一人で観に来ていても、「誰かと一緒に観ている」という感じこそが「劇場鑑賞の価値があった」と思わせてくれます。
そして何より、「食事シーン」は流石の演出の荻上監督に、「旨そうに食べる」を演じさせたらトップクラスの松山ケンイチさん、ムロツヨシさんの合わせ技は「破壊力抜群」です。
まったく、観てて腹減るわっw
ムコリッタ
リアル「めぞん一刻」
原作は読んでいないが、「めぞん一刻」が裏原作に違いない。
映画.COM の評価が3.7と高いので、鑑賞しました。
まず最初に気になったのは,
まるで16ミリ映画のような粗末な画質。
それでも そういう演出なのかと解釈して、観ていくが
何もかもB級機材を使っている? ので、とても鑑賞しづらい映画となっていた。
更に、カメラが不安げに微動撮影している。
細かいカット割りを失くして、カメラを動かす事で、場面を構成しようという意図のつもりだろうが、どうも監督からの演出指示は少なく
カメラマンが気を利かせて、自分の考えで動いているように思われる。
内容とは関係なく、撮影関係で映画評価を★2個は確実に落としている。
監督は演技指導もできていないようで、
各俳優陣が自分なりの演技をしていたが、自分を持っていないエセ俳優の演技は見られたものではなかった。
特に坊さんは酷い。重要な役柄だけに、もう少し演技のできる配役をキャスティングすべきだった。
ヤギが口を動かさずに、鳴くのは 糞演出。
アイスを食べるシーンで「僕は。。。」で切らるシーンは絶妙なタイミングは良かった。
主人公の部屋の前に住む親子?が家賃を5年間滞納しているくせに 親子が同室ではなく隣室住になっている。
その辺の 言われ は原作にはあるのだろうか? 興味が湧いた。
主人公があの部屋を紹介されるまでの
不動産屋さんとの やり取りを冒頭で描いた方が、映画の質が上がっただろう。
この映画を観たら、やはり アニメ映画「めぞん一刻」を見たくなった。
タブーの死に向き合った意欲作
思えば皆前科者のように何か抱えている。
#69 小さな幸せの積み重ね
前科者ゆえに幸せを感じちゃいけないと思い込んで、いつも仏頂面してる男が主人公のお話。
隣に住むズーズーしい男や、変な大家親子とか、絶対富山にはいなさそうな人ばかり。
唯一いそうなのは、山の上の大きな家に住む世間知らずのおばさん。ああいう金持ちはいそう。
久々に松山ケンイチの良さが全面に出てる作品で良かったっす。
死ぬまでに大成したい人じゃなくて、穏やかな人生を望む人向けのお話。
オール富山県内ロケってことだったのに、場所を特定出来そうな風景が映らないので川以外はどこかわからなかった(線路が並んで走ってる川は早月川だよね?)。
あの市営住宅風のボロアパートが魚津ってこと?
あとは山が低いので全部呉西地区での撮影よね?
映画見終わったらロケ地巡りしようと思ってたのに、寺以外に行きたくなる場所はなかったわ。
「たま」の音楽
ご飯と塩辛が食べたくなる
ムコリッタというより、身近な人の死がテーマであったが・・・・・・
解説では「ムコリッタ」は「ささやかな幸せ」と言う意味もあると書かれていました。
それを感じれられる、ほのぼのとした映画かと思っていたら、そこではなく、
「身近な人(生き物)の死や遺骨とどう向き合うか?」がテーマになっていました。
それに向けて伏線が張られ、そして回収されて行きました。
俳優も良いし、テーマも良いけど、何か面白くなかったな。そんな映画です。
松田聖子が歌ったラブソングも、みな印象的な訳ではない。そんな映画でした。
でもひとつ印象的だったのは、工場長の「これを毎日毎日、そして10年続ければその価値がわかるよ。」という言葉。(ブラック企業ではない前提ではありますが、)
我々の日常生活も同じようなものかも知れない。
子供を育て上げ独立し、仕事も一段落付けた。
もう「これを成し遂げるまでは、死んでも死にきれない!」なんて大テーマを背負って生きているわけではない。
日々の積み重ね、そこに少しの「ささやかな幸せ」もある。
あっ、これがムコリッタか!・・・・・・・・・・・・・・ちょっとハメられたね。
日本映画はこれでいいのだ!
『さかなのこ』に続き、今年のベストというか個人的なお気に入りの作品が続けて観れて嬉しいなぁ~。
もう日本映画はこの独自固有路線で突き進めば良いという思いが、更に強くなってしまいました。
本作の予告編を観た時「めぞん一刻」を思い出して観たくなったが、監督が「かもめ食堂」の荻上直子の作品だと知ったのは後からです。
この監督、特別に好きだった訳ではありませんが、本作は監督作品中で個人的に一番好きな作品となりました。
監督の特徴でもあるマイノリティを扱った作品でしたが、自分探しなどではなくもっと普遍性のある人間への思いの詰まったテーマだったので、今までの作品より好きだったのかも知れません。
観終わって作品の世界は「めぞん一刻」そのままでしたが、テーマは盛り沢山で大きく一つにまとめると「現在社会を生き抜く為の心の持ちよう」という感じではありました。
タイトルの“ムコリッタ”とは仏教の時間単位のひとつだそうで、ここでは「ささやかな幸せ」の意味で使われ本作の軸となるテーマでしたが、もっと細かく分けると“孤独”“貧困”“喪失感”等々、幸せの反対語の様な状態の登場人物達の各々の生き方と関わり方が描かれた作品でした。
私が特に個人的に刺さったのは、主人公の父親の死に方と弔われ方になりますかね。
私は母親をちゃんと弔うことが出来るのか?私が死ぬ時はちゃんと弔われるのか?恐らくこの父親と同じ状況(孤独死)になると想像できるので、これはちょっと怖かったです。
作品のトーンはドラマチックよりファンタジックに寄り、そんなに深刻ではなくユーモアもありコミカルなシーンも多かったのですが、テーマが“死(川っぺり)と生(ムコリッタ)”についてだったので、フェリーニや寺山修司や鈴木清順や大林宣彦などの“死”を意識した作品群や「おみおくりの作法」等々、様々な監督や作品を思い出していました。そういう作品に、思い入れがある人は是非観て貰いたい作品でした。
私自身は「ささやかな幸せ」を見つけるのは得意な方だと思ってはいるのですが、主人公達よりも死に行く側の人達に思いを馳せる年齢になってしまったので、幸福感を感じつつもキツサも同等に感じた作品となりました。
全211件中、121~140件目を表示