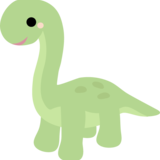「川口慧海著「チベット旅行記」の世界の一端に触れる」ブータン 山の教室 ブログ「地政学への知性」さんの映画レビュー(感想・評価)
川口慧海著「チベット旅行記」の世界の一端に触れる
「もっと詳しく見たい首都ティンプーからルナナ村への道」
主人公の不安や憂鬱な表情に反して、首都ティンプーからルナナ村への険しい行程に目を奪われた。厳しくも壮大な光景とそこにある自然を畏怖し共存・崇拝してきた現地の人たちの信仰の跡。8日間に及ぶ行程の中で、映画で紹介されているのはごく一部に過ぎない。辿った時代や行程、地域は異なるが、インドからチベットに向かった川口慧海の『チベット旅行記』を思い出した。特に共通する高山地帯に生きる人々のヤク(という動物)に対する愛情、文字だけでは伝わってこなかった肌感覚に近づけた気がした。
「突き刺さった村長の言葉」
主人公が夢が叶ったことを村長に伝えた際に返ってきた言葉、「この国は世界一幸福な国だと言われているが、未来ある若者は幸せを求めて外へ行ってしまう」。この言葉には、ブータン王国の誇る有名すぎる「国民総幸福」の意味を再考を促す視点が暗示されているように感じる。本当にその言葉が国民の総意ならば、僻地の村に赴任することを避ける教師などいないはずだ。国王の言葉を国民が盲目的に信じることは当の国王も本当は望んではいまい。決してこの国の国王夫妻は車窓から見える世界だけで庶民の生活を測るリーダーではない。(西水美恵子著『国を作るという仕事』英治出版(2009年)に詳しい。)
「山の上の教室という邦題には疑問」
タイトルからは僻地での教育現場を舞台・テーマとした映画かと思ってしまうが、実際はブータンの都市部から僻地、さらにはオーストラリアの環境・社会・人間の価値観を扱っている。原題『ルナナ:ヤクが教室に』もピンと来ない。主人公が首都ティンプーから任地のウララ村まで向かう行程はまさに、時の流れに逆行するタイムマシンに乗ったような光景に思えて、思わず笑ってしまった。筆者もネパールに行った時に首都カトマンズから端部まで辿った際の記憶が甦った。そしてオーストラリアは未来の姿として映し出されている。温暖化について理解していないが肌身で感じながら、雪山に住む雪豹の生活圏への悪影響に思いを馳せる案内人の言葉に身をつまされた。それでもより適切な邦題は閃かない。
「タイトルを変えてしまうほど眩しい少女の眼差し」
目を輝かせて先生を待つ村の子供達の代表がポスターの少女だ。決して優秀とは言えない先生を受け入れ、引き返そうとする彼を引き止める子どもたちの教育への強い渇望と先生への無条件の尊敬。先生の元に集う子供たちの表情はポスターやタイトルまでも自分たちに引き寄せてしまうほど眩しいのは認めざるを得ない。
「未来(都市)の人は幸福なのか。」
ギターも教師も特別な存在になってしまうルナナ村とギターも歌手もありふれた存在に過ぎないシドニー。どちらに幸せがあるのか?それに伴う経済的繁栄、教育の高度化、個人の余暇や娯楽の充実とそれに伴う競争や過酷な労働、対照的に人との密接な関わりと過酷な生活環境、多くがトレードオフとなってしまう都市部と農村部の間に生じる価値観の距離はブータン特有の問題ではないだろう。ルナナ村を離れて声高らかにヤクの唄を歌う主人公の心はすでに祖国に戻ったと信じたい。
全文はブログ「地政学への知性」でご覧ください。
共感・コメント、体験談も交えて頂き勉強になります。河口慧海は仏教が発祥の地インドでは廃れているので、仏教の原理的な教えに近いところとして鎖国していたチベットに入国したんですよね。仏教思想の伝播については勉強不足なのですが、ヒマラヤ山麓の地域って国に関わらず定着している民族にはチベット仏教って生活と切り離せない感覚で、日本人には理解しづらいものがあると思っています。
こんな教室で過ごしたら、戻ってきたいと思うはず。
「ヤクに捧げる歌」の素晴らしいこと!
ブータンの景色と大分違うのですが30数年前に、チベットに行ったことがあります。
ちょうど戒厳令がひかれてしまって、夜間外出禁止、ラサの街のあちこちに、自動小銃持った人民解放軍(?)兵士が立っていましたが、我々日本から来た害のない観光客だったので、特に怖い思いもしなかったし、せっかく来たのに閉まっていたポタラ宮の前で、「入りたいなあ」感を醸し出してツアーの一行、だらだら待っていたら、開けてくれて見学ができたりもしました。今度は青海鉄道に乗って行ってみたいです。
今やチベット仏教を信仰する唯一の国がブータンだと、聞いたことがあります。マニ車を回している人がいたような。
でも、私はオーストラリアも好きです。1ヶ月弱一人旅をしました。
個人的に視界を遮られる山に囲まれたところが苦手なので、永住するなら大地がだだっ広いオーストラリアがいいです。