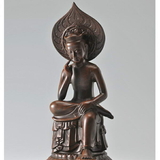アナザーラウンドのレビュー・感想・評価
全161件中、41~60件目を表示
酒パワー
生きてくのがつらいとき…
酒についての雑感
5年前、初めてビールを飲んだ日のことを思い出す。新宿のベルクだったか、友達に美味いからといって黒ビールを飲まされた。俺は大学一年生だった。
すげえ苦かった。どうしてこんなものをゴクゴク美味そうに飲んでるのか、友達だけじゃない、その場にいるほとんどすべての大人が、なんなんだマジで、本気でやってんのかそれ、意味わかんねーよ。俺は2、3口つけただけの残りを友達に全部飲ませた。
雑なことはあんまり言いたくなかった。その苦みが大人の苦みなんだよとか、飲まねえとやってらんねえのよとか知ったような口をきいてジョッキを飲み干す奴は、ものごとの機微を知らない、知ろうともしない愚か者だと思った。だいいちお前さ、まだ19歳じゃん。
5年経った。どっかの飲み屋にいた。同期に生でいいか?と訊かれた。俺はいいよと答えた。運ばれてくる、生、人数分。ハイお疲れー!ガラスがぶつかり合う音。それから波が引いたような無言。各々がジョッキを呷る。俺も。
相変わらず苦い。
が、飲める。
味覚が変わったのか、単に慣れてしまったのか、理由はわからない。だがジョッキはものの数分で空になった。大人の味だなあ、とはもう誰も言わなかった。言わずともわかりきっている、といった雰囲気だった。
最近、ふと大雑把に何かを断罪しようとしている自分がいることに気付くことがある。俺だってもっと丁寧に世界を見通したい。昼過ぎの無人の電車に流れる光の川を、目的地が過ぎても眺めていた日々が懐かしい。
今俺は地下鉄に乗っている。光も景色もない、つまらない道のり。余裕がなくなってきている。目の前に迫ってきたものを右か左に振り分ける、それで精一杯。
なんだかなあ、という気持ちで日々をやり過ごしている。ビールを飲む。なんだかなあ、という味がする。美味しいと思ったことは依然としてない。なんだかなあ、というぼんやりとした共通感というか、連帯感というか、それが心地いいような気がするから、苦いビールを飲んでいる。
やがて体にアルコールが回る。自分が両端のない空間にいるような錯覚に陥る。これも心地いい。長い長い現実世界のトンネルを抜けて薄橙色の花畑に躍り出たような、思わずスーツのまま踊り出したくなるような夢の世界。俺はそこまで恍惚の境地に踏み入れたことはないけど、たぶんそうなんだろう。酔っ払いがフラフラしているのは、頭の中で空を飛んでいるからだと思う。
酔っ払いが暴れるニュースをよく見る。誤ってホームに落ちる、商談をフイにする、信用を失う。
バカじゃねーの。19歳の俺は言うと思う。別に今だって言う。でも俺はビールを飲むとき、アルコールを体内に入れるとき、その苦さに自分を重ねてしまった、酔いがもたらす混濁に自由のイメージを思い描いてしまった。
飲まねえとやってられねえ人は、それがお決まりの定型句だからそう言ってるんじゃなくて、本当に飲まないとやってられねえから飲んでいる。そういう場合もあるということが最近ようやくわかってきた。
いや、わかってきたのか?それとも歳を取るごとに深く考えるのが面倒になってきて、わかったことにしているのか?何もわからない。
酒について考えているとわけがわからなくなってくる。ジュースでいいじゃん、という小学生の素朴なツッコミに、俺はいまだ有効な反論を思いつくことができない。そのわからなさが酒の魅力なのさ、と詭弁を弄してみたくなる。
酒を映画にするというのは綿飴を水に浮かせようとするようなものだ。
この映画は酒を否定も肯定もしない。単なるオブジェクトとして配置するだけ。でもそれが元で人々は悲喜交々の転換を迎える。
実際、酒それ自体に難しいところは何にもないのかもしれない。我々がそこに過度な期待や恐怖を抱くせいで無意味に意味慎重さを帯びているだけなのだ。
俺は一切合切の記憶を失ってみたい。知恵も知識も失った白紙状態になったとき、そのとき酒はいったいどんな味がするんだろう。
全体的に静かだが、普通に楽しめる
効能とリスク
人生は思い通りにはいかない…。深い懐をもって登場するすべての人の存在と感情を肯定。
酒好きな北欧デンマークらしい酒にまつわる物語。今年、米アカデミー賞国際長編映画賞を受賞した本作は奇妙な前向きさとエネルギーにあふれていて、思わず自分の人生を振り返りたくなるほど示唆に富んでいました。
「1、2杯引っかけた方が調子がいい」。酒飲みならきっと覚えがあるのではないでしょうか。それもそのはず、そのあたりが血中アルコール濃度0・05%で、その状態を保つとリラックスし、やる気と自信が漲ってくるのだという説を実際に提唱したノルウェーの哲学者がいたそうなのです。その哲学者フィン・スコルドゥールは「人間は血中アルコール濃度が0・05%足りない状態で生まれてきた」という理論を説きました。本作は デンマークのトマス・ヴィンターベア監督(おそらく飲んべえなのでしょう(^^ゞ)が、この理論からヒントを得た、ちょっと風変わりな陰りを帯びた喜劇になっています。とはいえ、既存の依存症映画とは異なります。
歴史教師のマーティン(マッツ・ミケルセン)は、このところ気力が減退。授業中もほとんどの生徒が私語ばかり。本人も自分は教師に向いていないと疑問を持っており、やる気はゼロ。生徒と親から大学受験に受からないと授業にダメ出しされ、家では仕事で忙しい妻のアニカとも心がすれ違い。妻と2人の息子はそんな父を見限っていました。何をやってもうまくいきません。
けれども思わぬ転機が訪れます。
ある日、同僚の心理学教師、ニコライ(マグナス・ミラン)の誕生祝いが開かれました。しかし水ばかり飲んでいるマーティンにあきれたニコライは、スコルドゥールの説を語り、「君に欠けているのは自信と楽しむ気持ちだ」と説教。仲間に促され酒を飲んだ。するとこれまで味わったことにない高揚感に感動したのです。
スコルドゥールの0・05%理論に興味を持ったマーティンは、こっそり酒をあおって教壇に立つと、驚くほど快活になって、魅力たっぷりの授業ができたのです。
マーティンの変化に意を強くしたニコライは、0・05%理論の実証を論文として発表することにします。そのため、ほかのふたりの同僚教師にも声をかけて、4人の教師がそれぞれ酒瓶を隠し持って授業に臨むことなりました。
マーティン以外の他の3人も似たり寄ったりで、中年の危機に瀕していました。それがアルコールの影響下で寛容かつ大胆になり、気分高揚、周囲の雰囲気も明るくなります。4人とも授業は大受け、家族との歯車も合って、実験は順調に進むのでした。
しかしもちろん、うまくはいきません。酒飲みの第2法則、ほどほどではやめられないもの(^^ゞ。調子に乗って血中濃度を少しずつ上げていき、濃度を0.12%に上げると、その結果もてきめん。しかし泥酔は誰の目にも明らかで、ほろ酔いから本格的酔っ払いへ、さらに依存症へと変貌していきます。こうなれば、あとは悲劇が待ち構えているだけでした。
こう書くと、酒の効用と危険を対比させて警告しているみたいですが、そんなに単純で道徳的な教訓話ではありません。それだけで終わらないのが本作の良いところ。行動に責任が伴うことを描くと同時に、それでも彼らの前に差し込む一筋の光明石描かれるのです。そして酒をきっかけに4人が直面している悲喜こもごものエピソードを点描し、「生きることとは何か」を語りかけてくるのです。
老犬の介助や、子供のおねしょにてんてこ舞いするそれぞれの家庭の些細な実情は、さらっとした描写なのに伏線となって心に響きます。そこに漂っているのはやるせない酩酊感と苦しいほどの寂寥!
特にうつろな目でぼそぼそと話していたマーティンが、自信に満ちた男に変身するのを見るだけで、もう十分に面白かったです。下戸の人には「なにをバカなことを」と鼻で笑われそうですが、けっこう説得力がありました。
職場で飲んでよいものかと一瞬ためらい、飲酒して朗らかに振る舞うしぐさは実に自然で、納得!名優ミケルセンをはじめ、俳優陣は酔っ払いを演じきるため、撮影前にどのくらい飲酒したらどんな酔い方をするか、実際に飲んで確かめ、演じ方を真剣に論じ合ったそうです。
ミケルセンとヴィンターベア監督は、ぬれぎぬを着せられた無実の男を描く「偽りなき者」でもタッグを組んでいますが、本作はぐっと軽やかなんです。酔ったマーティンたちが若者たちに向けて発するのは、ほとんどが励ましや包み込むような温かい言葉でした。
その説得力を支えているのがリアリズム重視の「ドグマ95」という手法です。ヴィンターベア監督は 提唱者の一人とあって、酒飲みの描写が迫真なんです。
「ドグマ95」とはセット撮影、人工照明、効果音などを禁止するルールに則った映画改革運動のことです。それにそうなら本来は照明効果は禁止ですが、本作ではそれと分からない光源を当てて撮影しています。それでも「ドグマ95」風に見えてしまうのは、若い撮影監督の腕がいいからでしょう。
タイトルは英語で 「もう一杯」という意味。「失敗を恐れずに挑めば、人生の新しいスタートを切ることができる」ということでしょうか。自分の歩んできた人生を見つめ直し、輝きを取り戻す方法は、何も酒とは限りません。そこに思いをはせると、ただの「酔っ払い映画」ではなく、全ての悩める人への応援歌であることに気づかされます。ラストの高揚感に包まれたシーンには、希望が溢れていました。
人生は思い通りにはいかない…。本作には出会いと別れ、希望と諦観、笑いと涙などなど、あらゆることがつまっていて、今にも溢れ出しそうなのです。そして、深い懐をもって登場するすべての人の存在と感情を肯定するのでした。
最後に流れる曲の歌詞は語りかけてきます。「誰が何と言おうと人生は最高」だと。そしてこの作品をアイーダに捧げるというテロップで終わっていました。その時はなにも気にかけなかったのですが、マッツ・ミケルセンの娘役を演じるはずだった実娘のアイーダが、撮影4日目に交通事故で亡っていたそうなのです。「娘が生きていた証し、記念碑として完成させると決めた。」という監督の悲しみと決意を後から知って、涙が止めもなく流れました。
それでも「誰が何と言おうと人生は最高」なのでしょう。(2021年9月3日公開/117分)
マッツミケルセンにほろ酔い!!
血中アルコール濃度0・05%で授業する教師たちの実験。
なんとも穏やかでない!
これってもしかして実話?!
2020年(デンマーク)監督:トマス・ヴィンターベア。
アカデミー国際長編映画賞を受賞したデンマーク映画です。
デンマークの国民的スター・マッツ・ミケルセンが主演しています。
題材に選んだテーマが、斬新でした。
「アルコールを適量飲んで仕事をしたら成果は上がるか??」
企画の勝利ですね。
とても考えさせられ、また泣き笑いする、とても良い作品でした。
中年男性の悲哀を感じました。
若い頃に較べて日々体力・気力・感覚の衰えをを感じ、仕事にも飽きて、妻にも新鮮味を感じない。
一番の問題は、彼らの教師としての授業が退屈なことです。
仕事への情熱が失せたため、生徒から受けないし、
授業に魅力が無いのです。
マーティン(マッツ・ミケルセン)は歴史の教師です。
脈絡のない授業に生徒はスマホをいじったり、途中で抜け出したり・・・。
遂には情熱のない授業に父兄からダメ出しを食らいます。
同じ悩みを持つ同僚の音楽、心理学、体育担当の4人で実験開始です。
やってみるとリラックスできるし、授業はノリノリで面白くなリ、
教室は笑い声で沸き立ちます。
合唱の授業でも生徒は素晴らしいハーモニーを響かせることに。
気を良くした4人はアルコール濃度をあげてみます。
マーティンは、更に限界に挑戦すると言い出す始末。
さてエスカレートした実験の結果は?
(ほろ苦いです、ビールより苦い)
高校生の若さは眩しいです。
若さは宝物と気付く映画でもありました。
挿入曲がセンス良くて映画を盛り立てます。
「デンマークに生まれて」の美しいこと。
デンマーク人は愛国心に溢れてますね。
そして何と言っても、マッツ・ミケルセンです。
ラストで見せるダンスの格好良いこと。
(なんとバレエアカデミー出身なんですねー)
黒いスーツの下の身体の線の引き締まってること。
(体操の選手だったこともある)
デンマークの宝は、くたびれた中年男役でも、その魅力を隠せなかったです。
お勧めです。
人生は美しい
面白い試みだなと思って観てました。
マッツミケルセンの枯れた演技が素晴らしく、
前半はこの先生の授業つまらなそうだなと言う感じ
をヒシヒシと感じました。
血中アルコール濃度を0.05に保つと精神的なバランス
が良くなると言う仮説を実証して行くのだけど、
好転するコントラストをもっとハッキリ見せて欲しかったけど、それだとコメディになっちゃうのか…
まぁ想像通り、酒を飲んで仕事して行き着く先は
地獄だろうなと誰もが思うのだけど、
どうやらデンマークは高校生も酒を飲めるらしく、
この辺りの風刺にもなってるのかなと思います。
学生のキルケゴールの話がこの映画のテーマとも
思え、不安や失敗から何を学ぶかが大切であり、
この試みを全て否定しないラストも良かったと思います。
それでも人生は素晴らしい。
つまらない人生をつまらないで終わらすのではなく、
何かやってみることもまたら大事なのかもなと思える
映画でした。
だけど、自分の場合
お酒を手に取ることはやめておきます。
メガネ坊 行け!
鑑賞動機:マッツ6割、アカデミー賞2割、あらすじ2割
行き詰まったときの仲間
コメディを期待するなかれ
「偽りなき者」のような辛マッツでなくて良かった
中年たちの悲哀
カメラワークと音楽が素敵で演者さんたちがとても良かった。けど、内容はややパンチの弱いものでした。
キルケゴール 「死にいたる病」デンマークの哲学者。
「絶望」は人間だけがかかる病気で、それは人間が動物以上の存在である証拠。だから誰でもそこに陥る。あとは、それに対して目を背けずに、自分がいかに主体的に関わっていくかが重要なのだと、彼は解いてる。
人は絶望する生き物。だからたまにはお酒に頼るのもいい。友人や家族と心を通わせて自分の弱さに酔いしれるのもいいと思う。ただ、それに溺れない強さが必要。
この4人の男たちの絶望あるあるに対する向き合い方と、その結果の違い。と、まだ絶望予備軍の学生たちのお酒との関わり方の違いに、この監督さんのシニカルさが出ていたかな。
絶望がテーマだけど最後に少し希望のエッセンスを入れて前向きに仕上げてるのか良かったです。
しかし、絶望できるから人間なんだというのはちょっと悲しい。
この映画を観て、酒との距離感を測れ‼️❓
酒飲みの端くれとして、ゆうべきことがある。
血中濃度だの、酒に力で生きるだの、胡散臭いことゆうなよ、それがこの映画の主題。
酒は楽しむもんであり、それ以上でも、それ以下でも無い。
だからこんの映画では、酒でえらい目にあう、それでよし、わかるならよし。
なら、酒でひどい目にあう、楽しむ、それだけで良い。
人生はそれと別に考える、べし、別に考えて、家庭がうまくいくなら、良し、そうでなくても良し。
つくづく、良いことも悪いことも、酒のせいにはしなさんな。
デンマークみたいに年齢自由で酒を楽しむも良し、日本みたいにいじめで殺されるより、マシだね。
いいじゃん、短い人生なんだし、迷惑かけんで、呑めたら良いじゃ無い。
酒飲み万歳でいいじゃんし🙌
今、飲んでるけど、ええやろ、え。
全161件中、41~60件目を表示