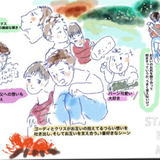アナザーラウンドのレビュー・感想・評価
全207件中、141~160件目を表示
辛いこともあるけど、人生を楽しもう
主人公が授業の中で、3人のうちどの政治家が良いかを生徒に選ばせる。
2人は大酒飲み、1人は飲まない。
生徒は皆、飲まない政治家を選ぶ。
大酒飲みは、ルーズベルトとチャーチル、飲まない方はヒトラーだと明かされる。
この映画が30年程後にリメイクされる時、この飲まない政治家はヒトラーではなく、「トランプ」になっているかもしれない。
過ぎたるは
飲んだくれおバカ映画なのかと思ってましたースミマセン!
コレはもうポスターのミケルセンのカッコ良さに惹かれて観ました!血中アルコール度を0.05%に保ち続けるとどうなるか。仕事も過程もうまく行っていない中年教師をミケルセンが自然に冴えない中年を演じてます(でもそこはかとなく漂うカッコよさ)
途中まではみんなイケイケどんどんで全てうまくいくかのように思わせておいて、やはりそんな事はなく。
悲しい展開になって…でも最後の卒業生に囲まれる中ダンスを踊るシーンは、え?結局妻とうまくいくの?どういう展開?なんて疑問も吹き飛ぶ素敵さでした!ミケルセンカッコよすぎ!!
生徒たちの国家の合唱の素晴らしさとか、サッカーチームのメガネ坊がトミーの手を握るシーンとか(可愛くてもう!好き!)ミケルセンの家族でカヌーの旅行に行くシーンとか大好きなシーンがたくさんある映画でした。
お酒は飲んでも飲まれるな、色々あるけど人生は美しい✨な映画です!好き!
もし、この作品を見なければ
北欧•デンマークの(我が国の常識から見れば)ネジの外れた飲酒事情を知ることは無かったと思います。
異国文化を覗き見ることが出来たうえに、「北欧の至宝」ことマッツミケルセンが踊るキレキレのジャズバレエを堪能できるので、大変お得な映画です。
それだけではなく、お話についても
「鬱屈を抱えた仲間たちが」、「事態を好転させるために悪い事をはじめる」、「最初は上手くいくも」「徐々に深みにはまり、とりかえしのつかないことが起こる」、「すべてを失ったのちに残るものは…」
みたいな話かと。
これは、ジャンルは違えど、私の好きな邦画である「日本で一番悪い奴ら」とも共通する骨組みだし、こういうタイプの映画が大好きって人は結構いるのではないでしょうか。
幕切れについても、お酒のネガティブな側面をクローズアップさせたのちに、もう一回ポジティブ面も描くという説教臭さを抑えた着地。
それをマッツミケルセンがダンスで体現するという洒落た演出が良かったです。
ただ、「中年の危機」モノとして壊れた夫婦関係も描くのはいいとして。
奥さんが浮気してましたは微妙かな。なんか唐突かつ、腑に落ちない展開に感じました。
「マンネリでギクシャクした関係に陥った→酒で一瞬修復しかけたかに見えた→やっぱり生活が荒れて、より一層関係悪化→そして…」で良かったような。
悪い飲酒とそれによる弊害を描いているわけなので、パートナー側の責任に転嫁するのは何だかな…と。序盤のギクシャクした家庭の風景がよく出来ていたので蛇足ではないでしょうか。
とかく北欧っていうと「かもめ食堂」のほわほわした感じとか、IKEAのシンプルでお洒落な家具とか思い浮かべがちです。
「北欧のそういう面に憧れる人には、本作とミッドサマーを観せてあげたいなあ」などと思い至りました。
北海道大学、一升瓶リレー
冒頭に出てくる、ビールを飲みながらグループで池を一周したら優勝というイベントがあった。
これを観てデジャブに陥った。
私の出身校の北大では昭和60年代)に各学部対抗で、グループでリレー方式で一升瓶を飲みながら400mを完走し、且つ飲み干し、ゴールするイベントがありました。
また、私の居た医学部は、学校祭の最終日はビアパーティーがあり、最後はビールのかけあいとなり、その後、噴水に飛び込むのが風習でした。
アルコールに対する事故が相次いだため、そのような行事はなくなりましたが、少し懐かしくなりました。
映画は「ヒヤッパー」という内容を期待しておりましたが、思った以上にヘビーな内容で、デート向きではない。自分は酒を飲むので、身につまされる問題であった。
人によって印象は随分異なるだろうが。
飲酒をする人間としない人間とだとだいぶ受け止め方が異なる映画だろう。ほぼ毎日呑む僕の感想は、1)酒は飲みすぎてはいけない。2)何を飲むかよりも誰と飲むかはもっと大事。映画を見終わって帰宅して早速家内と呑んだ。しかしこんなに楽しそうに酒を飲む演技をできるメンバー(酒の力を借りたのかもしれないが)をよくも集めたものだ。デンマーク映画は年に2−3本観るが大変印象に残る作品だった。良い意味でエンデイングの予想は大きく外れた。
現代人の孤独と不安を描いた映画?
スゲーな
デンマーク発・酔っ払い大行進
恐怖のアル中ホラー~最後まで酒から抜けられないのは誰だ!
トマス・ボー・ラーセン一択やろー。(偏見だ。)13日の金曜日でイチャイチャしてるカップルが犠牲者ってくらい明解やろー(偏見だ。)
潤滑油
飲みたくなった
酒はキ◯ガイ水ってのを、見事に表現。
本音を言うのに酒の力を借りるようになったら、アル中一直線。
舞台になるデンマークでは高校生の飲酒が認められているので、そこを踏まえて観ると、若者に「ルールを守り適度に飲めばハッピー」「度を超えた飲酒は、いかに危ないか」を教える、上手い作りになっていました。
また、人と一緒に仕事し成功するのに必要なのは、リラックスして実力を出しながら、陽気に楽しく興味をひく明るい話し方なのであって、酒じゃないよと。
失敗したときは、自分の弱さや実力のなさに目を向けて、酒(や実際にその場から)逃げるんじゃなくて真っ向から立ち向かうことの重要性も伝えつつ。
さらに、役者たちがすごい。
本当に酩酊してないかと思うレベルの、迫真の酔っ払い演技は神がかり的。
東京、神奈川のお店での酒類販売自粛要請な状況を考えると、あんなに美味そうに酒を飲むシーンばかり見せつけられるのは、目の毒でした。
あー、酒を楽しく飲みたい。
コロナのバカ。
最後まで楽しめて後味も良い北欧の良作
行き着くところは、やっぱこうだよね! 北欧インテリアで魅力度2割増し!
映画のあらすじ読んだだけで爆笑してしまったなんて、今までなかった経験だ。
なので期待度高めで鑑賞。その割には、、、のことろも無きにしも非ずだったけど、おしゃれな北欧住宅・インテリア雑貨に囲まれ、いいおっさんたちがエセ理論の探求の挙句、単なる依存症になって迎えるカタルシスをユーモアたっぷりに紡いでくれた。馴染みのなかったデンマークという国の、豊かさゆえに陥りがちな人々のギクシャクした感じが丁寧に描かれていたと思う。部屋の光量の低さも、酒を注ぐグラスのグッドデザインも、窓から見える景色も、実に美しい北欧の世界。これと同じことを日本の学校やコーポを舞台に描いても荒むと思った。残念だけど。
すぐ日本と比べてはいけない
デンマーク
ドイツの北・スカンジナビア半島の間に位置する
バイキングの流れをくむ立憲君主制国家
高福祉高負担国家・世界一幸福な国として知られる
(こういう根拠の薄いランキングには更々疑問だが)
がこと飲酒に関しては年齢制限が原則なく
(購入等には一応制限がある)吞んべえ大国と
しても知られている
酒を浴びるように飲んでいた学生時代を知る
教員を務める中年4人組が張り合いのない
毎日を送るうち誕生日で集まった時に
アルコールの血中濃度を0.05%に保つと
脳の回転が良くなるという仮説をもとに
授業の前に酒を飲んでいくように
なるごとに起こる出来事
なんてことはないテーマのようで
仕事中に酒を飲むなんて不謹慎極まりない
という風潮は日本では当たり前で
海外にもそれなりに現代社会ではあると
思いますがそうした常識を破った先に
見える世界といった描写が印象的でした
呑んべえ大国でアルコールの血中濃度なんて
気にしてる人がよほどいないみたいのも
エッセンスなんでしょうか
まあそんな4人ですがやはり酒
歯止めが利かなくなり酒をどんどん飲んで
いく事で色々問題が起こってきてついには
仕事をクビになってしまったり
奥さんが家を出ていったり散々になってきます
色々な酒がでてきます
パブでみんなで飲むビール
誕生日会で飲むシャンパン
食欲がなくて飲む冷やした白ワイン
酔うためだけに作ったごちゃ混ぜ酒
楽しい奴も悲しい奴も悲喜交々
それらを乗り越え
卒業する教え子を送り出し祝杯をあげるエンディングは
何とも言えない爽快感がある物でした
この映画は単に飲酒を礼賛するわけでなく
本当の自己責任がどこにあるかを突き止める
作りとなっています
日本ではコロナ禍もあり飲酒事態が反社会行為
みたいな取り上げられ方もしますが
結局自己責任の範疇でコントロールするしか
ないのですね
自分は風呂上りの缶ビール一杯で十分なくらい
なのでなにがなんでも飲みたい人たちの
鬱憤まではわかりかねますが
ちなみにデンマークはコロナワクチンの接種率
非常に高いそうで国民580万人全員に
ほぼ打ち終わっているそうです
デンマーク人、お酒強っ❗️ 血中アルコール濃度0.05%って 日本...
デンマーク人、お酒強っ❗️
血中アルコール濃度0.05%って
日本人なら半分くらいとして
ワイングラス一杯程度が適量なのかな
この先
マーティンのように
八方塞がりになったら
人生を諦めてしまう前に
ダメ元で試してみようかな
菅総理も会見前に
一杯飲んだら
饒舌になったかもね
マッツ・ミケルセン
冴えない役なんだけど
なかなかイケてるわ
【”酒は飲んでも、吞まれるな!”酒を百薬の長にするか、酒により身を破滅させるかは、自らの意志次第。この作品は、生きる事を尊ぶ、やや捻りを入れた人生賛歌でもある。】
◆この映画の撮影4日目に、この作品に出演予定だった娘さんを交通事故で亡くしたトマス・ヴィンターベア監督に謹んで哀悼の意を表します。
そして、その悲しみの中、映画製作を続けた気概に対しても・・
ー 高校で歴史を教えているマーティン(北欧の至宝、マッツ・ミケルセン。誰がこの素敵な異名を付けたのか知らないが、激しく同意する。)は、歴史教師の仕事、家庭生活に行き詰まり、無気力な日々を送る。
そんな中、心理学教師ニコライの誕生日を祝う同僚の体育教師トミー、音楽教師ピーターとの会食中に話題になったノルウエー哲学者フィン・スコルドゥールの奇想天外な学説
”血中アルコール濃度を常に0.05%に保つと人生が向上する・・”
を真に受け、ほろ酔いで教壇に立ったマーティンの退屈な授業は徐々に生徒を魅了する面白き授業に・・。そして他の3人の教師達も・・。ー
◆感想
・マーティン達のアルコールによる"人生充実実験"が、酒に呑まれた彼らの弱さを露にして行く過程の描き方の巧さ。
- 自分達はアルコールをコントロールしていると思っていた4人が徐々に酒に呑まれて行く姿。身に覚えが数々あるなあ・・。-
・アルコールにより、明るく前向きになり、妻や子供達との関係性も良くなって行くマーティン。
- だが、酒に呑まれたマーティンは、積年の妻への不満を口にしてしまう。それは、言ってはいけない言葉だった・・。-
・酒に呑まれた体育教師トミーの死を挿入することで、今作が只の酒飲み達の映画ではない事を、雄弁に物語っている。常に控えだった幼きサッカー選手のメガネ坊のセンスを見抜くシーンからの、トミーが、酒に呑み込まれて行く姿。
ー メガネ坊が、トミーの棺桶の上にそっと置いた花一本・・。ー
・ 再後半、心理学教師ニコライのアドバイスにより(コラコラ!)試験の緊張を解きほぐし、見事に試験に合格した生徒の嬉しそうな表情。
そして卒業パーティーでの皆の弾ける笑顔。
距離を置いていた妻からの”私も寂しい・・”と言うメールの言葉。
酒をラッパ飲みしながらの、マーティンの軽やかなダンス!ダンス!ダンス!
ラストは見事な海へのダイブ!
- 嬉しい時に酒を飲む楽しさを再認識し、軽やかにステップを踏むマーティンの姿がとても素敵である。ー
<この作品は、アルコールをコントロールする事で、豊かな人生を見つけようとする4人の男達の姿を描いている。
そこでは、生きる事の素晴らしさと共に、酒に呑まれてしまった恐ろしさもキチンと描かれている。
出来れば、アルコールの力を借りなくとも、豊かな人生を歩むのが一番であることを伝える映画でもある。
矢張り、酒は楽しい時に朗らかな気持ちで飲みたいモノであるなあ・・。>
飲んで飲んでまた呑んで
全207件中、141~160件目を表示