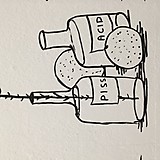マルモイ ことばあつめのレビュー・感想・評価
全49件中、1~20件目を表示
アイデンティティ
言語と名前は自分のアイデンティティであるそして、自分まで連綿と繋がってきた祖先からの大切な預かり物である。また次の世代へと繋いでゆく大切な預かり物である。
1930年代の日本統治時代に朝鮮語の使用禁止や創氏改名を主とする朝鮮民族固有の文化への弾圧がはじまった京城。総督府の監視も厳しく、朝鮮語を守ろうとする学者たちは息を潜めて辞書編纂のために「マルモイ ことばあつめ」をしている。
総督府や警察からの弾圧や同じ朝鮮民族でも生き延びるために親日派となったであろう者たちからの妨害で難航する作業。
命がけで作業を進める「学会」のメンバーたち。そして非識字者であったが「学会」と出会い識字できることで世界が広がっていくうるさくて家族思いだがうだつの上がらないパンス。中盤のたるみをチャラにしてしまうエネルギーが後半に炸裂する。
言葉は魂であり、民族やその文化圏を繋ぐもやいでもある。その言葉をもって親が子に授ける名前は言霊の最たるものだ。
当たり前に日本語を話し、親からもらった名前と自らの意思で選んだ名前で生きていることに感謝と誇りを持とうと感じた。
118-47
文化を守る、その意義を伝えてくれた
言語とは文化の土台であり、最も基本的なものだ。存在するのが当たり前すぎて、忘れがちになるが、言葉もまた誰かが守らないとなくなってしまうようなものなのだ。この映画で描かれたように占領統治の政策で危機に陥ることもあれば、地方の方言のように徐々に標準語に侵食されていくことでなくなる場合、民族自体が少数となり使える人間がほとんどいなくなってしまうなど、様々な理由がある。
どの民族にも固有の表現があり、物語がある。土台である言語がなくなれば、それらはほとんど全て消えてしまう。この映画が描いた言語を守るという行為は、その民族の全ての文化を守ることだ。
映画館の使われ方がとても印象的だ。映画というのは、戦前・戦中・戦後も色々な国でプロパガンダとして使われたメディアだ。日本も例外ではない。その映画館で密かに辞書編集の大会議を開き、言語を守る戦いをしていたというのはなかなか皮肉が効いている。国や人種、民族の違いを超えて、文化を大事にする人々との連帯を大切にしたいと思った。
惜しい!
1940年代の日本統治下の朝鮮を舞台に、公用語として日本語を強制され、さらに創氏改名をも強要される中で、朝鮮全土の方言を含む言葉を集めた『朝鮮語辞典』を作ろうとした人々の史実をモデルとしたフィクション映画。
なんか前に観た光州事件が題材の『タクシー運転手 約束は海を越えて』に似てるなと思ったら、同じ脚本家の監督デビュー作らしい。似てるというより基本構造がほとんど同じで、もうちょっと何か違いがあったほうが良かったような。『タクシー運転手』にもあった、泣かせ笑わせることを狙うベタな人情喜劇要素がさらに強くなっていて、特に前半はどうもいまいち入り込めなかった。日本人を演じてるのが韓国人俳優なので、みんな日本語が片言なのもマイナス。まあ風俗描写はほとんど違和感なかったけど。
ただ後半はさすがになかなか盛り上がり、まあまあ面白かった。大日本帝国の他民族に対する抑圧的な言語政策を描いた映画としても価値がある。それだけにせめて日本警察の役を日本人俳優に演じさせていればとちょっと残念に思う。
【”言葉は民族の精神”大日本帝国支配下の朝鮮で、母国語の辞書作りに命を懸ける人たちの姿を描いた逸品。ユ・ヘジン演じる文盲の男と朝鮮語学会の代表との交流と別れが沁みる作品でもある。】
■大日本帝国支配下の朝鮮、京城が舞台。
前科持ちでお調子者のパンス(ユ・ヘジン)はある日、息子の授業料を払うために朝鮮語学会の代表リュ・ジョンファン(ユン・ゲサン)のバッグを盗む。
ジョンファンは大日本帝国陸軍により使用を禁止されて行く朝鮮語の辞書を作ろうと“方言も含めた朝鮮語”を集め、自国の精神、文化のために辞書を作ろうとする男だった。
ジョンファンと接するうちに文盲のパンスは字を覚え、読み書きが出来る事の喜びと、母国語の魅力に気づかされていく。
◆感想<Caution!内容に触れています。>
・序盤は、ユ・ヘジンならではのコミカルな展開が面白い。
・だが、中盤、後半も大日本帝国陸軍による、朝鮮文化統制、朝鮮民族への日本語教育の徹底、日本の名前への改名に至るシーンや、朝鮮語学会メンバーに対する拷問などは、観ていてキツイ。
・だが、ユ・ヘジン演じるパンスが、字を覚え、読み書きが出来る事の喜びに目覚め、朝鮮語学会の代表リュ・ジョンファンに協力していくシーンは沁みる。
方言を集めるために、パンスの悪友達を集め、夫々の出身地域の方言を収集していくシーンや、映画館に朝鮮語学会に賛同する人たちを集め、集会を開くシーン。
■日本が、終戦が近づくにつれ朝鮮民族への弾圧を強めて行くシーン。矛先は朝鮮語学会にも向けられる中、パンスとリュ・ヘジンは必死に辞書を作るための言葉を守ろうとするが、大日本帝国軍人たちに襲われて行く。
<パンスが銃弾に斃れた後、終戦になり朝鮮語辞典は無事に創刊されるのだが、そこに挟まっていたパンスが子供達に残した手紙のシーンも、沁みた作品である。
戦争になると、文化統制が行われるのは歴史の必然ではあるが、それに屈せずに成果を成し遂げた方々には尊崇の念を改めて抱いた作品である。>
■学生時代に、朝鮮ではなく中国を一カ月半放浪していた事があるが、その際に金が無かったので汽車の硬座(二等車)に乗って旅をつづけた際に、中国の年配の方々から笑いながら”バカヤロー”と言われた事を思い出す。あとは、腕を組んでいると日本の軍人を思い出すらしく、笑いながら”怖いよ”とも言われたなあ。
今作を観ている時と同様に、居心地が悪かった事を思い出してしまったよ。
「辞書」の持つ重み
「博士と狂人」や「舟を編む」などの作品同様、本作も「辞書」の編纂がストーリーの柱だったが、言葉を集めて意味を定義するという、「辞書」の持つ意味と重みを考えさせられた。
言葉は、文化そのもの。文字の読み書きができないパンスであっても、暴力に関わる微妙な言葉づかいの違いには敏感だったり、方言集めにユニークな発想を持ち込んだりと、彼がこれまで生きてきた道のりが、辞書の内容の豊かさや正確さに繋がっていく。そのパンスが少しずつ文字を獲得し、自分の世界を広げていく様は、「言語の確立=文化の成熟」を観客に追体験させる仕掛けになっていたように感じた。
また、この映画は、その国の言葉の使用を意図的に制限するというのは、正に「蹂躙」そのもので、相手の尊厳を踏みにじる目的以外の何物でもないことをきっちりと描き出す。
劇中に登場する「日本語しか話せない少年たち」を見て、きっと誇らしく思う日本人はいないだろう。その居心地の悪さは、これからも大事にしていきたいと思う。
韓国映画の総合力
韓国映画はやはり強い。
まずテーマが圧倒的に正しい。
そして個人やローカルなどのミクロを描きながら最終的にテーマを普遍的なものに昇華させている。
更には作品独自のエンターテイメント性もしっかりと備えている。
そのエンターテイメント性も、サスペンスやアクションのシンプルなものから、逆境からの知恵や工夫による逆転、作劇の基本かつ必殺技である円環構造などによる重層的な見せ方によって、どのレベルの鑑賞者でも楽しめる作りになっている。
正しさだけでは見る気にならないし、普遍性だけでは伝わらない。
映画の難しさと面白さが詰まってる作品だと思う。
そして何と言ってもユ・ヘジン力が炸裂しててめっちゃ楽しい。
学はない彼が果たす役割の痛快さと、知識によって世界が広がる普遍的な喜びはユ・ヘジンが演じてこそだと思う。
オ・ダルスが健在(?)なら彼が演じていたかもしれないけど。正反対のキャラクターとのバディ感も最&高。
ただ、調べてみた限りだと作品中の統治に関する描写は諸説ありっぽい感じだったので、そこは判断保留として作品内の情報のみで評価したいと思う。
判断保留の部分があっても★★★★★の映画だと思います。
言葉は民族の精神を盛った器
言葉は民族の精神を盛った器
僕が敬愛する東京の牧師さん、・・もう亡くなられたが。
あの方はハングルと朝鮮語の会話を長く勉強しておられた。
「○○くん、語学を習得するということはねー、これは本当に大変なことなんですよ、ホッホッホ」。
小柄で、垂れ目で、ベレー帽が似合う。柔和な笑顔の先生だった。
1970年代、韓国でパク・チョンヒ(朴正煕)大統領が、韓国国内の民主化活動家を徹底して弾圧していた頃に、穏やかなお顔に似合わず、その民主化活動や亡命者たちの受け入れを、ここ日本の地から密かに支えていた先生だ。
「日本はね、朝鮮の人々から言葉を奪ったのです」。
先生は(日本語はペラペラに話せる世代の)韓国からの年配のお客さんと面会する時にも、先生は敢えて頑張って朝鮮語で会話をするように努めておられた・・
あれはまさしく、
《かつて言葉を奪ったことへの償い》と、
《異国の言語を学ばされた かの地の人々の 語学習得の難儀をば我が身に負うて追体験する》ためであったのだと、僕はあの笑顔の底にある強い意志というものを、はっきり理解していました。
・・・・・・・・・・・・・
台詞の発音の問題 ―
本作は、映画の配役と人選について問題ありでした。
日本人の僕として観ている立場からするとかなりの混乱が起こります、
リュ代表を締め上げる「眼光鋭い制服の男」の喋り方が、これが
「総督府の役人で内地から派遣されてきた『日本人』官憲の人間」なのか、それとも
「朝鮮の人間なのだが率先して日本の手先になった=創氏改名を済ませた『地元民』」の哀しい姿なのか、
・・恐らくそこまでの深読みはなしで、脚本上前者なのだと思いますが、あの日本語の発音を韓国人キャストの口を通して我々が聞くとき、どちらの立場の人間なのかがちょっと判明しなくなるのです
あのへんは日本人俳優を一人立てて使うべきだったのではないかと、日本と韓国の両鑑賞者のためにも、これは残念だった点です。
・・・・・・・・・・・・・
邦画で
「辞書編纂」がテーマになった映画といえば、加藤剛、松田龍平、宮﨑あおいの「舟を編む」が名作でした。
膨大な数の言葉カードを収集し、生きている日本語を丹念に辞書に分類し 残していく、あの地道な作業。
あれに心動かされた人ならば、本作「マルモイ」( =朝鮮語で辞書作成のための「ことばあつめ」)もご覧になったら良いと感じました。
劇中、何度も京城(キョンソン)駅が登場します。
主人公リュ代表にぶつかってきた駅前広場の男の子の、咄嗟に出た言葉
・男児「すみません」
・リュ「朝鮮民族なら朝鮮語を話しなさい」
・男児「朝鮮語は話せません」。
言葉を失うリュ。
日本政府の出先機関=朝鮮総督府の命により、学童の世代から粛々と確実に、教育の力で、母語と民族へのプライドを失わせていく“植民地における同一化政策”。
親世代と子世代・孫世代が家庭内で会話しづらくなる。そうやって民族の魂と結束を壊していく。
植民地政策の悪魔性です。
これが逆の立場だったらどうだったかを、僕らは想像してみるべきではないか・・
石川啄木の金字塔
「ふるさとの訛り懐かし停車場に
人混みの中に そを聞きにいく」
・・この句が誕生しなかったかもしれないのだから。
・・・・・・・・・・・・・
◆「第二次世界大戦後、独立を回復した国の中で唯一自国の言語を取り戻した国家となった」
このラストのナレーションはあまりにもあまりにも重たい。
◆DVDを2枚購入した、
1枚は北海道で機関誌「アヌタリ・アイヌ」(われら人間)を主宰している友人に、
1枚は沖縄で琉球語の伝承と琉球独立学会に携わっている友人へプレゼントだ。
タンポポの綿毛は、ふわふわと頼りないが、命を秘めて風に乗り、人の心に言の葉を芽生えさせる。
歴史は人々の思いでできている
1910年に韓国が併合され、
1919年に三・一独立運動が起こった。
1939年には創氏改名が実施され、韓国の8割の人が日本式の苗字を届け出た。
(ちなみに、この映画は1939年が舞台だと思われます。創氏改名が登場しますから)
と、教科書で、こんな事実を習ったはずですが、
歴史には、詳細な事実(人々が日常で体験したこと)は、記述されません。
ましてや、そこに生きていた人々の気持ちは、なかったかのごとくです。
「ひとりの百歩より、百人の一歩が大切」
代表と呼ばれていたリュ・ジョンファンが、子供のころ、心に刻んだ父親の言葉です。
時は過ぎ、その父親は中学校の校長として、皇民化の教育に加担している。
父親を責める息子に、父親は言います。「昔は独立できると思っていた」
「昔」とはもしかしたら、三・一独立運動のころのことでしょうか。
しかし、20年の月日は父親を変えた。
同じ日本人になる、という巧みな、
しかし、現実には差別的な扱いのもと、
牙を抜かれていく同朋たちの中での20年。
片や、外国留学から帰ってきて、20年前の思いそのままの息子。
父親が現実と折り合ったからこそ、得られた収入があり
その資金が支えた外国留学が、現実と抗う息子を育てたという皮肉です。
元スリのキム・パンスには、息子との間に逆パターンの分断があります。
生まれた時から併合下にあり
あたりまえのように日本人に殴られる環境下で育った息子。
アウトローの父親とは、気持ちが通じるはずもありません。
共通のアイデンティティーを失うということは
親子の間にさえも分断を生み出すということです。
だからこそ、アイデンティティーの源泉のひとつである言葉に
命をかけた人々が存在した、ということなのです。
『皇民化政策』『創氏改名』という単語に、
命を吹き込んでくれたこの映画に感謝です。
「もしもOOだったら…」というフィクションとして楽しむにはよいですが、史実と考えると大きく間違えてしまいます。
楽しく感動しました
コロナ禍の中、韓国ドラマや映画にハマり、目下韓国語と歴史を勉強中です。
韓国語講師のお勧めで見てみましたが本当に良い作品だなと思いました。
強国に尊厳を否定される事は何国人であっても嫌なことだと思うので、私も一個人として感情移入できました。韓国の人が大日本帝国を否定するのは当然のことなので、反日だのどうのと騒ぐこともないと思います。
韓国人の先生曰く「この内容の作品を禁止しない日本は素晴らしい国です!」
そういう日本を大切に守って行くことが大切なのだと改めて感じました。
韓国作品の常ではありますが、日本人が日本人と感じられない発音なので−★です。
日本人にとってだけでしょうが、そのたびリアリティがぐっと下がり、ああドラマなんだなと興ざめするからです。
戦時下に文化を守ろうと抗った人々の物語
複雑な思い…
日本人として見ていて非常に心苦しい。韓国併合、創氏改名など、朝鮮語文化を廃し、学校でも日本語教育が進む中、朝鮮語の辞書を作ろうと、日本の警察に弾圧されながらも、命懸けで奮闘する朝鮮語学会の人々の話。文字は民族の精神、言葉は民族の命。どの国でもそうだろう。反日映画と言われれば、そうかもしれないが、この歴史に向き合わなければならない。同時に改めて自国語の大切さに気付かされた。シリアス一辺倒では描かれず、ユ・ヘジン演じるお調子者のパンスが和ませる。ユン・ゲサン演じるリュ代表との次第に打ち解けていく様が音楽と共に良かった。比較的、極端に下手なイントネーションの日本語が出演陣になかったのも、徹底した役作りだった。
言葉には精神が宿る
2本立て2本目。戦争の悲劇。 言葉は民族の命。奪えるものではない。...
2本立て2本目。戦争の悲劇。
言葉は民族の命。奪えるものではない。必死に母国語を守る姿に心うたれる。
ただ、これを見て日本人って何て悪いことしたんだ、朝鮮民族に謝らなければ…と、ようやく脱却できつつある自虐史観に戻らないようにしてほしい。これはあくまでも時代の悲劇なのです。
日本は反省し、謝罪もし、お金も出しました。もうそろそろ互いに前を向くべきなのです。ところが行き過ぎた反日教育が邪魔をしています。教育って怖い。今、この悲劇に気づいた両国民が増えつつあるのが救いです。
それさえ気をつければ映画は凄く面白いです。韓国映画、素晴らしいです。完全に邦画は遅れをとっていると思う。競い合うならこんな部分でやって欲しい。
韓国の女優さんは超絶美しいのに、なぜ男優さんは野暮ったい人が多いのですか?…すいません、完全なる負け惜しみです(笑)
韓国と日本人のことを、改めて考えるいい機会です
全49件中、1~20件目を表示