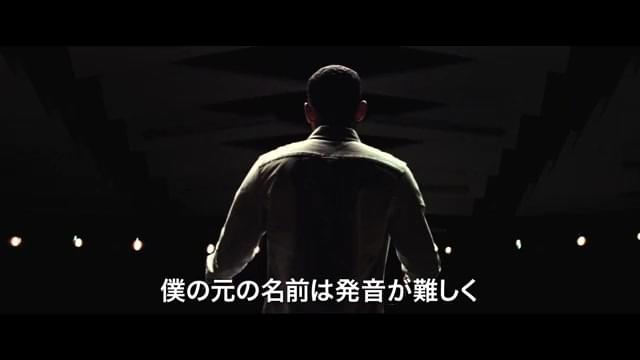ルース・エドガーのレビュー・感想・評価
全77件中、41~60件目を表示
アメリカにおける視点
映画の内容もなんですが、劇中流れる楽曲がこれから何か起こるんじゃないかと不安を煽ってきて効果絶大です。
おそらくルースはとても感受性が強く尚且つ自分の感情をあまり表に出さない子で、それが彼がアメリカで生きていくすべだったんだろうと思います。
最後にカメラに向かってくるシーンはそれらの感情全てが凝縮して今にも爆発しそうで鳥肌が立ちました。
設定がいいだけにもったいない
最終回手前で連載打切り…的な映画
ポリコレの袋小路
数少ない新作という事で観賞
感想としては
リベラル・フェミニズム・ポリコレに囲まれ
閉塞したアメリカの現実が綴られているな
って感じでしょうか
ちょっと日本人でどこまで理解できるかな
という印象も受けました
アフリカの内戦地から幼少期にアメリカの白人夫婦に
養子として引き取られ学業も性格も素晴らしく成長した
ルースに様々な災難が巻き起こり
一見幸せに見えた家族に亀裂が入っていき
大事なことは何かを観る者に問う作風となっています
ストーリーの規模的には中学生日記っぽい感じです
世界史の女性黒人教師ウィルソンは
歴史上の人物の代弁をするというロールプレイ課題を出し
故郷アフリカの独裁者をテーマにしたルースのレポートを
思想的に危険だとしロッカーも勝手に開け危険物が入っていた
と一方的にルースに疑いの目を向け親も呼び出します
この教師は黒人生徒に厳しく対応する事で知られており
優秀なルースと比較して説教するなどスパルタ教師
指導のためなら生徒のプライバシーもお構いなしで
生徒からは少なからず反感を受けているようです
そして精神疾患の妹も抱えており
「優れた黒人」に対するコンプレックスがないとも
言えません
ルースの母エイミーはルースを庇いますが
夫ピーターは実子でないルースに懐疑的になります
この映画こうした部分でやっぱり人種的に相容れないと
思わせる描写がちょくちょく出てきます
そこで時折考えていたのはその「寛容」は「我慢」な
だけではないかという疑問を投げかけているのかなという
事でした
アフリカの孤児を引き取って育てる
理想の家庭を築く
それは世間の目のためにしていたことなのか
本意に目指していた者だったのでしょうか
ルースは優しいので悪友とも付き合いを続け悩みも聞くので
奨学金を取り消され退学にもなった生徒とウィルソンに
復讐を仕掛けます
どこからどこまでがルースの計画だったのかはわかりませんが
(全部?)ウィルソンはまんまとハメられてしまいます
色々な見方が出来る作品だと思いますが自分が思ったのは
アメリカに命を救われ将来有望に育ったアフリカ出身黒人の若者が
アメリカの差別社会に蝕まれた黒人に将来を揺らがされる虚しさ
のようなものを感じました
だからこの映画自体は人種差別を前面にしているわけではなく
あくまで立場や出生の違う者同士がわかり合えるかという
テーマじゃないかなと思いますが
昨今のアメリカのコロナどうなったんだと言う規模の
差別反対暴動などもありなんだか混同されているように感じます
この混同というのが非常に危険だと思います
差別反対運動をコツコツやってきた人もいるはずですが
暴動や街の破壊、警官への暴行、略奪と言った行為と
一緒にされてしまっている気がします
そもそも人種差別反対なんて個人の内面の意識で
必要なものであってデモをしたり暴れたりパフォーマンスを
する意味が全く判りませんの全部偽物だと思っています
そんな運動に参加するくらいならこうした映画一本観るだけで
内面に生まれる意識は確実にあると思います
前述の通り海外ほど人種差別意識のない(なんかあることにしたい勢力ありますが)
日本人にどこまで理解できるかはわかりませんが
一見の価値ある作品だと思います
歯切れが悪い
17歳で学校の模範的で誰からも慕われるのルース・エドガーの知られざる内面を描いた。人間の内面を探るかのような見る人にとっては多角的でありどう捉えるかの観点で見解は分かれる作品。
観客の想像力にお任せするかのようなシーンが所々にあり、終始緊張感漂う雰囲気等でもう少し何かしら有るのかと思っていたけれど、アッサリ幕切れとなってしまったのは少し残念である。
自分的にはそこまで響くもの見えなかった。同じアフリカ系の女性教師ウィルソンと対立する部分も、社会的に今問題となっている部分とも重なるところあるものの、レポートでルースが危険な思想に染まっているのではというウィルソンの疑惑は、ルースの養父母にも疑念を生じさせドラマを盛り上げる材料ともなっているのだけれども、出来ればもう少し彼の生い立ちについて掘り下げていたらルースエドガーに感情移入はでき終始軽くは見えなかったのかもしれない。結果としては、頭のいい悪ガキが教師を陥れるだけという見方に自分としては見えなかった。
違った見方という点では、ルースの行動の一挙一動に意味がありそれを嘘か本当か見抜こうとするところに、この作品への真意があり。人間関係への個人への見解や関わり方を深く考察し、自分の身に置き換えるという事なのかと思えたが
個人的には見終わり後味がよろしくなく、そこまで深く考えさせるには至らなかった点ではもったい作品かと感じた。
黒人(有色人種)差別の根の深さを思う
リスぺクタビリティ・ポリティクス(差別されないように模範的な行動をすること)が自分に求められていると感じている優等生の主人公ルースと、それを仮の姿と見抜き、その裏に暗黒があるのを確信している黒人の教師ウィルソン。そして、何があっても息子を信じなければならないと思っている母親と、世間並みの客観性を持つ父親は、自分達の間に子供ができなかった苦悩をまだ乗り越え切っていない。結局、花火(爆竹?)の犯人も落書きの犯人もわからないが、このままだと教師ウィルソンは失職するし、自滅する。ルースの高校の校長も、何が評価されて校長になったのかと思う人物だが、ルースの両親にしろ校長にしろ、平時は問題なくその役割を果たしていられたのだろう。キーとなっている韓国系の女子生徒も、ルースと同じ(ある種の)二重人格なのかもしれない。
最初は表面的だったルースとウィルソンの対立が、直接対決でお互いに意見をぶつけ合う場面があるが、もっと早くこれが出来ていれば、助け合うことができたのでは、と思った。
もやもやする
里親映画だと思って期待したのだけど、モヤモヤする構成。
ルースが賢い子であるのは分かるのだけど、本当にもっと賢かったら狡猾にするのではないだろうか。先生と対立している時期に意地悪するのは状況的に露骨で、落ち着いた時期にこっそり意地悪すればいいのにと思う。
そもそも花火は何を目的に持ち込んでいたのだろうか。コリアンの彼女の話もどこが本当なのか不明、ルースの子ども時代には何がどうだったのか、あまりよく描かれていない。
におわすばかりの構成で、読み解く気力もわかない。
モヤる心理戦、憎たらしいと思うのは単純すぎるのか?
アメリカで生きていくのは大変だ
他者の求める役割
誰かによって担わされる役割。優秀な有色人種としてその悲惨なルーツと共に聖人の如く求められるその人物像。女性は弱く被害者であるという告発の要求。どうしても今世界で巻き起こっている事を想起せざるを得ない。
有色人種であるがこの国では多数派である日本人として、この映画を観る。日本でも今世界で起こっているデモが行われたけど、わたしは日本で行われたその運動に違和感を感じていて。それはそのデモで訴えた事は、誰かが望んだ加害者と被害者という役割を誰かに都合よく担わされたものではないのか?と。
エリトリアからのアメリカ移民となって、名前を変えた美しく聡明なルースが、懸命に喘ぎながら顔を歪めて走るその姿。
音楽がとても奇妙だったんですが作曲家のベン・サリスベリーとポーティスヘッドのジェフ・バーロウだったんですね。なるほど。ひとつは完全に均衡の取れたバッハのようであり、ひとつは原始的な地からの声が響く。
駅前留学高校
昨日『ハリエット』を観たばかりだというのに、高校の教師の名前がハリエットだったことに驚いた。すでにこの名前自体が人種差別問題に一石を投じている気がしてならない。敢えてハリエット・ウィルソン(オクタビア・スペンサー)の目線で考えてみると、黒人の生徒にしろ、アジア系の女生徒にしろ、型にはめながらも彼らを無事に社会の中へと送り出したかっただけなのだと思う。
ところが、真面目に15年間続けてきた歴史教師なのですが、「箱の中の人間で光が当たるのはごく僅か」という考えを持っているため、優等生ルースを際立たせ、引き立て役には処罰を下してランク付けするという間違いを犯してしまった。その間違いが元で、ルースによって天才的な復讐をされる物語(だと思う(個人の感想であり、正解ではないかもしれない)。
ハリエットの妹が精神的難病を抱えていることや、突如学校に現れて暴れだす事件もあり、そこでの警察官の対応もドキっとさせられましたが、これもルースの企みの一つだったのでしょうか。彼が遅刻してきたことも引っ掛かります。とにかく、ルースがメールしていた相手の名前“D-runner”が誰なのかわからないのもサスペンスの魅力です(想像ではデショーン)。
レイシストも出てこないし、人種差別問題というよりも、偏見、固定観念、「愛と信頼」を訴えたいのだと感じました。黒人だから目立たないように、ランク付けし、この子はこういう性格だからと決めつける。内申書に書けばいいだけなのに、他の生徒の前でそれを言う教師。ステレオタイプを嫌う光のルースによって、人を出自や噂や事件だけで判断する教師に対して静かな復讐が行われたのだった。
複雑な
黒人差別は黒人の力では解消できない問題だと示した衝撃作なのです!
観たらもやもやするでしょう、それは特殊な設定の中で生活する人々の物語だから。
黒人の地位向上を目指して黒人生徒の魔女狩りをして黒人生徒の質向上をしようとするデブ黒人女教師。
オバマの再来と賞賛される優等生黒人生徒は仲間を護るために、デブ黒人教師の罠にわざとかかり、逆に陥れることに成功する。
二人の行動は、黒人差別の解消には寄与することがない、ある意味、凄い能力と行動力がありながら、なにも好転しない、それは主人公の最後の表情に表れている。
でも、少し光明があるとしたら、ナオミワッツの存在、黒人を養子にして育て、良心と尊厳について親子で共有しようとする姿に感動しました。
私たちも、この差別を、黒人だけ、アメリカだけの問題だと考えないで、意識して、行動する責任があると、そう、思います。
今だからこそ、アメリカの不当な人種差別に反発して、何かを変えることが必要だと実感した、映画でした。
妥協と協調でまわる世界共通の普遍性をもつ
「ルース・エドガー」(原題:Luce)。
黒人の高校生ルース・エドガーは、アフリカの戦時下エリトリアで生まれ、言葉より先に拳銃の使い方を覚えた。7歳でアメリカの白人の養父母に引き取られ、両親の手厚い養育で、言葉や文化の壁、そして言い知れない恐怖を克服した。
成績優秀、スポーツ万能、学校代表のスピーチを依頼されるなど、誰からも慕われ、模範生徒として将来を嘱望されていた。"スピーチが上手い"という設定や、俳優のキャスティングは、"ミニ・オバマ"を想起させるように作られている。
そんな彼が、授業で出されたあるレポートをめぐって、同じアフリカ系の女性教師ウィルソンと対立することになる。レポートの内容が、"暴力で何でも解決する"といった危険な思想家の考えだったからだ。
疑念を持った教師ウィルソンはプライバシー無視で、ルースのロッカーを捜索、法令違反の花火を発見する。それが養父母に報告されることにより、徐々に養父母や学校をめぐる人々を巻き込んでいく。
ルースは"秀でた優等生なのか"、"隠された怪物なのか"と、サスペンスドラマのように観る者をグイグイと引き込む。
もともとは舞台向けに作られたJ・C・リーの同名戯曲(「Luce」)を映画化。映画批評サイトのRotten Tomatoesでの批評家支持率は92%。まさにクロウト受けする絶妙なストーリーだ。
困難な環境に生まれた黒人の少年が、自身の努力と養父母の愛情でそれを克服する…そんなお決まりは、本当に正しいのだろうか。
高校生たちの繊細な内面、大人の理想の勝手な押し付け、両親の子供を想う期待とそれに応えていこうとする模範生の葛藤。
これまでも多くの青春映画が、"大人と子供の(理想の)対立"をテーマにしてきたように、本作もそういう意味では"青春映画の一種"と単純化もできるが、ひと味もふた味も違う。
この作品は、多国籍社会のアメリカにおける黒人の典型的なイメージをテーマに、さまざまなルーツを持つアメリカ人のための話のように見える。しかしそれは表面上の設定で、実は全世界に通じる普遍性を持っている。
人間は他人を型にハメたがる。それが安心だからだ。本人は周りに溶け込もうと違和感のない型に合わせる。そうやって社会は回っている。妥協と協調である。
しかし当然、大衆に共通のイメージ(=いわゆる常識)がすべてではない。
皆、典型的な型に自分を合わせようと、苦労している。だから多くの人が共感できる。
観たものを惹き付ける本作だが、これは俳優の力量によって成し遂げられた作品で、原作の素晴らしさに基づいている。映像はオマケみたいなもので、まさに戯曲。映画的な魅力はそれほど発揮されていないとも思う。
(2020/6/7/ヒューマントラストシネマ渋谷 Screen3/シネスコ/字幕:チオキ真理)
微妙なラスト
決定的なシーンがないサスペンス
全77件中、41~60件目を表示