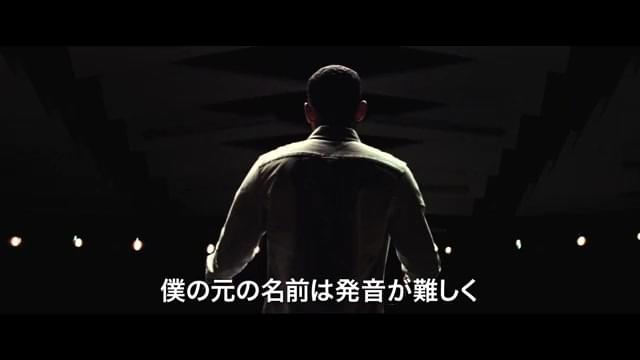「妥協と協調でまわる世界共通の普遍性をもつ」ルース・エドガー Naguyさんの映画レビュー(感想・評価)
妥協と協調でまわる世界共通の普遍性をもつ
「ルース・エドガー」(原題:Luce)。
黒人の高校生ルース・エドガーは、アフリカの戦時下エリトリアで生まれ、言葉より先に拳銃の使い方を覚えた。7歳でアメリカの白人の養父母に引き取られ、両親の手厚い養育で、言葉や文化の壁、そして言い知れない恐怖を克服した。
成績優秀、スポーツ万能、学校代表のスピーチを依頼されるなど、誰からも慕われ、模範生徒として将来を嘱望されていた。"スピーチが上手い"という設定や、俳優のキャスティングは、"ミニ・オバマ"を想起させるように作られている。
そんな彼が、授業で出されたあるレポートをめぐって、同じアフリカ系の女性教師ウィルソンと対立することになる。レポートの内容が、"暴力で何でも解決する"といった危険な思想家の考えだったからだ。
疑念を持った教師ウィルソンはプライバシー無視で、ルースのロッカーを捜索、法令違反の花火を発見する。それが養父母に報告されることにより、徐々に養父母や学校をめぐる人々を巻き込んでいく。
ルースは"秀でた優等生なのか"、"隠された怪物なのか"と、サスペンスドラマのように観る者をグイグイと引き込む。
もともとは舞台向けに作られたJ・C・リーの同名戯曲(「Luce」)を映画化。映画批評サイトのRotten Tomatoesでの批評家支持率は92%。まさにクロウト受けする絶妙なストーリーだ。
困難な環境に生まれた黒人の少年が、自身の努力と養父母の愛情でそれを克服する…そんなお決まりは、本当に正しいのだろうか。
高校生たちの繊細な内面、大人の理想の勝手な押し付け、両親の子供を想う期待とそれに応えていこうとする模範生の葛藤。
これまでも多くの青春映画が、"大人と子供の(理想の)対立"をテーマにしてきたように、本作もそういう意味では"青春映画の一種"と単純化もできるが、ひと味もふた味も違う。
この作品は、多国籍社会のアメリカにおける黒人の典型的なイメージをテーマに、さまざまなルーツを持つアメリカ人のための話のように見える。しかしそれは表面上の設定で、実は全世界に通じる普遍性を持っている。
人間は他人を型にハメたがる。それが安心だからだ。本人は周りに溶け込もうと違和感のない型に合わせる。そうやって社会は回っている。妥協と協調である。
しかし当然、大衆に共通のイメージ(=いわゆる常識)がすべてではない。
皆、典型的な型に自分を合わせようと、苦労している。だから多くの人が共感できる。
観たものを惹き付ける本作だが、これは俳優の力量によって成し遂げられた作品で、原作の素晴らしさに基づいている。映像はオマケみたいなもので、まさに戯曲。映画的な魅力はそれほど発揮されていないとも思う。
(2020/6/7/ヒューマントラストシネマ渋谷 Screen3/シネスコ/字幕:チオキ真理)